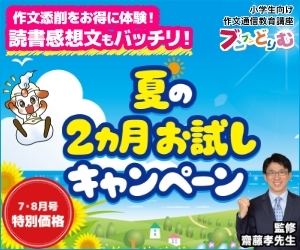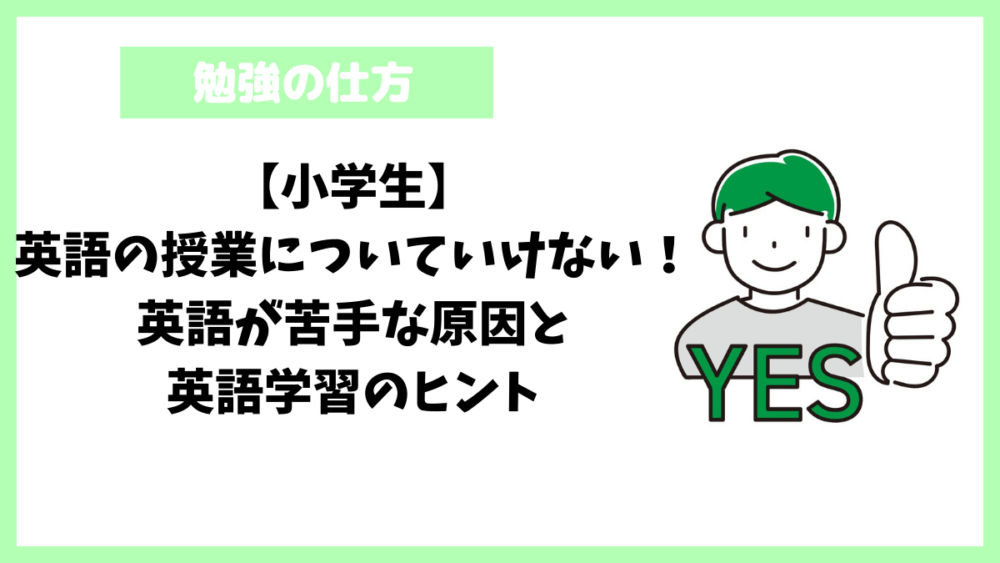
「※この記事には一部PRが含まれます」
「何を書いたらいいかわからない」「書くのに時間がかかる」など、小学生の作文の宿題に頭を悩ませていませんか?
この記事では、作文の基本ルールから原稿用紙の使い方、読み手を惹きつける書き方のコツまで、元個別指導塾教室長の筆者が具体的に解説します。
この記事を読めば、小学生が自信を持って作文に取り組めるようになり、保護者の方も的確なサポートができるようになりますよ。
もし、読み終えても作文が書けない場合、小学生向け作文通信教育講座「ブンブンどりむ」がおすすめです。
「ブンブンどりむ」は、家で学習できる、齋藤孝先生監修の小学生向け作文通信教育講座です。
「作文の基礎」から「公立中高一貫校の受験記述対策」まで対応しています。
「ブンブンどりむ」が気になる方は、公式ホームページをチェックすると良いでしょう!
記事のポイント
小学生の作文の書き方:10個のルール
作文を書くときのポイント
原稿用紙の使い方
作文を書く時に親ができるサポート
おすすめ塾
国語に特化した!貴重な塾
東大生オンライン個別指導!
東大生との1対1での対話を通して、
文章題にも強くなる「一生モノ」の読解力
国語の苦手が解消できる!
東大生の指導で国語の点数アップ
↓↓↓
「ヨミサマ。」公式ホームページ
Contents
小学生の作文の書き方とは?書く前にやるべき3つの準備

作文を書き始める前には、「何を、どう書くか」を明確にするための準備が不可欠です。
この準備をしっかり行うことで、書いている途中で手が止まることを防ぎ、お子さんがスムーズに文章を書き進めることができます。
具体的なテーマ決めから内容の整理術まで、作文の土台作りとなる大切なポイントをご紹介します。
- 書くテーマを決めるコツ
- 「5W1H」で内容を整理する
- 箇条書きで書くことをまとめよう
書くテーマを決めるコツ
「作文のテーマ選びは、お子さんが楽しく書き進めるための最初のステップです。
宿題でテーマが決まっている場合もありますが、自由に決められる場合は、お子さんの興味や関心事を深掘りしてあげましょう。
例えば、かつて私が担当した、夏休みの宿題で作文が苦手だった小学5年生のAくんは、大好きなカブトムシ観察のテーマにしたことで、生き生きとした作文を書き上げ、先生に褒められました。
無理に難しいテーマを選ぶ必要はありません。
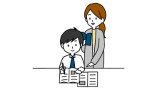
「5W1H」で内容を整理する
作文の骨格を作る上で役立つのが、「いつ (When)・どこで (Where)・誰が (Who)・何を (What)・なぜ (Why)・どのように (How)」の5W1Hです。
これを意識して情報を整理すると、文章に具体性が増し、読者にも伝わりやすくなります。
例えば、「運動会の思い出」をテーマにするなら、「いつ(去年の秋)」「どこで(学校の校庭で)」「誰が(ぼくが徒競走で)」「何を(転んでしまって)」「なぜ(練習不足で)」「どのように(悔しかったけど、友達が励ましてくれた)」のように情報を洗い出していくと良いでしょう。
| 項目 | 内容 | 例(作文テーマ:遠足) |
|---|---|---|
| When(いつ) | いつの出来事か | 5月の晴れた日 |
| Where(どこで) | どこで起きたことか | 動物園に行った |
| Who(だれが) | だれが登場するか | 友だちと先生と |
| What(なにを) | なにをしたか | キリンを見たり、お弁当を食べたりした |
| Why(なぜ) | なぜそれをしたのか | 学校の行事で、みんなで楽しく学ぶため |
| How(どうやって) | どのようにしたか、どんなふうに感じたか | バスで行って、ワクワクした気持ちだった |

箇条書きで書くことをまとめよう
頭の中で考えていることをいきなり文章にするのは難しいものです。
そこで、書く内容を箇条書きで書き出してみましょう。
箇条書きで書き出すことにより、書きたいことの全体像が見えやすくなり、情報の抜け漏れも防げます。
例えば、遠足の作文を書くなら「集合場所での出来事」「バスの中でのこと」「お弁当の時間」「遊んだ場所と内容」「帰りのバス」「一番心に残ったこと」のように書き出すと、流れが作りやすくなります。
小学生の作文の書き方:原稿用紙の使い方の基本ルール10選

作文を書く上で避けて通れないのが、原稿用紙の正しい使い方です。
句読点や記号の位置、段落の始め方など、基本的なルールを知っているかどうかが、作文全体の印象を大きく左右します。
このセクションでは、小学生のお子さんが迷いがちな原稿用紙のルールについて、具体的な例を交えながら10個のポイントに絞ってわかりやすく解説します。
- 題名と名前の正しい書き方
- 段落の始まりは1マス空ける
- 句読点の位置とルール
- かぎかっこの正しい使い方
- 小さい「ゃ・ゅ・ょ・っ」はどう書く?
- 数字・アルファベットの書き方の注意点
- 文末表現は統一する
- 段落の変え方とタイミング
- 文字数の目安とマスの使い方
- 書き直し・消しゴムの使い方
題名と名前の正しい書き方
原稿用紙に作文を書く際、まず最初に悩むのが題名と名前の書き方かもしれません。
縦書きの原稿用紙では、一般的に右端から数マス空けて題名を書き、その次の行に名前を書きます。
名前は姓と名の間に1マス空けるのが一般的です。
見た目の美しさも作文の評価ポイントの一つですよ。
段落の始まりは1マス空ける
話が変わるタイミング、つまり段落を変える際には、必ず行の先頭を1マス空けてから書き始めましょう。
これは作文の基本的なルールであり、文章のまとまりを分かりやすくする大切な役割があります。
読者が文章を理解しやすくなるだけでなく、作文全体が整頓された印象になります。
句読点の位置とルール
句読点(「、」と「。」)は、文章の区切りを示す大切な記号です。
基本的に1マスに1つ書きますが、行の先頭には書かないというルールがあります。もし句読点が行の終わりに差し掛かった場合、そのマスに文字と一緒に書き入れるか、次の行の最初のマスに書き入れます。
読点の多すぎ、少なすぎは文章の読みにくさにつながります。
かぎかっこの正しい使い方
会話文や引用、強調したい言葉などには、かぎかっこ(「 」)を使います。
かぎかっこの始めと終わりもそれぞれ1マスを使います。
会話文の場合、新しい行からかぎかっこで始めることが一般的ですが、心の中で思ったことなど、文中に挿入する場合には行を変えずに使うこともあります。
使い分けが明確だと、読み手はスムーズに内容を理解できます。
小さい「ゃ・ゅ・ょ・っ」はどう書く?
小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」「っ」などの促音や拗音は、前の文字と同じマスに小さく書くのではなく、単独で1マスを使って書きます。
例えば、「がっこう」と書く場合、「が」「っ」「こ」「う」とそれぞれ1マスずつ使います。
これらは意外と間違えやすいポイントなので、お子さんと一緒に確認してみましょう。
数字・アルファベットの書き方の注意点
縦書きの作文では、数字は基本的に漢数字(一、二、三など)を使います。
ただし、統計的なデータや西暦など、算用数字(1、2、3など)の方が適している場合は、2マスに2文字ずつ書くことが多いです。
アルファベットも同様に、2マスに2文字ずつ書くのが一般的です。統一感を持たせることが大切です。
文末表現は統一する
作文全体で「です・ます調」か「だ・である調」のどちらかに統一することが重要です。
途中で混じってしまうと、文章が読みにくく、幼稚な印象を与えてしまいます。
小学校の作文では、一般的に「です・ます調」が推奨されます。一貫した表現は、読み手に安定した印象を与えます。
段落の変え方とタイミング
段落を変えるタイミングは、話の区切りや内容が変わる時です。
新しい話題に入る時、場所や時間が変わる時、登場人物の気持ちが変化する時などが目安になります。
適切な段落分けは、文章にリズムを生み出し、読者が内容を理解しやすくなります。
作文の「呼吸」とも言える大切な要素です。
文字数の目安とマスの使い方
指定された文字数がある場合、9割以上は書くように心がけましょう。
原稿用紙は1マスに1文字が基本ですが、句読点やかぎかっこの終わりがマスの右下に小さく書かれることもあります。
文字数に到達させるためには、具体例を増やしたり、自分の感想を詳しく書いたりする工夫が必要です。
最後まで諦めずに書くことが重要です。
書き直し・消しゴムの使い方
原稿用紙で書き間違いをしてしまった場合、二重線で消して訂正するか、消しゴムで丁寧に消すのが基本です。
あまりに何度も消しゴムを使うと紙が破れてしまうことがあるため注意が必要です。
清書する前に下書きをする習慣をつけると良いでしょう。これは、私が塾で生徒に作文指導をする際にも、必ず教えていたことです。
作文の構成を知ろう!書きやすくなる基本パターン

作文には、いくつかの基本的な構成パターンがあります。
これを知っていれば、「何から書き始めたらいいかわからない」という悩みを解決し、作文をスムーズに書き進めることができます。
特に小学生のお子さんには、まずはシンプルな構成から慣れていくことをおすすめします。
このセクションでは、代表的な構成パターンとその活用法について解説します。
- 起承転結ってなに?
- 小学生におすすめの構成3パターン
- 読書感想文や夏休み作文にも使える構成のコツ
起承転結ってなに?
作文の基本的な構成としてよく耳にするのが「起承転結」です。
「起」で話の始まりを、「承」で話を展開させ、「転」で意外な展開や視点の変化を加え、「結」でまとめや結論を示すものです。
小学生の作文では、完璧な起承転結でなくても大丈夫です。
まずは、「始まり→真ん中→終わり」のシンプルな構成を意識してみましょう。
| 部分 | 書く内容のポイント | 例(テーマ:遠足) |
|---|---|---|
| 始まり | いつ・どこで・なにをしたかを簡単に書く | 「先週、学校の遠足で動物園に行きました。」 |
| 真ん中 | くわしい出来事や体験、そのときの気持ちを書く | 「キリンがとても大きくてびっくりしました。お弁当もおいしかったです。」 |
| 終わり | 感想や学んだこと、心に残ったことを書く | 「楽しい思い出ができたので、また行きたいです。」 |

小学生におすすめの構成3パターン
小学生の作文では、複雑な構成よりも、シンプルで分かりやすいパターンがおすすめです。
- 時間順:出来事を時間の流れに沿って書く最も基本的なパターンです。例えば、遠足の作文なら朝の集合から帰宅までを順に書きます。
- 体験から学びへ:経験したこと(体験)から、そこで感じたことや学んだこと(学び)へつなげる構成です。読書感想文などで特に有効です。
- 一番言いたいことから:結論や一番伝えたいことを最初に述べ、その理由や具体例を後に続くパターンです。発表形式の作文で効果的です。
これらのパターンを参考に、お子さんが書きやすいものを選んでみてください。

読書感想文や夏休み作文にも使える構成のコツ
読書感想文や夏休みの作文といった課題では、特定のテーマに沿って書く必要があります。
読書感想文や作文でも、基本的な構成のコツは変わりません。
読書感想文なら、「本を選んだ理由→印象に残った場面→そこから感じたこと・考えたこと→自分の生活にどう活かすか」といった流れが一般的です。夏休みの作文であれば、「夏休みのテーマ(例えば自由研究)→取り組んだこと→苦労したこと・工夫したこと→結果・感想」のように、目的意識を持って構成を考えると良いでしょう。
書き出しと結びの表現アイデア
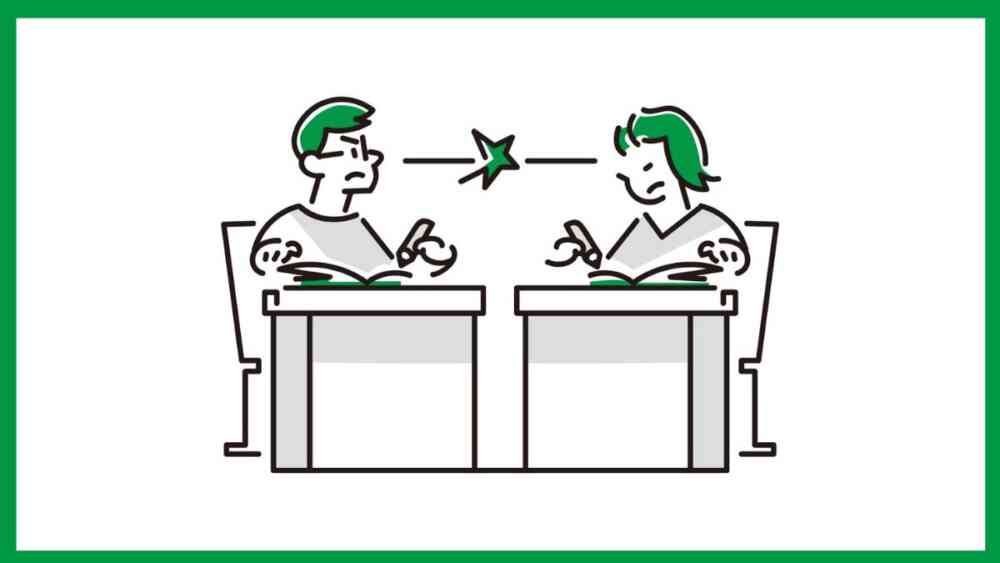
作文の「顔」とも言える書き出しと、読み終えた後の印象を決める結びは、作文の出来栄えを大きく左右します。
読者を惹きつけ、「もっと読みたい」と思わせるような書き出しと、読後にすっきりとした気持ちにさせる結びのアイデアを具体的にご紹介します。
- 印象に残る書き出しの例
- 自然な終わり方のヒント
印象に残る書き出しの例
作文の書き出しは、読者の興味を引きつけるための重要な部分です。
例えば、以下のような工夫があります。
- 一番伝えたいことから始める:「僕は、この夏休みに人生で初めての大冒険をしました。」
- 会話文から始める:「『やったー!』思わず大きな声が出ました。」
- 音や状況描写から始める:「ザーッという雨の音と雷の光で、目が覚めました。」
- 問題提起から始める:「みなさんは、環境問題について考えたことはありますか?」
「え、続きが気になる!」と思わせるような工夫をしてみましょう。
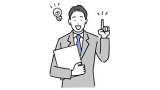
自然な終わり方のヒント
作文の結びは、読者に「読んでよかった」と感じてもらうための大切な部分です。
- 感想や学びをまとめる:その体験や学びを通して、自分がどう変わったか、何を得たかを簡潔にまとめます。
- 未来への展望を示す:今後の抱負や、これからどうしていきたいかを書きます。
- 読者へのメッセージ:読者に向けて、何か問いかけたり、共感を促したりする言葉で締めくくります。
「作文の終わり方がわからない」という小学生の悩みを解決するために、これらのヒントを教えてあげてください。
作文の中で大事にしたい表現のポイント

作文は、単に出来事を並べるだけでなく、自分の考えや気持ちを伝えることが最も重要です。
どうすれば自分の伝えたいことが、読み手にしっかりと届くのか。
このセクションでは、作文をより魅力的にするための表現のコツについて、具体的な例を交えながら解説します。
- 感想や気持ちを自分の言葉で書こう
- 会話文で場面をリアルに伝える
- 面白く読んでもらうための工夫
感想や気持ちを自分の言葉で書こう
作文で一番大切なのは、「自分の気持ち」や「考え」を素直に書くことです。
「楽しかった」「悲しかった」だけでなく、「なぜそう感じたのか」「その時、どんな気持ちになったのか」を具体的に表現しましょう。
例えば、「楽しかった」ではなく、「ジェットコースターに乗った時、心臓がドキドキして、まるで空を飛んでいるような気分で、思わず『わー!』と叫んでしまいました」のように、五感を交えて表現すると、読者に情景が伝わりやすくなります。

会話文で場面をリアルに伝える
会話文を効果的に使うと、作文に臨場感が生まれます。
登場人物が実際に話しているように書くことで、読者はその場の状況をより鮮明にイメージできます。
ただし、会話文ばかりにならないよう、適度に説明文と組み合わせるのがポイントです。
例えば、「お母さんが『がんばったね』と声をかけてくれました」と書くよりも、「お母さんがにこにこしながら『がんばったね!』と、ぼくの頭をなでてくれました」とすると、より場面が伝わります。
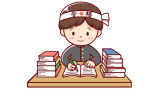
面白く読んでもらうための工夫
読者が飽きずに読み進めてもらうためには、いくつかの工夫があります。
- 比喩表現を使う:「空に浮かぶ雲は、まるで綿菓子みたいだった」のように、何かを例えて表現すると、文章に奥行きが生まれます。
- 擬音語・擬態語を使う:「ワクワクしながら」「ドタバタと走り回った」など、音や動きを表す言葉を使うと、文章に躍動感が生まれます。
- 具体例をたくさん入れる:抽象的な表現だけでなく、具体的なエピソードや出来事をたくさん盛り込むことで、読者はより理解しやすくなります。
これらの工夫は、作文に個性と魅力を与えるだけでなく、お子さんの表現力を豊かにすることにもつながります。
小学生低学年・高学年別!書き方の違いとアドバイス

小学生の作文指導は、学年によってアプローチを変えることが大切です。
低学年と高学年では、言葉の語彙力や思考力に大きな違いがあるため、それぞれの発達段階に合わせた指導が求められます。
このセクションでは、学年ごとの作文の特徴と、保護者の方ができる具体的なアドバイスについて解説します。
- 低学年向け:短くて簡単な構成でOK
- 高学年向け:理由や感想をしっかり書こう
低学年向け:短くて簡単な構成でOK
小学1~3年生の低学年のお子さんの場合、まずは「書くこと自体を楽しむ」ことが最優先です。
長い文章を書くのが苦手でも、短くても良いので、思ったことや感じたことを素直に表現できることを目標にしましょう。
| ポイント | 低学年向けアドバイス |
|---|---|
| 構成 | 「始め・中・終わり」の3部構成を意識するだけで十分です。 |
| 文字数 | まずは、原稿用紙1~2枚程度でOK。 |
| 表現 | 感想は「楽しかった」「悲しかった」など、シンプルな言葉で構いません。 |
| 親のサポート | 一緒に話しながら、書く内容を箇条書きで整理してあげましょう。 |
作文が初めての小学生や低学年でも、このようにポイントを押さえると無理なく取り組めます。
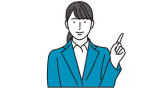
高学年向け:理由や感想をしっかり書こう
小学4~6年生の高学年になると、論理的な思考力や語彙力が飛躍的に向上します。
この時期は、単なる出来事の描写だけでなく、自分の考えや感想、そこに至った理由を深く掘り下げて書く練習をしましょう。
| ポイント | 高学年向けアドバイス |
|---|---|
| 構成 | 「起承転結」や、問題提起から結論に至る構成など、より複雑な構成にも挑戦してみましょう。 |
| 文字数 | 原稿用紙2~5枚程度を目安に、内容を深掘りします。 |
| 表現 | 「なぜそう感じたのか」「その出来事から何を学んだのか」など、より具体的に描写しましょう。 |
| 親のサポート | 作文の内容について、お子さんに質問を投げかけ、考えを深掘りする手助けをしましょう。 |
上記の表は、高学年の小学生が「考える作文」にステップアップするためのポイントを、親が理解しやすいようにまとめました。
読書感想文・発表用作文のコツと例文紹介
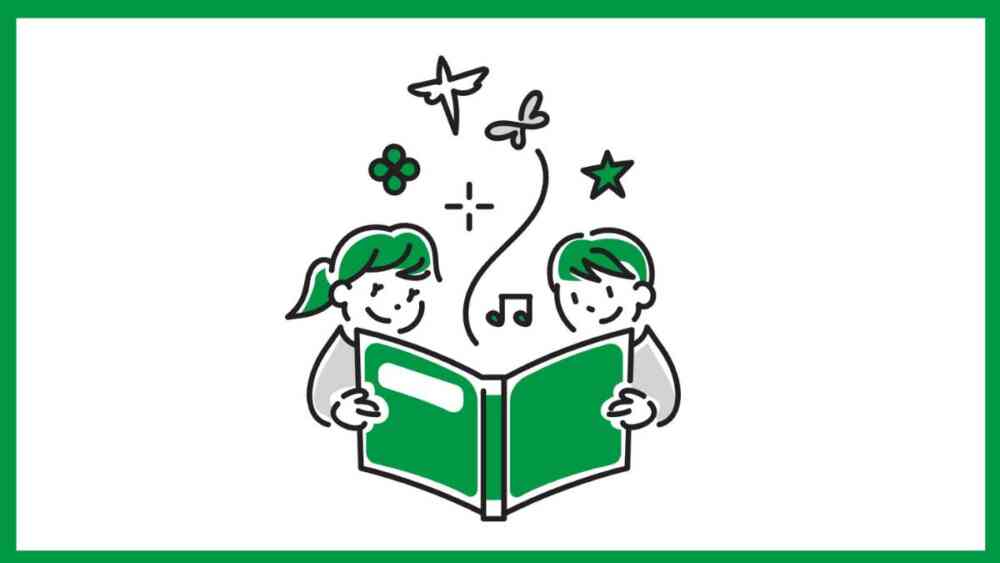
夏休みの宿題などで、多くの小学生が苦手意識を持つのが読書感想文や発表用作文ではないでしょうか。
これらは通常の作文とは少し異なるポイントがあります。
このセクションでは、それぞれの作文を効果的に書くためのコツと、すぐに使える例文をご紹介します。
- 読書感想文を書くときのポイント
- 発表を意識した作文のコツ
- 宿題にそのまま使える作文例文
読書感想文を書くときのポイント
読書感想文は、本を読んで感じたことや考えたことを自分の言葉で表現するものです。
単に「面白かった」だけでなく、「なぜ面白かったのか」「どの場面が心に残ったのか」を具体的に書くことが大切です。
- あらすじは簡潔に:本のあらすじは、最低限の内容にとどめ、感想文のほとんどを割く必要はありません。読書感想文で一番大切なのは、あなたの感じたことです。
- 心に残った場面を深掘り:特に印象に残った場面を一つか二つ選び、その場面の登場人物の気持ちや行動について、深く掘り下げて考えてみましょう。
- 自分と重ねる:本の内容と自分の経験や考えを重ね合わせ、「もし自分だったらどうしただろう」「この本から何を学んだか」などを書くと、オリジナリティのある感想文になります。
読書感想文例文
「〇〇という場面で、主人公が友達を助けるために勇気を出した姿に、私はとても感動しました。
なぜなら、私だったら怖くて動けなかったかもしれないからです。
この本を読んで、困っている人がいたら、自分も勇気を出して行動したいと思いました。」

発表を意識した作文のコツ
発表用作文は、実際に声に出して発表することを前提に書かれます。
そのため、読む人が聞き取りやすく、理解しやすいような工夫が必要です。
- 結論を最初に:何について話すのか、一番伝えたいことを最初に明確に述べましょう。
- 具体例を多く:聞き手がイメージしやすいように、具体的なエピソードや例をたくさん盛り込みましょう。
- 語りかけるような言葉遣い:「みなさん、ご存知ですか?」のように、聞き手に問いかけるような表現を使うと、興味を引きつけやすくなります。
- 短い文章で区切る:一文が長すぎると、聞き手は理解しにくくなります。短い文章でリズムよく話すことを意識しましょう。
発表を意識した作文の例文
「今日は、私が夏休みに挑戦した自由研究についてお話します。
私が研究したのは、身の回りにある色々なものの重さです。
例えば、消しゴムと鉛筆、どちらが重いと思いますか?」

宿題にそのまま使える作文例文
作文の宿題で行き詰まった時に参考にできる、簡単な例文をいくつかご紹介します。
これらの例文を参考に、お子さんのオリジナリティを加えてみましょう。
「私の夏休み」作文例文
「今年の夏休み、私は家族で海に行きました。初めてのシュノーケリングで、たくさんの魚たちと泳げて、まるで水族館の中にいるみたいでした。
最初は少し怖かったけれど、お父さんが『大丈夫だよ』と言ってくれたので、頑張れました。
この夏休みは、新しいことに挑戦する楽しさを知ることができました。」
「将来の夢」作文例文
「私の将来の夢は、動物のお医者さんになることです。
小さい頃から動物が大好きで、特に近所の公園で見る犬がかわいくてたまりません。
もし病気になった動物がいたら、私が治してあげたいです。
そのためにも、これからもっと色々なことを勉強して、たくさんの動物を助けられるようになりたいです。」
作文を書き終えたら見直しをしよう!

作文を書き終えたら、「これで終わり!」ではありません。
見直しは、作文の質をさらに高めるための大切なプロセスです。自分が書いた文章を客観的に見つめ直し、より伝わりやすい文章にするためのポイントを解説します。
- 間違い探しチェックリスト
- 読み返して気持ちが伝わるか確認
間違い探しチェックリスト
見直しをする際には、以下のチェックリストを活用してみてください。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 誤字脱字はないか? | 一文字ずつ丁寧に読み返しましょう。 |
| 句読点の使い方は正しいか? | 位置や数が適切か確認します。 |
| かぎかっこの使い方は正しいか? | 会話文の始めと終わりにきちんとあるか確認します。 |
| 文末表現は統一されているか? | 「です・ます」調か「だ・である」調のどちらかに統一されているか確認します。 |
| 同じ言葉を繰り返していないか? | 似たような言葉が何度も出てこないか確認し、他の表現に置き換えられないか考えましょう。 |
このチェックリストを使って見直すだけでも、作文の完成度が大きくアップします。
特に小学生のうちは、基本的なミスを防ぐことが「わかりやすく伝わる作文」への第一歩です。

読み返して気持ちが伝わるか確認
技術的なチェックだけでなく、「自分の気持ちがちゃんと伝わるか」という視点で見直すことも重要です。
書いた作文を声に出して読んでみるのも良い方法です。スムーズに読めるか、詰まる部分はないかを確認しましょう。
もし読みづらいと感じたら、文章の順番を入れ替えたり、言葉を分かりやすいものに変えたりする工夫が必要です。
読み手に共感してもらえるかがポイントです。
小学生向け作文通信教育講座「ブンブンどりむ」が気になる方は、公式ホームページをチェックしてください!
親ができる!作文サポートのポイント
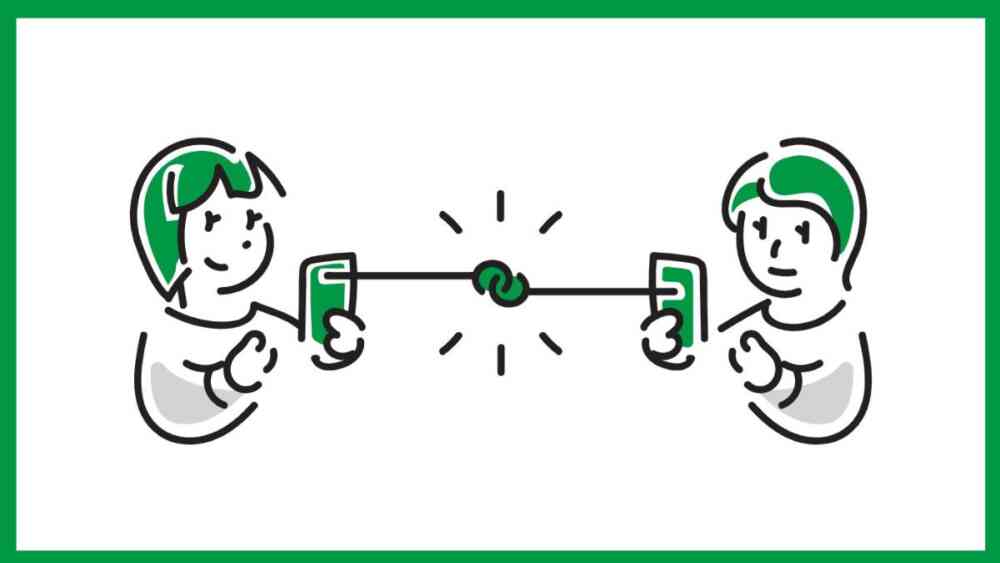
「作文の宿題、どうやって手伝えばいいんだろう…」と悩む保護者の方は多いのではないでしょうか。
大切なのは、お子さん自身が作文を書く楽しさを見つけることです。
このセクションでは、私が長年、個別指導塾で多くの保護者の方にアドバイスしてきた経験をもとに、家庭でできる具体的な作文サポートのポイントをお伝えします。
- 子どもにテーマを質問で引き出す
- 書いた内容に共感してあげる
- 書き方のルールを一緒に確認しよう
子どもにテーマを質問で引き出す
お子さんが「何を書いたらいいかわからない」と悩んでいる時、親が代わりにテーマを決めるのではなく、「質問」を通して引き出してあげることが重要です。
「最近あったことで、一番楽しかったことは何?」、「〇〇についてどう思う?」など、お子さんの興味や関心に寄り添い、具体的なエピソードを引き出すための質問をしてみましょう。
例えば、かつて、作文の宿題がまったく進まなかった小学4年生のB君は、お母さんが「この間、動物園で一番面白かった動物は?」と質問したことをきっかけに、パンダの面白い行動についてスラスラ書き始めました。

書いた内容に共感してあげる
お子さんが作文を書き終えたら、まず「頑張って書いたね!」と努力を認め、書かれている内容に共感して褒めてあげることが大切です。
「〇〇について、よくここまで詳しく書けたね!」「ここを読んで、お母さんも同じ気持ちになったよ」など、具体的な部分を褒めることで、お子さんは「自分の作文は伝わるんだ!」という喜びを感じ、次の作文への意欲につながります。
誤字脱字や表現の間違いを見つけても、まずは褒めることを優先し、その後に「もっと良くなるために、ここも見てみようか」と優しくアドバイスしましょう。

書き方のルールを一緒に確認しよう
作文のルールは、一度教えただけで完璧に身につくものではありません。
繰り返し一緒に確認することが大切です。
例えば、お子さんが作文を書く際に、原稿用紙のルールブックを一緒に見ながら「ここはこうだったよね?」と確認したり、書けた文章を声に出して読み合わせたりするのも良いでしょう。
親子で一緒に取り組むことで、お子さんは「一人で悩まなくていいんだ」と安心し、積極的にルールを学ぼうとするはずです。
「ブンブンどりむ」が気になる方は、公式ホームページをチェックすると良いでしょう!
小学生の作文の書き方&ルールに関するよくある質問【Q&A】

ここでは、作文に関するよくある質問にお答えします。
- 小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」は行頭に来てもよいか?
- 作文が上手い子の特徴は?
- 作文を書く6つの手順は?
- 作文の基本的な構成は?
小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」は行頭に来てもよいか?
いいえ、小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」や「っ」などの促音・拗音は、行頭に来てはいけません。
これらは前の文字とセットで一つの音を作るため、前の文字と同じマスに小さく書くか、前の行の最後のマスに一緒に収めるのが正しい書き方です。
例えば、「学校」と書くときに「がっ」で前の行が終わる場合、「こう」を次の行の先頭に書くことはできますが、「っ」だけが行頭に来ることはありません。これは、原稿用紙の基本的なルールの一つです。
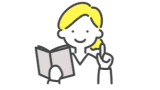
作文が上手い子の特徴は?
作文が上手な子には、以下のような特徴があります。
小学生でも意識できるポイントを中心に、わかりやすく箇条書きでまとめました。
- 自分の体験や気持ちを素直に書ける
- 話の順番がわかりやすい(時系列や場面の流れがスムーズ)
- 読み手のことを考えて、ていねいに説明している
- 「なぜそう思ったか」など、考えや理由をしっかり書いている
- 言葉のくり返しが少なく、表現に工夫がある
- 段落ごとに話題がまとまっている
- かぎかっこ(会話)や感情表現を使って、場面を生き生きと描いている
- 原稿用紙の使い方やルールを守って書けている
- 最後に感想や学んだことなど、自分なりの「まとめ」がある
- 書く前にメモや構成を考えてから取り組んでいる
こうした特徴は、練習やサポートで少しずつ身につけることができます。
「上手に書く」よりも「伝えたいことをしっかり伝える」ことが大切です。

作文を書く6つの手順は?
作文をスムーズに書くための基本的な手順は、主に6つのステップに分けられます。
この手順を踏むことで、「何から手をつけていいか分からない」という悩みを解決し、効率的に作文を完成させることができます。
- テーマを決める:何について書きたいか、一番興味のあることを見つけます。
- 材料を集める:テーマについて、自分の経験や調べたこと、感じたことなどを箇条書きで書き出します。
- 構成を考える:書き出した材料を、「始め」「中」「終わり」などの流れで組み立てます。
- 下書きをする:構成に沿って、実際に文章を書き進めます。この段階では、完璧さを求めず、自由に書いてみましょう。
- 見直しをする:書いた文章を読み返し、誤字脱字や表現の分かりにくさがないか確認します。
- 清書する:ルールに従って、丁寧に原稿用紙に書き写します。
この手順はあくまで基本的なものですが、お子さんの習熟度に合わせて柔軟に取り組んでみてください。
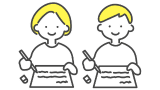
作文の基本的な構成は?
作文の基本的な構成は、大きく分けて「序論」「本論」「結論」の3つの部分から成り立っています。
この構造を意識することで、文章に一貫性が生まれ、読者にとって分かりやすい作文になります。
- 序論(始め):作文の導入部分です。何について書くのか、読者に興味を持ってもらうためのきっかけを提示します。例えば、読書感想文であれば、その本を選んだ理由などを書きます。
- 本論(中):作文の中心となる部分です。テーマに関する具体的なエピソードや体験、それに対する自分の考えや感想を詳しく述べます。複数の段落に分けて、内容を展開させることが多いです。
- 結論(終わり):作文の締めくくりです。本論で述べた内容をまとめ、改めて自分の考えや学び、今後の抱負などを記します。
小学生の作文では、「起承転結」といったさらに複雑な構成もありますが、まずはこの「始め・中・終わり」の3段構成を意識することから始めてみましょう。
東大生家庭教師
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
当サイトで人気の「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
オンライン東大家庭教師友の会
※東大生をはじめとする難関大生がマンツーマンでオンライン指導!講師の2人に一人が厳しい採用基準を突破した現役東大生!
オンライン家庭教師e-live
※東大生や英学部生の講師が選べるオンライン家庭教師!オンライン家庭教師の実績は15年以上!信頼と実績のあるオンライン家庭教師
MeTULAB(ミートゥーラボ)
※講師は全員現役の東大生!大学受験、高校受験合格を目指す生徒に向けて、現役の東大生から親切・丁寧な個別指導が特徴
スタディコーチ
※講師は東大生・旧帝大・早慶生!勉強の計画作成や進捗管理を行うコーチンが特徴!スタッフの丁寧な対応が印象的なオンライン家庭教師
STRUX
※東大出身の塾長が生徒を合格に導いてくれる!勉強の仕方を生徒に合わせて指導してくれるオンライン家庭教師!
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
まとめ:【小学生向け】作文の書き方&原稿用紙のルール10選+例文付きで解説

最後までご覧いただき、ありがとうございました。
以上、「【小学生向け】作文の書き方&原稿用紙のルール10選+例文付きで解説」でした。
【小学生向け】作文の書き方&原稿用紙のルール10選+例文付きで解説
まとめ
ここまで、小学生の作文の書き方から原稿用紙のルール、そして保護者の方のサポート方法について詳しく解説してきました。
作文は、お子さんの思考力や表現力を育む大切な学習です。
「何を書けばいいの?」というお子さんの悩みや、「どう教えればいいの?」という保護者の悩みは、適切なルールと構成を知ることで解決できます。
特に、作文を書く前の「準備」、原稿用紙の「ルール」を理解し、そして「構成」のパターンを知ることで、お子さんは「書けた!」という成功体験を積み重ねられるはずです。
作文は、すぐに得意になるものではありませんが、今回ご紹介したポイントを少しずつ実践し、お子さんを温かくサポートしてあげることで、きっと作文が楽しいものへと変わっていくでしょう。
個別指導塾で27年間、数々の生徒を見てきた私からのメッセージです。
ぜひ、今日から実践してみてください。