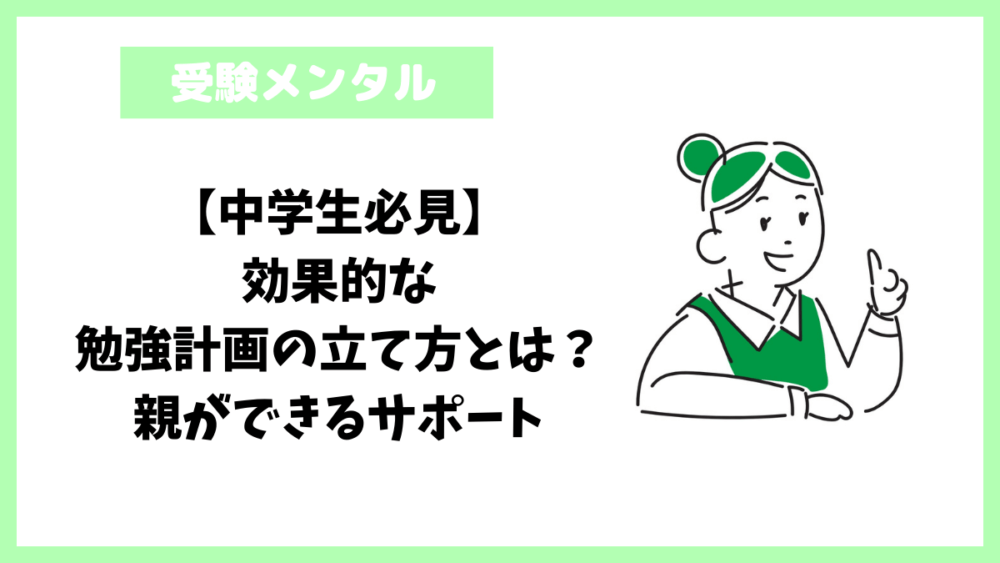
※この記事には一部PRが含まれます。
中学生の皆さん、社会や理科、英単語の暗記が苦手で、「何度やっても覚えられない」「どうせ自分は記憶力がない」と悩んでいませんか?
テストの点が伸びず、勉強へのやる気も下がってしまいます。
この記事では、私が長年大手個別指導塾の教室長として、多くの生徒を暗記嫌いから得意に変え、志望校合格へと導いてきたノウハウを大公開します。
あなたの「暗記できない」という悩みを根本から解決し、暗記力を高めて成績を上げるための具体的な方法と、明日から実践できるコツを徹底的に解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
暗記ができない中学生を解決して、成績がグングン伸びる!おすすめのオンライン塾はこちらから!
記事のポイント
中学生が「暗記できない」と感じる本当の原因を整理する
成績が上がる3つのコツ(暗記が苦手でも結果が出る学習設計)
科目別:「中学生 暗記できない」を解決する具体的な方法
1週間で実感!効率の良い暗記法トレーニングプラン
暗記ができない中学生におすすめのタブレット学習教材
おすすめ塾
講師のほとんどが東大・東大院生
東大生が指導する塾としてはコスパが良い
オンライン個別指導
部活が忙しい生徒にも対応!
自宅で勉強できるから、集中力UP!
成績アップの近道!
30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/
↓↓↓
トウコベの公式HPをチェック!
Contents
- 1 中学生が「暗記できない」と感じる本当の原因を整理する
- 2 成績が上がる3つのコツ(暗記が苦手でも結果が出る学習設計)
- 3 科目別:「中学生 暗記できない」を解決する具体的な方法
- 4 「中学生 記憶力 低い」と感じたときに読む章:記憶を定着させる方法
- 5 暗記が苦手な子の特徴と、今すぐ直せる行動リスト
- 6 中学生の勉強法:覚えられないときのリカバリー手順
- 7 高校受験を見据えた暗記戦略
- 8 保護者・教師ができるサポート
- 9 1週間で実感!効率の良い暗記法トレーニングプラン
- 10 中学生:暗記ができないに関するよくある質問【Q&A】
- 11 暗記ができない中学生におすすめ!タブレット学習教材
- 12 まとめ:中学生「暗記できない」を徹底解決!苦手を克服し成績が上がる3つのコツ
中学生が「暗記できない」と感じる本当の原因を整理する

多くの中学生が暗記に苦戦するのには、必ず理由があります。
中学生の「記憶力がない」という思い込みを打ち破り、なぜ今までの暗記法がうまくいかなかったのか、その本当の原因を一緒に見ていきましょう。
インプットとアウトプットのバランス、復習のタイミング、そして意外と見落としがちな心身の要因まで、多角的に分析していきます。
- 「記憶力が低いだけ」と思い込む誤解を解く
- インプット偏重(書いて覚えるだけ)でアウトプットが足りない
- 復習タイミングのミス(忘却曲線を無視している)
- 睡眠・集中環境・ストレスなど身体的・心理的要因
- 科目別特性を無視して同じ方法で覚えようとしている(社会・理科・英語)
「記憶力が低いだけ」と思い込む誤解を解く
「自分は記憶力が低いから、どうせ覚えられない」と感じていませんか?実は、これは大きな誤解です。
脳の機能に問題があるケースは稀で、多くの場合、記憶力が低いのではなく、正しい暗記の方法を知らないだけなのです。
人間は誰でも情報を記憶する力を持っています。
大切なのは、脳の仕組みに合った効率的な覚え方を知り、それを実践すること。
例えば、過去に私が指導した生徒の中には、「自分は頭が悪いから無理」と諦めかけていた生徒がいましたが、正しい方法を伝えただけで、見違えるように暗記ができるようになりました。
中学生の記憶力は、あなたが思っている以上に高い可能性を秘めているのです。

インプット偏重(書いて覚えるだけ)でアウトプットが足りない
多くの中学生が陥りがちなのが、教科書を読んだり、ノートをひたすら書いたりするだけのインプット偏重の勉強法です。
確かに書くことで一時的に覚えた気にはなりますが、これは脳に情報を「入力」しているだけに過ぎません。
本当に記憶を定着させるためには、入力した情報を「出力」するアウトプットの練習が不可欠です。
例えば、友達に説明してみる、自分でテスト問題を作って解いてみる、声に出して復習するなど、覚えたことを「使う」練習がなければ、知識はすぐに抜けていってしまいます。
かつて担当した生徒も、「書く」作業ばかりに時間を費やし、テストで全く点が取れないと悩んでいました。
アウトプットの重要性を伝えたところ、学習効率が劇的に向上し、成績も大幅にアップしました。
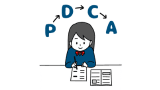
参考記事:【英語がわからない中学生】超簡単!ゼロから理解できる勉強法を解説
復習タイミングのミス(忘却曲線を無視している)
せっかく覚えたはずなのに、すぐに忘れてしまうのは、復習のタイミングが間違っているからかもしれません。
人間は覚えたことを時間と共に忘れていく生き物で、これを「忘却曲線」と呼びます。
多くの中学生が、一度覚えたら満足してしまい、忘れる前に復習するという視点が抜けています。
例えば、テスト前日に徹夜で詰め込んでも、一夜漬けの知識は数日でほとんど忘れてしまうでしょう。
これは、記憶が脳に定着する前に放置しているためです。
正しい復習のタイミングを知り、「忘れそうになった時にもう一度思い出す」習慣をつけることが、長期記憶への重要なカギとなります。
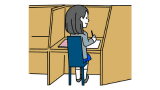
参考記事:高校受験の内申点を上げ方のコツをこれを読めばわかります!
睡眠・集中環境・ストレスなど身体的・心理的要因
暗記ができない原因は、勉強法だけではありません。
睡眠不足は、記憶の定着を妨げる最大の敵です。
脳は寝ている間にその日覚えた情報を整理し、定着させます。
散らかった部屋や騒がしい環境での勉強は、集中力を著しく低下させ、記憶効率を下げてしまいます。
「どうせ覚えられない」といったストレスやプレッシャーも、脳の働きを鈍らせる要因となります。
例えば、過去に担当した生徒で、真面目なのに伸び悩んでいた生徒がいました。
話を聞くと、夜遅くまでゲームをして寝不足、部屋も散らかり放題。
生活習慣を見直し、集中できる環境を整えただけで、勉強へのモチベーションが上がり、暗記もスムーズになったケースがあります。
心身の健康が、記憶力と直結していることを忘れないでください。
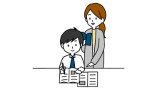
科目別特性を無視して同じ方法で覚えようとしている(社会・理科・英語)
社会、理科、英語など、暗記が必要な科目は多岐にわたりますが、それぞれの科目には独自の特性があります。
にもかかわらず、どの科目も「書いて覚える」など、同じ方法で学習していませんか?
例えば、歴史の年号は語呂合わせが有効でも、理科の実験手順を語呂合わせで覚えるのは非効率です。
英語の単語は発音や例文と一緒に覚えるのが効果的ですが、地理の地形を音だけで覚えようとしても難しいでしょう。
科目ごとの「覚えやすい」特性を理解し、それに合わせたアプローチを選ぶことが、暗記の効率を飛躍的に向上させる秘訣です。
かつて、私が担当した生徒で、どの科目も同じように暗記しようとして成績が伸び悩んでいた生徒がいました。
科目ごとに暗記法を変えるアドバイスをしたところ、それぞれの科目の点数が着実に上がり始めました。
成績が上がる3つのコツ(暗記が苦手でも結果が出る学習設計)
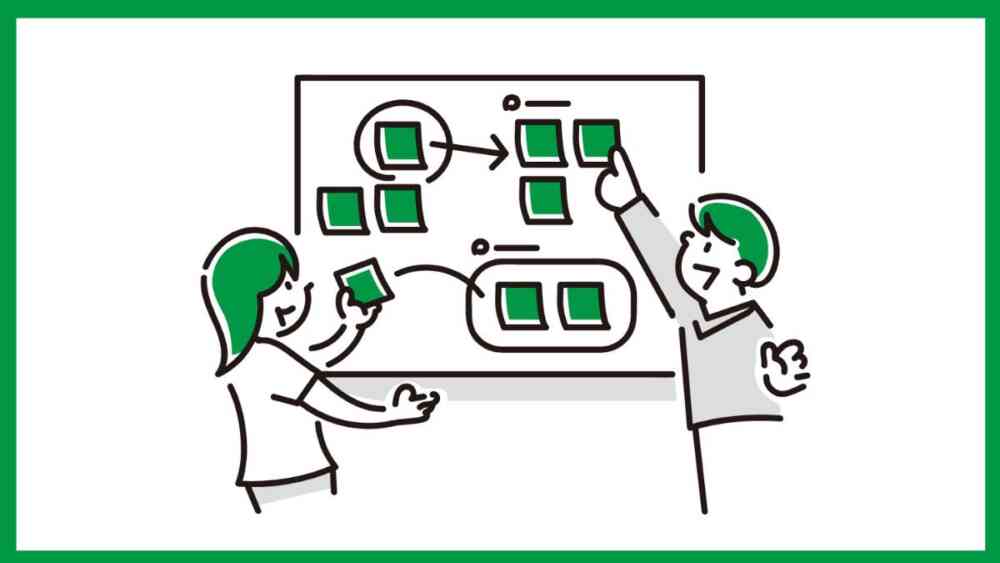
「暗記できない」という悩みを解消し、成績を上げるためには、単に「頑張る」だけでなく、「正しい努力」をするための学習設計が重要です。
ここでは、私が長年の指導経験から編み出した、暗記が苦手な中学生でも確実に結果を出せる3つの学習設計のコツをお伝えします。
この3つのコツを実践すれば、あなたの暗記力は劇的に変化するでしょう。
- コツ1:理解→整理→アウトプットの順番で覚える
- コツ2:分散復習とテスト化で「覚えたつもり」をなくす
- コツ3:五感とストーリーで記憶のフックを作る
コツ1:理解→整理→アウトプットの順番で覚える
暗記の第一歩は、「理解すること」です。
ただの文字の羅列として覚えるのではなく、その用語や事柄が持つ意味、背景、他の情報との繋がりを理解することから始めましょう。
理解することで、情報は脳の中でバラバラにならず、知識として整理されやすくなります。
理解・整理した情報を「自分の言葉で表現する」というアウトプットのステップへ進むことで、記憶がさらに強固になります。
例えば、歴史の出来事を覚えるなら、その事件が「なぜ起きたのか」「誰が関わったのか」「結果どうなったのか」というストーリーとして理解し、その後に自分で説明してみる、という流れです。
自分の言葉で説明する・要約する・人に教える
覚えたことを「自分の言葉で説明する」「要約する」「人に教える」というアウトプットは、最も効果的な暗記法の一つです。
曖昧な理解を明確にするだけでなく、脳内で情報を整理し直す作業になるため、記憶の定着率が格段に上がります。
かつて指導した生徒で、暗記が苦手だった生徒がいました。
その生徒は私が教えたことを、毎日弟に説明する練習をしたところ、自分でも驚くほど知識が定着し、定期テストの社会の点数が20点もアップしました。
声に出して説明することで、耳からも情報が入り、記憶の定層が厚くなります。
家族や友達、あるいは架空の誰かでも構いません。声に出して説明する習慣をつけてみましょう。
問題演習を “確認テスト化” して即時フィードバック
問題演習は、単に「合っているか間違っているか」を確認する場ではありません。
「自分がどこまで覚えられているか」を確認する「テストの場」として活用しましょう。
間違えた問題や、少しでも曖昧だった知識は、すぐに教科書や参考書に戻って確認し、理解し直すことが重要です。
この「即時フィードバック」こそが、記憶を強化する鍵となります。
例えば、単語帳を使って英単語を覚える際、ただ意味を隠して確認するだけでなく、その単語を使った簡単な英作文を頭の中で作ってみるなど、アウトプットの要素を取り入れると効果的です。
間違えた問題に印をつけ、後で集中して復習する習慣をつけましょう。

コツ2:分散復習とテスト化で「覚えたつもり」をなくす
人間の記憶は、時間とともに薄れていくのが自然です。
「忘却曲線」という仕組みに逆らって、効率的に記憶を定着させるためには、「分散復習」と「テスト化」が不可欠です。
一度にまとめて長時間復習するよりも、短時間でも良いので、間隔を空けて繰り返し復習する方が、記憶ははるかに定着しやすくなります。
そして、「覚えたつもり」を防ぐためには、定期的に自分自身にテストを課すことが重要です。
1日・3日・7日・14日の復習スケジュール
効率的な分散復習には、「1日後、3日後、7日後、14日後」という具体的な復習スケジュールを設定するのがおすすめです。
例えば、今日覚えた単元は、明日、3日後、1週間後、2週間後に必ず復習する計画を立ててみましょう。
このタイミングで復習することで、忘れかけていた情報を脳に再度インプットし、記憶を強化することができます。
かつて私が担当した、計画的な学習が苦手な生徒がいました。その生徒にこの復習スケジュールを提案し、毎日小さな復習を習慣づけたところ、長期記憶として知識が定着するようになり、テスト前も焦らずに済むようになりました。
最初から完璧を目指す必要はありません。
まずは1日後の復習からでも始めてみてください。
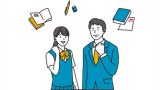
ミニテスト&エラーノートで弱点を可視化する
「覚えたつもり」になっていないかを確認するために、自分でミニテストを作成したり、問題集をテストとして活用したりする習慣をつけましょう。
そこで間違えた問題や曖昧だった知識は、必ず「エラーノート」にまとめてください。
このエラーノートは、あなたの弱点を可視化する最強のツールです。
テスト前にこのノートを見直すだけで、効率的に苦手分野を克服できます。
例えば、歴史のテストで間違えた年号や出来事を、エラーノートに赤字で書き出し、その原因や関連事項を青字で追記するといった工夫を凝らしましょう。
同じ間違いを繰り返すことを防ぎ、効率的に成績を上げることができます。
コツ3:五感とストーリーで記憶のフックを作る
暗記が苦手な生徒の多くは、文字や数字を「ただの記号」として捉えがちです。
人間の脳は、五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)や感情、ストーリーと結びついた情報をより強く記憶します。
五感を活用し、覚える内容に「フック」を作ることで、記憶への定着率は格段に上がります。
音読・図解・マインドマップ・語呂合わせの使い分け
暗記には様々な方法があり、それぞれの内容やあなたの得意な感覚に合わせて使い分けることが重要です。
- 音読:目で見て、声に出して、耳で聞くことで、脳の複数の領域が刺激され、記憶に残りやすくなります。特に英単語や歴史の用語に有効です。
- 図解・マインドマップ:情報を視覚的に整理することで、全体の繋がりや構造が把握しやすくなります。理科の仕組みや社会の地理、公民の制度などに特に効果的です。自分で絵を描いたり、色分けしたりすることで、さらに記憶にフックが生まれます。
- 語呂合わせ:複雑な数字や羅列を、意味のある短いフレーズに変えることで、記憶しやすくなります。歴史の年号や、化学の元素記号などに応用できます。自分で語呂合わせを考えるプロセス自体が、記憶を強化します。
例えば、、社会の歴史で「1192年 鎌倉幕府成立」を覚えるなら、定番の「いい国(1192)作ろう鎌倉幕府」と声に出して読んでみましょう。
このとき、鎌倉幕府がどんな時代だったか、頭の中でイメージしながら音読すると、より記憶に残りやすくなりますよ。
関連づけ(原因・結果・比較)で“理解して覚える”に変える
ただ単語や年号を覚えるのではなく、「なぜそれが起こったのか(原因)」「その結果どうなったのか」「他の事柄とどう違うのか(比較)」といった、関連性を持たせて覚えるようにしましょう。
脳は、バラバラの情報よりも、繋がりのある情報の方が記憶しやすいからです。
例えば、地理で日本の各地域の特産品を覚える際、「なぜこの地域でこの野菜が有名なのか?(気候や地形)」と原因を考えてみたり、社会で異なる時代の改革を覚える際に、それぞれの改革の目的や内容、結果を比較する表を作ってみたりするのも有効です。
【比較表の例:歴史上の改革】
| 改革名 | 時代(年代) | 目的 | 主な内容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大化の改新 | 飛鳥時代(645年) | 天皇中心の国家形成 | 公地公民制、班田収授法、租庸調など | 中央集権国家の基礎を築く |
| 享保の改革 | 江戸時代(1716年〜) | 幕府財政の立て直し、社会秩序の安定 | 上げ米の制、質素倹約令、公事方御定書など | 一時的に幕府財政が好転 |
| 寛政の改革 | 江戸時代(1787年〜) | 幕府財政再建、風紀の立て直し | 倹約令、異学の禁、棄捐令、人足寄場など | 庶民の反発を招き、短期間で終わる |
| 天保の改革 | 江戸時代(1841年〜) | 幕府財政再建、農村復興 | 上知令、株仲間の解散、人返しの法など | 失敗に終わり、幕府の権威が失墜 |
情報を整理し、関連付けて覚えることで、知識が点ではなく線になり、忘れにくくなります。
科目別:「中学生 暗記できない」を解決する具体的な方法
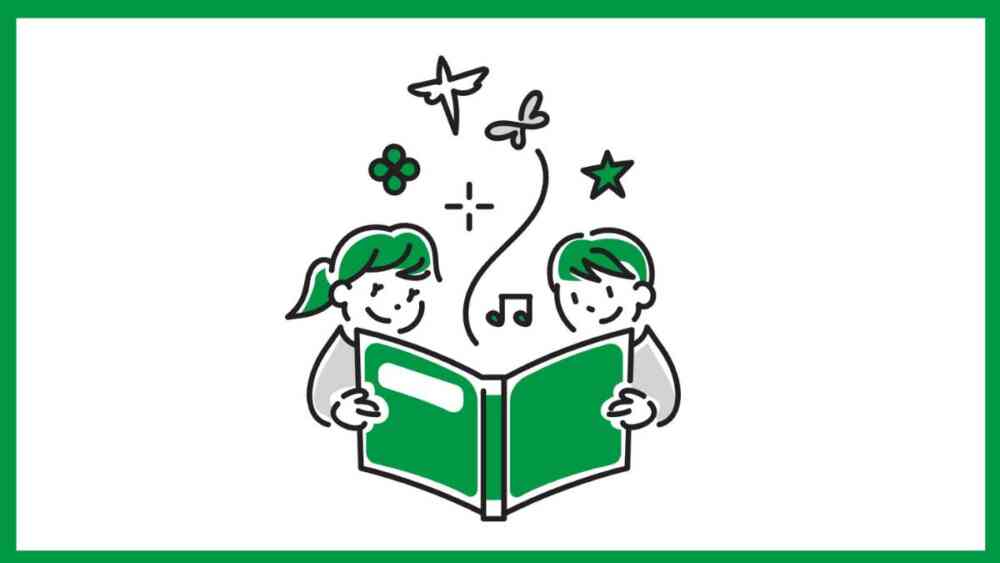
社会、理科、英語、国語と、中学生が暗記に苦戦する科目は多岐にわたります。
それぞれの科目には独自の性質があり、その特性に合わせた暗記法を用いることが、効率的に成績を上げる秘訣です。
ここでは、各科目の「暗記できない」を解決するための、具体的なアプローチをご紹介します。
- 社会が覚えられない中学生向けの覚え方(地図・年表・ストーリー化)
- 理科が覚えられない中学生向けの覚え方(図解・現象の因果関係で理解)
- 英語が覚えられない中学生向けの覚え方(英単語は音・例文・チャンクで)
- 国語(漢字・古文単語)を効率よく暗記するルーティン
社会が覚えられない中学生向けの覚え方(地図・年表・ストーリー化)
社会科は、歴史、地理、公民と広範囲にわたりますが、丸暗記では限界があります。
| 教科 | 効果的な覚え方・工夫 | 補足・具体例 |
|---|---|---|
| 歴史 | 出来事を「物語」として捉える | 「誰が・いつ・どこで・何を・なぜ・どうなったか」の流れで理解する/年号は語呂合わせ、人物は相関図で整理/歴史漫画で人物の気持ちを想像させると理解が深まる |
| 地理 | 地図を使ったビジュアル学習 | 白地図に地形・都市・特産品・気候などを書き込み、色分けする/なぜその地域にその産業があるのかを理由と関連付けて覚える |
| 公民 | 身近な出来事と関連付けて覚える | ニュースの話題と教科書の内容を結びつけて「生きた情報」として記憶に残す |

理科が覚えられない中学生向けの覚え方(図解・現象の因果関係で理解)
理科の暗記は、用語や法則だけでなく、その現象が「なぜ起きるのか」「どういう仕組みなのか」という因果関係を理解することが重要です。
| 学習法 | 内容・工夫 | 具体例・ポイント |
|---|---|---|
| 図解を活用する | 自分で図を描くことで、視覚的に理解しやすくなり記憶にも残る | 消化の仕組み → 消化器官のイラストを描き、各器官の働きを書き込む |
| 現象と結びつける | 用語だけでなく、実際の現象やプロセスと関連づけて覚える | 光合成 → 植物が光・水・二酸化炭素からデンプンと酸素を作る流れをイメージ/実験結果の予測や理由の説明も効果的 |
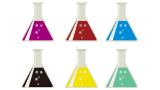
英語が覚えられない中学生向けの覚え方(英単語は音・例文・チャンクで)
英語の暗記は、単語だけでなく、音や使い方、文の構造と一緒に覚えることが大切です。
| 学習法 | 内容・工夫 | 具体例・ポイント |
|---|---|---|
| 単語は「音」と「例文」で覚える | スペル・意味だけでなく、発音と一緒に覚えることで記憶が定着しやすくなる | 声に出して繰り返し発音/例文や教科書の文章で使い方も一緒に覚える/単語をチャンク(意味のまとまり)で覚えると効率的 |
| リスニング・スピーキングを取り入れる | 聞く・話すを取り入れて、単語やフレーズを「使える知識」にする | シャドーイング/簡単な英文を作って話す練習/例文の音読を毎日継続することでテスト成績が向上した実例あり |
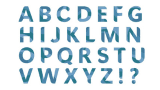
参考記事:英語の成績(点数)を上げる方法中学生編│英語の成績が悪くても諦めるな!
国語(漢字・古文単語)を効率よく暗記するルーティン
国語の暗記も、効率的なルーティンを取り入れることで得意になります。
| 学習対象 | 効果的な覚え方・工夫 | 具体例・ポイント |
|---|---|---|
| 漢字 | 書くだけでなく、部首や意味、熟語の中で覚える/同音異義語・形が似た漢字を比較する | 「訂正」と「改訂」など、使い方の違いに注目/読み書きテストを繰り返す/意味を理解して覚えると効率アップ |
| 古文単語 | 意味だけでなく文脈の中で覚える/古典常識と一緒に理解することで記憶に残る | 現代語訳の例文と一緒に暗記/背景知識があるとニュアンスが理解しやすく、読解力も向上 |
「中学生 記憶力 低い」と感じたときに読む章:記憶を定着させる方法

「自分は記憶力が低いんじゃないか」と感じる中学生は少なくありません。
それは決してあなたの能力の問題ではありません。
記憶は才能ではなく、誰にでもできる「技術」です。
ここでは、脳の仕組みを理解し、効率的に記憶を定着させるための具体的な方法をお伝えします。
- 忘却曲線に合わせた反復設計と短時間多回数学習
- 30秒アウトプットとスキマ時間活用(アプリ・単語カード)
- 睡眠・運動・食事が記憶定着に与える影響
忘却曲線に合わせた反復設計と短時間多回数学習
人間が覚えた情報を忘れていく「忘却曲線」というグラフをご存知でしょうか?
この忘却曲線を意識した「反復設計」こそが、記憶力アップの鍵を握ります。
一度に長時間勉強するよりも、短時間でも良いので、何度も繰り返し復習する「短時間多回数学習」の方が、記憶の定着にはるかに効果的です。
例えば、通学中の電車の中で5分間だけ英単語を復習する、寝る前に10分だけ今日の社会の要点を見直すなど、細切れの時間を有効活用しましょう。
「忘れる前に復習する」ことが、長期記憶への道を切り開きます。
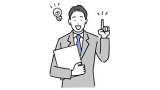
30秒アウトプットとスキマ時間活用(アプリ・単語カード)
「覚えたつもり」を防ぎ、記憶を定着させるには、積極的にアウトプットする習慣が不可欠です。
例えば、参考書を読み終えたら、目を閉じて30秒間で覚えた内容を頭の中で復唱する「30秒アウトプット」を試してみてください。
声に出して説明するのも良いでしょう。
曖昧な知識が明確になります。
通学中や休み時間、食事の待ち時間など、ちょっとした「スキマ時間」も暗記のチャンスです。
スマートフォンアプリや自作の単語カード、一問一答形式の参考書などを活用し、手軽にアウトプットできる環境を整えましょう。
【暗記ツール比較表】
| ツール名 | 特徴 | おすすめの科目/用途 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 単語カード | 手軽に持ち運べ、裏表で確認できる | 英単語、社会の用語、理科の記号など | 作成することで記憶定着/手軽に持ち運べる | 量が多いと管理が大変/なくしやすい |
| 学習アプリ | ゲーム感覚で学べる/自動で復習タイミングを管理 | 英単語、一問一答、歴史の年号など | 移動中にも学習可能/進捗管理が容易/音声機能あり | スマートフォン依存/課金が必要な場合あり |
| 一問一答形式の問題集 | 基礎知識の定着に特化 | 社会、理科の用語、国語の漢字、英単語など | 効率的な知識確認/短時間で多くの問題に触れられる | 応用問題対策には不向き |
| 白地図・年表 | 視覚的に情報を整理 | 地理(地形・特産品)、歴史(出来事の流れ) | 全体像の把握ができる/関連付けして記憶しやすい | 持ち運びには不便/書き込みに時間がかかる |
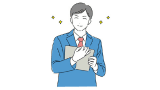
睡眠・運動・食事が記憶定着に与える影響
意外に思われるかもしれませんが、睡眠、適度な運動、そしてバランスの取れた食事は、記憶力と密接に関わっています。
| 項目 | 内容・効果 | 補足・具体例 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 記憶の定着に不可欠。脳は睡眠中に情報を整理して長期記憶に変える | 7〜8時間の質の良い睡眠が必要/短時間学習でも定着度アップ/睡眠不足で成績が伸び悩むケースあり |
| 運動 | 血流を促進し、脳の働きを活性化。集中力アップにも効果的 | 軽いジョギングやストレッチで気分転換にもなる/脳細胞の成長を促すと言われている |
| 食事 | 脳のエネルギー源となる栄養を摂ることが重要 | DHA、不飽和脂肪酸、ビタミン、ミネラルなどを意識的に摂取する/バランスの良い食事が基本 |
中学生の生活習慣は、直接的に勉強している時間ではないかもしれませんが、記憶の土台を築く上で欠かせない要素です。
暗記が苦手な子の特徴と、今すぐ直せる行動リスト

暗記が苦手だと感じている中学生には、共通して見られる特徴があります。
もし、あなたが以下の行動に心当たりがあるなら、それは暗記ができない「原因」かもしれません。
しかし、心配はいりません。
これらの行動は、今すぐにでも直すことができます。
ここからは、具体的なNG行動とその改善策をリスト形式でご紹介します。
- ノートまとめに時間をかけすぎる
- 問題演習を後回しにしてしまう
- 一気に詰め込んで長期間復習しない
- 「できない原因」を記録せず毎回同じ失敗を繰り返す
ノートまとめに時間をかけすぎる
あなたは、教科書の内容をカラフルなペンで丁寧に書き写したり、イラストをたくさん描いたりして、「綺麗なまとめノート」を作ることに時間を費やしていませんか?
確かに綺麗なノートは達成感があり、見た目も良いですが、肝心なのは「覚える」ことです。
ノート作りが目的になってしまい、知識をインプットするだけでアウトプットの時間が不足していると、暗記はなかなか定着しません。
【今すぐ直せる行動リスト】
- ノートは「覚えるためのツール」と割り切る: 完璧を目指さず、重要なポイントだけを簡潔にまとめる。
- 余白を多めに残す: 後からアウトプットした内容や疑問点を書き込めるようにする。
- 参考書をメインに活用する: 市販の分かりやすい参考書でインプットし、ノートは補助的に使う。

問題演習を後回しにしてしまう
教科書を読み終えたり、ノートをまとめ終わったりすると、そこで満足してしまい、問題集を解くことを後回しにしていませんか?
これは、「覚えたつもり」で終わってしまう典型的なパターンです。
前述したように、インプットした知識はアウトプットすることで初めて脳に定着します。
問題演習は、「本当に覚えられているか」を確認する、最も効果的なアウトプットの場です。
かつて担当した生徒で、「問題集は答えが丸見えになるから意味がない」と敬遠していた生徒がいました。
その生徒に「答えを隠して、テストだと思って解く」ことを徹底させたところ、自分の理解度を正確に把握できるようになり、驚くほど成績が伸びました。

一気に詰め込んで長期間復習しない
テスト前日に一夜漬けで頑張るものの、テストが終わるとすぐに内容を忘れてしまう。
これは、知識を短期記憶のまま放置している証拠です。
人間は、一気に大量の情報を詰め込んでも、その多くはすぐに忘れてしまいます。
一度覚えたら、次のテストまで全く復習しないというのも、暗記が苦手な中学生によく見られるパターンです。
知識を長期記憶として定着させるためには、計画的な「分散復習」が不可欠です。
【今すぐ直せる行動リスト】
- 「寝る前の10分」を復習に当てる: 睡眠中に記憶が整理されるゴールデンタイムを活用する。
- 「週末に一週間の復習」をルーティン化する: 短時間でも良いので、定期的に触れる習慣をつける。
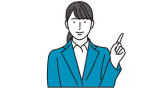
「できない原因」を記録せず毎回同じ失敗を繰り返す
暗記がうまくいかない時に、「なぜ覚えられなかったのか」を分析せず、ただ漠然と同じ方法を繰り返していませんか?
これでは、いつまで経っても同じ間違いを繰り返してしまいます。
例えば、「歴史の年号が覚えられない」という悩みを抱えていても、その原因が「語呂合わせを使っていないから」なのか、「復習が足りないから」なのか、「背景を理解していないから」なのかを特定しなければ、効果的な対策は打てません。
自分の「できない原因」を記録し、改善策を考える習慣をつけましょう。
【今すぐ直せる行動リスト】
- 「エラーノート」を作る: 間違えた問題だけでなく、なぜ間違えたのか、どうすれば覚えられたのかを記録する。
- 「勉強ログ」をつける: どのくらいの時間、何を、どんな方法で勉強したかを記録し、効果を検証する。
中学生の勉強法:覚えられないときのリカバリー手順
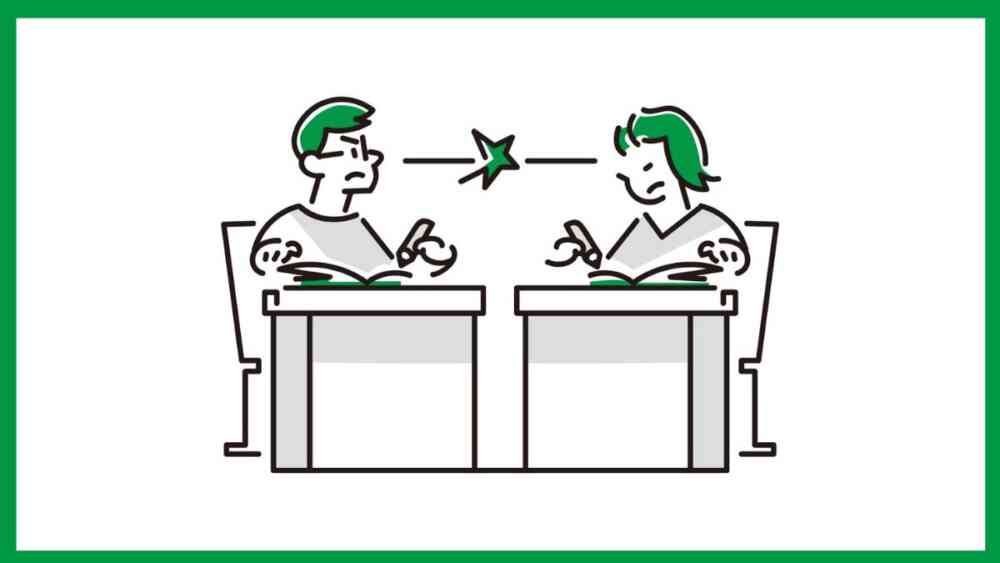
一生懸命勉強しているのに、なかなか覚えられない…そんな時は、焦らずに「リカバリー手順」を踏むことが大切です。
闇雲に勉強を続けるのではなく、一度立ち止まって、「なぜ覚えられないのか」を分析し、効率的な軌道修正を行うことで、停滞していた成績を再び引き上げることができます。
- どこでつまずいたかを特定するエラーノート術
- 理解不足を洗い出す“逆引き学習”の進め方
- 2週間で効果が出なければ学習法を切り替える判断基準
どこでつまずいたかを特定するエラーノート術
暗記がうまくいかないと感じたら、まずは「どこで、なぜ、つまずいたのか」を具体的に特定することが重要です。
そのために役立つのが、先ほども触れた「エラーノート」です。
- テストや問題集で間違えた問題だけでなく、少しでも曖昧だった知識も記録する。
- 単に正解を書き写すだけでなく、「なぜ間違えたのか(理由)」「正しい答え(復習)」「次にどうすれば覚えられるか(対策)」までを記録する。
例えば、社会のテストで「江戸三大改革の名前を全て書け」という問題で「寛政の改革」だけ思い出せなかった場合、エラーノートに「寛政の改革が抜けた。享保・寛政・天保の順序が曖昧だった」と書き、「それぞれの改革の開始年と、担当した人物、具体的な内容を比較表でまとめて覚える」と対策を記入します。
この作業を繰り返すことで、自分の弱点が明確になり、無駄のない効率的な復習が可能になります。

理解不足を洗い出す“逆引き学習”の進め方
「覚えられない」原因が、そもそも「理解不足」にあるケースも少なくありません。
そんな時に有効なのが「逆引き学習」です。
これは、問題集や過去問で間違えた箇所から、教科書や参考書の該当ページに戻り、その周辺知識も含めて深く理解し直すという学習法です。
- 例えば、理科の問題で「水に溶けたアンモニアの性質」が分からなかった場合、単に答えを覚えるだけでなく、教科書のアンモニアの章全体を読み返し、性質、発生方法、用途などを総合的に理解し直します。
- さらに、「なぜ水に溶かすとアルカリ性になるのか?」といった「なぜ?」を掘り下げていくことで、表面的な暗記ではなく、深い理解に基づいた記憶へと繋がります。
この逆引き学習を習慣にすることで、断片的な知識が繋がり、全体像が見えるようになるため、「覚えたはずなのに使えない」という状態を解消できます。

2週間で効果が出なければ学習法を切り替える判断基準
新しい暗記法や勉強法を試しても、すぐに効果が出ないと感じることもあるでしょう。
しかい、そこで諦めてしまうのはもったいないことです。
まず「2週間」は一つの方法を継続してみてください。脳が新しい学習法に慣れるまでには、ある程度の時間が必要です。
- 2週間試しても、全く改善が見られない場合:その方法があなたに合っていない可能性が高いので、別の方法を試すサインだと考えましょう。
- 少しでも手応えを感じた場合:そのまま継続し、さらに工夫を加えてみてください。
私が個別指導塾で生徒を指導する際も、まずは1つの方法を試してもらい、2週間後の学習効果を一緒に検証していました。
自分に合った勉強法を見つけるまでには、試行錯誤が必要です。
大切なのは、「自分はできない」と諦めるのではなく、「より良い方法」を探し続けることです。
高校受験を見据えた暗記戦略

高校受験は、中学3年間の膨大な知識が問われるため、計画的な暗記戦略が不可欠です。
特に社会や理科、英語などの暗記科目は、合否を分ける重要なポイントとなります。
「中学生 暗記 できない 高校受験」と悩むあなたも、今から正しい戦略を立てることで、志望校合格に大きく近づけます。
- 内申対策:定期テストで点を落とさない暗記計画
- 入試直前期:頻出範囲の優先順位付けと高速回転復習
- 過去問分析で「出題頻度×苦手度」で学習配分を最適化
内申対策:定期テストで点を落とさない暗記計画
高校受験では、日頃の定期テストの成績(内申点)も非常に重要です。
内申対策の暗記計画の基本は、「忘れさせないこと」。
- 授業内容はその日のうちに復習: 新しい知識はその日のうちに軽く復習することで、短期記憶から長期記憶への移行を促します。
- 例:授業後5分で教科書とノートを見返す。
- テスト範囲を細分化し、計画的に暗記を進める: テスト2週間前から計画を立て、毎日少しずつ暗記を進めましょう。一度に詰め込まず、前述の「分散復習」を取り入れることで、知識の定着を図ります。
- 例えば、社会の歴史なら、1日1章ずつ用語と流れを覚え、週末に確認テストをする、といった具合です。
- 「定期テスト予想問題」を徹底活用: 多くの塾や参考書にある予想問題を解き、出やすい傾向を掴んで重点的に暗記しましょう。
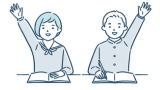
入試直前期:頻出範囲の優先順位付けと高速回転復習
入試直前期は、全ての範囲を完璧に覚える時間はありません。
「頻出範囲の優先順位付け」と「高速回転復習」が鍵となります。
- 過去問分析で頻出分野を特定: 志望校の過去問を徹底的に分析し、よく出題される分野や単元を特定しましょう。
- 苦手分野と頻出分野のクロス確認: あなたが「暗記できない」と感じる分野と、頻出分野が重なる場合は、最優先で対策が必要です。
- 高速回転復習: 完璧を目指すのではなく、「これだけは間違えない」という基礎知識を短時間で何度も回す復習方法です。
例えば、社会の一問一答を1日200問、英語の単語帳を1日100単語など、量をこなしながらスピードを上げていきます。
「わかった」と感じたらすぐに次の問題へ進み、間違えた問題だけに集中するのがポイントです。
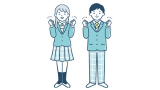
過去問分析で「出題頻度×苦手度」で学習配分を最適化
過去問分析は、志望校合格への羅針盤です。
単に問題を解くだけでなく、「出題頻度」と「あなたの苦手度」をかけ合わせて、学習配分を最適化しましょう。
- 出題頻度が高い×苦手度が高い分野: 最優先で徹底的に対策します。時間をかけてでも克服すべき分野です。
- 出題頻度が高い×苦手度が低い分野: 高得点を狙える分野なので、定期的な復習で維持しましょう。
- 出題頻度が低い×苦手度が高い分野: 時間に余裕があれば手をつける程度に留め、無理に深入りしないのが賢明です。
- 出題頻度が低い×苦手度が低い分野: ほぼ対策不要ですが、基礎的な確認は怠らないようにしましょう。
例えば、私が指導した高校受験生で、社会の歴史は得意でも地理が苦手という生徒がいました。
過去問を分析すると、志望校は歴史の配点が高く、地理の頻出分野は限定的だと判明。
そこで、歴史は維持しつつ、地理は頻出の分野に絞って重点的に対策させることで、効率的に合格に導くことができました。
「選択と集中」が合格への近道です。
保護者・教師ができるサポート
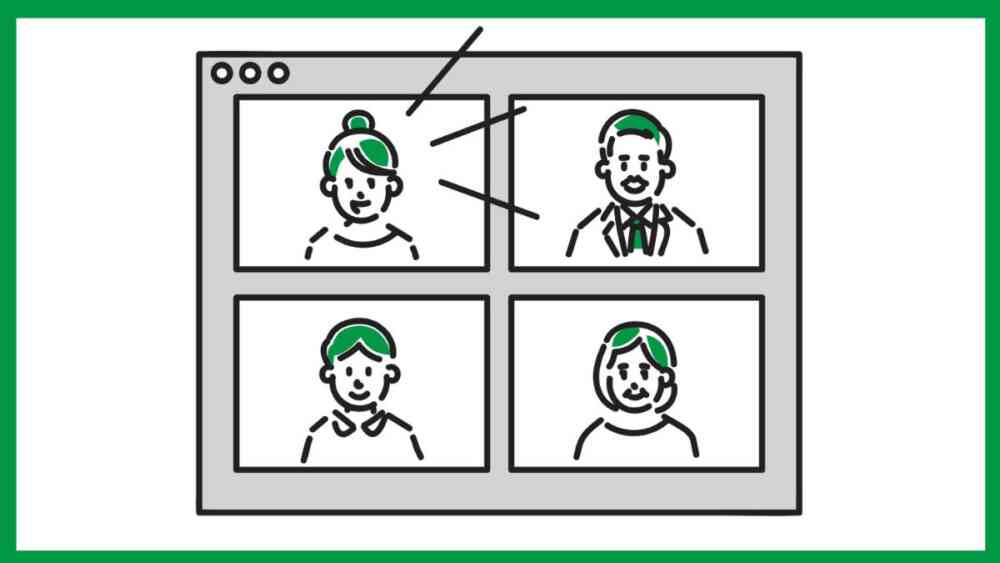
「中学生が暗記できない」という悩みを抱えているのは、生徒本人だけではありません。
保護者の方や学校・塾の先生もまた、「どうサポートすれば良いのか」と悩んでいらっしゃることでしょう。
ここでは、長年の指導経験を持つ私が、保護者や教師の皆様に明日からでも実践できる具体的なサポート方法をお伝えします。
- 「努力不足」ではなく「方法」を変える声かけ
- 学習ログ・復習スケジュールの見える化と伴走
- ミニテストでアウトプットを促す仕組みづくり
「努力不足」ではなく「方法」を変える声かけ
お子様が暗記で苦戦している時、つい「もっと努力しなさい」「ちゃんとやりなさい」と言ってしまっていませんか?
しかし、それはお子様をさらに追い詰めてしまう可能性があります。
多くの場合、中学生は「努力していない」のではなく、「努力の仕方が間違っている」だけなのです。
- 「なんで覚えられないの?」ではなく「どうしたら覚えられるか一緒に考えよう」と問いかける。
- 「努力不足」と決めつけず、「君に合った暗記法がまだ見つかっていないだけ」と伝える。
例えば、私が教室長時代に接した保護者の方々にも、まずは「お子さんの努力を認め、方法に焦点を当てること」を一番にお伝えしていました。
具体的な声かけとしては、「この前の勉強、頑張っていたね!でも、もしかしたらもっと効率の良い覚え方があるかもしれないから、一緒に探してみない?」といったポジティブな言葉がけが効果的です。

学習ログ・復習スケジュールの見える化と伴走
中学生が「何を」「いつ」「どれくらい」勉強したのか、そして「いつ復習するべきか」を「見える化」するサポートは、非常に有効です。
- 学習ログの作成: 毎日、何を何分勉強したか、簡単な記録をつけさせる。親子で共有できるアプリなどを活用するのも良いでしょう。
- 復習スケジュールの共有: 「1日後、3日後、7日後、14日後」といった復習のタイミングをカレンダーやシートで一緒に管理し、リマインドしてあげる。
かつて私が指導した生徒の保護者の方に、この学習ログと復習スケジュールを導入していただいたところ、お子様が自律的に勉強に取り組むようになり、保護者の方も安心して見守れるようになったという成功事例があります。
ただし、親が全てを管理するのではなく、あくまで「伴走者」として、お子様自身が主体的に計画を立てられるようにサポートする姿勢が大切です。

ミニテストでアウトプットを促す仕組みづくり
家庭学習で最も不足しがちなのが「アウトプット」です。
保護者の方が、お子様が覚えた内容をアウトプットできる仕組みを作ってあげましょう。
- 口頭でのミニテスト: 食卓で「今日の歴史で一番大事な出来事は何?」など、簡単なクイズ形式で問いかける。
- 単語カードや一問一答アプリの活用を促す: 「これやってみてどうだった?」と、使ったツールの感想を聞いてあげるだけでも効果があります。
- 「ママ(パパ)に説明してみて」と促す: 教えることで理解が深まる効果(プルトン効果)を活用します。
例えば、夕食の準備中に「今日の理科で習ったマグマって何?」と質問してみるだけでも、子どもは覚えたことを頭の中で整理しようとします。
定期的にアウトプットの機会を作ることで、「覚えたつもり」を防ぎ、知識の定着を促すことができます。
ただし、テスト形式にこだわりすぎず、「楽しく知識を確認する場」として設定することが重要です。
1週間で実感!効率の良い暗記法トレーニングプラン

「中学生 暗記できない」と悩むあなたも、今日から「できる!」を実感できるはずです。
ここでは、私が塾の現場で実際に指導していた、「1週間で効果を実感し、3週間で定着させる」ための具体的な暗記法トレーニングプランをご紹介します。
この計画に沿って毎日コツコツ取り組めば、あなたの暗記力は見違えるように向上し、「暗記が得意」だと自信を持って言えるようになるでしょう。
- Day1〜Day7の具体メニュー設計
- 3週間で定着を完成させる復習テンプレート
Day1〜Day7の具体メニュー設計
まずは最初の1週間で、暗記の基礎となる習慣を身につけていきましょう。
ここでは、社会の歴史(例:江戸時代)をテーマに具体例を示します。
| Day | 朝(10分) | 昼(5分) | 夜(20分) |
|---|---|---|---|
| Day1 | 前日分の復習(あれば) | なし | 江戸時代の流れをざっくりインプット(年表・出来事・将軍の在位などの全体像を図解で確認) |
| Day2 | 江戸時代の基礎復習(徳川家と将軍名、封建制度の特徴など) | なし | 享保の改革を詳しく学習(背景、内容:上げ米の制、公事方御定書など、目的と成果も整理) |
| Day3 | Day1・2の内容の口頭テスト(家族・友達に出してもらう) | なし | 寛政の改革を詳しく学習(背景、内容:倹約令、異学の禁など、結果と民衆の反応もセットで理解) |
| Day4 | Day1〜3の主要キーワードを確認(改革名・人物・用語) | なし | 3つの改革をまとめた一問一答形式の演習(享保・寛政の比較を中心に) |
| Day5 | 間違えた用語や年号だけをピックアップして再確認 | なし | 天保の改革を詳しく学習(背景、内容:株仲間の解散、人返しの法など、改革の失敗原因も分析) |
| Day6 | 1〜5日目の内容をざっと通読・図解を見返す | なし | 江戸三大改革の総まとめミニテスト(自作 or 問題集/並べ替え・正誤問題などを含める) |
| Day7 | Day6でミスしたポイントを重点復習 | 来週に学ぶ範囲(明治時代など)をざっくりチェック | 1週間の江戸時代まとめノートを作成/「なぜ改革が続いたのか」など自分の言葉で説明してみる |
ポイント
- 新しい知識のインプットと、過去の復習をバランス良く組み合わせる。
- 毎日「アウトプット」の機会を作る。
- 短い時間でも毎日続けることを最優先にする。
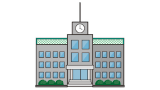
3週間で定着を完成させる復習テンプレート
1週間のトレーニングで基礎を固めたら、次の2週間で記憶の定着をさらに確固たるものにしていきます。
合計3週間で、学んだ知識を長期記憶として脳に刻み込むことを目指しましょう。
| 週 | 復習頻度と内容 |
|---|---|
| 1週目 | 毎日復習:新しく学んだ内容を、その日のうち・翌日・3日後に細かく復習(Day1〜Day7の計画に沿って実施)。アウトプット(音読・テスト・説明など)を重視する。 |
| 2週目 | 週2〜3回の復習:1週目の内容を全体的に復習。ミニテストやエラーノートを活用し、理解が曖昧な箇所を重点的に克服する。 |
| 3週目 | 週1回の総復習:過去2週間で学んだ内容を1回でまとめて復習。問題集・過去問など実戦形式で取り組み、知識の定着度をチェックする。この時期には自信がついてくる。 |
このテンプレートに沿って復習を続けると、記憶が脳に定着するだけでなく、復習の効率自体も上がっていきます。
最初はこのスケジュールを守るのが大変に感じるかもしれませんが、慣れてくれば自然とできるようになります。
継続は力なり、この言葉を胸に頑張ってみてください。
中学生:暗記ができないに関するよくある質問【Q&A】

中学生の皆さんや保護者の方からよく寄せられる「暗記できない」に関する疑問にお答えします。
あなたが抱える疑問も、ここにあるかもしれませんね。
- 中学生で勉強できない子の特徴は?
- 暗記ができないのはなぜですか?
- 中学生は1日何時間勉強する?
- 中学生が記憶力を上げる方法はありますか?
- 何回繰り返せば覚えられますか?
- 書かない暗記法でも本当に大丈夫ですか?
- 記憶力を上げるトレーニングや習慣はありますか?
- [部活が忙しくても続けられる暗記法は?
中学生で勉強できない子の特徴は?
「勉強できない子」という表現は適切ではありませんが、勉強でつまずきやすい中学生にはいくつかの共通した特徴が見られます。
- 勉強法が確立されていない: 漫然と教科書を読むだけ、ノートをまとめるだけで満足してしまう。
- 目標が不明確: 何のために、何を、いつまでに覚えるのかが曖昧。
- 自己管理が苦手: 計画を立てられない、誘惑に弱い、集中が続かない。
- 「なぜ?」を追求しない: 表面的な理解で満足し、根本的な原因や仕組みを理解しようとしない。
- アウトプットが不足している: 問題を解く、人に説明するなど、覚えた知識を使う練習が足りない。
これらの特徴は「治せない」ものではありません。
正しい方法とサポートがあれば、誰でも変わることができます。

暗記ができないのはなぜですか?
暗記ができない主な理由は、あなたの「記憶力」に問題があるのではなく、脳の仕組みに合わない方法で暗記しようとしているからです。
具体的には、
- 意味を理解せずに丸暗記しようとしている(電話帳を覚えるようなもの)
- インプットばかりでアウトプットが不足している(覚えたつもりになっているだけ)
- 復習のタイミングが間違っている(忘却曲線を無視している)
- 睡眠不足や集中できない環境など、記憶を妨げる要因がある といった点が挙げられます。これらの原因を一つずつ解消していくことで、あなたの暗記力は確実に向上します。
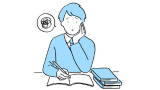
中学生は1日何時間勉強する?
「1日何時間勉強すればいいか」という質問をよく受けますが、時間よりも「質」が重要です。ただ机に向かっているだけでは意味がありません。
- 中学1・2年生: 平日1〜2時間、休日3〜4時間程度が目安です。
- 中学3年生: 受験を意識し、平日2〜3時間、休日4〜6時間程度を目指しましょう。
大切なのは、短時間でも集中して、質の高い勉強を毎日続けることです。
ダラダラと長時間やるよりも、集中して効率の良い勉強法を実践する方が、はるかに成績は上がります。
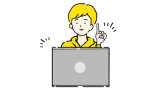
中学生が記憶力を上げる方法はありますか?
はい、中学生でも記憶力を上げる方法はたくさんあります。
この記事でご紹介した3つのコツ、特に「理解を伴う学習」「効率的なアウトプットと復習」「五感の活用」が基本です。
- 音読や図解、マインドマップを使う
- 覚えたことを誰かに説明する
- 忘却曲線に合わせた復習(1日後、3日後、7日後など)
- 十分な睡眠を確保し、集中できる環境で勉強する
これらを継続することで、あなたの記憶力は着実に向上します。
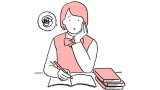
何回繰り返せば覚えられますか?
「何回繰り返せば覚えられる」という明確な回数はありません。
なぜなら、繰り返しの「質」と「タイミング」が重要だからです。
ただ漫然と繰り返すだけでは、何百回やっても覚えられないことがあります。
- 理解してから繰り返す
- アウトプットを挟んで繰り返す
- 忘却曲線に合わせたタイミングで繰り返す
例えば、初めて覚える英単語なら、理解した上で3〜5回声に出して、その日の終わりにもう一度、そして3日後、1週間後と分散して繰り返すことで、効率的に定着します。
大切なのは回数よりも、「脳に定着させるための正しい繰り返し方」です。
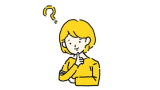
書かない暗記法でも本当に大丈夫ですか?
はい、書かない暗記法でも全く問題ありません。
むしろ、書くことに時間を取られすぎて、他の効率的な学習が疎かになるよりは、書かない暗記法の方が効率的である場合も多いです。
- 音読やシャドーイング
- 頭の中で整理したり、誰かに説明したりするアウトプット
- 学習アプリや単語カードを視覚的に活用する
これらは書かない暗記法として非常に有効です。
ただし、漢字や英単語のスペルなど、「書くことでしか身につかない」要素もあるため、全てを書かないわけではなく、バランスを見て使い分けることが大切です。
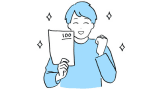
記憶力を上げるトレーニングや習慣はありますか?
はい、日常生活の中で記憶力を高めるためのトレーニングや習慣はあります。
- 毎日のニュースに興味を持つ: 社会の出来事を理解しようとすることで、脳が情報を処理する力が向上します。
- 好奇心を持つ: 好きなことや興味があることに関する情報を積極的に取り入れることで、脳が活性化されます。
- 適度な運動をする: 脳への血流が良くなり、脳の機能が向上すると言われています。
- バランスの取れた食事と十分な睡眠: これらは脳が健康に機能するための最も基本的な土台です。
- 脳トレゲームやパズルを楽しむ: 楽しく脳を刺激することで、記憶力や思考力を鍛えられます。
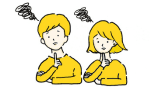
部活が忙しくても続けられる暗記法は?
部活が忙しい中学生でも、効率的に暗記を進めることは十分可能です。
鍵は、「スキマ時間の有効活用」と「質の高い勉強」です。
- 通学中の電車やバスの中: 単語カードや学習アプリで10分間だけ暗記に集中。
- 部活の休憩時間や待機時間: 5分でも良いので、今日の授業内容の振り返りや、前日に覚えたことの確認。
- お風呂の中や寝る前: 防水シートにまとめた要点や、スマホの読み上げ機能で耳からインプット。
- 短期集中で成果を出す: 「この15分でここだけ覚える」と目標を明確にし、集中して取り組む。
忙しいからこそ、「いつ」「何を」「どれだけ」やるかを具体的に計画することが重要です。
私の指導経験でも、部活で全国大会を目指しながらも、効率的な勉強法で成績を維持し、志望校に合格した生徒はたくさんいます。
暗記ができない中学生におすすめ!タブレット学習教材
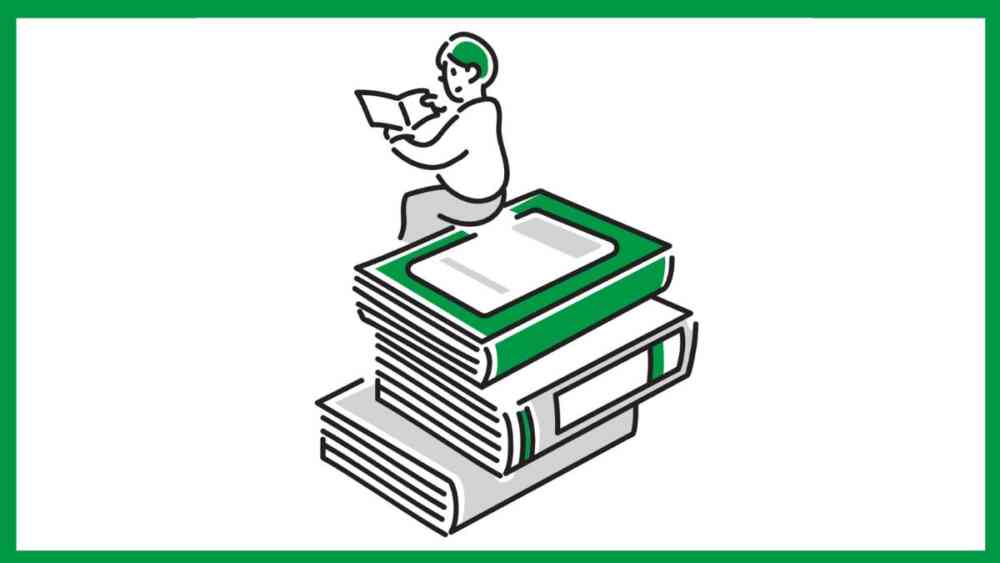
中学生におすすめタブレット学習教材比較表
| タブレット学習教材名 | 月謝 | 特徴 |
| 進研ゼミ:中学講座 | 中学1年生:6,400円〜 | ベネッセが提供している、タブレット学習教材。中学生の利用者数No.1。 |
| すらら | 小中コース 8,800円〜 | AI×アダプティブラーニング「すらら」、マナブをサポートする最先端学習システム。小学生から高校生まで、国・数・理・社・英の5教科を学習できるICT教材 |
| スマイルゼミ | 7,480円〜 | 「まなぶ」「みまもる」「たのしむ」の3つのバランスを大切にして、勉強したい気持ちを逃さない。 |
| デキタス | 中学生:5,280円〜 | 勉強嫌いでも、勉強が習慣化できる!おすすめのタブレット学習教材 |
※オンライン料金の詳細については公式サイトからお問い合わせください。※社名をタップすると公式ホームページに移動します。
※学年や講師ランク・授業時間により料金は変動します。
進研ゼミ:中学講座で暗記が得意に!
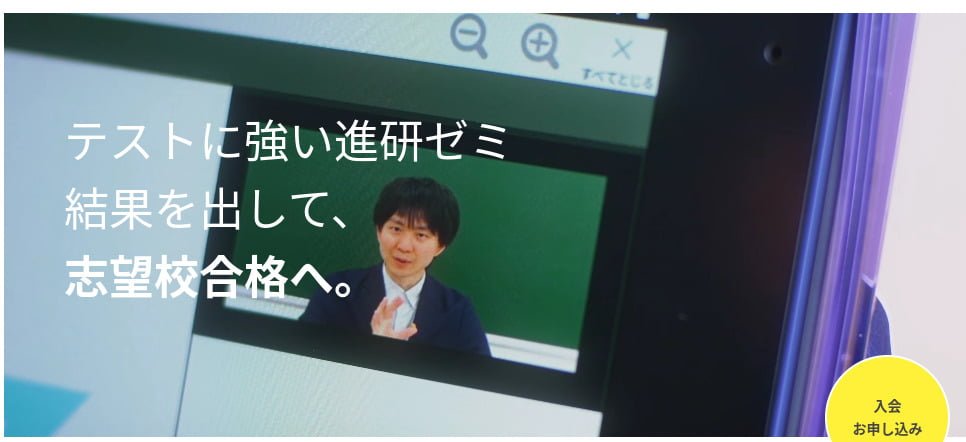
中学生利用者NO.1!進研ゼミ:中学講座の基本情報
| 月謝 | 【月謝例】 中学1年生:6,400円〜 中学2年生:6,570円〜 中学3年生:7,090円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、理科、社会、英語 |
| 学習機能 | 教科書対応のテキストで、予習も復習もバッチリ! お使いの教科書に合わせたテキストなので、予習はもちろん復習にも効率的に |
| 管理機能 | AIのレッスン提案で迷わない実力に合わせて学習スタート 学習達成後のごほうびでやる気が続く |
| サポート体制 | 月1回、赤ペン先生がお子さま一人ひとりを添削し、丁寧に指導。担任制なので、毎回同じ先生に提出する楽しみがうまれ、毎月の学習の仕上げとしてしっかり取り組めます。 |
進研ゼミ中学講座の特徴
進研ゼミ中学講座は、ベネッセコーポレーションが提供している中学生向けの通信教育です。
1969年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。進研ゼミ中学講座の特徴は、以下の通りです。
- 学校の授業内容に沿った教材で、予習・復習が効率的にできる。
- タブレット学習を利用することで、ゲーム感覚で学習できます。
- 赤ペン先生による添削指導で、記述力や思考力を鍛えられる。
- 応用問題や演習問題で、実力を身につけられる。
- 夏休み特訓や冬期講習など、季節ごとの特別講座が充実。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、中学生の学習状況を把握できます。
進研ゼミ中学講座は、中学校の授業内容をしっかり学びたい、記述力や思考力を鍛えたい、夏休みや冬休みの学習を充実させたい、といった中学生におすすめです。
\中学生の利用者NO.1の通信教育/
安心して利用できる
↓↓↓
進研ゼミ中学講座公式HP
すらら:暗記が得意になる無学年方式オンライン教材

「すらら」の基本情報
| 受講費用の安さ | ■入会金 ・小中・中高5教科コース:7,700円 ・小中・中高3教科、小学4教科コース:11,000円 ■3教科(国・数・英)コースの月謝例 ・小中コース 月額:8,800円〜 小学1年生~中学3年生までの3教科(国・数・英)の範囲が学び放題 ・中高コース 月額:8,800円〜 |
| 対応科目・コース | 4教科(国・数・理・社)コース 5教科(国・数・理・社・英)コース 無学年方式で中学英語も先取り学習できる |
| 学習機能 | キャラクターによるレクチャーからドリル機能が充実 「すらら」は読み解くだけではなく、見て、聞いて学べる |
| 管理機能 | 「すらら」はAI搭載型ドリルだから自分のつまずきポイントがわかる! |
| サポート体制 | 学習習慣の身に付け方を始めとした学習に関する悩みや、基礎学力、成績を上げるための学習設計をサポートします。 |
すららの特徴
すららは、株式会社すららネットが提供している中学生向けのオンライン学習教材です。
2010年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
すららの特徴は、以下の通りです。
- 学年にとらわれない無学年方式で、中学生のペースに合わせて学習できます。
- 中学生の弱点をAIが自動診断し、苦手な分野を効率的に克服できます。
- ゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な中学生でも楽しく学習できます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、中学生の学習状況を把握できます。
すららは、学習に苦手意識を持っている中学生や、効率的に学習を進めたい中学生におすすめです。
当サイトで人気No.1の通信教材!
是非!すららを選択肢の一つに
↓↓↓
すららの公式サイトをチェックする!
スマイルゼミ:暗記の学びが継続するタブレット教材
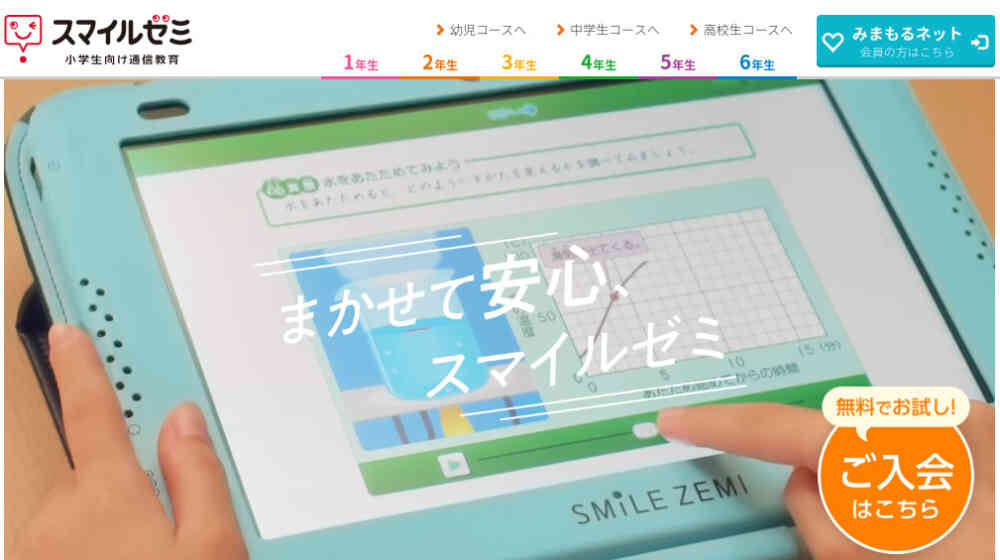
スマイルゼミの基本情報
| お手軽な受講費用 | 【中学1年生】月謝例 <標準クラス> ・7,480円〜:12か月一括払い/月あたり |
| 対応科目・コース | 国語・数学・理科・社会はもちろんのこと、英語やプログラミングも1年生から学習できる |
| 学習機能 | アニメーションによる解説で公式の持つ意味を正しく理解できる 手をついて書ける学習専用タブレットを使用 |
| 管理機能 | スマイルゼミのタブレットは、利用時間を「1日〇時間」という形で制限可能 |
| サポート体制 | 全額返金保証制度あり |
スマイルゼミの特徴
スマイルゼミは、ジャストシステムが提供している中学生向けのタブレット学習教材。
2012年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
スマイルゼミの特徴は、以下の通りです。
- タブレット端末を使って学習できるので、ゲーム感覚で楽しく学べます。
- 中学生の学習状況をAIが分析して、一人ひとりに合った学習内容を自動的に提案してくれます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、中学生の学習状況を把握できます。
スマイルゼミは、学習に苦手意識を持っている中学生や、効率的に学習を進めたい中学生におすすめです。
中学生の学びが継続するタブレット
\返金保証制度あり/
↓↓↓
スマイルゼミの公式サイトはこちらから
中学生に最適なタブレット教材:デキタス
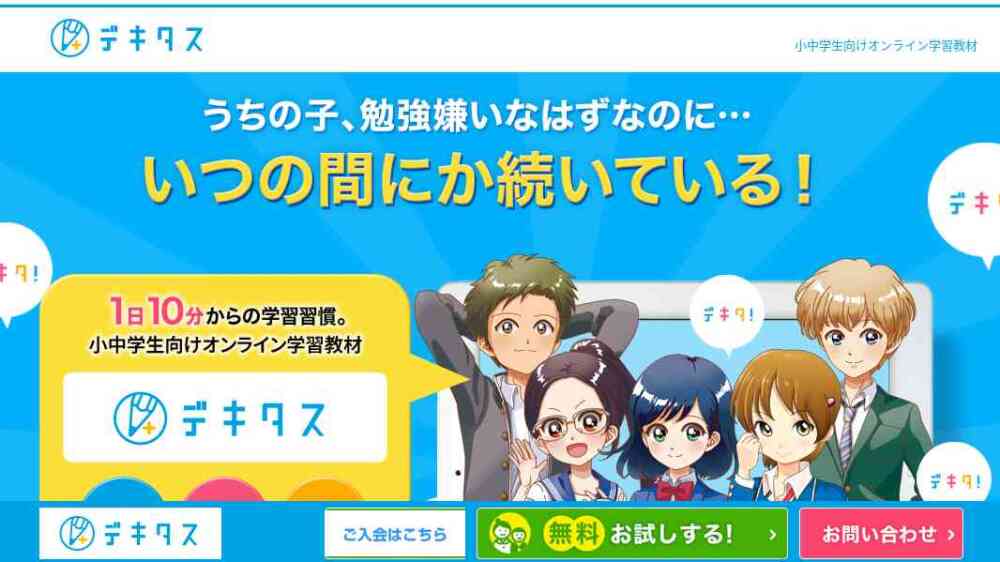
中学生におすすめ!デキタスの基本情報
| 項目 | デキタスの公式サイト |
| 受講費用 | 中学生:5,280円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、地理、歴史、公民、国文法、英語検定 |
| 学習機能 | ポップなキャラクター&わくわくする授業! |
| 管理機能 | テストモード搭載 |
| サポート体制 | 学習結果は表・グラフ・カレンダー等でひと目で確認することができます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
デキタスのおすすめポイント
学校の勉強を確実に理解していくことを目指し開発された、小中学生用オンライン学習教材です。
教科書内容に合った映像授業や、演習問題。さかのぼり学習で前の学年前の授業に戻ったり、定期テスト問題を作成して挑戦したりと、学校の勉強を自宅で、自分のペースで自由に行えます。
以下にデキタスの特徴を3つ紹介します。
段階的な学習体系: デキタスは「授業」→「○×チェック」→「基本問題」→「チャレンジ問題」というスモールステップで構成され、基礎から応用まで段階的に学習が進められます。この体系により、生徒は小さな成功体験を積み重ねながら学習し、「デキタ!」の達成感を実感できます。
デキタ'sノートと複合学習: デキタスでは授業に沿った穴埋め式ノートが印刷可能であり、デジタル教材と紙と鉛筆を組み合わせて効果的な学習ができます。この複合学習により、視覚的なデジタル学習と手書きによるノート作成が組み合わさり、理解の定着が促進されます。
学習習慣の形成: デキタスは学習結果を表・グラフ・カレンダーで確認し、保護者と共有する機能があります。親子で学習状況を共有し、成績アップを目指すことで学習習慣が自然に形成されます。
教科書の内容を確実に理解
学校の成績が上がる!
↓↓↓
デキタスの公式サイトチェック!
東大生家庭教師
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
当サイトで人気の「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
オンライン東大家庭教師友の会
※東大生をはじめとする難関大生がマンツーマンでオンライン指導!講師の2人に一人が厳しい採用基準を突破した現役東大生!
オンライン家庭教師e-live
※東大生や英学部生の講師が選べるオンライン家庭教師!オンライン家庭教師の実績は15年以上!信頼と実績のあるオンライン家庭教師
MeTULAB(ミートゥーラボ)
※講師は全員現役の東大生!大学受験、高校受験合格を目指す生徒に向けて、現役の東大生から親切・丁寧な個別指導が特徴
スタディコーチ
※講師は東大生・旧帝大・早慶生!勉強の計画作成や進捗管理を行うコーチンが特徴!スタッフの丁寧な対応が印象的なオンライン家庭教師
STRUX
※東大出身の塾長が生徒を合格に導いてくれる!勉強の仕方を生徒に合わせて指導してくれるオンライン家庭教師!
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
まとめ:中学生「暗記できない」を徹底解決!苦手を克服し成績が上がる3つのコツ

まとめ:中学生「暗記できない」を徹底解決!苦手を克服し成績が上がる3つのコツ
まとめ
中学生の皆さん、「暗記できない」という悩みは、決してあなたの才能や記憶力の低さによるものではありません。
これまでご紹介してきたように、それは「正しい方法と学習設計」を知らなかっただけなのです。
私が長年、個別指導塾の教室長として数々の中学生を指導し、中学生が「暗記の苦手」を克服して志望校に合格していく姿を見てきました。
中学生に共通していたのは、「なぜ覚えられないのか」という原因を理解し、そこに合わせた「効率的な暗記方法」を実践したことです。
この記事で解説した3つのコツ、
- 理解→整理→アウトプットの順番で覚える
- 分散復習とテスト化で「覚えたつもり」をなくす
- 五感とストーリーで記憶のフックを作る
これらを実践し、あなた自身の学習スタイルに合わせて工夫を凝らしてみてください。
そして、保護者や先生のサポートも積極的に活用しましょう。
最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、「できる」と信じて一歩踏み出し、小さな成功体験を積み重ねていくことが、最終的に大きな自信となり、あなたの成績を劇的に向上させるでしょう。
暗記は技術です。
正しい技術を身につければ、誰でも暗記を得意にすることができます。
あなたの未来のために、今日から新しい暗記法を始めてみませんか?
心から応援しています。
暗記が苦手な中学生におすすめ塾の紹介
そら塾の口コミ・評判を徹底調査|良い・悪い口コミから特徴と向いている子
トウコベの口コミ・評判・レビュー【小中学生の保護者向け】講師の質・サポート・効果を徹底検証
家庭教師の銀河は本当にやばい?口コミと評判&高い教材費の真相とは?
【中学生向け】安いオンライン塾おすすめ20選!料金相場・費用を徹底比較
中学生にオンライン家庭教師は必要?選び方とおすすめ15社を徹底比較
都立高校受験に強いオンライン塾・個別指導塾20選│偏差値アップ!
高校受験に強い!オンライン家庭教師おすすめ20選!口コミ・料金を徹底比較
【中学生向け】安いオンライン家庭教師15選!料金・月謝を徹底比較


