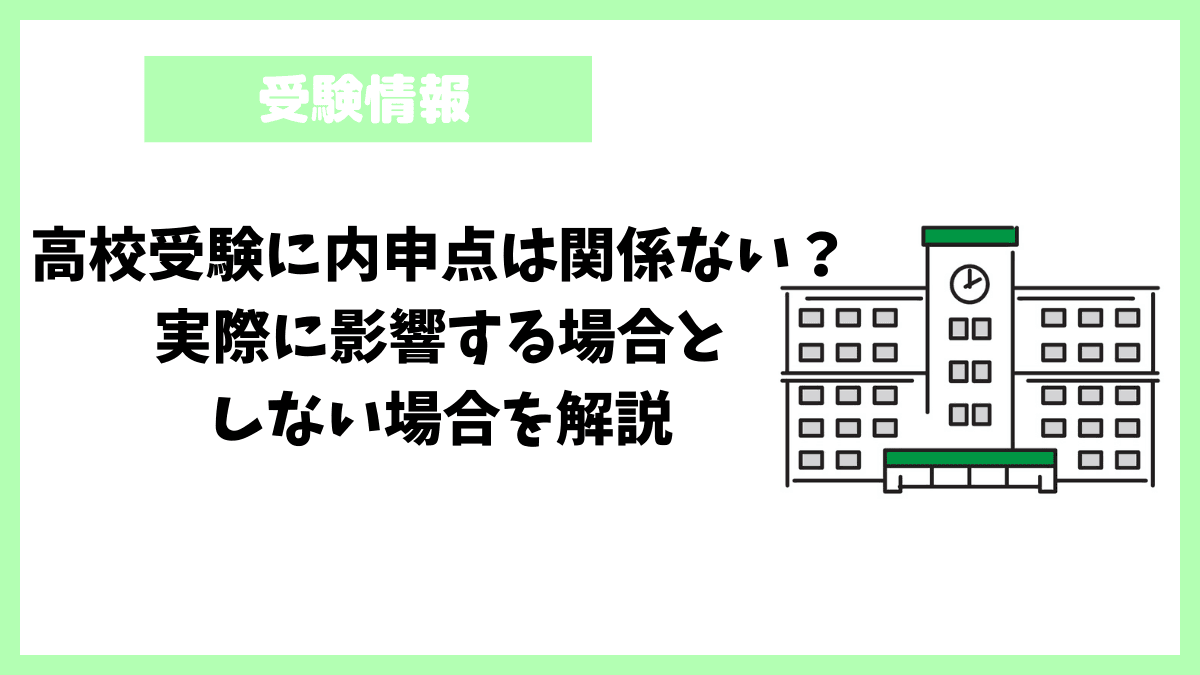
「※この記事には一部PRが含まれます」
高校受験では、国語の試験において漢字問題が大きな割合を占めていることをご存じですか?
たとえば、多くの高校で漢字の配点は全体の約15%〜20%にものぼることが珍しくありません。
この漢字問題で確実に点数を取れるかどうかは、合否を大きく左右する要因となるのです。
苦手な子でも伸びる!漢字は「努力が結果に直結するパート」
他の国語の分野、例えば長文読解などは、読解力や思考力を養うのに時間がかかる場合があります。
しかし、漢字は「覚えれば覚えるほど点数に直結する」、まさに努力が裏切らない分野です。
私の長年の指導経験から断言できますが、漢字は努力次第で誰もが得点源にできる科目なんです。
高校受験対策を本格的にしたいのであれば、生徒数No.1のオンライン個別指導そら塾がおすすめ!
なぜなら、そら塾は受験対策・内申点対策がとても充実しているからです。

オンライン塾のそら塾は、月額5,800円〜授業が受けられる、圧倒的な安さが特長。
安さだけではなく、生徒の89.1%が成績アップを実現しています。※2021年4月〜2022年3月 そら塾の生徒で半年以上、週1回以上受講し、受講科目が1科目以上成績アップ(5段階評価で+1以上)した生徒の割合
そら塾が気になる方は、無料体験授業が用意されていますので、公式ホームページをチェックしてください。
記事のポイント
高校受験における漢字の重要性
効率的な漢字の学習方法
高校入試によく出る漢字と対策
漢字学習に役立つ教材とツール
おすすめ塾
参考記事:【そら塾の口コミ・評判】ひどい?塾経験者が徹底調査した結果は?
Contents
高校受験の漢字勉強法と対策、まず押さえるべきポイントは?
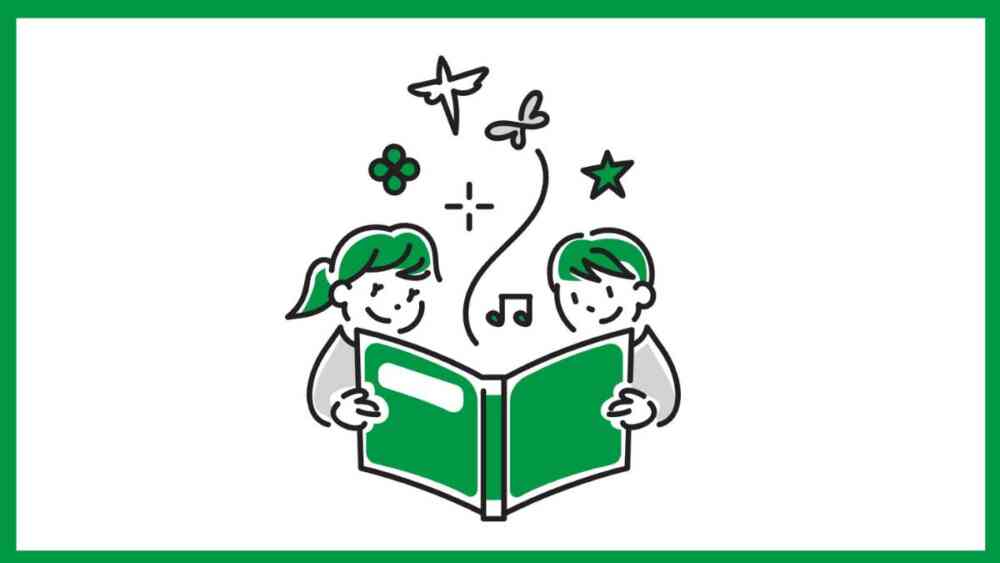
高校受験の漢字対策を始める前に、まずは「どのような漢字が求められるのか」「出題傾向はどうか」といった全体像を把握することが大切です。
闇雲に勉強するのではなく、入試の特性を知ることで、効率的な学習計画を立てることができます。
- 高校受験で求められる漢字レベルは?
- 公立と私立で異なる漢字の出題傾向
高校受験で求められる漢字レベルは?
高校受験で求められる漢字のレベルは、一般的に中学校で学習する範囲が中心となりますが、漢字検定3級〜準2級レベルを目安にすると良いでしょう。
学校の教科書で習う漢字だけでは不十分な場合もあります。
たとえば、教科書には載っていても入試ではあまり出ない漢字もあれば、その逆もあります。
・学校の教科書とのギャップと対策法
学校の教科書は基礎を固めるには最適ですが、入試問題は教科書内容を横断的に理解しているかを問う傾向があります。
具体的には、過去問を解くことで、自分の志望校がどのようなレベルの漢字を出題しているかを把握し、教科書とのギャップを見つけることが対策の第一歩です。

公立と私立で異なる漢字の出題傾向
公立高校と私立高校では、漢字の出題傾向に明確な違いがあることが多々あります。
この違いを理解することが、効果的な漢字対策につながります。
・都道府県別の傾向の簡単な紹介(例:神奈川は語彙力重視、私立は難漢字も)
たとえば、神奈川県の公立高校入試では、漢字の「読み書き」だけでなく、四字熟語やことわざといった語彙力が重視される傾向にあります。
難関私立高校では、中学校の常用漢字の範囲を超えた難解な漢字の読み書きや、漢文からの出題が見られることもあります。
志望校の過去問を数年分解いて、出題形式や難易度、よく出る分野を分析することが非常に重要です。
【基礎編】漢字の覚え方10選!苦手でもできる勉強法

漢字の勉強が苦手だと感じる中学生は少なくありません。
ただひたすら書き続けるだけが漢字の勉強ではありません。
ここでは、私の長年の指導経験から編み出した、苦手な子でも効率的に漢字を覚えられる10の勉強法をご紹介します。
- 音訓の法則と語源を使って「読む力」を鍛える
- 声に出す×反復練習で「書く力」を身につける
- 例文や熟語とセットで覚える:文脈の力を活用
- 部首・構成要素から覚える漢字の仕組み
- スキマ時間×一問一答で記憶定着
- 自分だけの漢字ノート作成術
- アウトプット学習:人に教える・ミニテスト
- ご褒美・タイマー学習でモチベーション維持
音訓の法則と語源を使って「読む力」を鍛える
漢字の「読み」を強化するには、ただ丸暗記するのではなく、音訓の法則や語源を意識することが大切です。
たとえば、「工」を含む漢字は「コウ」や「ク」と読むことが多い、といった共通の法則を見つけると、初めて見る漢字でも推測できるようになります。
具体的なエピソードとして、以前「複雑」という漢字がどうしても書けない生徒がいました。
そこで「複」の音読みが「フク」であることと、「雑」が「ざつ」である理由(「木」が集まっているから「ごちゃごちゃ」している、など)を語呂合わせで教えたところ、驚くほど定着が早まりました。

声に出す×反復練習で「書く力」を身につける
漢字の書き取りは、黙々と書くだけではなかなか覚えられません。
「声に出して読みながら書く」ことと、「短期間での反復練習」が非常に効果的です。
例えば、「継続」と書くときに「けいぞく、けいぞく」と声に出しながら10回書く。
そして、翌日、そのまた翌日と短いスパンで再度10回ずつ書く、といった練習を繰り返すと、脳への定着が格段に早まります。
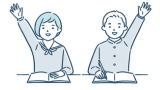
例文や熟語とセットで覚える:文脈の力を活用
漢字は単体で覚えるよりも、実際の文脈の中で使われている例文や熟語と一緒に覚えることで、意味と形がより強く結びつき、記憶に残りやすくなります。
例えば、「貢献」という漢字を覚える際に「社会に貢献する」という例文や、「貢献度」という熟語をセットで覚えるようにしましょう。
以前、漢字の書き取りが壊滅的だった生徒がいました。
私は生徒に「今日から覚える漢字は必ず短い例文を自分で作ってノートに書く」という宿題を出したところ、意味を理解するようになっただけでなく、その漢字を使う場面を想像できるようになり、書ける漢字が飛躍的に増えました。

部首・構成要素から覚える漢字の仕組み
漢字は、それぞれ意味を持つ部首や構成要素の組み合わせでできています。
「漢字の仕組み」を理解することで、漢字を体系的に覚え、忘れにくくすることができます。
たとえば、「氵(さんずい)」がついている漢字は水に関するもの、「言(ごんべん)」がついている漢字は言葉に関するもの、といったように、部首の意味を意識しながら覚えましょう。
多くの人が誤解していますが、ただ画数を数えて書くだけでは、漢字の本当の意味や成り立ちを理解できません。
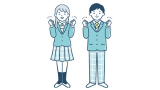
スキマ時間×一問一答で記憶定着
通学時間や休み時間など、ちょっとしたスキマ時間を漢字学習に活用しましょう。
この時に効果的なのが「一問一答形式」での学習です。
単語カードや漢字アプリを活用し、短時間で多くの漢字に触れることを繰り返します。
例えば、朝の電車で5分間、夜寝る前に5分間、のように毎日短い時間でも継続することが記憶の定着につながります。

自分だけの漢字ノート作成術
市販の漢字ドリルも良いですが、自分だけの漢字ノートを作成することも非常に効果的です。
特に、自分が間違えやすい漢字や覚えにくい漢字を重点的に書き出し、読み方、書き順、熟語、簡単な例文などをまとめます。
色ペンを使ったり、イラストを描いたりして、視覚的に分かりやすくする工夫をすると、より楽しく、効率的に学習できます。

アウトプット学習:人に教える・ミニテスト
覚えた漢字は、積極的にアウトプットすることで記憶が強化されます。
友達や家族に「この漢字の読み方、知ってる?」と問題を出してみたり、自分で簡単なミニテストを作成して解いてみたりするのも良いでしょう。
人に教えるためには、自分がその漢字を完璧に理解している必要があるため、より深い学習につながります。
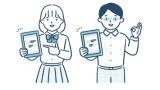
ご褒美・タイマー学習でモチベーション維持
漢字の勉強は地道な作業なので、モチベーションを維持する工夫も大切です。
たとえば、「今日覚える漢字を完璧にしたら好きな漫画を10分読む」といったご褒美を設定するのも良いでしょう。
タイマー学習を取り入れるのもおすすめです。
例えば「10分間集中して漢字を覚える」と決めてタイマーをセットし、時間内は他のことを一切考えずに取り組むことで、集中力を高めることができます。
【実践編】学年別・時期別の漢字対策スケジュール

漢字の勉強は、ただやみくもに始めるのではなく、学年や時期に合わせた計画を立てることが重要です。
ここでは、私の経験に基づいた効果的な学習スケジュールと、それぞれの時期で意識すべきポイントをお伝えします。
- 中1・中2から始めると有利!基礎の積み上げ
- 中3からの短期集中!夏休み・直前期の学習法
- 過去問の活用術:傾向分析と自作問題
- 苦手を克服する「間違いノート」の作り方
中1・中2から始めると有利!基礎の積み上げ
高校受験の漢字対策は、中学3年生になってから焦って始めるよりも、中学1・2年生のうちからコツコツと基礎を積み重ねていくのが断然有利です。
早い段階から漢字に慣れておくことで、中学3年生になった時に他の受験科目に集中する時間を確保できます。
【中学1・2年生向け基礎学習のポイント】
- 学校の定期テスト対策を漢字学習の基盤にする: 日々の授業で出てくる漢字や、定期テスト範囲の漢字を完璧に覚えることを意識しましょう。
- 苦手な漢字を放置しない: 少しでも「これは苦手だな」と感じる漢字があれば、その場で解決するように心がけてください。
- 漢字ドリルを一冊完璧にする: 中学生向けの漢字ドリルを1冊選び、繰り返し解いて完璧にマスターするまでやり込みましょう。
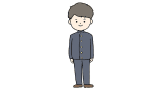
中3からの短期集中!夏休み・直前期の学習法
中学3年生になってから本格的に漢字対策を始める方も少なくありません。
特に夏休みと受験直前期は、漢字の点数を大きく伸ばすチャンスです。
【夏休み:集中的な復習と弱点克服】
夏休みはまとまった時間が取れるため、中学3年間で習う漢字の総復習に最適です。
- 入試頻出漢字リストを徹底的に覚える: 市販の「高校入試によく出る漢字」のような問題集や、後述する当記事の頻出漢字リストを活用し、集中的に覚え込みましょう。
- 苦手な分野を洗い出す: 模擬試験や過去問を解き、自分が特に苦手とする漢字の分野(例:同音異義語、四字熟語など)を特定し、重点的に学習します。
【直前期:過去問中心の実践演習と最終確認】
受験直前期は、新しい漢字を覚えるよりも、これまで覚えた漢字を確実に点数につなげることを意識してください。
- 過去問を繰り返し解く: 志望校の過去問を解き、本番の出題形式に慣れるとともに、時間配分の感覚を養います。
- 「書く」練習を怠らない: 読みはできても書きでミスをしやすいのが漢字です。最後まで書き取り練習を継続しましょう。
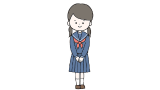
過去問の活用術:傾向分析と自作問題
過去問は、ただ解くだけではもったいない「宝の山」です。
過去問を徹底的に分析することで、志望校の漢字の出題傾向や頻出パターンを把握し、効率的な対策を立てることができます。
【傾向分析のポイント】
- 出題形式の確認: 読み問題、書き取り問題、熟語、対義語・類義語、四字熟語など、どのような形式で出題されるかを確認します。
- 頻出漢字の特定: 繰り返し出題されている漢字や、読み書きのパターンをメモしておきましょう。
- 難易度の把握: 自分のレベルと過去問の難易度が合っているかを確認し、今後の学習の参考にします。
【自作問題で応用力アップ】
過去問に出てきた漢字や、自分が間違えた漢字を使って自分だけのミニ問題集を自作するのも効果的です。
たとえば、過去問の文中に登場した漢字を別の熟語に置き換えたり、読みを問う問題から書きを問う問題に変えたりすることで、応用力を養うことができます。
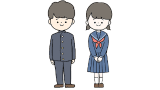
苦手を克服する「間違いノート」の作り方
漢字の勉強で最も重要なことの一つは、間違えた漢字をそのままにしないことです。
同じ間違いを繰り返さないために、「間違いノート」を必ず作りましょう。
【間違いノート作成のステップ】
- 間違えた漢字を書き出す: 問題集やテストで間違えた漢字を、正しい漢字とともに書き出します。
- 間違えた原因を分析する: 読み間違い、書き間違い、送りがなの間違いなど、なぜ間違えたのかを具体的にメモします。
- 関連情報をまとめる: 漢字を使った熟語や例文、対義語・類義語、似ている漢字などを書き添えます。
- 定期的に見直す: 覚えたつもりでも忘れてしまうことがあるので、週に一度など定期的に見直し、ミニテストを行いましょう。
【成功した生徒のエピソード】 私が指導した生徒の中に、漢字が本当に苦手で、テストでいつも足を引っ張られていた中学生がいました。その生徒は私が勧めた「間違いノート」を愚直に作り続け、間違えるたびに「なぜ間違えたのか」を徹底的に分析しました。最初は書くのに時間がかかりましたが、半年もすると、同じ漢字で間違えることがほとんどなくなり、最終的には漢字問題で満点近くを取れるようになりました。これはまさに、自分の弱点と真剣に向き合った努力の成果です。
高校入試頻出漢字100選:読み・書き徹底攻略!
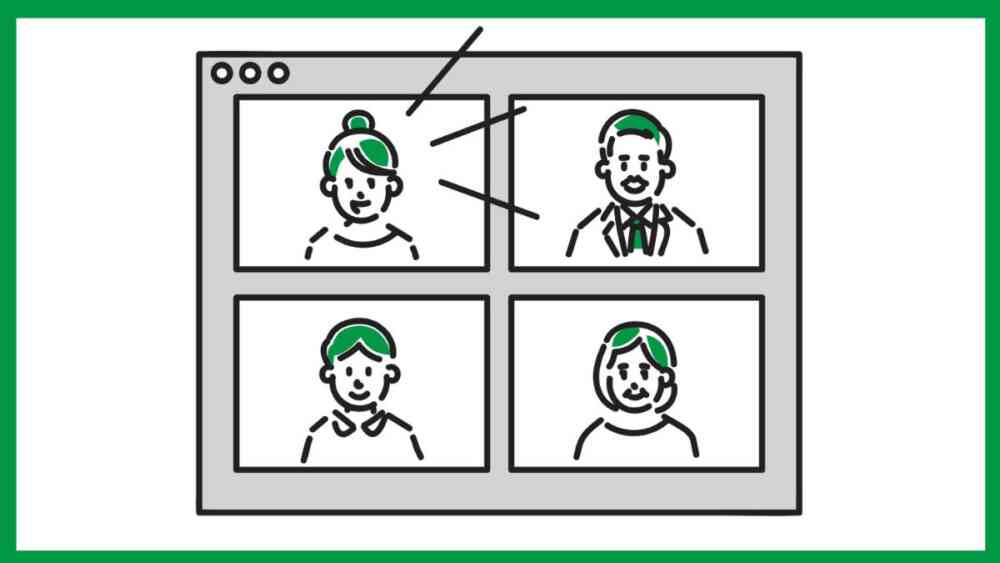
ここでは、高校入試で特に出やすい漢字を「読み」と「書き」の視点から厳選しました。
これらの漢字をマスターすることが、得点アップへの近道です。
- 高校入試頻出漢字100選(読み・書き)
- 私立高校で出やすい漢字とその対策
- 高校入試によく出る対義語30選
- 高校受験によく出る類義語30選
- よく出る熟語・四字熟語・ことわざ・慣用句
高校入試頻出漢字100選(読み・書き)
【高校入試によく出る漢字の読み50選】
まずは、入試で頻繁に問われる漢字の読み方から確認していきましょう。
文脈の中で正しく読めるように、熟語と一緒に覚えるのがポイントです。
| 漢字 | 読み | 熟語例 |
|---|---|---|
| 家族 | かぞく | 私の家族はとても仲が良い。 |
| 経済 | けいざい | 最近の経済状況は安定しています。 |
| 勉強 | べんきょう | 毎日一生懸命に勉強しています。 |
| 友達 | ともだち | 私の友達はみんな優しい人です。 |
| 教育 | きょういく | 良い教育を受けることは重要です。 |
| 理由 | りゆう | なぜそう思うのか、理由を教えてください。 |
| 経験 | けいけん | 新しい経験をすることは成長につながります。 |
| 高校 | こうこう | 来年から高校生活が始まります。 |
| 理解 | りかい | 問題の内容をしっかりと理解してから解いてください。 |
| 進学 | しんがく | 大学進学を目指して頑張っています。 |
| 夢中 | むちゅう | 彼はゲームに夢中になってしまっているようです。 |
| 成績 | せいせき | 努力の結果、成績が上がりました。 |
| 注意 | ちゅうい | 授業中は先生の言葉に注意して聞きましょう。 |
| 発表 | はっぴょう | 自分の意見を発表する機会を得ました。 |
| 先生 | せんせい | 私の理科の先生はとても優しい。 |
| 音楽 | おんがく | 音楽を聴くことが好きです。 |
| 美術 | びじゅつ | 美術の授業で絵を描くことが得意。 |
| 社会 | しゃかい | 社会の仕組みを学ぶことは大切。 |
| 期待 | きたい | 将来の進路に期待しています。 |
| 活動 | かつどう | 部活動に積極的に参加しています。 |
| 交通 | こうつう | 交通ルールを守って安全に過ごしましょう。 |
| 世界 | せかい | 世界各国の文化に興味があります。 |
| 天気 | てんき | 明日の天気予報を確認しておきましょう。 |
| 目標 | もくひょう | 自分の目標に向かって努力を続けています。 |
| 気持ち | きもち | 感謝の気持ちを忘れずに行動しましょう。 |
| 人生 | じんせい | 人生の中で大切なことを学んでいきます。 |
| 挑戦 | ちょうせん | 新たなことに挑戦する勇気を持ちましょう。 |
| 自由 | じゆう | 自分の思いを自由に表現できます。 |
| 態度 | たいど | 誠実な態度で取り組みましょう。 |
| 文化 | ぶんか | さまざまな文化に触れることで広い視野を持てます。 |
| 夢 | ゆめ | 自分の夢に向かって一歩ずつ進んでいきます。 |
| 希望 | きぼう | 将来の希望を持って頑張りましょう。 |
| 目的 | もくてき | 勉強の目的を明確にしましょう。 |
| 意見 | いけん | 自分の意見をしっかりと主張できるようになりたい。 |
| 心配 | しんぱい | 試験の結果が心配です。 |
| 努力 | どりょく | 努力は成果を生むものです。 |
| 成功 | せいこう | 努力の末に成功を手にできました。 |
| 重要 | じゅうよう | この問題は重要なポイントです。 |
| 責任 | せきにん | 自分の行動には責任を持ちましょう。 |
| 関係 | かんけい | 人との関係を大切に築いていきます。 |
| 問題 | もんだい | 問題を解くために考え方を工夫しましょう。 |
| 場合 | ばあい | 雨の場合は傘を持って行きましょう。 |
| 行動 | こうどう | 考えるだけでなく、行動することも大切です。 |
| 自分 | じぶん | 自分の可能性を信じて努力します。 |
| 能力 | のうりょく | 自分の能力を高めるために日々努力しています。 |
| 確認 | かくにん | 答えを確認する前に問題文をよく読みましょう。 |
| 休憩 | きゅうけい | 集中力を保つために適度な休憩を取りましょう。 |
| 限り | かぎり | 時間の限りを最大限に活用しましょう。 |
| 感動 | かんどう | その映画は心に感動を与える作品でした。 |
| 大切 | たいせつ | 友情はとても大切なものです。 |
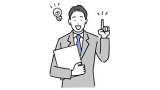
高校入試によく出る漢字の書き50選
次に、入試で差がつきやすい漢字の書き取り練習です。
正確に書けるように、部首や画数にも注意しながら繰り返し練習しましょう。
| 漢字 | 読み | 熟語例 |
|---|---|---|
| 意欲的 | いよくてき | 意欲的に学習に取り組む姿勢を持つ。 |
| 結果 | けっか | 努力の末に結果を出す。 |
| 努力 | どりょく | 努力不足の状態を改善する。 |
| 実績 | じっせき | 実績を積み重ねて信頼を得る。 |
| 基礎 | きそ | 基礎をしっかりと固めることが重要である。 |
| 発想 | はっそう | 柔軟な発想力を養うことが求められる。 |
| 意識 | いしき | 自身の意識を改革して成長する。 |
| 重要 | じゅうよう | 問題の重要なポイントを押さえる。 |
| 表現 | ひょうげん | 豊かな言語表現を身につけることが必要である。 |
| 状況 | じょうきょう | 状況に応じた対応が求められる。 |
| 創造 | そうぞう | 創造的な解決策を見つける能力を養う。 |
| 無駄 | むだ | 無駄な時間や努力を省き、効率的に学習する。 |
| 目標 | もくひょう | 明確な目標を持ち、それに向かって努力する。 |
| 評価 | ひょうか | 自己の成果や能力を客観的に評価する。 |
| 応用 | おうよう | 知識を実際の問題に応用する能力を養う。 |
| 収集 | しゅうしゅう | 必要な情報を収集し、活用する能力を持つ。 |
| 国語 | こくご | 文章や言葉の理解・表現能力を高める。 |
| 配分 | はいぶん | 学習時間を適切に配分することが重要である。 |
| 対策 | たいさく | 試験の形式や出題傾向に合わせた対策。 |
| 統合 | とうごう | 統合的な視点で問題を解決する能力を身につける。 |
| 幅広 | はばひろ | 幅広い知識を持つことで問題に対応する。 |
| 模擬 | もぎ | 実際の試験に近い形式の模擬試験。 |
| 継続 | けいぞく | 継続的な学習や取り組みが重要である。 |
| 管理 | かんり | 学習や時間の管理を自己で行う能力を身につける。 |
| 充実 | じゅうじつ | 学習以外の要素も含めて自己を充実させる。 |
| 記憶 | きおく | 記憶力を高めるための方法を学ぶ。 |
| 集中 | しゅうちゅう | 高い集中力を持って学習に取り組む。 |
| 調査 | ちょうさ | 調査・分析能力を養う。 |
| 表現 | ひょうげん | 自己表現能力を磨く。 |
| 信念 | しんねん | 自分の信念に基づいて行動する。 |
| 適応 | てきおう | 環境の変化に適応する能力を養う。 |
| 習得 | しゅうとく | 知識を効率的に習得する方法を身につける。 |
| 解決 | かいけつ | 問題解決能力を高めるための訓練。 |
| 好奇心 | こうきしん | 知的好奇心を持ち、探究心を養う。 |
| 判断 | はんだん | 状況を正しく判断する能力を身につける。 |
| 探求 | たんきゅう | 自己探求の姿勢を持ち、自己成長を図る。 |
| 一生懸命 | いっしょうけんめい | 一生懸命勉強する。 |
| 心配事 | しんぱいごと | 心配事を解消する。 |
| 達成 | たっせい | 目標達成に向けて頑張る。 |
| 努力家 | どりょくか | 努力家として知られる。 |
| 共同 | きょうどう | 共同作業で課題を解決する。 |
| 積極的 | せっきょくてき | 積極的な姿勢を持つ。 |
| 主体的 | しゅたいてき | 主体的に行動する。 |
| 模範的 | もはんてき | 模範的な態度を示す。 |
| 高度 | こうど | 高度な技術を持つ。 |
| 平均 | へいきん | 平均点を上回る。 |
| 進歩 | しんぽ | 日々進歩を遂げる。 |
| 責任感 | せきにんかん | 責任感を持って行動する。 |
| 自信 | じしん | 自信を持って挑戦する。 |
| 予習復習 | よしゅうふくしゅう | 授業前に予習し、授業後に復習することで理解を深める。 |
私立高校で出やすい漢字とその対策
難関私立高校の入試では、公立高校とは異なる、より難易度の高い漢字が出題されることがあります。
私立高校の漢字対策は、合否を分けるポイントになり得ます。
- 特有の難読語:一般的な常用漢字の範囲を超えるような、読みにくい漢字が出題されることがあります。たとえば、「烏賊(いか)」や「団扇(うちわ)」のように、普段見慣れない漢字の読みを問われることも。
- 書き取り注意ポイント:画数が多かったり、似た漢字と混同しやすい漢字の書き取りは特に注意が必要です。過去問を分析し、自分の志望校の私立高校の漢字出題傾向を把握することが重要です。

高校受験:入試によく出る漢字の読み50選
| 家族 | かぞく | 私の家族はとても仲が良い。 |
| 経済 | けいざい | 最近の経済状況は安定しています。 |
| 勉強 | べんきょう | 毎日一生懸命に勉強しています。 |
| 友達 | ともだち | 私の友達はみんな優しい人です。 |
| 教育 | きょういく | 良い教育を受けることは重要です。 |
| 理由 | りゆう | なぜそう思うのか、理由を教えてください。 |
| 経験 | けいけん | 新しい経験することは成長につながります。 |
| 高校 | こうこう | 来年から高校生活が始まります。 |
| 理解 | りかい | 問題の内容をしっかりと理解してから解いてください。 |
| 進学 | しんがく | 大学進学を目指して頑張っています。 |
| 夢中 | むちゅう | 彼はゲームに夢中になってしまっているようです。 |
| 成績 | せいせき | 努力の結果、成績が上がりました。 |
| 注意 | ちゅうい | 授業中は先生の言葉に注意して聞きましょう。 |
| 発表 | はっぴょう | 自分の意見を発表する機会を得ました。 |
| 先生 | せんせい | 私の理科の先生はとても優しい。 |
| 音楽 | おんがく | 音楽を聴くことが好きです。 |
| 美術 | びじゅつ | 美術の授業で絵を描くことが得意。 |
| 社会 | しゃかい | 社会の仕組みを学ぶことは大切。 |
| 期待 | きたい | 将来の進路に期待しています。 |
| 活動 | かつどう | 部活動に積極的に参加しています。 |
| 交通 | こうつう | 交通ルールを守って安全に過ごしましょう。 |
| 世界 | せかい | 世界各国の文化に興味があります。 |
| 天気 | てんき | 明日の天気予報を確認しておきましょう。 |
| 目標 | もくひょう | 自分の目標に向かって努力を続けています。 |
| 気持ち | きもち | 感謝の気持ちを忘れずに行動しましょう。 |
| 人生 | じんせい | 人生の中で大切なことを学んでいきます。 |
| 挑戦 | ちょうせん | 新たなことに挑戦する勇気を持ちましょう。 |
| 自由 | じゆう | 自分の思いを自由に表現できます。 |
| 態度 | たいど | 誠実な態度で取り組みましょう。 |
| 文化 | ぶんか | さまざまな文化に触れることで広い視野を持てます。 |
| 夢 | ゆめ | 自分の夢に向かって一歩ずつ進んでいきます。 |
| 希望 | きぼう | 将来の希望を持って頑張りましょう。 |
| 目的 | もくてき | 勉強の目的を明確にしましょう。 |
| 意見 | いけん | 自分の意見をしっかりと主張できるようになりたい。 |
| 心配 | しんぱい | 試験の結果が心配です。 |
| 努力 | どりょく | 努力は成果を生むものです。 |
| 成功 | せいこう | 努力の末に成功を手にできました。 |
| 重要 | じゅうよう | この問題は重要なポイントです。 |
| 責任 | せきにん | 自分の行動には責任を持ちましょう。 |
| 関係 | かんけい | 人との関係を大切に築いていきます。 |
| 問題 | もんだい | 問題を解くために考え方を工夫しましょう。 |
| 場合 | ばあい | 雨の場合は傘を持って行きましょう。 |
| 行動 | こうどう | 考えるだけでなく、行動することも大切です。 |
| 自分 | じぶん | 自分の可能性を信じて努力します。 |
| 能力 | のうりょく | 自分の能力を高めるために日々努力しています。 |
| 確認 | かくにん | 答えを確認する前に問題文をよく読みましょう。 |
| 休憩 | きゅうけい | 集中力を保つために適度な休憩を取りましょう。 |
| 限り | かぎり | 時間の限りを最大限に活用しましょう。 |
| 感動 | かんどう | その映画は心に感動を与える作品でした。 |
| 大切 | たいせつ | 友情はとても大切なものです。 |

参考記事:中学生オンライン個別指導塾おすすめ20選ハイレベル対策から苦手克服まで
高校入試によく出る対義語30選
| 明確 | 不明瞭 |
| 喜び | 悲しみ |
| 優れた | 劣った |
| 高い | 低い |
| 正確 | 誤った |
| 進歩 | 後退 |
| 大勢 | 少数 |
| 優先 | 後回し |
| 健康 | 病気 |
| 継続 | 中断 |
| 積極的 | 消極的 |
| 成功 | 失敗 |
| 快適 | 不快 |
| 健康 | 不健康 |
| 明るい | 暗い |
| 終わり | 始まり |
| 自由 | 制約 |
| 簡単 | 難しい |
| 賛成 | 反対 |
| 良い | 悪い |
| 幸福 | 不幸 |
| 安定 | 不安定 |
| 明白 | 曖昧 |
| 真実 | 嘘 |
| 具体的 | 抽象的 |
| 平和 | 戦争 |
| 親切 | 冷たい |
| 透明 | 不透明 |
| 順序 | 無秩序 |
| 前進 | 後退 |
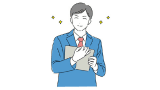
参考記事:【中学生国語の勉強法】基礎力アップ!読解・記述・文法の苦手を攻略
高校受験によく出る類義語30選
| 綺麗 | 美しい |
| 大切 | 重要 |
| 必要 | 不可欠 |
| 考える | 思う |
| 難しい | 困難 |
| 高い | 価格が高い |
| 優れた | 優秀な |
| 実現する | 達成する |
| 改善する | 向上する |
| 普通 | 一般的 |
| 多い | 多数の |
| 順調 | スムーズ |
| 充実 | 満足 |
| 確か | 確実 |
| 悩む | 困る |
| 適切 | 適当 |
| 明確 | はっきり |
| 快適 | 快い |
| 活気 | 元気 |
| 緊張 | こわばり |
| 発展 | 成長 |
| 賛成 | 同意 |
| 情報 | データ |
| 急速 | 早い |
| 経験 | 体験 |
| 真剣 | 真面目 |
| 幸せ | 幸福 |
| 静か | 静寂 |
| 健康 | 健やか |
| 信頼 | 信用 |
参考記事:【オンライン塾】月謝が安い!中学生に人気15選!費用を安くするオンライン塾
よく出る熟語・四字熟語・ことわざ・慣用句
漢字の読み書きだけでなく、熟語や四字熟語、ことわざ、慣用句も高校入試では頻繁に出題されます。
意味と合わせて覚えることで、国語全体の得点力アップにつながります。
- 熟語:曖昧(あいまい)、克明(こくめい)、漸進(ぜんしん)など、意味を理解しながら覚えましょう。
- 四字熟語:一石二鳥、試行錯誤、温故知新など、意味と具体的な例文をセットで覚えるのが効果的です。
- ことわざ・慣用句:「棚からぼたもち」「足を引っ張る」など、比喩的な意味を理解し、実際に使う場面をイメージすると記憶に残りやすくなります。
| 種類 | 語句 | 意味・使い方の例 |
|---|---|---|
| 熟語 | 貢献 | 社会に貢献する |
| 熟語 | 克服 | 困難を克服する |
| 熟語 | 強調 | 意見を強調する |
| 熟語 | 拒否 | 要求を拒否する |
| 熟語 | 促進 | 発展を促進する |
| 熟語 | 改善 | 生活を改善する |
| 熟語 | 観察 | 行動を観察する |
| 熟語 | 分析 | 結果を分析する |
| 熟語 | 連携 | チームで連携する |
| 熟語 | 保護 | 環境を保護する |
| 四字熟語 | 一石二鳥 | 一つの行動で二つの利益を得ること |
| 四字熟語 | 起死回生 | 絶望的な状況から立ち直ること |
| 四字熟語 | 温故知新 | 昔のことを学んで新しい発見を得る |
| 四字熟語 | 十人十色 | 人それぞれ個性や考え方が異なること |
| 四字熟語 | 自業自得 | 自分のしたことの報いを自分が受けること |
| 四字熟語 | 一期一会 | 一生に一度の出会い |
| 四字熟語 | 絶体絶命 | 逃げ場のないピンチ |
| 四字熟語 | 七転八起 | 何度失敗しても立ち上がること |
| 四字熟語 | 馬耳東風 | 他人の意見を聞き流すこと |
| 四字熟語 | 一喜一憂 | 状況に一喜一憂する様子 |
| ことわざ | 急がば回れ | 急いでいる時こそ慎重にした方が良い |
| ことわざ | 猿も木から落ちる | 名人でも失敗することがある |
| ことわざ | 石の上にも三年 | 辛抱強く続ければ成功する |
| ことわざ | 二兎を追う者は一兎をも得ず | 欲張るとどちらも失うことになる |
| ことわざ | 灯台下暗し | 身近なことはかえって気づきにくい |
| ことわざ | 雨降って地固まる | トラブルの後はかえってうまくいく |
| ことわざ | 善は急げ | 良いことはすぐにやったほうがいい |
| ことわざ | 転ばぬ先の杖 | 万一に備えて準備すること |
| ことわざ | 知らぬが仏 | 知らないほうが幸せなこともある |
| ことわざ | 蓼食う虫も好き好き | 好みは人それぞれ |
| 慣用句 | 顔が広い | 知り合いが多い |
| 慣用句 | 手を抜く | 力を入れずにいい加減にする |
| 慣用句 | 足が出る | 予算をオーバーする |
| 慣用句 | 胸を張る | 自信を持つ |
| 慣用句 | 頭が切れる | 頭の回転が速くて賢い |
| 慣用句 | 首を長くする | 楽しみにして待つ |
| 慣用句 | 手が空く | 忙しくなくなる |
| 慣用句 | 舌を巻く | 驚き感心する |
| 慣用句 | 肩を落とす | がっかりする |
| 慣用句 | 顔を出す | 集まりなどに少しの間参加する |
| 慣用句 | 腹をくくる | 覚悟を決める |
| 慣用句 | 胸が高鳴る | わくわくする |
| 慣用句 | 声を大にする | 強く主張する |
| 慣用句 | 耳が痛い | 図星を突かれてつらく感じる |
| 慣用句 | 火に油を注ぐ | 事態をもっと悪くする |
| 慣用句 | 口をすっぱくする | 何度も注意する |
| 慣用句 | 歯が立たない | 相手が強すぎてかなわない |
| 慣用句 | 腰が低い | 丁寧でへりくだっている |
| 慣用句 | 手を焼く | 扱いに困る |
| 慣用句 | 顔から火が出る | とても恥ずかしい |
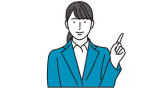
参考記事:漢字の勉強ができる中学生がやっている勉強法と漢字ドリル10選
高校受験の漢字の勉強におすすめのタブレット教材

漢字の学習を効率的に進めるためには、自分に合った教材を見つけることが不可欠です。
ここでは、私の指導経験から得たおすすめの学習ツールをご紹介します。
- 無料プリント&問題サイトの活用
- スマホアプリで楽しく学ぶ!ゲーム感覚で継続しよう
- 中学生におすすめタブレット学習教材比較表
無料プリント&問題サイトの活用
「高校受験 漢字 プリント 無料」や「高校受験 漢字 サイト」といったキーワードで検索すると、無料で利用できる漢字プリントや問題を提供しているサイトが多数あります。
これらを活用しない手はありません。
- おすすめの活用法
- 弱点補強: 苦手な漢字のプリントをダウンロードして集中的に練習したり、問題形式に慣れるために利用したりしましょう。
- 手軽な反復練習: 印刷して持ち運び、通学時間などのスキマ時間に活用するのも効果的です。

スマホアプリで楽しく学ぶ!ゲーム感覚で継続しよう
最近では、「高校受験 漢字 アプリ」と検索すると、学習をサポートしてくれる多くのスマホアプリが見つかります。
ゲーム感覚で学べるアプリは、勉強への抵抗感を減らし、継続を促すのに非常に有効です。
- メリット: いつでもどこでも手軽に学習できる、自動採点機能で効率的、ゲーム要素で飽きにくい。
- 選び方のポイント: 高校受験対策に特化したもの、自分の学習レベルに合ったもの、広告が少なめで集中できるものを選びましょう。
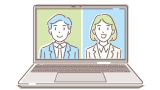
中学生におすすめタブレット学習教材比較表
| タブレット学習教材名 | 月謝 | 特長 |
| 進研ゼミ:中学講座 | 中学1年生:6,400円〜 | ベネッセが提供している、タブレット学習教材。中学生の利用者数No.1。 |
| すらら | 小中コース 8,800円〜 | AI×アダプティブラーニング「すらら」、マナブをサポートする最先端学習システム。小学生から高校生まで、国・数・理・社・英の5教科を学習できるICT教材 |
| スマイルゼミ | 7,480円〜 | 「まなぶ」「みまもる」「たのしむ」の3つのバランスを大切にして、勉強したい気持ちを逃さない。 |
| デキタス | 中学生:5,280円〜 | 勉強嫌いでも、勉強が習慣化できる!おすすめのタブレット学習教材 |
※オンライン料金の詳細については公式サイトからお問い合わせください。※社名をタップすると公式ホームページに移動します。
※学年や講師ランク・授業時間により料金は変動します。
進研ゼミ:中学講座は中学生の漢字の勉強におすすめの教材
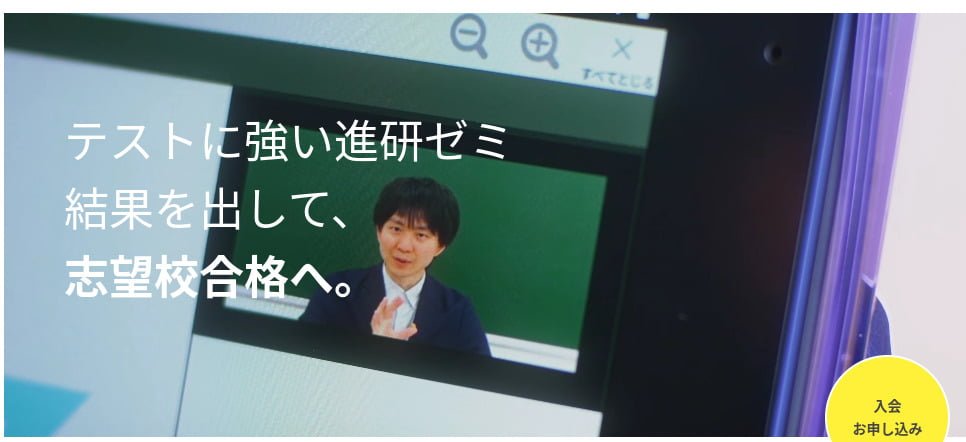
中学生利用者NO.1!進研ゼミ:中学講座の基本情報
| 月謝 | 【月謝例】 中学1年生:6,400円〜 中学2年生:6,570円〜 中学3年生:7,090円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、理科、社会、英語 |
| 学習機能 | 教科書対応のテキストで、予習も復習もバッチリ! お使いの教科書に合わせたテキストなので、予習はもちろん復習にも効率的に |
| 管理機能 | AIのレッスン提案で迷わない実力に合わせて学習スタート 学習達成後のごほうびでやる気が続く |
| サポート体制 | 月1回、赤ペン先生がお子さま一人ひとりを添削し、丁寧に指導。担任制なので、毎回同じ先生に提出する楽しみがうまれ、毎月の学習の仕上げとしてしっかり取り組めます。 |
進研ゼミ中学講座の特長
進研ゼミ中学講座は、ベネッセコーポレーションが提供している中学生向けの通信教育です。
1969年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。進研ゼミ中学講座の特長は、以下の通りです。
- 学校の授業内容に沿った教材で、予習・復習が効率的にできる。
- タブレット学習を利用することで、ゲーム感覚で学習できます。
- 赤ペン先生による添削指導で、記述力や思考力を鍛えられる。
- 応用問題や演習問題で、実力を身につけられる。
- 夏休み特訓や冬期講習など、季節ごとの特別講座が充実。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
進研ゼミ中学講座は、中学校の授業内容をしっかり学びたい、記述力や思考力を鍛えたい、夏休みや冬休みの学習を充実させたい、といった中学生におすすめです。
\中学生の利用者NO.1の通信教育/
安心して利用できる
↓↓↓
進研ゼミ中学講座の公式サイトはこちらから
すらら:無学年方式オンライン教材で漢字を楽しく学ぶ!

「すらら」の基本情報
| 受講費用の安さ | ■入会金 11,000円 ■3教科(国・数・英)コースの月謝例 ・小中コース 月額:8,800円〜 小学1年生~中学3年生までの3教科(国・数・英)の範囲が学び放題 ・中高コース 月額:8,800円〜 |
| 対応科目・コース | 4教科(国・数・理・社)コース 5教科(国・数・理・社・英)コース 無学年方式で中学英語も先取り学習できる |
| 学習機能 | キャラクターによるレクチャーからドリル機能が充実 「すらら」は読み解くだけではなく、見て、聞いて学べる |
| 管理機能 | 「すらら」はAI搭載型ドリルだから自分のつまずきポイントがわかる! |
| サポート体制 | 学習習慣の身に付け方を始めとした学習に関する悩みや、基礎学力、成績を上げるための学習設計をサポートします。 |
すららの特長
すららは、株式会社すららネットが提供している中学生向けのオンライン学習教材です。
2010年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
すららの特長は、以下の通りです。
- 学年にとらわれない無学年方式で、子どものペースに合わせて学習できます。
- 子どもの弱点をAIが自動診断し、苦手な分野を効率的に克服できます。
- ゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な子どもでも楽しく学習できます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
すららは、学習に苦手意識を持っている子どもや、効率的に学習を進めたい子どもにおすすめです。
当サイトで人気No.1の通信教材!
是非!すららを選択肢の一つに
↓↓↓
「すらら」の公式サイトはこちらから
スマイルゼミ:漢字の学びが継続するタブレット教材
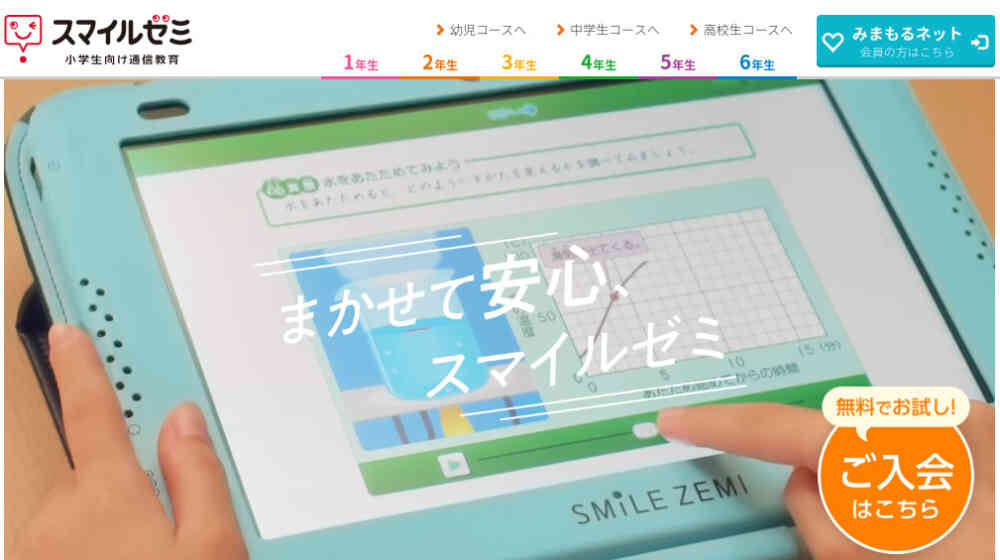
スマイルゼミの基本情報
| お手軽な受講費用 | 【中学1年生】月謝例 <標準クラス> ・7,480円〜:12か月一括払い/月あたり |
| 対応科目・コース | 国語・数学・理科・社会はもちろんのこと、英語やプログラミングも1年生から学習できる |
| 学習機能 | アニメーションによる解説で公式の持つ意味を正しく理解できる 手をついて書ける学習専用タブレットを使用 |
| 管理機能 | スマイルゼミのタブレットは、利用時間を「1日〇時間」という形で制限可能 |
| サポート体制 | 全額返金保証制度あり |
スマイルゼミの特長
スマイルゼミは、ジャストシステムが提供している中学生向けのタブレット学習教材。
2012年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
スマイルゼミの特長は、以下の通りです。
- タブレット端末を使って学習できるので、ゲーム感覚で楽しく学べます。
- 子どもの学習状況をAIが分析して、一人ひとりに合った学習内容を自動的に提案してくれます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
スマイルゼミは、タブレットで最適な学習を継続させたい人におすすめです。
中学生の学びが継続するタブレット
\返金保証制度あり/
↓↓↓
スマイルゼミの公式サイトはこちらから
中学生の漢字の勉強に最適なタブレット教材:デキタス
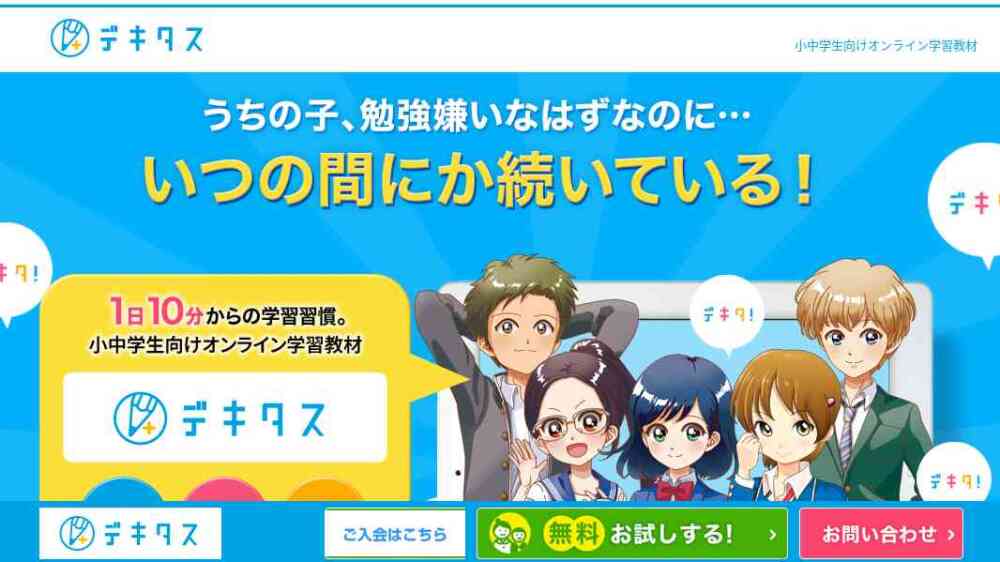
中学生におすすめ!デキタスの基本情報
| 項目 | デキタスの公式サイト |
| 受講費用 | 中学生:5,280円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、地理、歴史、公民、国文法、英語検定 |
| 学習機能 | ポップなキャラクター&わくわくする授業! |
| 管理機能 | テストモード搭載 |
| サポート体制 | 学習結果は表・グラフ・カレンダー等でひと目で確認することができます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
デキタスのおすすめポイント
学校の勉強を確実に理解していくことを目指し開発された、小中学生用オンライン学習教材です。
教科書内容に合った映像授業や、演習問題。さかのぼり学習で前の学年前の授業に戻ったり、定期テスト問題を作成して挑戦したりと、学校の勉強を自宅で、自分のペースで自由に行えます。
以下にデキタスの特徴を3つ紹介します。
段階的な学習体系: デキタスは「授業」→「○×チェック」→「基本問題」→「チャレンジ問題」というスモールステップで構成され、基礎から応用まで段階的に学習が進められます。この体系により、生徒は小さな成功体験を積み重ねながら学習し、「デキタ!」の達成感を実感できます。
デキタ'sノートと複合学習: デキタスでは授業に沿った穴埋め式ノートが印刷可能であり、デジタル教材と紙と鉛筆を組み合わせて効果的な学習ができます。この複合学習により、視覚的なデジタル学習と手書きによるノート作成が組み合わさり、理解の定着が促進されます。
学習習慣の形成: デキタスは学習結果を表・グラフ・カレンダーで確認し、保護者と共有する機能があります。親子で学習状況を共有し、成績アップを目指すことで学習習慣が自然に形成されます。
教科書の内容を確実に理解
学校の成績が上がる!
↓↓↓
デキタスの公式サイトチェック!
高校受験:漢字の勉強法に関するよくある質問

高校受験の漢字学習に関して、生徒や保護者の方からよくいただく質問とその回答をまとめました。
- 高校受験の漢字の勉強の仕方は?
- 高校受験の漢字は何級レベルですか?
- 受験漢字はいつから勉強すればいいですか?
- 漢字の効率的な覚え方は?
- 漢字検定は何級を目指せばいい?
- 国語以外の教科でも漢字力は役立つ?
- 過去問はいつ・どう使うべき?
高校受験の漢字の勉強の仕方は?
高校受験に向けた漢字の勉強は、まず基本をしっかり押さえることが大切です。
語源や成り立ちを理解することで、漢字そのものへの興味が湧き、記憶に残りやすくなります。
例えば、「海」という漢字が「水」と「毎」から成り立っていることを知ると、自然と関連性が感じられます。
また、漢字は「書いて覚える」が基本です。フラッシュカードや漢字アプリを使って、隙間時間に繰り返し復習することも効果的です。
さらに、例文の中で漢字を使ってみることで、実際に使える知識として定着します。
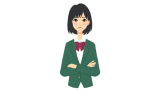
高校受験の漢字は何級レベルですか?
高校受験で問われる漢字のレベルは、一般的に漢字検定3級程度が基準とされています。
これは中学校卒業レベルに相当し、日常生活でよく使われる漢字や読み方が中心です。
しかし、難関校や進学校の場合、さらに高いレベルの漢字が出題されることもあります。
例えば、「標準」では3級レベルの漢字、「難関」では準2級レベルの漢字が出ることもあるため、過去問や模試で出題傾向を確認しながら、自分に合ったレベルの学習を進めることが重要です。
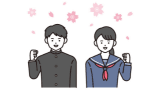
受験漢字はいつから勉強すればいいですか?
受験に向けた漢字の勉強は、できるだけ早めに始めるのが理想的です。
中学1年生の段階から毎日の学習に漢字を取り入れておくと、受験の直前に焦らずに済みます。
とはいえ、受験直前になってから漢字を強化したい場合でも、焦らずに計画的に取り組むことで効果が出ます。
まずは頻出漢字に重点を置き、試験でよく出る漢字から順に勉強することで、効率よく学べます。
具体的には、漢字ドリルやアプリを使い、毎日少しずつ学習を続けることがポイントです。

漢字の効率的な覚え方は?
漢字を効率よく覚えるためには、まず「読む」ことから始めましょう。
漢字の読み方を覚えたら、次は形を覚えるために「書く」練習が必要です。
例えば、お手本を見ながら漢字をノートに書き、その後にお手本を見ずに自分で書いてみると、記憶に残りやすくなります。
また、フラッシュカードや漢字アプリを活用することで、場所や時間に関わらず勉強できます。
1週間後に再度確認するなど、繰り返し学習することが、漢字をしっかりと定着させる秘訣です。
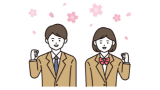
漢字が覚えられない時の対処法は?
「漢字が覚えられない」と悩む生徒は多いです。
そんな時は、原因を特定し、アプローチを変えることが大切です。
- 書くだけでは定着しない場合:音読しながら書く、例文や熟語とセットで覚える、人に教える(アウトプット学習)といった方法を試してみてください。
- 似た漢字で間違える場合:漢字の「違い」に焦点を当てた間違いノートを作り、それぞれの漢字のポイントを意識して覚えるようにしましょう。
- 単調で飽きてしまう場合:スマホアプリやゲーム感覚でできる問題集を取り入れるなど、学習方法に変化をつけてみてください。

漢字検定は何級を目指せばいい?
高校受験における漢字検定の目標級数は、一般的に3級〜準2級が目安です。
- 3級:中学校卒業程度の漢字能力とされ、高校入試の基本的な漢字レベルをカバーできます。
- 準2: 高校在学程度の漢字能力とされ、難関高校の対策や、漢字力をアピールしたい場合に有利です。 多くの高校では、漢字検定の取得が内申点加点や推薦入試の要件になることもありますので、目標級を設定して計画的に学習することをおすすめします。
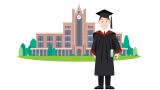
国語以外の教科でも漢字力は役立つ?
漢字力は、国語の試験だけでなく、他の教科の学習にも非常に役立ちます。
- 社会:歴史上の人物名、地名、専門用語など、漢字で書かれる言葉が多いため、漢字力があると内容の理解が深まります。
- 理科: 科学用語や現象名など、漢字で表される専門用語が多く、正確な理解には漢字力が不可欠です。
- 数学: 問題文の読解において、正確な漢字の理解が求められる場面もあります。 漢字力は、すべての学習の土台となる基礎力なのです。

過去問はいつ・どう使うべき?
過去問は、入試の傾向を知り、実践力を養うための最も重要な教材です。
- いつ使うか:中学3年生の夏休み以降、本格的な受験対策が始まる頃から取り組むのが一般的です。志望校の過去問は、最低でも3〜5年分は解いておきましょう。
- どう使うか
- 時間を計って本番同様に解く:時間配分の感覚を掴みます。
- 丸付けをして、間違えた漢字を「間違いノート」にまとめる:自分の弱点を把握します。
- なぜ間違えたのかを分析し、対策を立てる:同じ間違いを繰り返さないための具体的な学習計画を立てます。 過去問は単なる演習問題ではなく、志望校合格への道しるべです。
おすすめ塾
参考記事:国語塾『ヨミサマ。』の口コミ・評判を徹底調査!料金や授業内容の実態とは?
まとめ:【高校受験】漢字の勉強法と高校入試によく出る漢字を100個で得点UP!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。
以上、「【高校受験】漢字の勉強法と高校入試によく出る漢字を100個で得点UP!」でした。
【高校受験】漢字の勉強法と高校入試によく出る漢字を100個で得点UP!
まとめ
高校受験における漢字対策は、決して地味な努力ではありません。
むしろ、「継続×工夫」によって着実に点数に繋がり、最終的な合格を掴み取るための強力な武器となります。
私の長年の指導経験から、漢字の勉強は「すぐに結果が出ない」と諦めてしまう生徒が多いことを知っています。
しかし、多くの生徒が漢字の勉強で成功体験を積み、自信をつけていきました。
まずは、今日から「1日5分だけ漢字を勉強する」といった小さな目標から始めてみませんか?
たとえば、通学中に漢字アプリで10問だけ解く、寝る前に昨日間違えた漢字を5つだけ見直す。
こうした小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな自信となり、漢字を得点源へと変えてくれます。
漢字を制する者は、受験を制する。
ぜひこの記事でご紹介した勉強法と教材を参考に、今日から実践してみてください。
応援しています!
高校受験におすすめ塾の紹介
オンライン塾


