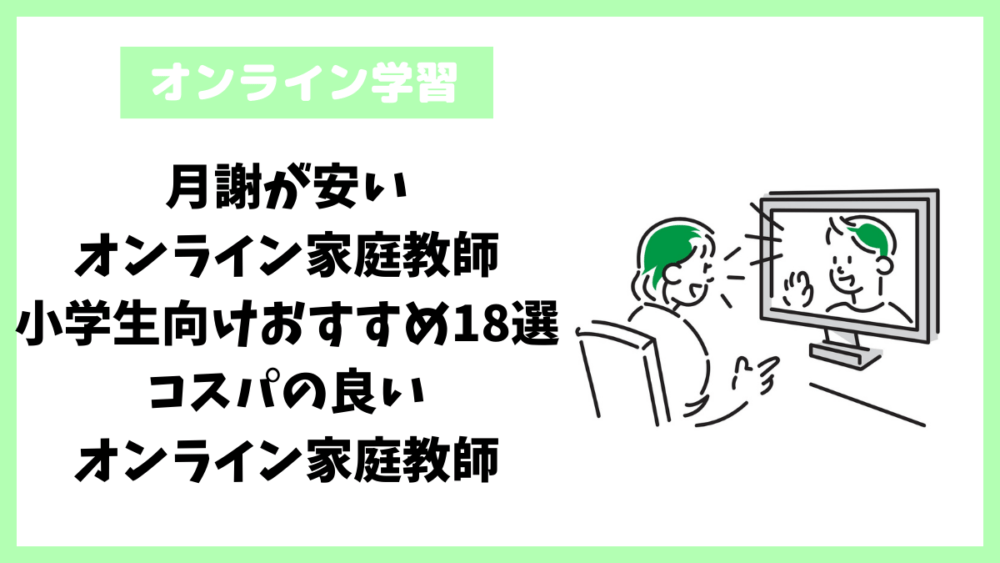
※この記事には一部PRが含まれます。
塾オンラインドットコム「合格ブログ」です。
小学生と中学生向けに、勉強に役立つ情報を発信している教育メディアです。
今回のお悩みはこちら。

タブレット学習に興味があります!
中学生におすすめのタブレット教材について教えてください!
タブレット教材は中学生に大人気!
今回は、中学生におすすめのタブレット教材について解説します。

中学生の皆さん!手軽に勉強できるタブレット教材って気になりませんか?
今回紹介する、「高校受験タブレット学習教材中学生│安い!おすすめ9選!塾よりお得」を読めば、おすすめのタブレット教材がわかります。
この記事では、おすすめのタブレット教材や選び方を具体的に紹介!
記事を読み終わると、自分にピッタリのタブレット教材が見つかるはずです。
読み終えるとわかること
タブレット学習のメリット・デメリット
中学生におすすめ!タブレット教材の選び方
中学生におすすめ!タブレット教材の紹介
タブレット学習の注意点
Contents
- 1 高校受験:中学生に人気のタブレット学習教材とは?
- 2 高校受験:中学生におすすめ!タブレット学習のメリット
- 3 高校受験:中学生向け:タブレット学習のデメリット
- 4 【高校受験対策】中学生におすすめタブレット学習教材一覧
- 5 高校受験におすすめタブレット学習教材「すらら」
- 6 進研ゼミ:中学講座は中学生に人気のタブレット教材
- 7 スマイルゼミ:中学生の学びが継続するタブレット教材
- 8 中学生に最適なタブレット教材:デキタス
- 9 Z会 中学生向けコース
- 10 中学生におすすめ!松陰スタディ
- 11 定額料金で中学生におすすめ!サブスタ
- 12 東進オンライン学校 中学部
- 13 スタディサプリ中学講座は中学生におすすめ!
- 14 【高校受験】中学生におすすめ!タブレット教材の選び方
- 15 タブレット学習教材が中学生におすすめな理由
- 16 高校受験タブレット学習の注意点
- 17 まとめ:高校受験タブレット学習教材中学生│安い!おすすめ9選!塾よりお得
高校受験:中学生に人気のタブレット学習教材とは?
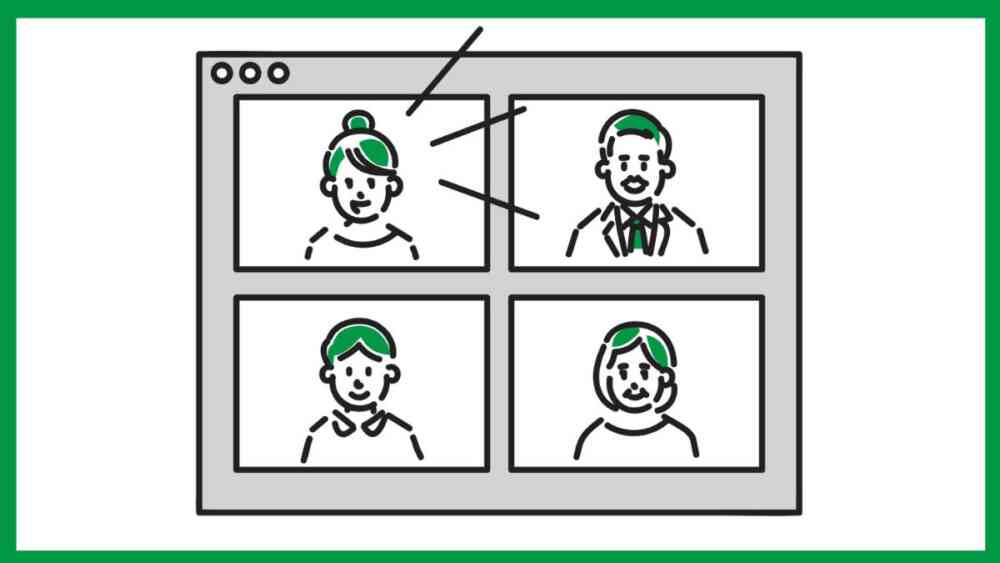

中学生向けのタブレット学習教材について解説します。
- タブレット教材とはどんな教材ですか?
- 中学生のタブレット学習は効果的ですか?
タブレット教材とはどんな教材ですか?
タブレット教材とは、タブレット端末を使って学習する教材です。
教科書やドリルなどの紙教材とは異なり、動画や音声、アニメーションなどを活用したインタラクティブな学習が可能です。
主な特徴は以下の通りです。
- 場所や時間に縛られない学習が可能:自宅はもちろん、外出先でも学習することができます。
- 楽しみながら学習できる:ゲーム感覚で取り組めるコンテンツも多く、学習へのモチベーションを高めることができます。
- 個別最適化された学習が可能:学習履歴や理解度に基づいて、最適な問題や課題を提供することができます。
- 学習状況を把握しやすい:問題ごとの正答率や学習時間などを記録することができ、学習状況を把握しやすくなっています。
タブレット教材の種類
タブレット教材には、教科書準拠のものとオリジナルのものがあります。
教科書準拠のものは、学校の授業内容に沿った内容で学習することができます。
オリジナルのものは、より自由度の高い内容で学習することができます。

中学生のタブレット学習は効果的ですか?
はい、中学生のタブレット学習は効果的です。
下記で紹介しますが、タブレット教材には多くのメリットがあります。
また、中学生はスマートフォンやタブレット端末に慣れているため、タブレット学習を受け入れやすいという利点もあります。
ただし、
- 教材を選ぶ際には、中学生のニーズに合ったものを選ぶことが重要です。
- 長時間画面を見続けるのは避け、適度に休憩を取るようにしましょう。
- 保護者の方も、子どもの学習状況を把握し、サポートすることが大切です。
これらの点に注意すれば、中学生のタブレット学習は、学習効果を高め、学習習慣を身につけるのに役立ちます。
高校受験:中学生におすすめ!タブレット学習のメリット


最初は、タブレット学習のメリットについて解説します。
タブレット学習のメリットはたくさんあります。
- 短期間で成績アップが期待できる
- いつでもどこでも学習できる
- 個別学習で効率的に学習できる
- ゲーム感覚で楽しく学習できる
- タブレット教材は費用が安い
短期間で成績アップが期待できる
中学生向けのタブレット学習は、短時間で学習ができるよう設計されており、個別の学習ニーズに対応しています。
学習履歴を元に苦手な分野が提示され、効率的かつ個別に合わせた学習が可能です。
個人に適したカリキュラムが提供され、これにより短時間で効果的に学習し、成績向上が期待できます。
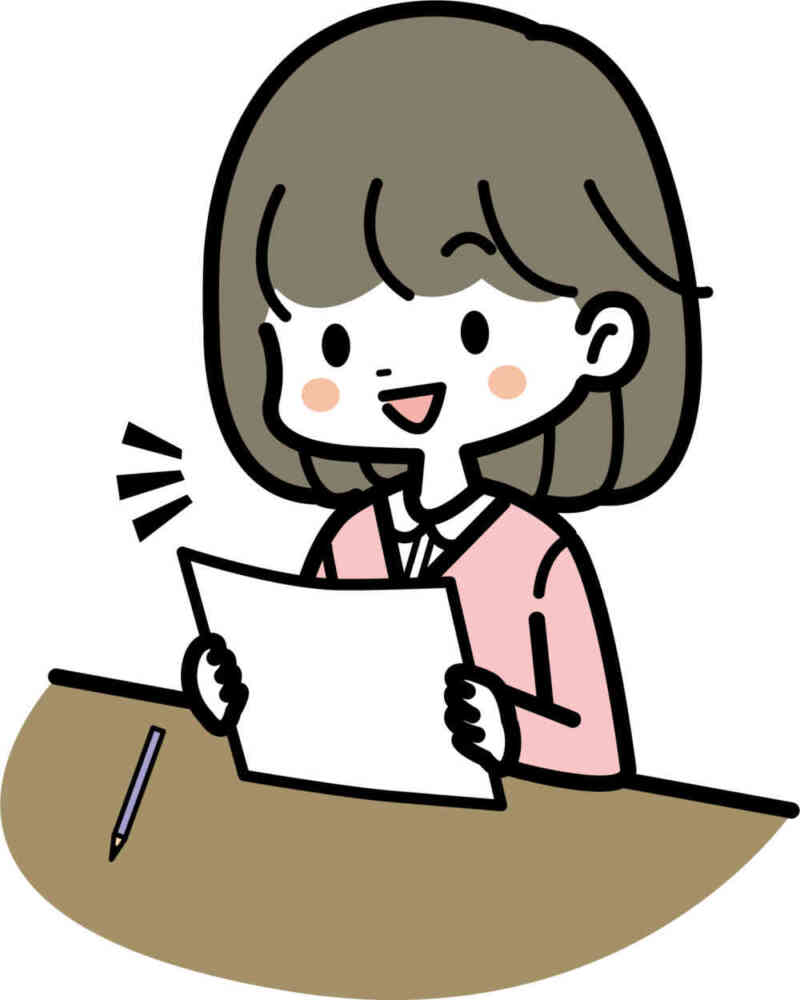
タブレット学習のメリット:いつでもどこでも学習できる
高校受験タブレット学習の大きなメリットは、学習をいつでもどこでも行える点です。
生徒は自宅、図書館、外出先などで、スマートタブレットを使用して学習できます。
この柔軟性により、通学時間や待ち時間を有効活用し、学習時間が増やせます。

個別学習で効率的に学習できる
高校受験タブレット学習は個別学習をサポートし、生徒の学習スタイルに合わせた効率的な学習が可能です。
生徒は自分の進度に合わせて学習内容を調整し、難しい問題などにも時間をかけて習得できます。
例えば、数学の苦手単元がある場合、それに専念して練習することが可能です。
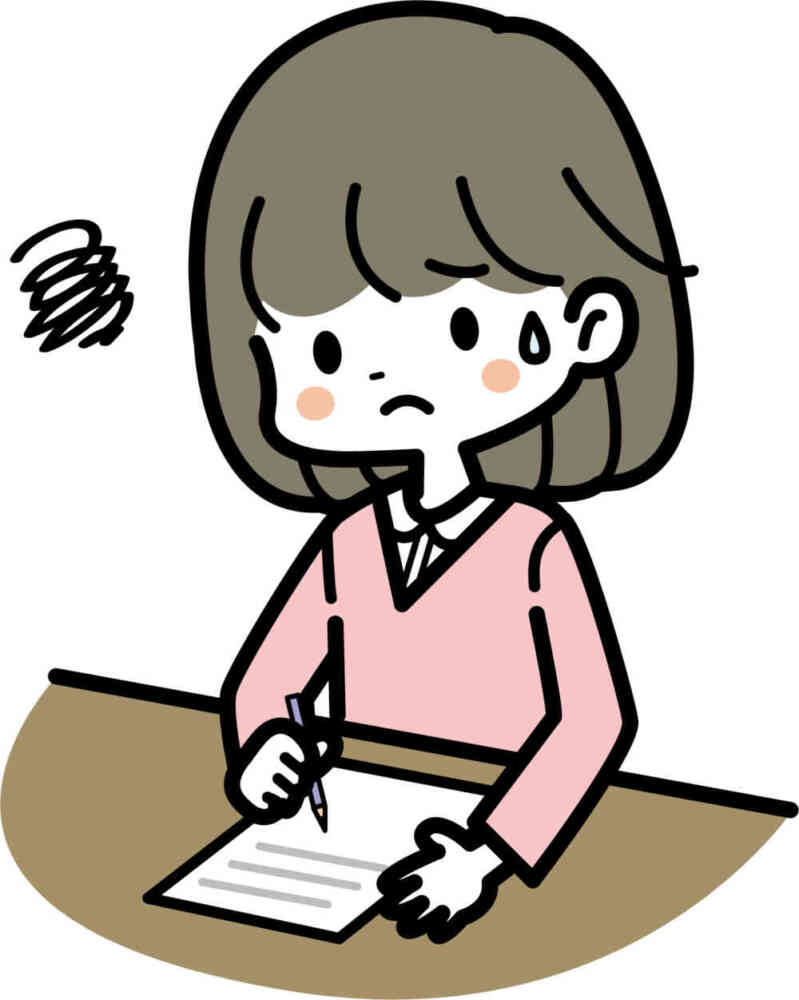
タブレット学習はゲーム感覚で楽しく学習できる
多くの高校受験タブレット学習プラットフォームは、ゲーム要素を取り入れています。
クイズ、パズル、競争要素などを通じて、生徒は楽しみながら学びます。
このアプローチはモチベーションを高め、学習意欲を維持するのに効果的です。
例えば、英単語の学習を単なる暗記から、単語ゲームを通じて楽しく勉強できます。

タブレット教材は費用が安い
タブレット学習の費用は、従来の紙の教材に比べて安いことが多い。
なぜなら、タブレット教材は、紙の教材を印刷する必要がなく、デジタルで配信されるためです。
また、タブレット教材は、更新や追加が簡単にできるので、毎年新しい教材を買い替える必要もありません。
そのため、タブレット学習は、家計の負担を軽減できます。
タブレット学習の費用は、教材の種類やコンテンツによって異なりますが、一般的に月額1,000円から10,000円程度です。
また、一部の教材では、無料で利用できるコンテンツも提供されています。
タブレット学習は、費用が安いだけでなく、いつでもどこでも学習できる、個別学習で効率的に学習できる、ゲーム感覚で楽しく学習できるなどのメリットがあります。
参考記事:中学生向けオンライン塾人気ランキングTOP20|入会金・月謝を徹底比較
高校受験:中学生向け:タブレット学習のデメリット
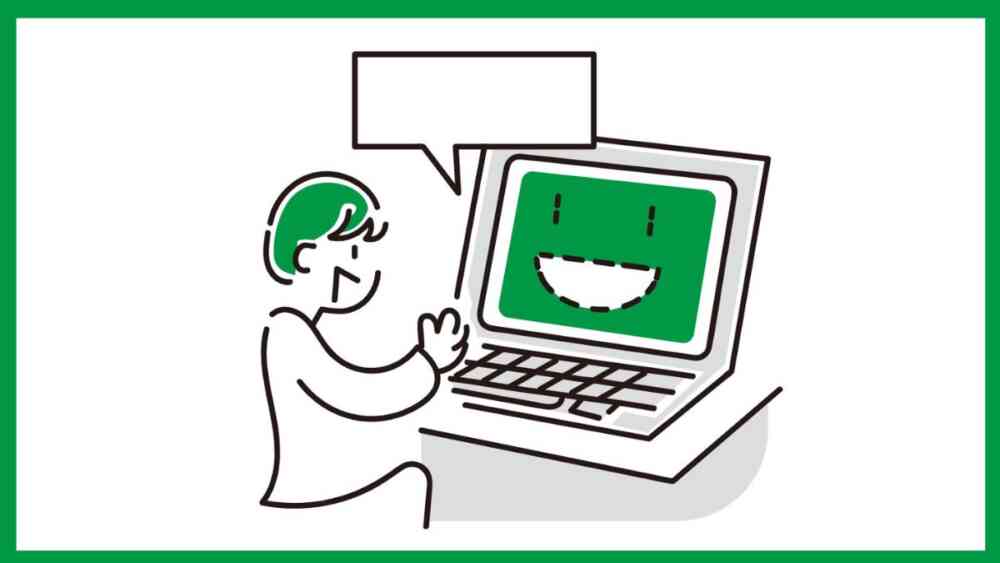

タブレット学習はメリットもありますが、デメリットもあります。
タブレット学習のデメリットを説明します。
- 視力への影響
- ネットの依存症
- セキュリティリスク
タブレット学習のデメリット:視力への影響
高校受験タブレット学習は、長時間の画面時間を必要とするため、生徒の視力に悪影響を及ぼす可能性があります。
長時間の画面閲覧は目の疲れやドライアイを引き起こす可能性があります。
この問題に対処するために、適切な休憩時間や画面からの遠ざかりを取り入れる必要があります。

ネットの依存症
高校受験タブレット学習はオンライン環境で行われるため、ネット依存症に陥るリスクが存在します。
生徒は学習の一環としてネットサーフィンを行い、時間を無駄にしてしまう可能性があります。
この問題に対処するために、学習と娯楽の区別を明確にし、学習時間を計画的に使うことが重要です。
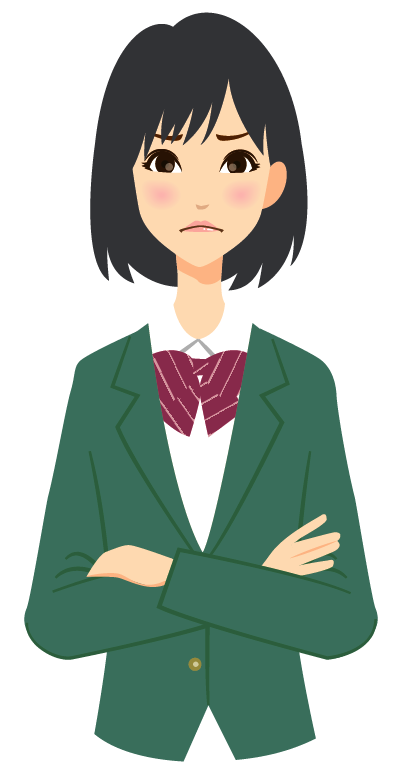
セキュリティリスク
高校受験タブレット学習では、オンラインで個人情報を入力することが必要な場合があります。
しかし、セキュリティの不備や信頼性の低いプラットフォームを使用すると、個人情報が漏洩するリスクがあります。安全なプラットフォームを選択し、セキュリティ対策をしっかりと実施することが必要です。
参考記事:【中学生】オンライン個別指導塾おすすめ15選!忙しい中学生も頑張れる!
【高校受験対策】中学生におすすめタブレット学習教材一覧

| タブレット学習教材名 | 入会金 | 月謝 |
| すらら | 小中・中高5教科コース: 7,700円 小中・中高3教科、小学4教科コース:11,000円 | 小中コース:8,800円〜 |
| 進研ゼミ:中学講座 | 無料 | 中学1年生:6,400円〜 |
| スマイルゼミ | 無料 | 小学生:3,278円〜中学生:7,480円〜 |
| デキタス | 無料 | 小学生:3,960円、中学生5,280円 |
| Z会 中学生向けコース | 無料 | 中学生単科受講:2,023円〜 |
| 松陰スタディ | 22,000円※無料になるクーポンあり | 小学生:16,170円〜、中学生:17,050円〜 |
| サブスタ | 無料 | 小学生:4,900円、中学生:7,900円 |
| 東進オンライン学校中学部 | 無料 | 中学生:3,278円〜 |
| スタディサプリ中学講座 | 無料 | 2,178円〜 |
※オンライン料金の詳細については公式サイトからお問い合わせください。※社名をタップすると公式ホームページに移動します。
※学年や講師ランク・授業時間により料金は変動します。
- 中学生活、勉強がうまくいかなくて悩んでいませんか?
- 塾に通いたいけど、高額な費用がネックになっていませんか?
- 自習しようと思っても、なかなか集中できないことがありますよね?
中学での学習は、高校受験や将来への分かれ道となる重要な時期です。
基礎がしっかりできていないと、将来的に大きな差がついてしまう可能性があります。
勉強が苦手だと、自信を失い、やる気がなくなってしまうこともあります。
そんなあなたにおすすめなのが、タブレット学習教材です。
タブレット学習教材なら、塾よりも圧倒的に低価格で、いつでもどこでも学習することができます。
豊富なコンテンツで、苦手科目を克服し、学習習慣を身につけることができます。
今なら、無料体験を実施中!
- 無料体験では、全機能を自由に試すことができます。
- 実際に使ってみて、自分に合っているかどうかを判断できます。
- 気に入ったら、すぐに入会することができます。
実際、当サイトからたくさんのお申し込みを頂いているサービスなので、気になるタブレット学習教材があれば、積極的に無料体験してみましょう!
高校受験におすすめタブレット学習教材「すらら」

タブレット教材「すらら」の基本情報
| 項目 | すららの公式サイト |
| 料金 | ■入会金 ・小中・中高5教科コース:7,700円 ・小中・中高3教科、小学4教科コース:11,000円 ■3教科(国・数・英)コースの月謝例 ・小中コース 月額:8,800円〜 小学1年生~中学3年生までの3教科(国・数・英)の範囲が学び放題 ・中高コース 月額:8,800円〜 |
| 対応科目・コース | 4教科(国・数・理・社)コース 5教科(国・数・理・社・英)コース 無学年方式で中学英語も先取り学習できる |
| 学習機能 | キャラクターによるレクチャーからドリル機能が充実 「すらら」は読み解くだけではなく、見て、聞いて学べる |
| 管理機能 | 「すらら」はAI搭載型ドリルだから自分のつまずきポイントがわかる! |
| サポート体制 | 学習習慣の身に付け方を始めとした学習に関する悩みや、基礎学力、成績を上げるための学習設計をサポートします。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
中学生におすすめのタブレット教材!
↓↓↓
中学生におすすめ!すららの特徴
無学年式の学習プラットフォーム: すららは無学年式を採用しており、生徒が自分のペースで学習できる環境をサポートしています。これにより、苦手な箇所を重点的に学ぶことができ、個々の学習ニーズに合わせた教育が可能です。
アニメ講師による解説: 学習の際にはアニメ講師が解説を行い、生徒にわかりやすい形で学習内容を伝えます。アニメを通じた視覚的で親しみやすい解説は、生徒の学習意欲を高める一因となっています。
手軽なLINEサポート体制: すららではLINEを通じてサポートが提供されており、保護者や生徒は気軽に質問や相談を行うことができます。この手軽なサポートが利用者に安心感をもたらしています。
中学生におすすめ!すららのメリット・デメリット
メリット
無学年学習の柔軟性: 学習を何年も前に戻してやり直すことや、逆に未学習の内容を先取りすることができる。
サポート体制の充実: すららコーチによる保護者向けサポートと生徒向け応援メッセージがあり、学習の進捗や悩みに対して手厚いサポートが受けられる。
徹底した復習の効果: 復習に力を入れることで、苦手な分野を克服しやすくなっている。
複数のコース提供: 3教科、4教科、5教科のコースがあり、学習の幅を広げることができる。
ゲーム感覚での学習: 生徒がゲーム感覚で学習できるため、楽しみながら取り組むことができる。
デバイスの柔軟な利用: 手元のPCやタブレットを使用して学習できる。
デメリット
受講費用の高さ: 受講費用が高額であるため、経済的な負担が大きい。
復習問題の過多: 復習問題が多く、その量が受講者にとって過剰に感じられることがある。
基礎学力中心のカリキュラム: 受験対策よりも基礎学力の定着がメインであるため、受験に特化したニーズには十分に応えていない。
専用タブレットの不提供: 専用のタブレットが提供されていないため、デバイスの用意が必要となる。
中学生におすすめのタブレット教材!
↓↓↓
進研ゼミ:中学講座は中学生に人気のタブレット教材
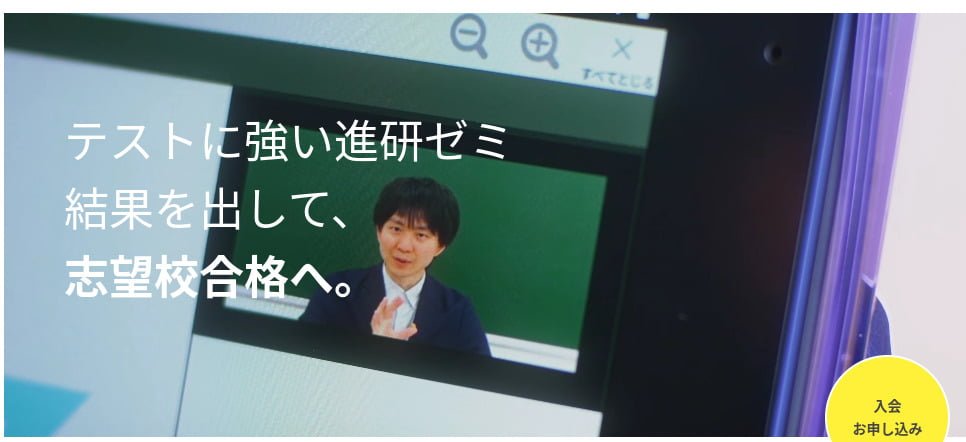
中学生利用者NO.1!進研ゼミ:中学講座の基本情報
| 項目 | 進研ゼミ公式サイト |
| 料金 | 【月謝例】 中学1年生:6,400円〜 中学2年生:6,570円〜 中学3年生:7,090円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、理科、社会、英語 |
| 学習機能 | 教科書対応のテキストで、予習も復習もバッチリ! お使いの教科書に合わせたテキストなので、予習はもちろん復習にも効率的に |
| 管理機能 | AIのレッスン提案で迷わない実力に合わせて学習スタート 学習達成後のごほうびでやる気が続く |
| サポート体制 | 月1回、赤ペン先生がお子さま一人ひとりを添削し、丁寧に指導。担任制なので、毎回同じ先生に提出する楽しみがうまれ、毎月の学習の仕上げとしてしっかり取り組めます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
利用者NO.1のタブレット教材
↓↓↓
中学生に人気の進研ゼミ中学講座の特徴
進研ゼミ中学講座は、ベネッセコーポレーションが提供している中学生向けの通信教育です。
1969年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。進研ゼミ中学講座の特徴は、以下の通りです。
- 学校の授業内容に沿った教材で、予習・復習が効率的にできる。
- タブレット学習を利用することで、ゲーム感覚で学習できます。
- 赤ペン先生による添削指導で、記述力や思考力を鍛えられる。
- 応用問題や演習問題で、実力を身につけられる。
- 夏休み特訓や冬期講習など、季節ごとの特別講座が充実。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
進研ゼミ中学講座は、中学校の授業内容をしっかり学びたい、記述力や思考力を鍛えたい、夏休みや冬休みの学習を充実させたい、といった中学生におす
進研ゼミ:中学講座のメリット・デメリット
メリット
多教科対応: 9教科にわたる幅広い科目に対応しており、学習の幅を広げられる。
ハイブリッドスタイル: タブレット学習と紙の学習が組み合わさり、それぞれのメリットを生かした効果的な学習が可能。
AIによる分析指導: 学習データを元にしたAIが個別分析指導を行い、学力向上に必要なテーマやテスト対策を的確に提案。
オンラインライブ授業: 双方参加型のオンラインライブ授業で、即座に質問ができるため、生徒の理解を深めるのに役立つ。
デメリット
学習項目の多様性: タブレット内での学習や添削問題、オンラインライブ授業、紙の学習など多くの学習項目があるため、管理が煩雑になる可能性がある。
Wi-Fi環境の制約: タブレットの利用にはWi-Fiが必要であり、環境やアクセス集中により繋がらない場合がある。
タブレットの保障: 保障がない場合、修理や交換代が高額になる可能性があり、コストがかかることが懸念される。
自主学習の誘惑: 塾や家庭教師のような束縛がないため、生徒にとっては自主学習の誘惑があり、意欲次第で成果が異なる。
利用者NO.1のタブレット教材
↓↓↓
スマイルゼミ:中学生の学びが継続するタブレット教材
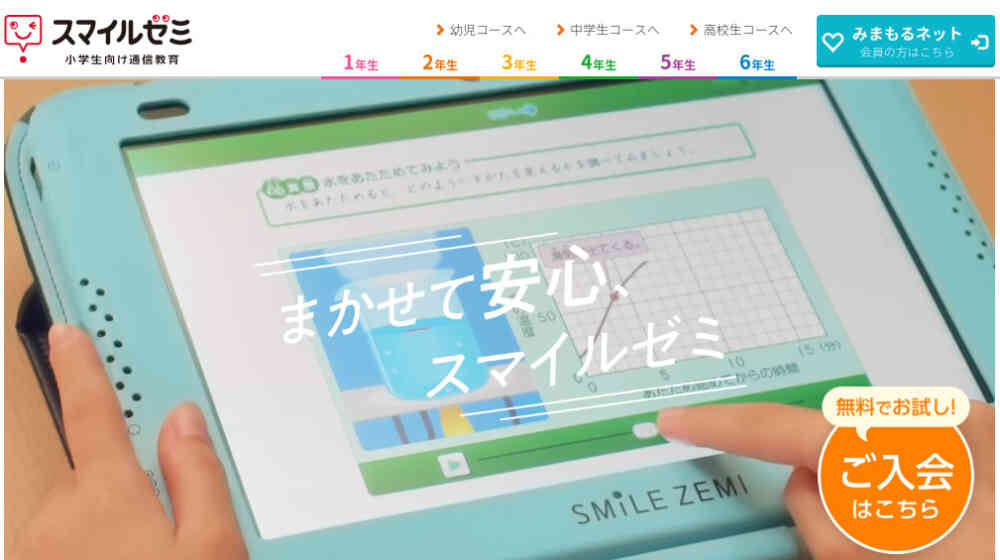
中学生におすすめ!スマイルゼミの基本情報
| 項目 | スマイルゼミの公式サイト |
| 料金 | 【中学1年生】月謝例 <標準クラス> ・7,480円〜:12か月一括払い/月あたり |
| 対応科目・コース | 国語・数学・理科・社会はもちろんのこと、英語やプログラミングも1年生から学習できる |
| 学習機能 | アニメーションによる解説で公式の持つ意味を正しく理解できる 手をついて書ける学習専用タブレットを使用 |
| 管理機能 | スマイルゼミのタブレットは、利用時間を「1日〇時間」という形で制限可能 |
| サポート体制 | 全額返金保証制度あり |
| 無料体験の有無 | 2週間の無料体験実施中 |
中学生の学びが継続するタブレット
↓↓↓
スマイルゼミの特徴
スマイルゼミは、ジャストシステムが提供している中学生向けのタブレット学習教材。
2012年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
スマイルゼミの特長は、以下の通りです。
- タブレット端末を使って学習できるので、ゲーム感覚で楽しく学べます。
- 子どもの学習状況をAIが分析して、一人ひとりに合った学習内容を自動的に提案してくれます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
スマイルゼミは、学習に苦手意識を持っている子どもや、効率的に学習を進めたい子どもにおすすめです。
スマイルゼミのメリット・デメリット
メリット
多教科対応: 英語、数学、国語、理科、社会、保健体育、音楽、美術、技術家庭の9教科に対応し、幅広い学習が可能。
高機能タブレット: タブレットの機能が他社に比べて高いため、より快適な学習環境が提供される。
単一デバイスで学習: タブレット1台で学習が可能で、テキストやプリントの増加を抑えられる。
個別データ分析と学習提案: 学習状況や習熟度をデータ化し、個別に適した学習プランを提示してくれる。
Android化可能: 退会後もタブレットをAndroid化して利用できるため、資産の有効活用が可能。
デメリット
添削指導の不足: 丁寧な添削指導がないため、学習の理解度を確認する手段が限られている。
学習の単一媒体: タブレットで行う学習のみなので、他の媒体がないため物足りなさを感じることがある。
自主学習の誘惑: 塾や家庭教師のような束縛がない分、生徒にとっては自主学習の誘惑があり、意欲次第で成果が異なる。
中学生の学びが継続するタブレット
↓↓↓
中学生に最適なタブレット教材:デキタス
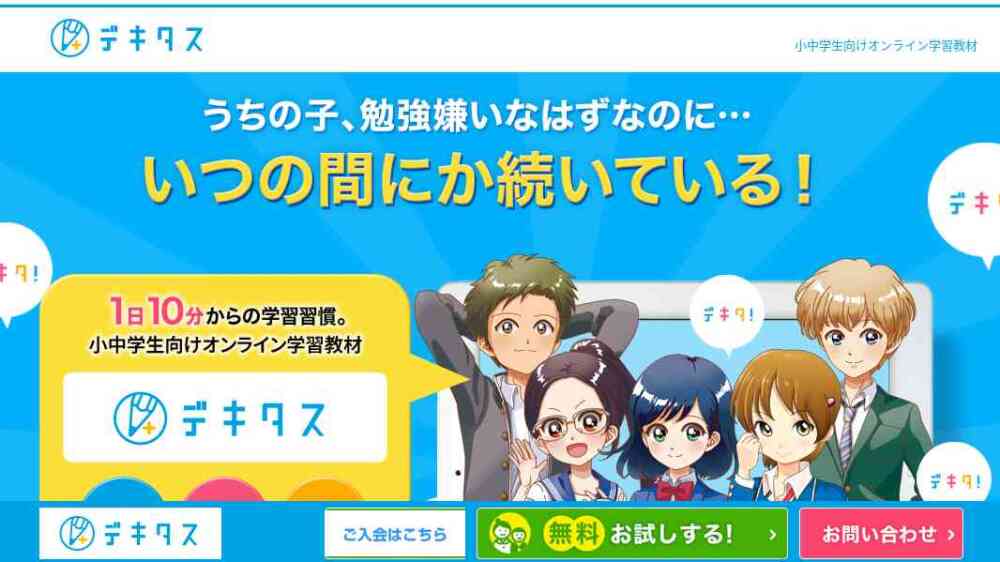
中学生におすすめ!デキタスの基本情報
| 項目 | デキタスの公式サイト |
| 料金 | 中学生:5,280円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、地理、歴史、公民、国文法、英語検定 |
| 学習機能 | ポップなキャラクター&わくわくする授業! |
| 管理機能 | テストモード搭載 |
| サポート体制 | 学習結果は表・グラフ・カレンダー等でひと目で確認することができます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
教科書の内容を確実に理解
↓↓↓
デキタスの特徴
学校の勉強を確実に理解していくことを目指し開発された、小中学生用オンライン学習教材です。
教科書内容に合った映像授業や、演習問題。さかのぼり学習で前の学年前の授業に戻ったり、定期テスト問題を作成して挑戦したりと、学校の勉強を自宅で、自分のペースで自由に行えます。
以下にデキタスの特徴を3つ紹介します。
段階的な学習体系: デキタスは「授業」→「○×チェック」→「基本問題」→「チャレンジ問題」というスモールステップで構成され、基礎から応用まで段階的に学習が進められます。この体系により、生徒は小さな成功体験を積み重ねながら学習し、「デキタ!」の達成感を実感できます。
デキタ'sノートと複合学習: デキタスでは授業に沿った穴埋め式ノートが印刷可能であり、デジタル教材と紙と鉛筆を組み合わせて効果的な学習ができます。この複合学習により、視覚的なデジタル学習と手書きによるノート作成が組み合わさり、理解の定着が促進されます。
学習習慣の形成: デキタスは学習結果を表・グラフ・カレンダーで確認し、保護者と共有する機能があります。親子で学習状況を共有し、成績アップを目指すことで学習習慣が自然に形成されます。
デキタスのメリット・デメリット
メリット
段階的な学習体系: デキタスは「授業」→「○×チェック」→「基本問題」→「チャレンジ問題」といった段階的な学習プロセスを提供しています。これにより、生徒は基礎から徐々に応用まで学習でき、小さな成功体験を通じて理解を深めることができます。
複合学習の機会: デキタスのノート機能は穴埋め式で印刷可能であり、デジタル教材と紙と鉛筆を組み合わせて学習できます。複合学習により、視覚的なデジタル学習と手書きノートの作成が組み合わさり、理解の定着を促進します。
学習習慣の形成: 学習結果を表・グラフ・カレンダーで可視化し、保護者と共有できる機能があります。親子で学習状況を確認し、目標に向かって進捗を共有することで、生徒は学習習慣を身につけやすくなります。
がんばったご褒美: ログインポイントや学習したポイントを貯めることで、豪華な景品やアバターと交換できる「がんばったご褒美」が用意されています。生徒が自分の努力に報酬を感じることでモチベーション向上に寄与します。
柔軟でアクセスしやすい環境: タブレット学習を中心に提供されているため、場所や時間に縛られず柔軟にアクセスできる環境が整っています。
デメリット
個別添削指導の不在: デキタスは主に自己学習を重視しており、個別添削指導が不足している可能性があります。生徒が理解に苦しんだ際に直接質問できるサポートが限られているかもしれません。
紙媒体の不足: デキタスは主にデジタル教材に焦点を当てていますが、一部の生徒にとっては紙媒体が好ましい場合があります。従って、紙ベースの教材や添削が不足すると感じることがあります。
オフライン利用の難しさ: タブレット学習が中心のため、インターネット接続が必要です。オフライン環境での利用が難しい場合、学習の制約を感じることがあります。
個別進度に対応しづらさ: 生徒それぞれの学習ペースに合わせて進めることができる一方で、個別進度に対応する柔軟性が制限されることも考えられます。
専門的な科目に対する深堀り不足: 幅広い科目に対応している一方で、専門的な科目に深堀りできる機会が不足する可能性があります。生徒が特定の科目に特に力を入れたい場合には物足りなさを感じるかもしれません。
教科書の内容を確実に理解
↓↓↓
Z会 中学生向けコース

中学生におすすめ!Z会 中学生向けコースの基本情報
| 項目 | Z会 中学生向けコースの公式サイト |
| 料金 | 中学生単科受講:2,023円〜、5講座:9,084円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、社会 |
| 学習機能 | 基礎完成ドリル機能 |
| 管理機能 | 学習管理機能「Z会学習支援者サイト」 |
| サポート体制 | Z会の教材でわからないことがあればプロが解消 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
合格率96.3%!無料体験
↓↓↓
Z会 中学生向けコースの特徴
Z会の中学生向けコースは、5年連続でイードアワード中学生タブレットの部でNo.1に輝いたタブレット学習教材です。
その特徴的なポイントの一つは、高い志望校合格率であり、96.3%という実績を誇っています。
Z会の中学生向けコースは他社通信教材よりも難易度が高いため、難関とされる高校受験に挑戦する中学生に最適です。
映像授業と演習を組み合わせたバランスの良い学習方法が採用されており、すべての学習がタブレット上で完結します。
生徒は自分のペースで学び、難易度の高い問題に挑戦することで、自己成長を促進できます。
Z会の中学生向けコースは無理なく学力を向上させるだけでなく、挑戦的な学習環境と刺激的な学びの機会を提供しています。
Z会は、高品質な教育コンテンツと効果的な学習サポートを通じて、中学生の学力向上をサポートしています。
Z会 中学生向けコースのメリット・デメリット
メリット
柔軟な学習プラン:5教科セットまたは1教科から選べる柔軟な学習プランが用意されている。
iPad対応:手持ちのiPadでも学習が可能(対応機種に限る)で、学習環境の柔軟性があります。
丁寧な添削:学習において添削があり、生徒一人ひとりに対する丁寧な添削が受けられます。
AI技術の活用:AI技術により学習到達度が一目でわかり、苦手を克服するのに役立ちます。
デメリット
試験対策中心:内申点対策よりも、受験当日の試験対策に焦点を当てているため、学校の内申点向上を重視する方には適していないかもしれない。
使用できる端末が限られる:Z会中学生向けコースは、使用できる端末が限られているため、特定の機種に制限される可能性があります。
主要5教科のみ:保健体育や音楽などの副教科がないため、幅広い教養を求める人には不向きかもしれません。
これらのメリットとデメリットを考慮することで、生徒や保護者はZ会の中学生向けコースが自分のニーズに合っているかどうかを判断できるでしょう。
合格率96.3%!無料体験
↓↓↓
中学生におすすめ!松陰スタディ

中学生におすすめ!松陰スタディの基本情報
| 項目 | 松陰スタディの公式サイト |
| 料金 | コーチングコース:中学生 60分 週2回~ 17,050円 ~ プライベートコース:中学生 60分 週2回~ 25,850円 ~ |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、社会 |
| 学習機能 | AI-Showin学習システム |
| 管理機能 | 指導報告は毎回 |
| サポート体制 | コーチは全員社会人 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
無料体験実施中!
↓↓↓
松陰スタディの特徴
松陰スタディの特徴は、まず、安心の定額月謝制度です。
小学1年生から中学3年生までの生徒が、小中5教科・12万問の問題を全てのコースで復習・予習可能で、月謝は定額制で発生する追加費用はありません。
次に、自立学習教材「Showinシステム」があります。
ショウインが自社開発したこのシステムは、わかるの3大法則に基づいて設計され、楽しみながら効率的に学力を向上できます。
そして、専用ノートを使用したアウトプット学習が特徴的です。
Showinシステムの学習内容に合わせて専用ノートを使用し、アウトプット学習を通じて確実な学力の定着をサポートします。
これにより、学習習慣が身につき、学力向上が期待できます。
松陰スタディのメリット・デメリット
メリット
自立学習強化: 松陰スタディはShowinシステムを導入し、自立学習を重視しています。子どもたちが自ら考え、学ぶことで、知識の定着が期待できます。
経験豊かな社会人コーチ: 学生アルバイトではなく、経験豊かな社会人コーチが指導。個別に合わせた効果的なサポートが受けられ、学習意欲の向上に寄与します。
柔軟な学習環境: 学校に行けない事情のある子どもや発達障害のある子どもにも適した学習環境を提供。個々の進度や学習方法に合わせたアプローチが可能。
デメリット
高額な月謝:プライベートコースなど一部のコースは月謝が高額であるため、経済的な負担が大きい可能性がある。
オンライン学習への適応が必要:完全にオンラインでの学習を行うため、生徒がオンライン学習に適応できるかどうかが課題となるかもしれません。
副教科の不足:主要5教科に対応しているものの、全ての副教科を網羅していないため、学校の補完となる面が限られる。
松陰スタディは、LINE追加のみで入塾金が無料になり、学習用ノートPC(45,890円相当)がプレゼントされるキャンペーンを実施中です。
このキャンペーンの条件は1年間の継続利用が必要ですが、この特典を利用することで、初期費用を抑えて松陰スタディを始めることができます。
無料体験実施中!
↓↓↓
定額料金で中学生におすすめ!サブスタ

中学生におすすめ!サブスタの基本情報
| 項目 | サブスタの公式サイト |
| 料金 | 中学1年〜3年生:7,900円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、社会 |
| 学習機能 | 小中学生向けに、1000本以上のプロ講師の授業動画が見放題。 |
| 管理機能 | 一人ひとりに合わせた学習計画表を作成 |
| サポート体制 | 全学年の学習内容を網羅、先取りも戻り学習も自由自在 |
| 無料体験の有無 | Line登録で体験版の利用が可能 |
おうち学習のサブスク
↓↓↓
サブスタの特徴
サブスタは、生徒の学年に関係なく、必要な学年の単元を選択的に学べる無学年式教材を特徴としています。
これにより、戻り学習や先取り学習が自由にでき、学び残しを解消できます。
各教科では、系統学習を重視し、中学1年生から3年生までの内容がセットになっています。
充実した教科カリキュラムは文部科学省の要領に基づき、例えば社会科では地理・歴史・公民を統合しストーリー性を取り入れています。
さらに、数学では基礎概念の理解を強調し、英語では動画学習で楽しみながら実用的な英語力を養います。
プロの学習アドバイザーが一人ひとりに合わせた学習計画を提供し、24時間いつでもアクセス可能な学習環境を整えています。
これにより、生徒は自分のペースで学習し、効果的な学び方を身につけることができます。
サブスタのメリット・デメリット
メリット
学習計画の作成:サブスタは生徒一人ひとりに合わせた学習計画を提供し、目標に向けたカスタマイズされた学習が可能です。
各社の教科書に対応:カリキュラムが各社の教科書に対応しているため、学校で使用されているテキストと連携して効果的な学習ができます。
先取・さかのぼり学習が可能:生徒が理解できていない部分について、戻り学習や先取り学習が柔軟にできるので、個々の進度に合わせた学習ができます。
料金が一定:月額料金が一定であるため、予算の管理がしやすく、途中での追加料金の心配がありません。
赤ペン映像を使った解答解説:間違えた問題に対する赤ペン映像を通じた解答解説があり、理解度向上に寄与します。
デメリット
追加オプションがない:サブスタには追加オプションがないため、生徒が特定の要望やニーズに対応する拡張機能が限定的です。
親のサポートが必要:オンライン学習は生徒だけでなく、親もサポートする必要があります。親がサポートできる状況でないと、学習の進捗に影響を与える可能性があります。
5教科以外は学べない:サブスタでは5教科以外の学習が提供されていないため、他の科目に興味がある場合には別途対応が必要です。
おうち学習のサブスク
↓↓↓
東進オンライン学校 中学部

東進オンライン学校 中学部の基本情報
| 項目 | 東進オンライン学校 中学部の公式サイト |
| 料金 | 中学生:3,278円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、社会 |
| 学習機能 | 一流の講師陣による映像授業 |
| 管理機能 | 「確認テスト」「月例テスト」を定期的に実施 |
| サポート体制 | 東進と四谷大塚のノウハウ |
| 無料体験の有無 | 10日間のお試し入会制度あり |
一流の講師陣の授業が受けられる
↓↓↓
東進オンライン学校 中学部の特徴
東進オンライン学校の中学部は、中学1~3年生向けに英語と数学の標準講座、国語・理科・社会の実戦力養成講座が用意されています。
標準講座では基礎から実力の底上げを目指し、英語はネイティブ講師による実践的な授業でスキル向上。
数学は難しい概念を視覚的に説明し、大学受験までフォローが受けられます。
実戦力養成講座では、平均点の壁を越え、国語・理科・社会で高得点を目指す勉強法を学びます。
テストの結果から成績向上が確認され、学力向上を実現できる中学生向けの効果的なカリキュラムが特徴です。
東進オンライン学校 中学部のメリット・デメリット
メリット
自宅で本格的な授業:パソコンやスマホで場所を選ばずに授業を受けられ、自分のペースで学習が進められる。
教育のプロによるノウハウ:四谷大塚と東進の提携により、経験豊富なプロ講師が生徒の理解を促進する分かりやすい授業を提供。
分かりやすい料金体系:料金は月払いと12ヵ月一括払いの2種類で、一括払いがお得。追加教材や通塾にかかる交通費がなく、費用を最低限に抑えられる。
デメリット
テストがマークシート方式:確認テストがマークシート形式であり、記述式のテストがないため、記述力向上には不向き。
テキスト印刷が必要:授業ごとにテキストをダウンロードして印刷する必要があり、プリンターの用意や手間がかかる。
一流の講師陣の授業が受けられる
↓↓↓
スタディサプリ中学講座は中学生におすすめ!

タブレット学習:中学生スタディサプリの基本情報
| 項目 | スタディサプリの公式サイト |
| 料金 | ・中学生:12か月一括払い:1,815円(税込)/月額 |
| 対応科目・コース | ・中学1年生〜中学3年生:数学・国語・理科・社会・英語、実技4教科(音楽・美術・技術家庭・保健体育)も対応! ・中学受験対策 |
| 学習機能 | 映像授業 |
| 管理機能 | 学習管理機能あり |
| サポート体制 | 授業動画視聴+テキストに書き込み |
| 無料体験の有無 | あり:会員登録により14日間無料体験可能(クレジットカード決済のみ適用) |
中学生の学習をサポートする!
↓↓↓
スタディサプリ中学講座の特徴
スタディサプリ中学講座は、中学生の学習をサポートするオンライン学習サービス。
学校の授業内容の予習・復習、苦手克服、先取り学習など、さまざまな目的に合わせて利用できます。
スタディサプリ中学講座の特徴は、以下のとおりです。
- わかりやすい授業動画:わかりやすく、面白いと定評のある先生による授業動画が充実しています。
- スキマ時間に学習可能:タブレットやスマートフォンで学習できるので、スキマ時間にどこでも学習できます。
- 苦手克服機能:つまずいた箇所は、何度でも繰り返し視聴できるので、無理なく理解できます。
- 先取り学習機能:得意な科目はどんどん先取りできるので、より高い学力を目指せます。
スタディサプリ中学講座は、中学生の学習をサポートするオンライン学習サービスです。
学校の授業内容の予習・復習、苦手克服、先取り学習など、さまざまな目的に合わせて利用できます。
スタディサプリのメリット・デメリット
メリット
教科書対応:主要な教科書に対応した講座が用意されており、学校の進度に合わせて効率的な予習・復習ができる。
9教科対応:幅広い教科に対応しており、英語、数学、理科、社会など9教科を一括で学習できる。
高校受験対策:公立標準・難関高校への対応や受験対策実践講座が提供されており、高校受験に向けた学習が可能。
ミッション機能:学習計画をサポートするミッション機能があり、進捗が可視化されて学習モチベーションを向上させる。
デメリット
対面授業の不足:スタディサプリはオンライン学習プラットフォームであり、直接的な質問や対話が難しい。生徒と教師とのリアルな対話が欠如する可能性がある。
ネット接続が必要:インターネット接続が必要であるため、環境によってはアクセスの難しさが考えられる。
個別対応の難しさ:生徒一人ひとりの進度や理解度に合わせた細かなサポートが難しく、全ての生徒に均等に対応する形となる。
自己管理力が必要:オンライン学習は自己管理が求められるため、生徒にとってはそれなりの自己責任が必要。
コスパで選ぶならスタディサプリ
↓↓↓
【高校受験】中学生におすすめ!タブレット教材の選び方


中学生におすすめのタブレット教材の選び方を解説。
以下のポイントを参考にして、自分の目的にあったタブレット教材を選びましょう!
- タブレット教材の充実度
- サポート体制
- タブレット教材の費用
タブレット教材の充実度
高校受験タブレット学習を選ぶ際に、教材の充実度を確認することが重要です。
教科ごとのカバー範囲や難易度、質問対応の有無などを検討しましょう。
例えば、数学の教材が数多くの問題集や解説付きのビデオ講義を提供しているかを調査します。
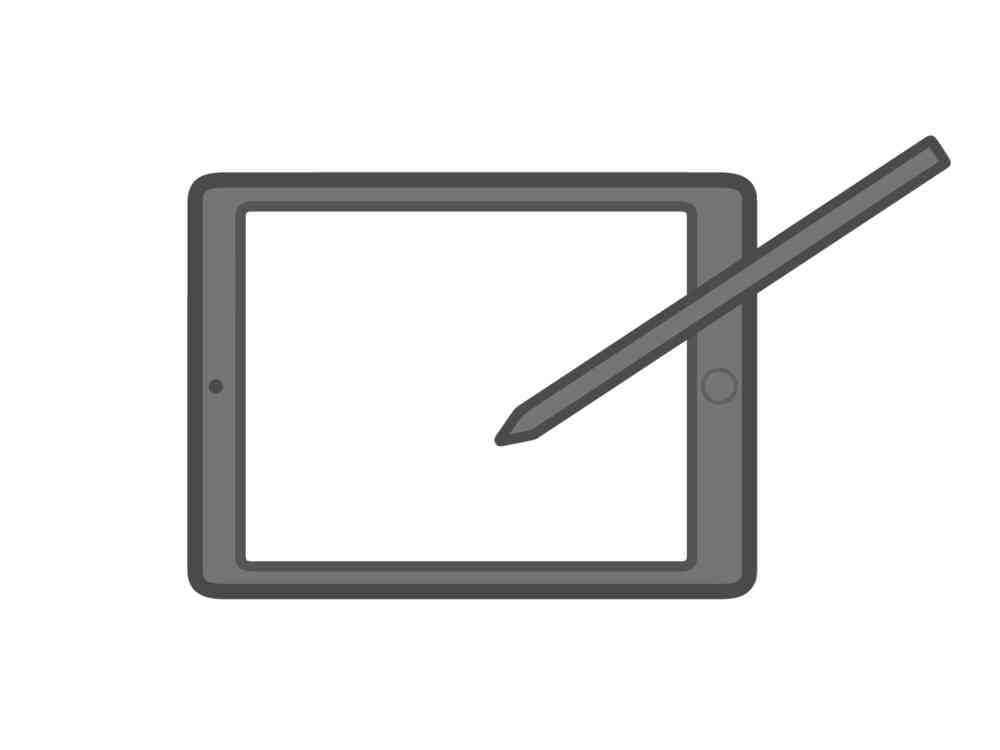
サポート体制
適切なサポート体制があるかどうかも検討すべきです。
質問への迅速な回答や進捗管理のサポートなど、生徒が困った際に頼れる仕組みが整っているか確認しましょう。
例えば、24時間オンラインサポートや専門家による指導があるかどうかをチェックします。

タブレット教材の費用
高校受験タブレット学習の費用も検討すべきです。
各プラットフォームの価格設定を比較し、予算に合ったものを選びましょう。
また、無料の試用期間を活用して、コンテンツと相性が良いかどうかを確認することもおすすめです。
タブレット学習教材が中学生におすすめな理由

勉強が嫌いな中学生は、タブレット学習教材で勉強するのも良い方法。
なぜなら、タブレット学習教材を利用することで、ゲーム感覚で集中して学習できるからです。
タブレット学習教材には、学校の授業内容を予習・復習できるものや、苦手な分野を克服するためのものなど、さまざまな種類があります。
また、子どもの年齢や学習レベルに合わせて選べるため、子ども一人ひとりに合った学習ができます。
タブレット学習教材は、子どもたちがゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な子どもでも楽しく学習できるでしょう。
また、タブレット学習教材には、子どもの学習状況を保護者が確認できる機能が付いているものもあるので、子どもの学習進捗を把握できます。
以下は、中学生向けのタブレット学習教材のおすすめポイント。
・学校の授業内容を予習・復習できる
・苦手な分野を克服できる
・子どもの年齢や学習レベルに合わせて選べる
・子どもたちがゲーム感覚で学習できる
・保護者が子どもの学習状況を確認できる
タブレット学習教材は、勉強が嫌いな中学生、学校の授業に遅れを取っている中学生や、勉強が苦手な中学生にもおすすめです。
高校受験タブレット学習の注意点


タブレット学習の注意点を解説します。
以下のポイントに注意して、タブレット教材を上手に活用しましょう!
- モチベーションの維持
- ネット環境の整備
- タブレットで学習する時間の管理
モチベーションの維持
高校受験タブレット学習は自己責任が大きいため、モチベーションを維持することが必要です。
具体的な方法として、定期的な目標設定や自己評価を行い、達成感を得ることが挙げられます。
また、学習の楽しさを忘れず、報酬を設定して自分を励ましましょう。

ネット環境の整備
高校受験タブレット学習に必要なネット環境を整備することも重要です。
安定したインターネット接続や適切なデバイスの選択が必要です。
遅延や接続の不具合が学習の妨げとならないように注意しましょう。
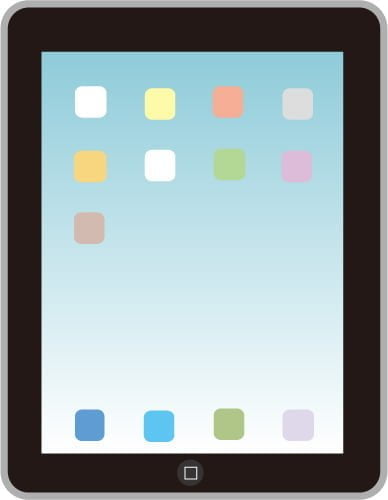
タブレットで学習する時間の管理
効果的な学習を実現するためには、学習時間を管理することが不可欠です。
学習スケジュールを立て、計画的に取り組むことで、学習の効率が向上します。
また、適切な休憩時間を確保し、長時間の画面閲覧を避けることも大切です。
まとめ:高校受験タブレット学習教材中学生│安い!おすすめ9選!塾よりお得

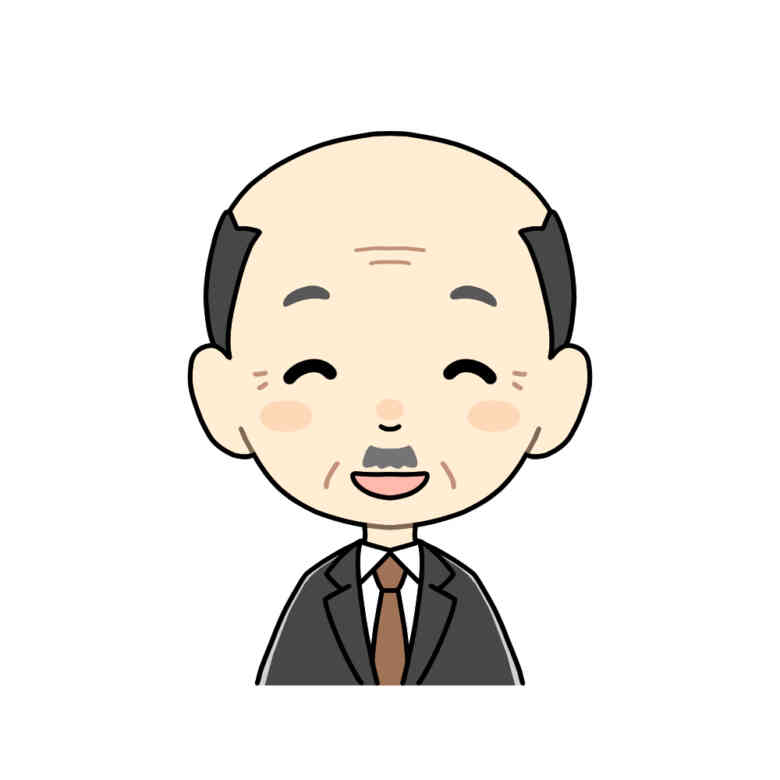
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今回の記事、「高校受験タブレット学習教材中学生│安い!おすすめ9選!塾よりお得」は参考になりましたか?
中学生におすすめのタブレット学習教材がわかりました。
早速、資料請求してみます。

以上、「高校受験タブレット学習教材中学生│安い!おすすめ9選!塾よりお得」でした。
まとめ:高校受験タブレット学習教材中学生│安い!おすすめ9選!塾よりお得
まとめ
中学生にタブレット教材がおすすめな理由をまとめました。
【いつでもどこでも学習できる】
タブレット教材は、インターネットに接続すれば、いつでもどこでも学習できます。そのため、学校や塾に通う時間がなくても、自宅や図書館、カフェなど、好きな場所で学習できます。
【個別学習で効率的に学習できる】
タブレット教材は、一人一人の学習進度に合わせて学習内容を調整できるため、効率的に学習できます。また、苦手な分野を重点的に学習できます。
【ゲーム感覚で学習できる】
タブレット教材には、ゲーム感覚で学習できるコンテンツが豊富にあります。ゲーム感覚で学習することで、モチベーションを維持しながら学習できます。
【費用が安い】
タブレット教材は、従来の紙の教材に比べて、費用が安いことが多いです。そのため、家計の負担を軽減できます。
【便利】
タブレット教材は、紙の教材に比べて、持ち運びや保管が便利です。また、検索機能や音声機能など、便利な機能が搭載されているものもあります。
タブレット教材は、中学生にとって、効率的で効果的な学習方法です。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。


