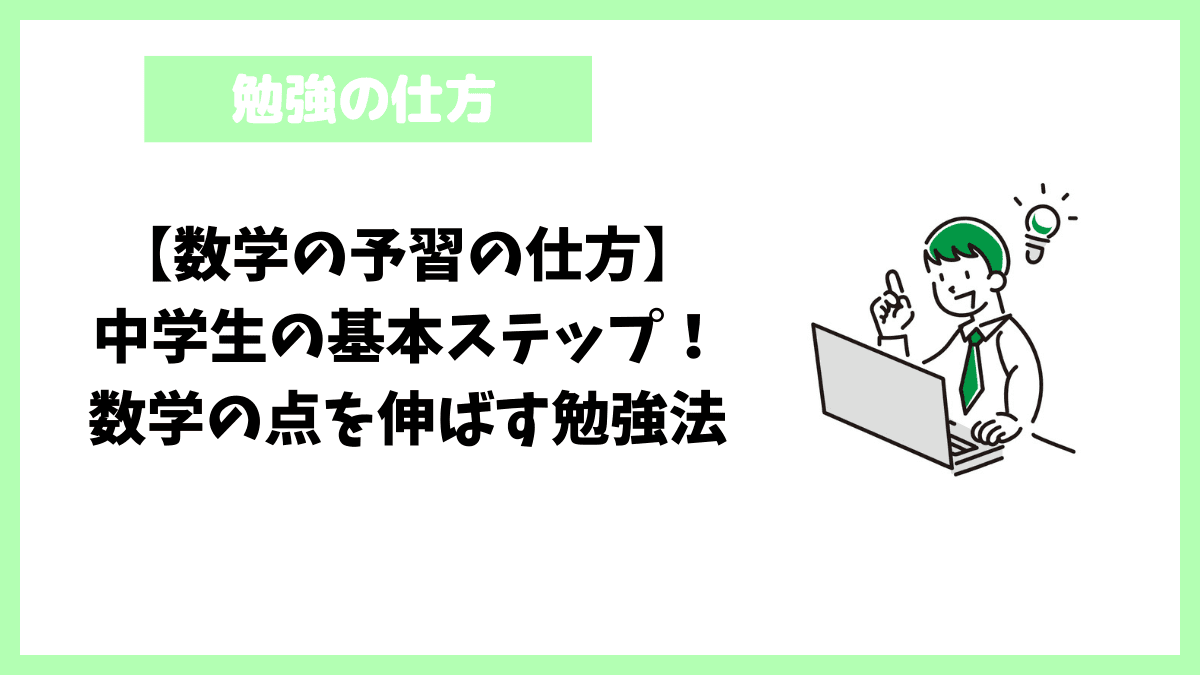
「※この記事には一部PRが含まれます」
高校受験に失敗したら、お子さまの将来はどうなるのだろう...。
お子さまが傷つくことへの不安、親としてどう振る舞うべきかといった悩みを抱えていませんか?
この記事は、学習塾業界に27年従事し、その豊富な指導経験をもとに執筆しました。
受験の「失敗」をどう捉えるべきか、その原因と対策、そして万が一不合格だった場合に親が知っておくべき具体的な進路の選択肢と心の支え方を解説します。
この記事が、お子さまの明るい未来を切り開くためのヒントになれば幸いです。
記事のポイント
高校受験「失敗」は多様な形があり、適切な理解が第一歩
不合格の原因を多角的に分析し、事前対策で「失敗」を回避する
万が一の「失敗」にも、多様な選択肢と具体的な行動で対応可能
親の適切な寄り添いとサポートが、お子さんの心を支え、未来を拓く鍵
この記事は、高校受験に失敗したときに、お子さんがどうなるのか、どうすべきなのかを解説する記事です。
より具体的な対策をお探しの方には、私が厳選したオンライン塾・家庭教師もご紹介しています
人気ランキング
人気のオンライン塾・家庭教師ランキング
毎月、多くのお問い合わせを頂いております!
第1位:東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
第2位:オンライン家庭教師「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
第3位:オンライン個別指導「そら塾」
※オンライン個別指導塾で生徒数No.1の実績!リーズナブルな料金で学校の成績がグングン伸びる!「お得に始めるならここ一択」
Contents
高校受験「失敗」とは?落ちたらどうなるのか

このセクションでは、高校受験における「失敗」の具体的なケースを定義し、それぞれの場合にどのような状況が起こりうるのかを解説します。
実際に受験失敗を経験した私の教え子の体験談も紹介し、読者の皆さまが持つ漠然とした不安を具体的に解消することを目指します。
- 志望校に不合格になるケース
- 全て不合格になった場合の進路
- 希望のコース・学科に進めないケース
- 受験失敗を経験した人の体験談
志望校に不合格になるケース
高校受験における「失敗」とは、まず第一に第一志望校に不合格になることを指します。
ほとんどの受験生は複数の学校を受験するため、併願校に合格して進学するケースが一般的です。
この場合、大きな問題にはなりませんが、お子さまは悔しさや喪失感を抱えることになります。
例えば、長年憧れていた公立高校に落ちてしまい、併願で合格した私立高校に進学することになった状況などがこれに該当します。
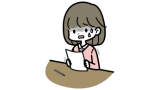
全て不合格になった場合の進路
最も親が心配する状況が、受験した全ての高校に不合格になるケースです。
しかし、この場合でも選択肢がなくなるわけではありません。
多くの都道府県では、公立高校の二次募集が行われますし、私立高校でも追加募集を行う場合があります。
「全て落ちたら高校に行けないのでは?」という心配は不要です。
ただし、選択肢は限られるため、迅速な情報収集と行動が重要になります。

希望のコース・学科に進めないケース
同じ高校に合格しても、希望のコースや学科に進めない場合も「失敗」と感じることがあります。
例えば、特進コースを目指していたが、一般コースに合格したケースです。
この場合、お子さまは努力が報われなかったと感じ、大きな挫折感を味わうかもしれません。
しかし、高校入学後の成績次第でコース変更が可能な場合もあるため、まずは現状を受け入れ、次に進む勇気を与えてあげることが大切です。

受験失敗を経験した人の体験談
実際に受験に失敗した人たちは、その後どうなったのでしょうか。
私が過去に指導した教え子に、第一志望の高校に不合格となり、滑り止めの私立高校に進学した生徒がいました。
その生徒は最初は「高校受験失敗者」というレッテルを気に病んでいましたが、その高校で素晴らしい友人や先生と出会い、新しい目標を見つけました。高校3年生の時には、難関大学に現役合格し、「あの失敗があったからこそ、今の自分がある」と語っていました。
この経験は、失敗が決して終わりではないことを示しています。
高校受験に失敗?落ちる主な原因とその対策
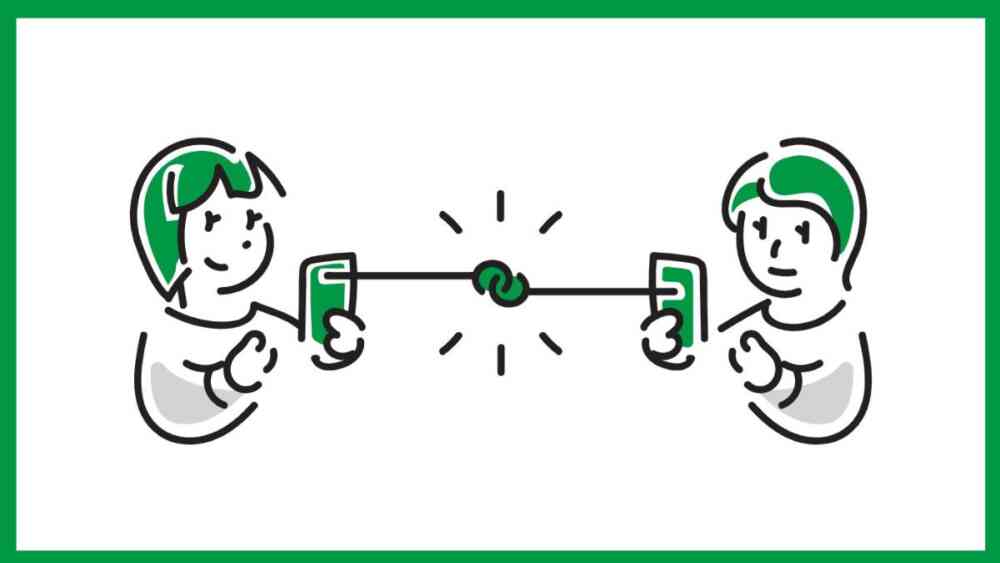
ここでは、高校受験の失敗がなぜ起こるのか、その原因を多角的に分析します。
単なる学力不足だけでなく、精神面や受験戦略といった見落としがちな落とし穴についても解説することで、親御さまが根本的な対策を講じられるようサポートします。
- 学力不足(基礎・応用力不足)
- 精神面(緊張・体調不良・メンタル)
- 戦略ミス(志望校選び・併願校の不備)
- 「落ちる人の特徴」と共通点
学力不足(基礎・応用力不足)
高校受験の失敗原因として最も多いのが、やはり学力不足です。
特に、基礎学力の定着不足と応用問題への対応力不足が挙げられます。
例えば、英語の文法や数学の公式を丸暗記しているだけで、それらを組み合わせて問題を解く力が不足しているケースです。
日々の学習では、ただ問題を解くだけでなく、なぜその答えになるのかを理解する習慣をつけさせることが重要です。
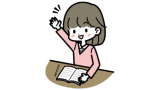
精神面(緊張・体調不良・メンタル)
本番で実力を出し切れない原因として、精神面の問題も非常に大きいです。
極度の緊張やプレッシャー、また体調管理の失敗は、ケアレスミスを誘発し、実力以下の結果に繋がります。
例えば、入試前日に緊張で眠れず、当日の試験で集中力が続かなかったというケースです。
日頃から適度な運動や十分な睡眠時間を確保し、本番で落ち着いて臨めるよう、心の状態を整えるサポートが必要です。
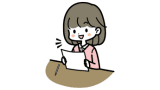
参考記事:中学生は親のプレッシャーを感じている!"勉強のプレッシャー解消法"
戦略ミス(志望校選び・併願校の不備)
お子さまの努力だけでなく、受験戦略のミスが不合格を招くこともあります。
特に、適切な志望校選びができていなかったり、併願校の検討が甘かったりすると、結果的に厳しい状況に追い込まれます。
例えば、学校の先生から「この高校は少しチャレンジ校だよ」と言われたにもかかわらず、その高校1校に絞ってしまったケースです。
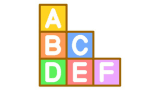
「落ちる人の特徴」と共通点
私が27年間の指導経験と数多くの受験生で見てきた中で、残念ながら不合格になってしまう生徒にはいくつかの共通点が見られます。
「得意科目だけに固執して、苦手科目を放置する」「過去問の点数ばかり気にして、基礎の復習を怠る」といった行動です。また、「親の期待に応えようとしすぎる」ことも、プレッシャーに繋がりやすい特徴です。
これらの特徴を事前に把握し、お子さまが陥らないようにサポートすることが大切です。
参考記事:【ケアレスミス対策】中学生がテスト前に読めば効果的
受験に失敗しないために親子でできること

このセクションでは、高校受験の「失敗」を防ぐために、親子で今からできる具体的な行動を提案します。
効率的な学習計画の立て方から、親ができるメンタルサポートまで、合格に向けて取り組むべきことを網羅的に解説します。
- 学習計画の立て直し
- 苦手科目対策と過去問活用
- 安全圏・実力圏・挑戦圏のバランスを取る志望校選び
- 受験直前期に親ができるメンタルサポート
学習計画の立て直し
高校受験に向けた学習計画は、お子さまのモチベーションを維持するために不可欠です。
私が過去に指導した生徒の多くが成績アップを実現できたのは、この計画性が大きな理由です。
まずは、現在の学力と志望校のレベルを客観的に把握しましょう。
そして、大きな目標(志望校合格)から逆算して、週ごとや月ごとの小さな目標を設定します。
「達成可能な小さな目標」をクリアしていくことで、お子さまは自信をつけ、勉強を続ける原動力になります。

苦手科目対策と過去問活用
苦手科目を放置することは、受験において大きな失点に繋がる可能性があります。
例えば、数学が苦手なお子さまの場合、得意な英語ばかり勉強してしまい、数学の点数が伸びないという状況です。
苦手科目こそ、日々の学習に計画的に組み込むことが重要です。
過去問は志望校の出題傾向や時間配分を把握するために最大限に活用してください。
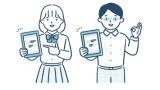
安全圏・実力圏・挑戦圏のバランスを取る志望校選び
志望校を選ぶ際には、「安全圏」「実力圏」「挑戦圏」という3つの視点でバランス良く考えることが重要です。
| 志望校の種類 | 模試の合格率の目安 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| 安全圏 | 80%以上 | ほぼ確実に合格できるレベル。安心して受験できる併願校として。 |
| 実力圏 | 50~79% | 実力相応の学校。最も合格の可能性が高いメインの併願校として。 |
| 挑戦圏 | 30%未満 | 難易度が高い学校。合格したら嬉しい第一志望校として。 |

受験直前期に親ができるメンタルサポート
受験直前期のお子さまは、大きなプレッシャーと闘っています。
親がしてあげられる最も重要なことは、お子さまのメンタルを支えることです。
具体的な行動としては、「日頃からお子さまとのコミュニケーションを密にすること」や、「十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事」を提供することです。
「頑張っているね」「応援しているよ」といった前向きな言葉かけを意識し、お子さまが安心して受験に臨める環境づくりに努めましょう。
万が一失敗した時の進路の選択肢
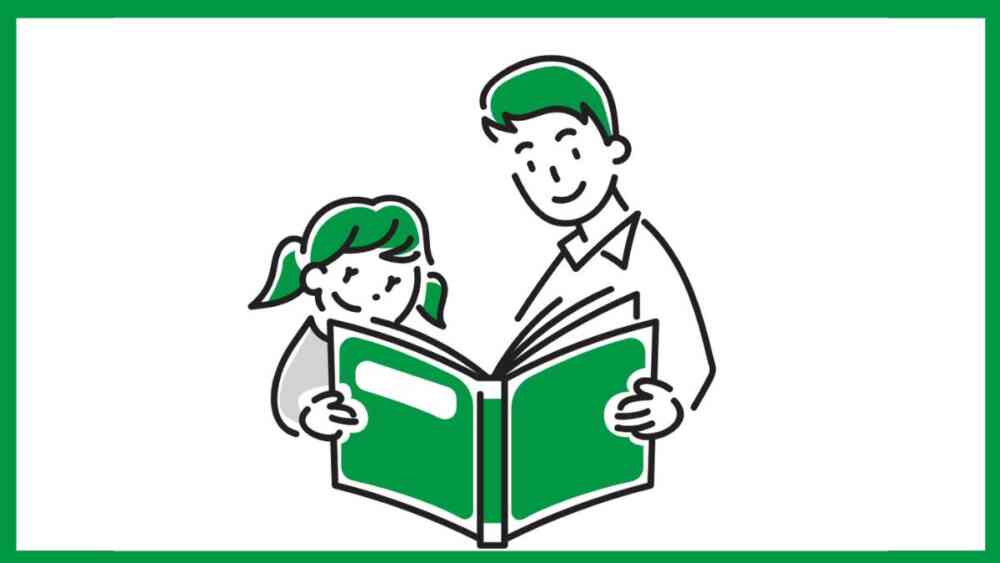
もし、お子さんが高校受験に不合格となってしまっても、決して終わりではありません。
道は必ずあります。ここでは、万が一の時に親が知っておくべき具体的な選択肢と、その際に取るべき行動について解説します。
- 公立高校の二次募集
- 私立高校の追加募集
- 通信制高校・定時制高校
- 高等専修学校・専門学校
- 浪人して再受験
- 海外留学・留学準備校という選択肢
公立高校の二次募集
公立高校の二次募集は、一般入試で定員割れした高校が、改めて合格者を募集する制度です。
通常、3月中旬から下旬にかけて実施されます。
募集を行う高校は限られているため、各都道府県の教育委員会のホームページなどをこまめにチェックし、情報を逃さないようにすることが重要です。
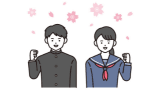
私立高校の追加募集
私立高校でも、二次募集や三次募集を行う場合があります。
これは、入学辞退者が出た場合に、その欠員を補充するために行われます。
公立高校の二次募集と同時期に行われることが多いです。
情報が表に出にくいこともあるため、受験を希望する私立高校に直接問い合わせてみるのが最も確実な方法です。
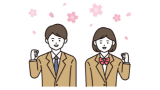
通信制高校・定時制高校
通信制高校や定時制高校も、重要な選択肢の一つです。
- 通信制高校:自宅学習が中心で、自分のペースで学習を進められます。
- 定時制高校:昼間や夜間に授業があり、働きながらでも高校卒業資格を取得できます。
これらの学校は、お子さまの学習スタイルやライフスタイルに合わせた学び方を提供してくれます。
通信制高校から難関大学に進学する生徒も珍しくありません。
たとえば、以前私が担当した生徒で、集団生活が苦手で全日制の高校に馴染めなかった生徒がいました。その生徒に通信制高校を提案したところ、自分のペースで学べる環境が気に入り、その後、得意なプログラミングの勉強を深め、大学に進学しました。
私は、通信制や定時制は決して「最後の砦」ではなく、お子さんの特性や目標によっては最適な選択肢になり得るということを、多くの保護者の方にお伝えしています。

高等専修学校・専門学校
高等専修学校や専門学校は、高校の普通科とは異なり、実社会で役立つ専門的な知識や技術を学べる進路です。
美容・調理・製菓・ファッション・デザイン・IT・医療・福祉など幅広い分野があり、授業は実習や実技を中心に構成されているため、将来の仕事を具体的にイメージしやすいのが特徴です。
早い段階から資格取得や専門スキルを身につけられるので、就職に直結する学びが可能です。
自分の興味や適性を活かせる環境で学べるため、学習意欲を高めやすく「将来やりたいことが明確になる」きっかけにもなります。
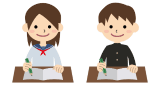
浪人して再受験
高校浪人という選択肢も、一つの道です。
浪人して翌年の再受験を目指す場合は、学習塾や予備校に通うのが一般的です。
浪人を選ぶことには、学力をさらに伸ばせるというメリットがある一方で、精神的な負担や経済的な負担が増えるというデメリットもあります。
お子さまと十分に話し合い、納得した上で決断することが重要です。
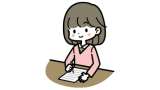
参考記事:高校受験の親がストレスを感じたら【原因はこれかも?】
海外留学・留学準備校という選択肢
少しハードルが高いかもしれませんが、海外留学という選択肢も、お子さんの視野を広げ、新たな可能性を見つけるきっかけとなることがあります。
例えば、高校の課程を海外で学ぶ「交換留学」や「私費留学」などがあります。
語学力の向上はもちろん、異文化理解や自立心を養う貴重な経験となるでしょう。
お子さんが国際的な視野に興味がある場合は、情報収集だけでもしてみる価値はあります。
子どもの心を支える親の接し方

受験失敗を乗り越えるには、親のサポートが不可欠です。
このセクションでは、不合格という現実を突きつけられたお子さまの心を支え、立ち直りを助けるための親の役割と、具体的な接し方について解説します。
- まずは感情を受け止める
- 努力をねぎらい、責めない
- 次の目標を一緒に考える
- 親自身の不安や後悔を乗り越える方法
まずは感情を受け止める
不合格を知ったお子さまは、強いショックや悲しみ、あるいは怒りを感じているかもしれません。
親はまず、お子さまの気持ちを否定せず、ありのまま受け止めてあげてください。
「泣きたいだけ泣いていいよ」「悔しかったね」と声をかけ、お子さまの感情に寄り添うことが大切です。
すぐに「次があるよ」と励ますのではなく、まずはその感情を共有することが第一歩です。
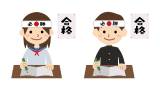
努力をねぎらい、責めない
お子さまは、受験のために懸命に努力してきたはずです。
結果が出なかったとしても、その頑張り自体は決して無駄ではありません。
「本当に頑張ったね、お疲れさま」と、努力した過程を心から褒めてあげてください。
この時、「もっと頑張っていれば…」といった言葉は絶対に口にしないでください。
お子さまを責めることは、さらなる自己否定に繋がり、立ち直りを困難にさせます。

次の目標を一緒に考える
感情が少し落ち着いたら、次のステップを一緒に考え始めましょう。
焦って結論を出す必要はありません。お子さまの意見を尊重しながら、進路の選択肢についてじっくりと話し合ってください。
この時、親が主導権を握るのではなく、お子さま自身が「どうしたいか」を考える機会を与え、その選択をサポートする姿勢が重要です。
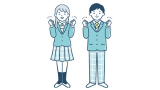
親自身の不安や後悔を乗り越える方法
お子さまが不合格になった時、親もまた「もっと何かできたのでは」という後悔や不安を感じることがあります。
27年間で数多くの親御さまを見てきましたが、自分を責めてしまう方は本当に多いです。
お子さまの失敗を自分の責任だと考えすぎないでください。
「完璧な親」を目指す必要はありません。
友人や家族、専門家など、周囲に助けを求める勇気も必要です。
親自身が気持ちを切り替えることで、お子さまも安心して前向きになれるのです。
高校受験の失敗を「未来の成功」につなげる

このセクションでは、一見ネガティブに見える高校受験の失敗を、いかにしてお子さまの人生における貴重な経験に変えていくかを解説します。
失敗から得られる教訓と、その後の成功事例を紹介することで、読者に希望を与えます。
- 失敗から学べること
- その後の成功事例・体験談
- 強みになる「失敗経験」
失敗から学べること
受験の失敗は、お子さまにとって大きな学びの機会となります。
「自分の課題を明確にし、具体的な改善策を考える」という経験は、その後の人生で直面するであろう困難を乗り越えるための大きな力となります。
例えば、計画性のなさが不合格の一因だと分かれば、高校での学習計画をより綿密に立てる意識が芽生えるでしょう。
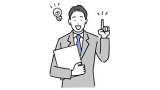
参考記事:必見!子供のやる気を引き出す魔法の言葉と逆効果の言葉とは?
その後の成功事例・体験談
高校受験に失敗したからといって、将来の可能性が閉ざされるわけではありません。
私の教え子には、第二志望の高校に進学したことで、新しい分野に興味を持ち、難関大学の推薦入試に合格した生徒がいます。
また、浪人を選んで努力を重ね、第一志望の高校にリベンジを果たした生徒もいました。
これは、失敗が次の成功への貴重な経験となることを証明しています。
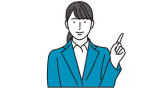
参考記事:受験生に言ってはいけない言葉を紹介|親ができることはこれだ!
強みになる「失敗経験」
「失敗を経験したからこそ得られる強み」というものがあります。
例えば、受験失敗を乗り越えたお子さまは、精神的なタフネスや、目標達成への粘り強さを養うことができます。
これらの力は、将来の大学受験や就職活動、そして社会に出てから困難に直面したときに、大きな自信と武器になります。
高校受験「失敗」に関連するよくある質問【Q&A】

高校受験「失敗」に関連するよくある質問【Q&A】で紹介します。
- Q:公立高校の二次募集はいつ、どうやって調べるの?
- Q:通信制高校からでも大学に進学できますか?
- Q:高校浪人を選んだ場合、親として他にどんなサポートが必要ですか?
- Q:受験生のメンタルを強くするにはどうしたらいいですか?
Q:公立高校の二次募集はいつ、どうやって調べるの?
A:公立高校の二次募集は、多くの場合、一般入試の合格発表後すぐに行われます。
都道府県の教育委員会の公式ウェブサイトで、募集の有無、出願期間、試験日などが公表されます。
募集期間が非常に短いことがほとんどなので、不合格が判明したら、すぐに確認することが最重要です。
お子さんが通う中学校の先生も最新情報を持っていますので、真っ先に相談してください。
毎年この時期は中学校や塾からの問い合わせが殺到しますので、躊躇せずに連絡することが肝心です。
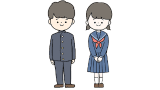
Q:通信制高校からでも大学に進学できますか?
A:はい、通信制高校から大学に進学することは十分に可能です。
近年、通信制高校の学習サポート体制は大きく進化しており、大学進学に特化したコースを持つ学校も増えています。
学習内容はもちろん、大学受験対策やAO・推薦入試のサポートまで手厚い学校も少なくありません。
実際に、私の教え子の中には、通信制高校で自分のペースで学びながら、難関大学へ進学した生徒もいます。お子さんの学習スタイルや目標に合った学校選びが成功の鍵です。
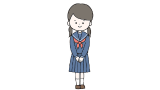
Q:高校浪人を選んだ場合、親として他にどんなサポートが必要ですか?
A:高校浪人を選ぶ場合、親御さんには精神的・経済的なサポートが特に求められます。
精神面では、お子さんの孤独感を理解し、定期的に学習の進捗や悩みを共有する時間を作りましょう。
時には息抜きの機会を設けることも大切です。
経済面では、塾や予備校に通う場合はその費用がかかりますし、自宅学習の場合でも参考書代などが必要です。
お子さんの強い意志を尊重し、「一年間、一緒に頑張ろう」という姿勢で寄り添うことが、お子さんが浪人生活を乗り切るための最大の支えとなります。
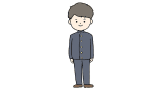
Q:高校受験の失敗が、将来の大学受験や就職に影響しますか?
A:高校受験の失敗が、将来の大学受験や就職に直接的に不利になることはほとんどありません。
大学受験は、高校3年間でどれだけ努力し、学力を伸ばしたかが問われます。
高校受験の失敗をバネに猛勉強し、難関大学に合格する生徒は毎年たくさんいます。
就職に関しても、多くの企業は「どの高校を出たか」よりも、「高校で何を学び、どんな経験をしたか」「どんな人間性か」を重視します。
むしろ、一度の挫折を乗り越えた経験は、お子さんの人間的な成長の証として、将来の強みになることもあります。
おすすめ塾
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
オンライン個別指導そら塾
※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師マナリンク
※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!
オンラインプロ教師のメガスタ!
※圧倒的な合格実績を誇る!学生講師からプロ講師まで多数在籍!きっと生徒にピッタリの講師が見つかるはずです。
トライのオンライン個別指導塾
※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!
オンライン家庭教師WAM
※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!
オンライン家庭教師ナイト
※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!
家庭教師の銀河
※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
まとめ:【高校受験失敗】「落ちたらどうなる?」親が知るべき選択肢と立ち直り方

高校受験は、お子さまの人生のほんの一部に過ぎません。
不合格という結果は辛いものですが、それは終わりではなく、新しい始まりのチャンスです。
大切なのは、お子さまが失敗から学び、前向きに次のステップへ進むことです。
親御さまが寄り添い、適切なサポートをすることで、お子さまはどんな逆境も乗り越える力を身につけ、未来を自らの手で切り開いていけるはずです。
高校受験の失敗を乗り越えろ!
ポイント
今回は、高校受験に失敗してしまったあなたへ、次に取るべき行動と心のケア、そして未来への希望についてお伝えしました。
- 不合格直後は冷静に:二次募集や追加募集の情報を集め、すぐに先生や塾に相談しましょう。
- 道は一つではない:全日制以外にも、定時制や通信制高校など、あなたに合った学びの場があります。
- 人生は終わりじゃない:高校受験の失敗は、大学受験での逆転が十分に可能な通過点です。
- 一人で抱え込まない:辛い気持ちは信頼できる人に話し、自分を大切にしてください。
高校受験の失敗は、確かに辛く、苦しい経験です。しかし、この経験は、あなたを必ず強くします。長い人生で見れば、それはほんの小さなつまずきに過ぎません。
今は辛くても、顔を上げて、新しい一歩を踏み出してください。心から応援しています。
高校受験対策!中学生におすすめ塾
おすすめ塾
【中学生】オンライン塾口コミ評価が高いおすすめ15選!失敗しない選び方
中学生にオンライン家庭教師は必要?選び方とおすすめ15社を徹底比較
都立高校受験に強いオンライン塾・個別指導塾20選│偏差値アップ!
【中学生向け】安いオンライン家庭教師15選!料金・月謝を徹底比較
オンライン家庭教師e-Liveの口コミ・評判は悪い?徹底調査した結果は?
「勉トレ」口コミ・評判・料金は?他のオンライン家庭教師と徹底比較
Z-NETSCHOOLの評判はどうなの?利用者の口コミと料金を徹底調査!
トウコベの料金(入会金・月謝)は高い?他のオンライン塾と徹底比較!
【そら塾】料金は高い?中学生の年間費用を他塾と比較!教材代・講習費は?
オンラインプロ教師メガスタと家庭教師のトライを徹底比較!どちらを選ぶべきか?
執筆者プロフィール
【執筆者プロフィール】

塾オンラインドットコム【編集部情報】
塾オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営者経験者、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。小学生・中学生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
塾オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram
