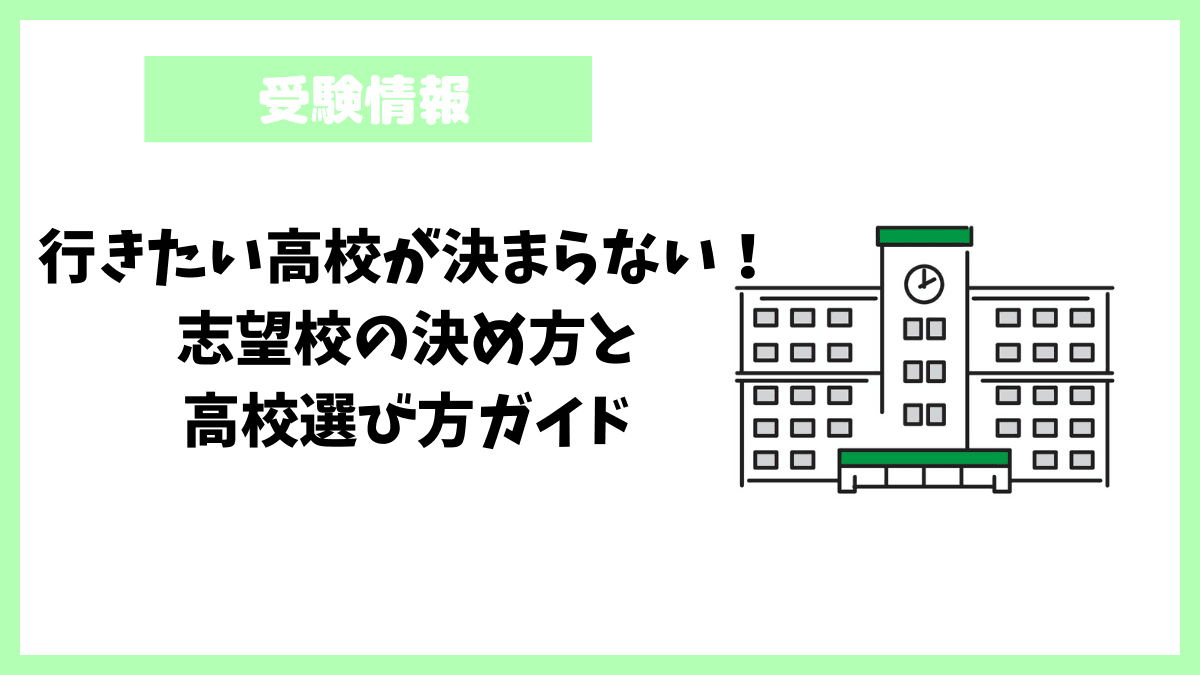
※この記事には一部PRが含まれます。
「志望校が決まらない」「行きたい高校がない」——そんな悩みを抱えていませんか。
周りはもう決めているのに、自分だけ焦ってしまう。
先生や保護者に聞かれるたびにつらい。
これは多くの中学生に共通するごく普通の悩みです。
この記事では、志望校が決まらないときの考え方と具体的な決め方のステップをわかりやすく解説します。
さらに、偏差値や成績に不安がある場合の対応、欠席日数や進路の選択肢(通信制・定時制・高認など)についても紹介します。
塾講師として27年、数多くの進路相談を受けてきた経験をもとに、今日から実践できる方法をまとめました。
焦らなくて大丈夫。
この記事を読めば、自分に合った高校を選ぶヒントがきっと見つかります。
記事のポイント
行きたい高校が決まらないのは、多くの人が通る道である
自己分析から始める4つのステップで、論理的に考える
偏差値だけでなく、校風や部活など多角的な視点で比較する
「仮の志望校」を設定するなど、焦りから抜け出す具体的な方法を知る
人気ランキング
人気のオンライン塾・家庭教師ランキング
毎月、多くのお問い合わせを頂いております!
第1位:東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
第2位:オンライン家庭教師「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
第3位:オンライン個別指導「そら塾」
※オンライン個別指導塾で生徒数No.1の実績!リーズナブルな料金で学校の成績がグングン伸びる!「お得に始めるならここ一択」
Contents
行きたい高校が決まらない!志望校の決め方と高校選び方ガイド

「行きたい高校が見つからない…」「周りがどんどん決まっていく…」と悩んでいる皆さん、安心してください。
志望校が決まらないのは、決して特別なことではありません。
むしろ、自分と向き合うための大切な時間です。
- 周りが決まっていても焦らなくて大丈夫
- 志望校が決まらないのは珍しいことではない
- 「12月になっても決まらない」場合の考え方
周りが決まっていても焦らなくて大丈夫
中学3年生のこの時期は、周りの友人が志望校を決め始め、焦りを感じるかもしれません。
大切なのは他の誰かと同じペースで進むことではなく、自分の納得のいく選択をすることです。
焦って適当に決めてしまうと、後から後悔することにもなりかねません。
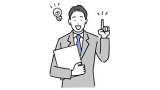
志望校が決まらないのは珍しいことではない
志望校が決まらないのは、あなただけの悩みではありません。
実際、多くの中学生が「どこを選べばいいのか分からない」と感じながら進路を考えています。
特に将来の夢や興味がまだはっきりしていない時期には、志望校をすぐに決められないのは自然なことです。
「自分だけが取り残されている」と焦る必要はありません。
むしろ、進路の悩みを持つこと自体が、自分の将来と真剣に向き合っている証拠だと考えてみましょう。
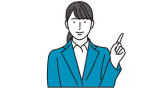
「12月になっても決まらない」場合の考え方
受験本番が迫る12月になっても志望校が決まらない場合、不安はさらに大きくなるでしょう。
この時期だからこそできることがあります。
例えば、まずは現在の学力で合格可能な高校をいくつかピックアップし、その中で最も興味が持てる学校を「仮の志望校」として設定してみましょう。
目標があると、日々の勉強にも身が入り、結果的に選択肢を増やすことにもつながります。
行きたい高校が決まらない!まずは実践!志望校の決め方4ステップ
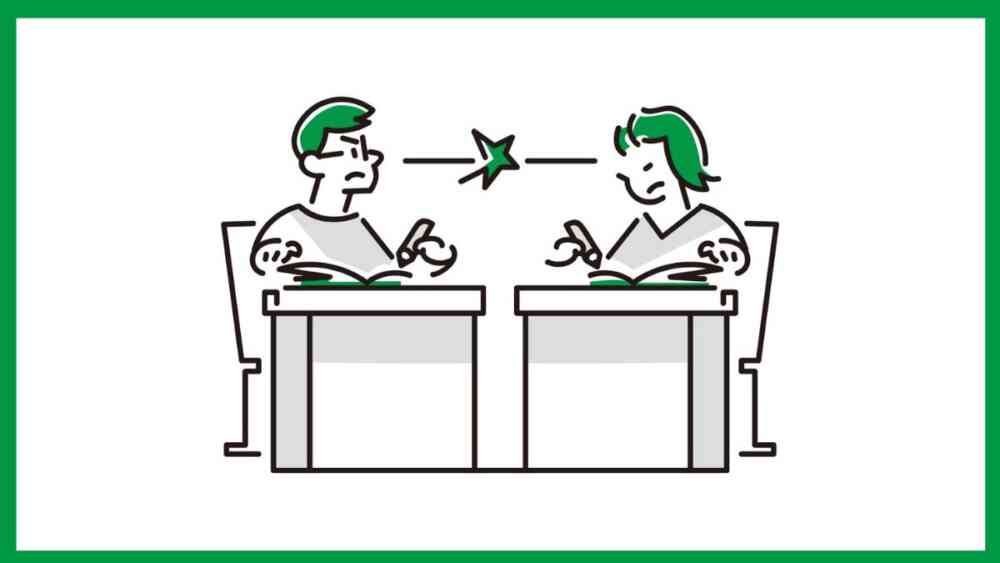
何から手をつければ良いか分からない…という人は、まずこの4つのステップに沿って進めてみましょう。
志望校の決め方の全体像を掴むことが、最初の一歩です。
- STEP1:自己分析で「自分の軸」を見つける
- STEP2:高校の情報を集めて選択肢を広げる
- STEP3:「比較の基準」で候補校を評価する
- STEP4:優先順位をつけて志望校を絞り込む
それでは、各ステップの具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
STEP1:自己分析で「自分の軸」を見つける
高校選びは「自分探し」の第一歩です。難しく考えすぎず、まずは自分自身にいくつか質問をしてみましょう。
好きなこと・得意なことから考える
自分の「好き」や「得意」は、学校生活を楽しくする大きなヒントになります。
例えば、以下のように考えてみましょう。
- 国語や社会が好き → 国際交流が盛んな高校、ディベートや発表の機会が多い高校
- 数学や理科が得意 → STEAM教育に力を入れている高校、理数系のコースがある高校
- 絵を描いたり、ものを作ったりするのが好き → 美術コースや工業系の学科がある高校
- 人と話すのが好き → 文化祭などの学校行事が盛んで、生徒が主体的に活動する高校
好きな教科や活動から、関連する特色を持つ高校を探してみると、興味が湧くかもしれません。
将来の夢やなりたい職業から逆算する
「将来の夢なんてまだないよ…」という人も全く問題ありません。ここでは、ぼんやりとした興味からで大丈夫です。
- 「人の役に立ちたい」→ 看護系や福祉系の大学への進学実績が豊富な高校
- 「海外で働いてみたい」→ 語学研修や留学制度が充実している高校
- 「ゲームが好き」→ プログラミングが学べる情報系の学科がある高校
このように、将来の可能性から逆算して高校を選ぶのも一つの有効な方法です。
どんな高校生活を送りたいか想像する
3年間という長い時間を過ごす場所だからこそ、自分がどんな高校生活を送りたいかを具体的にイメージすることが大切です。
- 部活動に全力で打ち込みたい
- 文化祭や体育祭などの学校行事を思いっきり楽しみたい
- 大学進学のために、勉強に集中できる環境が良い
- 校則は厳しすぎず、自由な雰囲気でのびのび過ごしたい
- 友達とたくさんおしゃべりしながら、穏やかに過ごしたい
理想の高校生活を思い描くことで、学校の「校風」や「雰囲気」という、偏差値だけでは分からない大切な基準が見えてきます。
譲れない条件を書き出す
最後に、現実的な視点で「これだけは譲れない」という条件を書き出してみましょう。
- 通学時間は1時間以内が良い
- 制服が可愛い(または私服OK)
- 学食がある学校が良い
- 最新のPCが使えるなど、施設がきれい
- どうしても学費は抑えたい
これらの条件は、学校生活の満足度に直接影響します。
自分にとっての「譲れない条件」を明確にしておくと、後々の学校選びがスムーズになります。
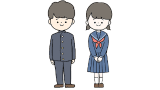
STEP2:高校の情報を集める具体的な方法
自己分析で自分の軸が見えてきたら、次は実際にどんな高校があるのか、情報を集めていきましょう。
オープンキャンパス・学校説明会に参加する
学校の雰囲気を肌で感じるためには、オープンキャンパスや学校説明会への参加が最も効果的です。
- 先生や在校生の雰囲気を知る 実際に通っている先輩たちの表情や、先生方の話し方から、学校のリアルな空気を感じ取れます。
- 施設・設備を直接見る 教室や図書館、体育館、部活動の練習場所などを自分の目で確かめることで、入学後の生活をイメージしやすくなります。
- 個別相談で疑問を解消する パンフレットだけでは分からない細かい点(校則、いじめ対策、学習サポートなど)を直接質問できる貴重な機会です。
学校公式サイト・パンフレットで特色を知る
公式サイトやパンフレットは、学校が公式に発信している最も信頼できる情報源です。
特に以下の項目に注目してチェックしてみましょう。
- 教育理念・方針 学校がどんな生徒を育てたいと考えているかが分かります。
- カリキュラム(授業内容) 特色ある授業やコース、選択科目の種類などを確認しましょう。
- 年間行事予定 文化祭や体育祭、修学旅行など、どんなイベントがあるかを知ることで、高校生活の楽しさを想像できます。
- 進路状況(大学進学実績・就職先) 卒業生がどのような進路に進んでいるかは、自分の将来を考える上で重要な参考になります。
先生・塾講師・先輩に相談する
自分一人で抱え込まず、周りの大人や先輩に相談することも非常に大切です。
- 学校の先生 あなたの成績や内申点を踏まえた上で、客観的で的確なアドバイスをくれます。
- 塾の講師 最新の受験情報や、様々な高校のデータを豊富に持っています。併願校の選び方など、受験の戦略についても相談できます。
- 身近な高校生の先輩 学校のリアルな口コミを聞ける最も身近な存在です。「実際、校則って厳しい?」「宿題の量は多い?」など、生徒目線の本音を聞いてみましょう。
高校選び診断や口コミサイトも参考にする
客観的なデータや第三者の意見を知りたい場合は、Webサイトを活用するのも一つの手です。
- 高校選び診断 いくつかの質問に答えるだけで、自分に合いそうな高校のタイプを提案してくれます。視野を広げるきっかけとして使ってみましょう。(例:スタディサプリ進路)
- 口コミサイト 在校生や卒業生のリアルな声が集まっています。ただし、あくまで個人の感想なので、参考程度にとどめ、鵜呑みにしないように注意しましょう。(例:みんなの高校情報)
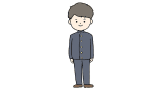
STEP3 高校選びで後悔しない比較ポイント
いくつかの候補が見つかったら、次は様々な角度から学校を比較検討していきます。
ここでは、高校選びで後悔しないためにチェックすべき8つのポイントを紹介します。
学力・偏差値
自分の学力に合っているかは、無理なく学校生活を送るための重要な基準です。
偏差値が高すぎる学校では授業についていくのが大変かもしれませんし、低すぎると物足りなさを感じる可能性もあります。
現在の自分の学力を把握し、「チャレンジ校」「実力相応校」「安全校」とバランス良く候補を考えるのがおすすめです。
学科・コース
高校には様々な学科やコースがあります。
- 普通科 大学進学を目指し、幅広い科目をバランス良く学びます。
- 専門学科 工業、商業、農業、看護、美術など、特定の分野の専門知識や技術を学びます。
- 総合学科 普通科目と専門科目の両方から、自分の興味関心に合わせて時間割を自由に組み立てられるのが特徴です。
将来やりたいことが決まっているなら専門学科、まだ決まっていないなら普通科や総合学科が選択肢になるでしょう。
校風・学校の雰囲気
「自由でのびのび」「規律を重んじ、落ち着いている」「文武両道で活気がある」など、学校によって校風は様々です。
自分がどんな環境で過ごしたいかを考え、自己分析の結果と照らし合わせてみましょう。
これはオープンキャンパスで肌で感じるのが一番です。
部活動・学校行事
高校生活の充実度は、勉強以外の活動も大きく影響します。
入りたかった部活がなかったり、活動が盛んでなかったりすると、残念な気持ちになるかもしれません。
文化祭や体育祭などの学校行事が、生徒主体で盛り上がる学校かどうかも、楽しい思い出作りのための大切なポイントです。
大学進学実績・就職先
高校卒業後の進路をどう考えているかによって、このポイントの重要度は変わります。
- 大学進学を希望する場合:国公立大学や有名私立大学への進学実績、指定校推薦の枠がどれくらいあるかなどを確認しましょう。
- 専門学校や就職を希望する場合:希望する分野への就職実績や、資格取得のサポート体制が整っているかを確認することが大切です。
公立か私立か
公立と私立には、それぞれメリット・デメリットがあります。
- 公立高校 メリットは学費が安いことです。デメリットとしては、施設が古かったり、先生の異動があったりする点が挙げられます。
- 私立高校 施設が新しく綺麗で、独自の教育プログラムや手厚い学習サポートが魅力です。一方で、学費は公立に比べて高くなる傾向があります。
家庭の経済状況も考慮し、保護者の方としっかり相談しましょう。
通学時間・立地
毎日のことなので、無理なく通える範囲かどうかは非常に重要です。
通学時間が長すぎると、勉強や部活動に使える時間が減ってしまいます。
一般的には、片道1時間〜1時間半が上限と考える人が多いようです。
実際にその時間帯の電車やバスに乗ってみて、混雑状況などを確認するのもおすすめです。
学費・奨学金制度
特に私立高校を検討する場合は、学費がどれくらいかかるのかを必ず確認しましょう。
入学金、授業料の他に、制服代、教材費、修学旅行の積立金など、様々なお金が必要です。
経済的な負担が心配な場合は、国や自治体の奨学金制度や、学校独自の特待生制度・授業料免除制度が利用できないか調べてみましょう。
- 参考:文部科学省「高等学校等就学支援金制度」
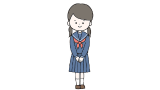
STEP4 優先順位をつけて志望校を絞り込む
高校選びでは「ここもいい」「あれもいい」と候補が増えてしまい、決められないまま時間が過ぎることがよくあります。
そんな時に大切なのが、自分にとっての優先順位を明確にすることです。
1. すべてを満たす高校はないと理解する
どんな高校にもメリットとデメリットがあります。
例えば、偏差値が理想に近いけれど通学が遠い、部活動は魅力的だけれど学費が高いなど、一長一短は必ずあります。
「100点満点の高校は存在しない」と割り切ることが大切です。
2. 「譲れない条件」と「妥協できる条件」を分ける
候補校を比較するときは、まず紙に書き出して整理しましょう。
- 譲れない条件(例:通学時間は1時間以内、学費は一定以内)
- 妥協できる条件(例:制服のデザイン、施設の新しさ)
こうして線引きをすることで、自然と候補が絞れていきます。
3. チャレンジ校・実力相応校・安全校をバランスよく選ぶ
受験では、学力に応じて3種類に分けるのが基本です。
- チャレンジ校:合格できるか微妙だけど挑戦したい学校
- 実力相応校:今の学力で合格可能性が高い学校
- 安全校:ほぼ確実に合格できる学校
このバランスを考えて志望校を絞ると、安心感が生まれます。
4. 家族や先生とすり合わせをする
最後に、親や先生と話し合い、現実的に受験できるかどうかを確認します。
特に学費や通学時間は家庭の事情も関わるため、自分一人で決めるのではなく相談が不可欠です。
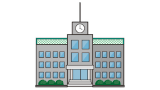
どうしても行きたい高校がない時の考え方
ここまで試しても「やっぱり行きたい高校が見つからない…」と悩んでしまう人もいるでしょう。
そんな時は、少し考え方を変えてみるのが効果的です。
「完璧な高校」はないと割り切る
すべての条件を満たす「完璧な高校」は、残念ながら存在しません。
「校風は好きだけど、制服が好みじゃない」「通いやすいけど、部活が強くない」など、どんな学校にも一長一短があります。
100点満点の学校を探すのではなく、自分にとっての「譲れない条件」をクリアしていればOK、と少し肩の力を抜いてみましょう。
「消去法」で選んでみる
「行きたい高校」が見つからないなら、「行きたくない高校」から消していく「消去法」を試してみましょう。
- 校則が厳しすぎるのは嫌だ
- 通学に1時間半以上かかるのは無理
- 男子(女子)だけなのは避けたい
このように「これだけは嫌だ」という条件で候補を絞っていくと、意外と選択肢が少なくなり、自分にとって許容できる範囲の学校が見えてくることがあります。
高校卒業後の進路から考えてみる
視点を変えて、高校の「次」のステップから考えてみるのも一つの手です。
- 大学に行きたい場合:「どの高校に行くか」よりも「どの大学に行くか」の方が重要かもしれません。その場合、希望の大学への進学実績が豊富な高校を選ぶのが合理的な判断です。
- 専門職に就きたい場合:看護師や美容師、調理師など、なりたい職業が決まっているなら、そのための専門知識が学べる高校や、関連する専門学校への進学に有利な高校を選ぶのが近道です。
まずは仮の志望校を決めて勉強を始める
志望校が決まらない焦りから、勉強に手がつかなくなってしまうのが一番もったいないことです。
そんな時は、ひとまず「仮の志望校」を決めてしまいましょう。
今の学力で行けそうな高校や、オープンキャンパスの印象が少し良かった高校など、どこでも構いません。
目標ができると、日々の勉強にも身が入りやすくなります。
勉強を進めて学力が上がれば、選べる高校の選択肢も自然と増えていきます。
仮の志望校は、後からいつでも変更できます。
自己分析で考えるポイント

高校選びは「自分探し」の第一歩です。
難しく考えすぎず、まずは自分自身にいくつか質問をしてみましょう。
- 好きなこと・得意なことから探す
- 将来の夢やなりたい職業から逆算する
- どんな高校生活を送りたいか想像する
- 譲れない条件を書き出してみる
好きなこと・得意なことから探す
自分の「好き」や「得意」は、学校生活を楽しくする大きなヒントになります。
例えば、国語や社会が好きならディベートの機会が多い高校を、数学や理科が得意なら理数系のコースがある高校を調べてみましょう。
自分の興味から関連する特色を持つ高校を探すことで、新しい発見があるかもしれません。

将来の夢やなりたい職業から逆算する
「将来の夢なんてまだない…」という人も多いでしょう。全く問題ありません。
ぼんやりとした興味からで大丈夫です。
例えば、「人の役に立ちたい」という漠然とした思いがあるなら看護系に進学実績が豊富な高校を、「ゲームが好き」ならプログラミングが学べる情報系の学科がある高校を探してみましょう。

どんな高校生活を送りたいか想像する
高校は3年間という長い時間を過ごす場所です。
そのため、「どんな毎日を送りたいか」をイメージすることがとても重要です。
「部活動に全力で打ち込みたい」なら、強豪チームがある学校や部活が盛んな校風を持つ学校を探すとよいでしょう。
「自由な雰囲気でのびのび過ごしたい」なら、校則が比較的緩やかで、生徒主体の活動が多い学校が向いています。
「大学進学のために勉強に集中したい」なら、進学実績が豊富で授業や補習が充実している学校を候補にするのがおすすめです。
このように、理想の高校生活を具体的に描くことで、偏差値や場所だけでは見えない“その学校らしさ”が分かるようになります。
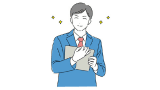
譲れない条件を書き出してみる
最後に、現実的な視点から「これだけは譲れない」という条件をリスト化してみましょう。
例えば、
- 通学時間は片道1時間以内が良い
- 制服が可愛い、または私服で通える学校が良い
- 学食や売店がある学校が希望
- 校舎や設備がきれいで使いやすい
- 学費はできるだけ抑えたい
これらの条件は、日々の学校生活の快適さや満足度に直結します。
すべてを完璧に満たす学校は難しいですが、「ここだけは外せない」という基準を決めておくことで、候補がぐっと絞りやすくなります。
高校の情報を集める方法

自己分析で自分の軸が見えてきたら、次は実際にどんな高校があるのか、情報を集めていきましょう。
- オープンキャンパス・学校説明会に参加する
- 学校公式サイト・パンフレットを活用する
- 先生・塾講師・先輩に相談する
- 高校選び診断・口コミサイトを参考にする
オープンキャンパス・学校説明会に参加する
学校の雰囲気を肌で感じるためには、オープンキャンパスや学校説明会への参加が最も効果的です。
私の経験上、最低でも3校は参加することを強く推奨します。
先生や在校生の雰囲気を知ったり、施設を直接見たりすることで、パンフレットだけでは分からないリアルな空気を感じ取ることができます。
個別相談では、内申点や受験科目などの具体的な質問をする絶好の機会です。

学校公式サイト・パンフレットを活用する
公式サイトやパンフレットは、学校が公式に発信している最も信頼できる情報源です。
例えば、「教育理念・方針」「カリキュラム」「年間行事予定」「大学進学実績」など、学校の特色や力を入れていることが分かります。
ウェブサイトでは最新情報が、パンフレットでは全体像が掴みやすいため、両方を活用しましょう。

先生・塾講師・先輩に相談する
自分一人で抱え込まず、周りの大人や先輩に相談することも非常に大切です。
例えば、学校の先生はあなたの成績や内申点を踏まえた上で、客観的で的確なアドバイスをくれます。
塾の講師は最新の受験情報を豊富に持っていますし、身近な高校生の先輩は学校のリアルな口コミを教えてくれるでしょう。

高校選び診断・口コミサイトを参考にする
客観的なデータや第三者の意見を知りたい場合は、Webサイトを活用するのも一つの手です。
高校選び診断は、いくつかの質問に答えるだけで自分に合いそうな高校のタイプを提案してくれます。
口コミサイトは在校生や卒業生のリアルな声が集まっていますが、あくまで個人の感想なので、鵜呑みにしないように注意しましょう。
高校だけが全てじゃない!多様な進路を知ろう
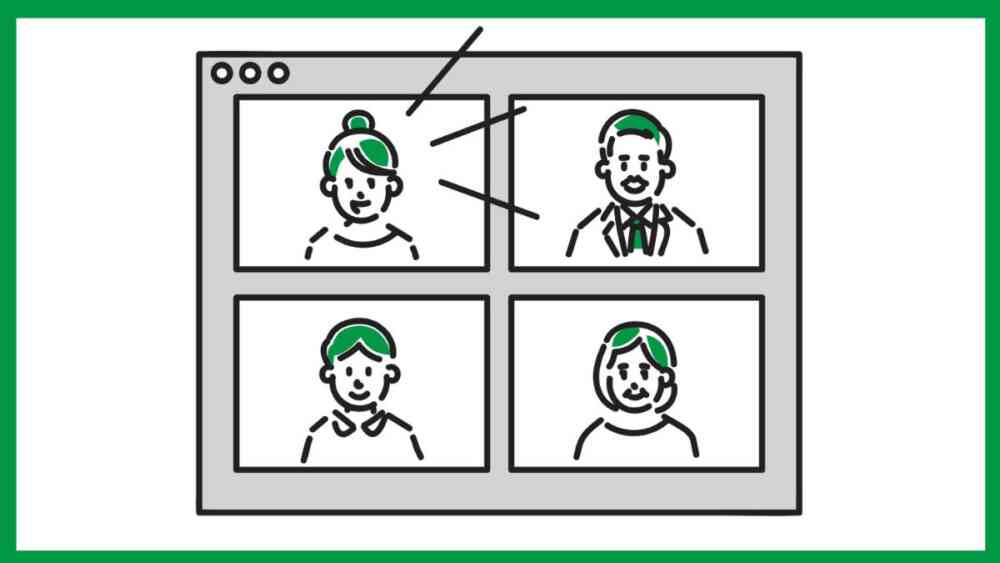
「学校に行くこと自体が嫌だ」と感じている人もいるかもしれません。
高校生活は、全日制高校だけが選択肢ではありません。自分のペースで学べる、多様な進路があることを知っておきましょう。
- 通信制高校や定時制高校という選択肢
- 高等専修学校や専門学校を視野に入れる
- 高卒認定試験(高認)を活用する方法
通信制高校や定時制高校という選択肢
通信制高校は、主に自宅学習を中心にレポート提出やスクーリング(登校日)で単位を取得する仕組みです。
通学日数が少ないため、
- 不登校経験がある人
- スポーツや芸術活動に専念したい人
- 病気や事情で毎日の通学が難しい人
に向いています。
近年は、オンライン授業や個別サポートを強化する通信制高校も増えており、大学進学を目指せる学校も少なくありません。
定時制高校は、夕方から夜間に授業が行われるケースが多く、昼間は働きながら学ぶことが可能です。
学費も比較的抑えられており、社会人や再チャレンジを目指す人が在籍することもあります。
年齢や背景が異なる仲間と学ぶことで、多様な価値観に触れられるのも魅力です。
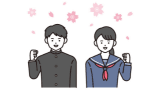
高等専修学校や専門学校を視野に入れる
特定の分野に強い関心がある場合、高等専修学校や専門学校も現実的な選択肢です。
例えば、
- 調理・製菓 → 調理師やパティシエを目指す
- 美容・ファッション → 美容師・デザイナーを目指す
- IT・工業 → プログラマーや技術者を育成
といったように、将来に直結するスキルを高校段階から学べます。
高等専修学校や専門学校は、文部科学省の認可を受けた課程もあり、卒業後に大学や専門学校への進学資格を得られる場合もあります。
「早く社会に出て役立つ力をつけたい」「手に職を持ちたい」と考える人には特に有効なルートです。
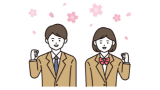
高卒認定試験(高認)を活用する方法
「どうしても高校に通うのが難しい」という人には、高卒認定試験(旧・大検)という選択肢もあります。
所定の科目試験に合格すれば、高校卒業と同等の学力を持つと認められ、大学・短大・専門学校の受験資格が得られる制度です。
高認は自分のペースで学習できるため、
- 早く大学進学を目指したい
- 学校に縛られず、自分のやりたいことに時間を使いたい
- 海外留学や特別な活動と並行して勉強したい
といったニーズに合います。
ただし、合格=即「高校卒業」とはならない点に注意が必要です。
就職や進学の際には「高卒」ではなく「高認合格」と表記されるため、その違いを理解した上で選ぶことが大切です。
志望校が決まらない!高校選びのよくある質問Q&A

最後に、高校選びで多くの人が抱える疑問にお答えします。
- Q!.学力とやりたいこと、どちらを優先すべき?
- Q2.親や先生と意見が合わない場合は?
- Q3.友達と違う高校を選ぶのは不安だけど大丈夫?
- Q4.模試の志望校欄はどう書けばいい?
- Q5.間違った高校を選んだらどうすればいい?
- 「志望校決まらない」「行きたい高校がない」と悩むのは普通?【知恵袋でも多い質問】
Q1.学力とやりたいこと、どちらを優先すべき?
理想は、両方が満たせる高校を見つけることです。
例えば、「部活を頑張りたいけれど、大学にも行きたい」なら、文武両道を掲げ、進学実績も良い学校を探してみましょう。
もしどちらかを選ばなければならない場合は、「高校3年間でしかできないことは何か?」を考えてみてください。
部活動や学校行事は高校時代ならではの経験です。
大学受験は浪人という選択肢もあります。どちらが自分にとって後悔が少ないか、じっくり考えてみましょう。

- 参考:高校生新聞オンライン:大学選び「偏差値」と「やりたいこと」どちらを重視? 悩んだ時の「第3の道」
Q2.親や先生と意見が合わない場合は?
まずは、なぜ自分がその高校に行きたいのか(または行きたくないのか)、理由を具体的に説明することが大切です。
自己分析や情報収集で考えたことを、自分の言葉で伝えてみましょう。
同時に、親や先生がなぜその高校を勧めるのか、理由を冷静に聞く姿勢も重要です。
お互いの意見を尊重した上で、塾の先生など第三者に間に入ってもらい、客観的なアドバイスをもらうのも良い方法です。
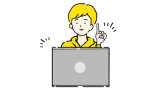
- 参考:進研ゼミ「志望校決定で子どもと意見が合わないときはどうしたらいいですか?」
Q3.友達と違う高校を選ぶのは不安だけど大丈夫?
友達と違う高校に進学するのは、不安に感じるかもしれません。
高校は新しい友達を作る場所でもあります。
同じ高校を選ばなかったとしても、高校生活を楽しみ、新しい友人関係を築くことは十分可能です。
自分の将来を真剣に考えた結果であれば、後悔することはありません。
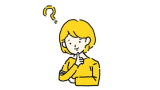
Q4.模試の志望校欄はどう書けばいい?
模試の志望校欄は、現時点での学力で合格可能性を測るためのものです。
空欄で出すのはもったいないので、少しでも興味がある高校や、今の学力で行けそうな高校を書いてみましょう。
結果を見ることで、「あとどれくらい頑張れば良いか」という具体的な目標設定に繋がります。
あくまで「仮の志望校」として気軽に書いて大丈夫です。
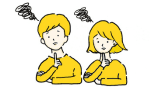
Q5.間違った高校を選んだらどうすればいい?
「もし入った高校が合わなかったら…」と不安になる気持ちはよく分かります。
高校生活が楽しくなるかどうかは、最終的には自分次第な部分も大きいです。
どんな環境でも、新しい友達を作ったり、夢中になれることを見つけたりすることで、充実した3年間を送ることは可能です。
もし本当に合わなくても、大学受験で自分の行きたい道に進むなど、挽回のチャンスはいくらでもあります。
高校選びが人生のすべてを決めるわけではないので、少しリラックスして考えてみてください。
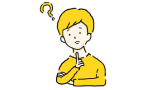
「志望校決まらない」「行きたい高校がない」と悩むのは普通?【知恵袋でも多い質問】
実際にYahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでも、同じ悩みを抱える中学生から多くの質問が寄せられています。
それだけ、この問題は特別なものではなく、多くの人に共通する悩みだといえます。
「自分だけが決まっていない」と不安に感じるかもしれませんが、志望校に迷うのは自然なことです。
むしろ、真剣に進路を考えているからこそ出てくる悩みであり、大切なのはその気持ちに向き合い、一歩ずつ前に進むことです。
おすすめ塾
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
オンライン個別指導そら塾
※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師マナリンク
※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!
トライのオンライン個別指導塾
※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!
オンライン家庭教師WAM
※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!
オンライン家庭教師ナイト
※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!
家庭教師の銀河
※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
まとめ:行きたい高校が決まらない!志望校の決め方と高校選び方ガイド

行きたい高校が決まらないと悩んでいるあなたへ、後悔しない志望校の決め方について解説してきました。最後に、大切なポイントを振り返りましょう。
行きたい高校が決まらない!志望校の決め方と高校選び方ガイド
ポイント
- 行きたい高校が決まらないのは、多くの人が通る道である
- 自己分析から始める4つのステップで、論理的に考える
- 偏差値だけでなく、校風や部活など多角的な視点で比較する
- 「仮の志望校」を設定するなど、焦りから抜け出す具体的な方法を知る
志望校選びは、あなたにとって初めての大きな決断かもしれません。悩むのは、あなたが自分の将来に真剣に向き合っている証拠です。
焦る必要はありません。この記事で紹介したステップを一つひとつ実践しながら、自分自身と向き合い、視野を広げていけば、きっと「ここなら頑張れそう」と思える高校が見つかるはずです。
あなたの高校選びが、素晴らしい未来に繋がることを心から応援しています。
進路に関連する記事
高校受験に関する記事
ポイント
執筆者プロフィール
【執筆者プロフィール】

塾オンラインドットコム【編集部情報】
塾オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営経験者、ファイナンシャルプランナー、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。小学生・中学生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
塾オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram

