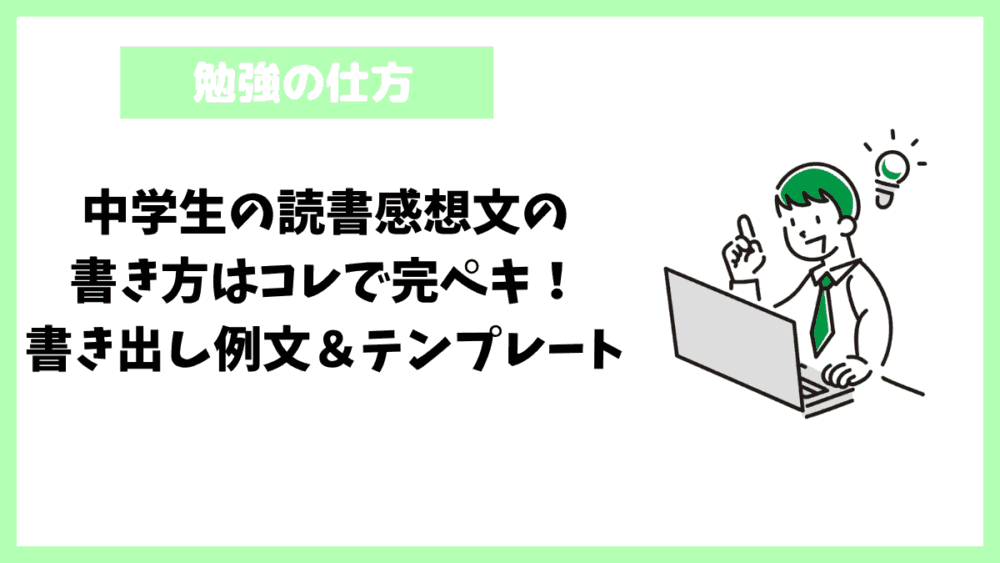
「※この記事には一部PRが含まれます」
「読書感想文、何を書けばいいの…?」「どうやって書けばいいか、全然わからない…」
そんな悩みを毎年抱える中学生の皆さん、こんにちは!
私は27年間、学習塾で読書感想文に悩む生徒たちをたくさん見てきました。
最初は書けなかった子も、ちょっとしたコツで「書けた!」と自信をつけていきました。
この記事では、そんな経験をもとに「中学生が本当に知りたい読書感想文の書き方」をまとめています。
中学生の読書感想文は、特別な才能がなくても大丈夫。
ちょっとしたヒントと手順を知るだけで、自分の言葉でしっかり書けるようになります。
この記事を読み終えるころには、「これなら書けそう!」と思えるはず。
さあ、一緒に始めましょう!
読み終えるとわかること
読書感想文の基本構成と書き方
魅力的な書き出しのパターンと中学生向け例文
感想を深めるための具体的な書き方のコツ
読書感想文をスムーズに書くための準備と注意点
オンライン塾
リーズナブルな料金で始められる。オンライン塾・家庭教師
月謝が安くても効果抜群のおすすめ塾!
第1位:オンライン個別指導「そら塾」
※オンライン個別指導塾で生徒数No.1の実績!リーズナブルな料金で学校の成績がグングン伸びる!「お得に始めるならここ一択」
第2位:家庭教師の銀河
※小中学生の月謝は、1コマ:2,750円〜、オンライン対応。定期テスト・受験対策。手厚いチャットサポートで生徒も保護者も安心!
第3位:東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
Contents
中学生の読書感想文の基本構成と書き方

まずは、読書感想文がどんなもので、どういう構成で書けば良いのか、基本的なところから押さえていきましょう。
ここを理解するだけで、ぐっと書きやすくなりますよ。
- 読書感想文とは?目的と評価点
- 基本構成「はじめ・なか・おわり」
- 各パートで書く内容の詳細
- あらすじの適切な書き方と量
読書感想文とは?目的と評価点
読書感想文とは、本を読んであなたが何を感じ、何を考えたのかを文章にまとめたものです。
ただ単に「面白かった」「つまらなかった」というだけでなく、なぜそう思ったのか、本の内容から何を学んだのかを自分の言葉で表現することが大切です。
読書感想文を書く目的は、主に以下の3つです。
・読解力を深める
本の内容を正しく理解する力がつきます。
・思考力を養う
本の内容について深く考え、自分の意見を持つ練習になります。
・表現力を高める
自分の考えや感じたことを、相手に分かりやすく伝える文章力が身につきます。
学校の先生は、主に次のような点を評価しています。
・自分の言葉で書かれているか
インターネットや他の人の感想文を丸写ししていないか。
・本の内容を理解しているか
あらすじだけでなく、作者が伝えたかったことなどを捉えられているか。
・自分の考えが深められているか
本を読んで何を感じ、どう考えたのかが具体的に書かれているか。
・文章の構成がしっかりしているか
話の流れが分かりやすく、論理的に書かれているか。
難しく考えず、まずは本と向き合い、素直な気持ちを表現することを心がけましょう。

基本構成「はじめ・なか・おわり」
読書感想文の基本的な構成は、「はじめ・なか・おわり」の3部構成です。
これは作文の基本でもあるので、覚えておくと他の文章を書くときにも役立ちます。
| パート名 | 位置 | 書く内容のポイント |
|---|---|---|
| はじめ | 序論(導入) | ・なぜこの本を選んだのか・読む前にどんな印象や期待を持っていたか・本との出会いのきっかけなど |
| なか | 本論(中心) | ・本の簡単なあらすじ(短く)・心に残った場面やセリフ・それに対する感想や考え、自分の体験との結びつけ |
| おわり | 結論(まとめ) | ・本から学んだことや気づき・これからどう活かしたいか・読後の気持ちや印象的な一言で締める |
この3つのパートを意識するだけで、文章全体の流れが整い、格段に書きやすくなります。

各パートで書く内容の詳細
それでは、「はじめ・なか・おわり」の各パートで、具体的にどのようなことを書けば良いのか見ていきましょう。
はじめ(序論):読者の心をつかむ導入
- この本を選んだきっかけ
例:「私がこの本を手に取ったのは、友達に強く勧められたからです。」「夏休みの課題図書リストの中に、ひときわ目を引く題名を見つけました。」
- 本を読む前の印象や期待
例:「表紙の絵から、きっと心温まる物語だろうと想像していました。」「この本を読めば、歴史の謎が解けるかもしれないとワクワクしていました。」
- 本との出会いのエピソード
例:「偶然立ち寄った本屋で、平積みにされていたこの本と目が合いました。」
- 読者の興味を引く問いかけ
例:「もし、未来の自分に手紙を送れるとしたら、あなたは何を伝えますか?」
「はじめ」は読書感想文の顔です。ここで読者の興味を引きつけられるかどうかがポイントになります。
なか(本論):感想文のメイン!あらすじと自分の考え
- 簡単なあらすじ
本を読んでいない人にも話が通じるように、物語の概要やテーマを簡潔に紹介します。ただし、あらすじが長くなりすぎないように注意しましょう。
- 最も心に残った場面やセリフ
なぜその場面やセリフが心に残ったのか、具体的な理由を説明します。
- 登場人物への共感や反発
登場人物の行動や考え方に対して、自分がどう感じたのかを書きます。「自分だったらこうするのに」といった視点も良いでしょう。
- 自分の体験との結びつき
本の内容と自分の経験を重ね合わせることで、感想に深みが増します。「主人公の〇〇な経験は、私が以前体験した△△と似ていると感じました。」のように具体的に書くと良いでしょう。
- 「なぜそう思ったのか」を掘り下げて書く
「感動した」「面白かった」だけでなく、なぜそう感じたのか、その理由を詳しく説明することが重要です。
「なか」は読書感想文で最も重要な部分です。あなたのオリジナルの視点や考えを存分に表現しましょう。
おわり(結論):学びと今後の抱負
- 本全体を通して学んだことや気づき
この本を読んで、あなたは何を学び、どんなことに気づきましたか?
- 自分の考えや価値観の変化
本を読む前と後で、自分の考え方や物事の見方がどのように変わったかを書きます。
- 今後の生活にどう活かしていきたいか
本から得た教訓や感動を、これからの自分の生活や目標にどう繋げていきたいかを具体的に述べます。
- 本を読んだ後の余韻や、他の人にも勧めたい気持ち
「この本は、私にとって忘れられない一冊となりました。」「ぜひ、多くの人にこの感動を味わってほしいです。」といった言葉で締めくくるのも良いでしょう。
「おわり」は読書感想文の総仕上げです。読後感が伝わるように、しっかりとまとめましょう。
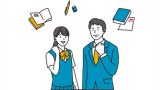
あらすじの適切な書き方と量
読書感想文でよくある悩みが、「あらすじばかり長くなってしまう」というものです。
あらすじとは、本の内容を短くまとめたものですが、感想文の主役はあくまであなたの「感想」です。
- あらすじの役割
本を読んでいない人にも、あなたが何について感想を述べているのかを理解してもらうために必要です。
- 適切な量
読書感想文全体の中で、あらすじが占める割合は多くても2~3割程度に抑えましょう。原稿用紙1枚が約400字だとすると、5枚書くならあらすじは1枚程度が目安です。
- 書き方のポイント
- 物語の結末まで全て書いてしまう「ネタバレ」は避けましょう。
- 感想を述べるために必要な部分に絞って書きます。
- 「主人公は〇〇という困難に立ち向かいます。その中で特に印象的だったのは…」のように、感想に繋げやすい形で書くとスムーズです。
あらすじは、あくまで感想を引き立てるための脇役と心得ましょう。
本選びと読書メモの準備

読書感想文をスムーズに書くためには、事前の準備がとても大切です。
どんな本を選び、どのように読書メモを取れば良いのか、具体的な方法を見ていきましょう。
- 感想文が書きやすい本の選び方
- 読書メモの取り方とポイント
- 事前に準備しておくものリスト
感想文が書きやすい本の選び方
どんな本を選ぶかによって、読書感想文の書きやすさは大きく変わります。
以下のポイントを参考に、自分に合った一冊を見つけましょう。
| 選び方のポイント | 解説内容 |
|---|---|
| 自分が心から「読みたい!」と思える本 | 興味が持てない本では感想が出てこないため、読みたいと思える本を選ぶのが最も大切。 |
| 登場人物に共感・感情移入しやすい本 | 感情が動きやすくなり、自然と感想が書きやすくなる。 |
| 考えさせられるテーマやメッセージ性のある本 | 「自分だったらどうするか?」など深く考えられる内容は、感想を深めやすくなる。 |
| 自分の年齢や興味に合ったジャンルの本 | 中学生向けの小説、伝記、ノンフィクション、SF、ファンタジーなど、親しみやすいジャンルが◎。 |
| 難解すぎたり、分厚すぎたりしない本 | 読み終えるのが大変だと感想文も進まない。無理なく読めるボリュームと内容の本を選ぶ。 |
| 学校の推薦図書や課題図書 | 先生が選んだ本は感想文向きで安心。友達と話し合える点もメリット。 |
| 困ったときは相談する | 図書館の司書さん、先生、本好きな友達に相談すると、自分に合った本が見つけやすい。 |
迷ったら、図書館の司書さんや学校の先生、本好きな友達に相談してみるのもおすすめです。
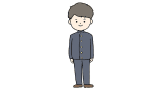
読書メモの取り方とポイント
読書メモとは、本を読みながら気になったことや感じたことを書き留めておくメモのことです。
これをしっかり取っておくと、後で感想文を書くときに非常に役立ちます。
なぜ読書メモが大切なのか?
- 読んでいる最中の新鮮な感動や疑問を忘れずに記録できる。
- 感想文の「ネタ」集めになる。
- どこに何が書いてあったか、後から見つけやすくなる。
【読書メモに書くことの例】
- 心に残った場面やセリフ、言葉→ページ数も一緒にメモしておくと便利です。
- 感動したところ、面白いと思ったところ
- 疑問に思ったところ、納得いかなかったところ
- 登場人物の行動や気持ちについて考えたこと→「なぜこの人はこんなことをしたんだろう?」「この時の気持ちはどんなだったんだろう?」
- 自分だったらどうするか、どう感じたか
- 本を読んで思い出した自分の体験
【読書メモの取り方のコツ】
| 方法・ポイント | 内容・説明 |
|---|---|
| 付箋(ふせん)を活用する | 気になったページに付箋を貼り、キーワードをメモ。後で見返しやすくなる。 |
| ノートにまとめる | 日付・本のタイトル・ページ数・引用・感想などを整理して記録すると、後で使いやすい。 |
| キーワード+簡単な感想を添える | 「すごい!」だけでなく、理由を少し書いておくと感想文に深みが出る。例:「〇〇の行動がすごい。なぜなら…」 |
| 完璧を目指さなくてOK | 殴り書きや箇条書きでOK。自分が見て分かる内容にすることが大事。 |
読書メモは、未来の自分へのプレゼントだと思って、楽しみながら取り組んでみてください。
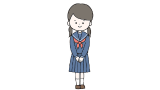
事前に準備しておくものリスト
読書感想文を書き始める前に、以下のものを準備しておくとスムーズに進められます。
| 準備するもの | 内容・ポイント |
|---|---|
| 感想文を書く本 | これが無いと始まりません。最初にしっかり読みましょう。 |
| 筆記用具 | 鉛筆(またはシャープペンシル)、消しゴム、清書用のボールペンなどを用意。 |
| 原稿用紙 | 学校指定がある場合はそれを使用。なければ市販の原稿用紙でOK。 |
| 読書メモ | 読みながら印象に残ったことを書き留めたメモや付箋。感想文の材料になります。 |
| 辞書 | 国語辞典・漢字辞典。言葉の意味や漢字を調べたいときに便利。 |
| パソコン・タブレット(任意) | 下書きや清書に使えるが、使用は学校のルールに従ってください。 |
| 静かで集中できる環境 | テレビやスマホの誘惑が少ない場所で取り組むのがおすすめです。 |
準備を万全にして、気持ちよく読書感想文に取り組みましょう!
参考記事:ヨミサマ【国語塾】の口コミ・評判は?良い・悪い声を本音で専門家が徹底分析
中学生の読書感想文の書き出しのコツと例文
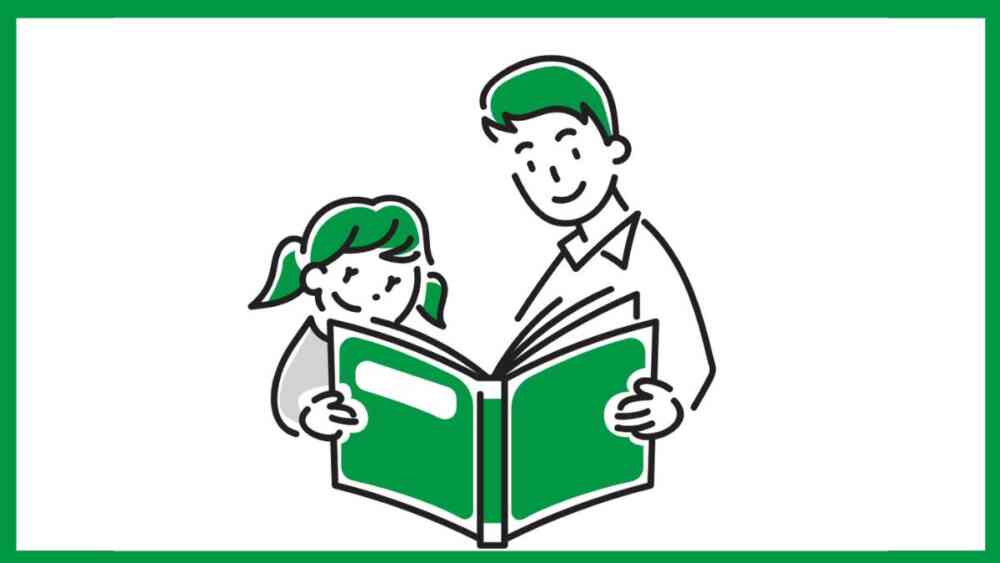
読書感想文で多くの人がつまずくのが「書き出し」です。「何から書き始めたらいいんだろう…」と悩んでしまいますよね。
ここでは、読者の心をつかむ書き出しのコツと、中学生向けの読書感想文の例文を紹介します。
- 読書感想文の書き出しが重要な理由
- 魅力的な書き出し作成パターン
- 中学生向け読書感想文:書き出し例文集
- 避けるべきNGな書き出し例
読書感想文の書き出しが重要な理由
書き出しは、読書感想文の第一印象を決定づける、非常に重要な部分です。
魅力的な書き出しは、読み手を引き込み、「この先を読んでみたい!」と思わせる力があります。
逆に、ありきたりな書き出しだと、せっかく良い内容を書いても読んでもらえないかもしれません。
書き出しで読者の心を掴むことができれば、その後の文章もスムーズに展開しやすくなります。
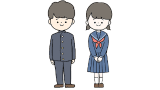
魅力的な書き出し作成パターン
「どうすれば魅力的な書き出しが書けるの?」という人のために、いくつか代表的なパターンを紹介します。
「本との出会いや選んだ理由を書く」
- 最もオーソドックスで書きやすいパターンです。
- 例:「私がこの本を手に取ったのは、夏休みの図書館で偶然見つけた、美しい表紙の絵に心惹かれたからだ。」
「本を読む前の印象や予想を書く」
- 読後の感想とのギャップを示すと面白くなります。
- 例:「『星の王子さま』という可愛らしい題名から、私はてっきり子供向けの楽しいお話だと思っていた。しかし、読み進めるうちに、その奥深さに驚かされることになった。」
「最も心に残った言葉や場面から始める」
- いきなり核心に触れることで、読者の興味を強く引きます。
- 「例:『本当に大切なものは、目に見えないんだよ』。物語の終盤で語られるこの一言が、私の胸に深く、そして温かく響いた。」
「読者への問いかけで始める」
- 読者を巻き込み、一緒に考えてもらうような書き出しです。
- 例:「もし、あなたにたった一つの願いが叶うとしたら、何を願いますか?この物語の主人公は、ある不思議な出会いから、そんな問いと向き合うことになります。」
「自分の体験談や身近な話題から始める」
- 本の内容と自分の経験を結びつけて導入する方法です。
- 例:「私は以前、部活動の試合で大きな失敗をしてしまい、ひどく落ち込んだことがある。そんな時、まるで自分のことのように感じられたのが、この物語の主人公の姿だった。」
これらのパターンを参考に、自分なりにアレンジしてオリジナルの書き出しを考えてみましょう。
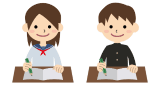
中学生向け書き出し例文集
ここでは、上記パターンを使った中学生向けの書き出し例文をいくつか紹介します。
本との出会い
「図書室の隅でほこりをかぶっていたその本は、まるで私に見つけてもらうのを待っていたかのようだった。題名は『〇〇』。それが、私の夏休みを大きく変える一冊になるとは、その時は思いもしなかった。」
読む前の印象
「戦争の話だと聞いて、最初は少し読むのが怖いと感じていた。しかし、ページをめくるうちに、そこで描かれる人々の日常や強い絆に、私は次第に引き込まれていった。」
心に残った言葉
「『あきらめたらそこで試合終了ですよ』。この有名なセリフを、私はただの漫画の言葉だと思っていた。しかし、この本を読んで、その言葉が持つ本当の重みを知った気がする。」
問いかけ
「本当の友達とは、一体どんな存在なのだろうか?この本は、私にそんな普遍的な問いを投げかけてきた。」
自分の体験談
「新しいクラスに馴染めず、一人でいることが多かった中学一年生の春。そんな私の心をそっと開いてくれたのが、主人公〇〇のひたむきな姿だった。」
これらの例文はあくまでヒントです。自分の言葉で、本を読んだ時の新鮮な気持ちを表現してみてください。
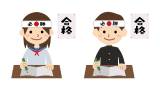
避けるべきNGな書き出し例
逆に、こんな書き出しは避けた方が良いという例も紹介します。
「私は〇〇という本を読みました。」→あまりにも平凡で、読者の興味を引きません。
いきなりあらすじから始まる→「この本は、〇〇という主人公が冒険をする話です。」これでは感想文ではなく、あらすじ紹介になってしまいます。
本の内容と全く関係ない話が長すぎる→導入は大切ですが、本題から逸れすぎないように注意しましょう。
辞書で引いたような言葉の定義から始める→「友情とは、友達同士の情愛である。この本では…」少し堅苦しい印象を与えてしまいます。
NG例を参考に、自分の書き出しが単調になっていないかチェックしてみましょう。
おすすめ塾
講師のほとんどが東大・東大院生
東大生が指導する塾としてはコスパが良い
オンライン個別指導
部活が忙しい生徒にも対応!
自宅で勉強できるから、集中力UP!
成績アップの近道!
30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/
↓↓↓
トウコベの公式HPをチェック!
関連記事
トウコベの口コミ・評判・レビュー【小中学生の保護者向け】講師の質・サポート・効果を徹底検証
本文:感想を深める書き方

書き出しが決まったら、いよいよ読書感想文のメインとなる「本文」です。
ここでは、あなたの感想や考えを具体的に、そして深く掘り下げて書いていきましょう。
- あらすじと感想の最適なバランス
- 自分の体験と本を結びつける方法
- 心に残った言葉の効果的な引用術
- 「なぜそう思ったか」を掘り下げる
あらすじと感想の最適なバランス
本文では、本のあらすじに触れながら、それに対するあなたの感想や考えを述べていきます。
大切なのは、あらすじと感想のバランスです。
- あらすじは必要最小限に
前にも述べた通り、あらすじは全体の2~3割程度に抑え、感想を述べるために必要な部分だけを簡潔に紹介しましょう。
- 感想がメインであることを意識する
「この場面で主人公はこう行動した。それに対して私はこう思った。なぜなら…」というように、あらすじをきっかけにして自分の考えを展開していくイメージです。
- あらすじと感想を交互に書く
「あらすじのブロック、感想のブロック」と分けるのではなく、自然な流れで織り交ぜていくと読みやすくなります。
読者はあなたの「感想」を知りたいのです。
あらすじの紹介に終始しないように気をつけましょう。
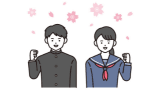
自分の体験と本を結びつける方法
読書感想文に深みを持たせる効果的な方法の一つが、本の内容と自分の体験を結びつけて書くことです。
- 共感した点や反発した点を見つける
「主人公のこの気持ち、すごくよく分かる!私も同じような経験をしたことがある。」「この登場人物の考え方には、どうしても納得できないな。」など、自分の心が動いた部分に注目しましょう。
- 具体的なエピソードを交える
「主人公が友達と喧嘩してしまった場面を読んで、私も以前、親友と些細なことで口論になり、何日も口をきかなかったことを思い出しました。あの時、私も主人公と同じように…」のように、具体的な自分の体験を語ることで、感想に説得力が増します。
- 「もし自分だったらどうしたか」を考える
「もし私が主人公の立場だったら、あんな行動はできなかったかもしれない。」「私なら、別の方法を選んだだろう。」といった視点で考えるのも、自分の考えを深める良い方法です。
自分の体験と重ね合わせることで、本の世界がより身近に感じられ、オリジナリティのある感想文になります。
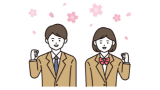
心に残った言葉の効果的な引用術
本の中で特に心に響いたセリフや文章を引用するのは、読書感想文でよく使われるテクニックです。
効果的に使うことで、あなたの感想をより強く印象づけることができます。
| ポイント | 内容・説明 |
|---|---|
| 引用する箇所は慎重に選ぶ | 自分の感想や考えを述べるうえで特に大切だと思う言葉を選びましょう。 |
| 正確に書き写す | 引用は「 」(かぎかっこ)で囲み、一字一句正確に。書名は『 』(二重かぎかっこ)で表すのが基本。 |
| 引用した理由や自分の考えも書く | ただ引用するだけでなく、「なぜ心に残ったか」「何を感じたか」「どう影響を受けたか」を具体的に説明しましょう。例文もあるとより伝わりやすくなります。 |
| 引用が長すぎないように注意する | 感想文全体のバランスを保つために、引用は数行程度にまとめるのが理想です。 |
引用は、あなたの感想を裏付けるための強力な武器になります。
上手に活用しましょう。
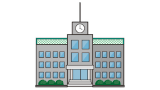
「なぜそう思ったか」を掘り下げる
読書感想文で最も大切なのは、「面白かった」「感動した」という表面的な感想だけでなく、「なぜそう思ったのか」という理由や背景を深く掘り下げて説明することです。
- 「なぜ?」を繰り返す
「この場面で感動した。」→「なぜ感動したの?」→「主人公の優しさに触れたから。」→「なぜそれが優しさだと感じたの?」→「自分のことを犠牲にしてまで他人を助けようとしたから。」…というように、自分自身に「なぜ?」と問いかけることで、考えが深まっていきます。
- 具体的な言葉で表現する
「すごい」や「やばい」といった曖昧な言葉ではなく、「息をのむほど美しい描写だった」「胸が締め付けられるような悲しい場面だった」など、具体的な言葉で感情や状況を表現するように心がけましょう。
- 自分の価値観と照らし合わせる
「この主人公の生き方は、私が大切にしている『誠実さ』という価値観と重なる部分がある。」のように、自分の価値観と本の内容を照らし合わせることで、より深い考察ができます。
- 多角的な視点を持つ
一つの出来事に対しても、登場人物それぞれの立場から見るとどう見えるか、作者は何を伝えたかったのか、など、様々な角度から物事を捉えようとすると、感想に厚みが出ます。
「なぜ?」を追求することで、あなただけのオリジナルの考察が生まれ、読書感想文の質が格段に向上します。
結論・まとめ方!中学生の読書感想文の例文
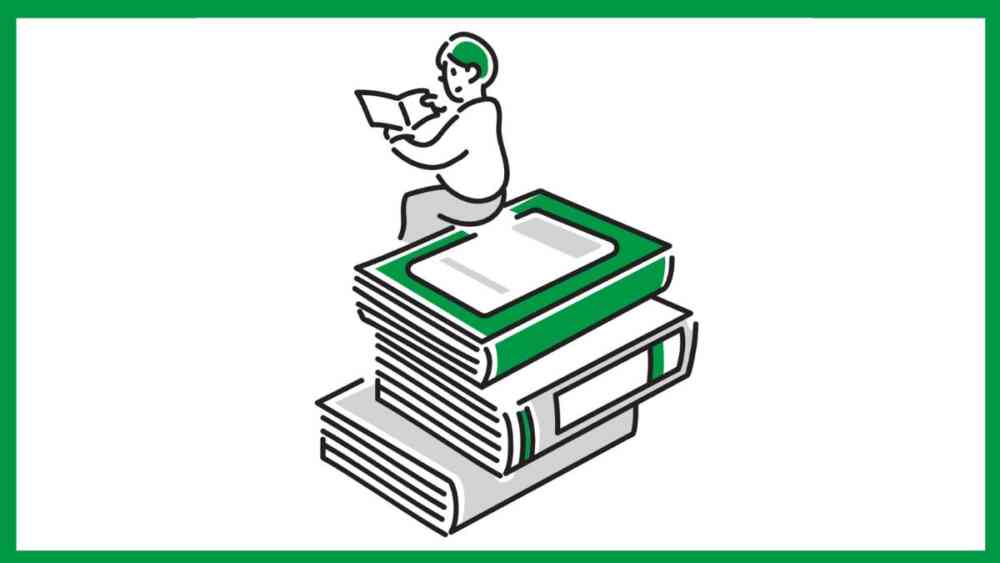
読書感想文の最後を飾る「結論・まとめ」。ここでしっかりと締めくくることで、読者に深い印象を残すことができます。
どのようなことを書けば良いのか、具体的なポイントと例文を見ていきましょう。
- 読書感想文のまとめで書くべき事
- 学びを今後にどう活かすかを示す
- 印象に残るまとめ方の例文紹介
読書感想文のまとめで書くべき事
「おわり(結論)」の部分では、主に以下の内容をまとめます。
- 本全体を通して学んだこと、最も強く感じたこと
この本を読んで、あなたが一番心に残ったメッセージや教訓は何でしたか?
- 自分の考えや価値観がどう変わったか
本を読む前と後で、あなたの中で何か変化はありましたか?新しい発見や気づきがあれば書きましょう。
- 本を読んだことで得られたもの
勇気、希望、知識、新しい視点など、この読書体験を通してあなたが得たものを具体的に示します。
「はじめ」で提示した問題意識や期待に対して、読書を通してどのような答えや気づきが得られたのかを意識して書くと、まとまりのある結論になります。
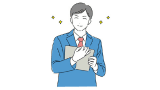
学びを今後にどう活かすかを示す
読書感想文のまとめで特に重要なのが、本から得た学びや気づきを、これからの自分の生活や考え方にどう活かしていきたいかを具体的に書くことです。
- 具体的な行動目標を立てる
例:「この本を読んで、諦めないことの大切さを学びました。これからは、苦手な数学の勉強も、すぐに諦めずに粘り強く取り組んでいこうと思います。」
- 将来の夢や目標と結びつける
例:「主人公の〇〇が困難を乗り越えて夢を叶えたように、私も将来の夢である△△になるために、日々の努力を続けていきたいです。」
- 人との関わり方を見直すきっかけにする
例:「この物語を通して、相手の気持ちを考えることの重要性を再認識しました。これからは、もっと友達の言葉に耳を傾け、思いやりのある行動を心がけたいです。」
「本を読んで終わり」ではなく、そこから得たものを自分の成長に繋げようとする姿勢を示すことが大切です。

印象に残るまとめ方の例文紹介
ここでは、印象的なまとめ方の例文をいくつか紹介します。
「この一冊の本は、私にとって暗い夜空を照らす星のような存在となりました。これから先、道に迷うことがあっても、この本から得た勇気と希望を胸に、前を向いて進んでいきたいと思います。」
「読書とは、まるで未知の世界への冒険のようだと、この本を読んで改めて感じました。これからもたくさんの本と出会い、自分の世界を広げ、心を豊かにしていきたいです。そしていつか、私も誰かの心を動かすような物語を紡げる人になりたいです。」
「『〇〇』という言葉が、今も私の心の中で強く響いています。この本との出会いは、私にとってかけがえのない財産です。この感動を忘れずに、日々の生活の中で小さなことにも感謝し、精一杯生きていこうと決意しました。」
自分の言葉で、読書体験の感動や決意を素直に表現することが、最も印象に残るまとめ方です。
中学生向け読書感想文の例文
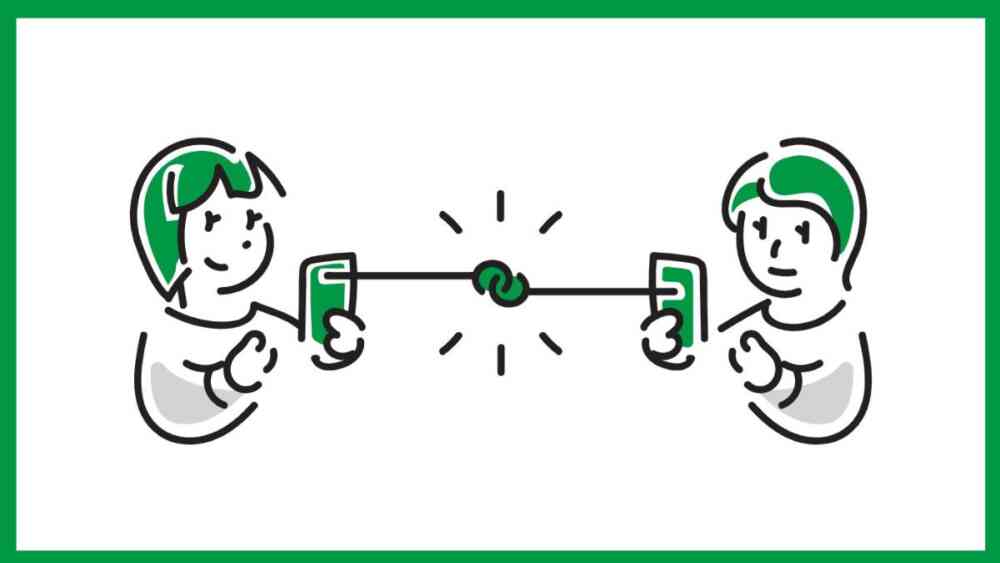
「具体的にどんな風に書けばいいの?」という人のために、ここでは中学生向けの読書感想文の例文を紹介します。
ただし、あくまで参考として、自分の言葉で書くことを忘れないでくださいね。
- 例文を活用する際の注意点
- 【物語文】読書感想文の例文
- 【説明文】読書感想文の例文
- 良い例文と惜しい例文の比較
例文を活用する際の注意点
例文はとても参考になりますが、使い方には注意が必要です。
- 丸写しは絶対にしないこと!
これは盗作にあたり、評価されないばかりか、場合によってはペナルティを受けることもあります。 - 構成や表現の仕方を参考にする
「はじめ・なか・おわり」の流れや、感想の述べ方、言葉遣いなどを参考にしましょう。 - 自分の体験や考えに置き換える
例文の骨組みを借りながら、中身は自分のオリジナルの言葉で埋めていくイメージです。 - あくまで「ヒント」として活用する
例文は、あなたが感想文を書く上での「きっかけ」や「アイデアの種」として捉えましょう。
大切なのは、あなた自身の言葉で、あなた自身の感じたことを表現することです。

【物語文】読書感想文の例文
(ここでは、架空の物語『虹色のコンパス』を読んだという設定で例文を作成します)
題名:未来を照らす虹色のコンパス
私が『虹色のコンパス』という本を手に取ったのは、図書室の新刊コーナーで、その美しい表紙に目を奪われたからだ。虹色に輝くコンパスの絵は、まるで私を未知の世界へと誘っているように見えた。正直、最初はよくあるファンタジー小説だろうと高をくくっていた。しかし、読み進めるうちに、この物語が持つ深いメッセージに、私は心を揺さぶられることになった。
この物語の主人公は、内気で自分に自信が持てない中学生の少女、アカリだ。彼女はある日、不思議な老婆から「虹色のコンパス」を譲り受ける。そのコンパスは、持ち主が本当に進むべき道を示すという不思議な力を持っていた。アカリはコンパスに導かれ、様々な困難や出会いを経験しながら、少しずつ成長していく。特に印象的だったのは、アカリが親友との間に生じた誤解を解くために、勇気を出して自分の気持ちを伝える場面だ。以前の私なら、きっとアカリのように行動できなかっただろう。私も友達と些細なことで気まずくなった時、本当の気持ちを伝えられずに後悔した経験があるからだ。「ごめんね」の一言が、どうしても言えなかった。だからこそ、アカリが涙ながらに親友と向き合う姿は、私の胸に強く響いた。
この本を読んで、私は「自分の心に正直に生きることの大切さ」を学んだ。アカリは、コンパスに頼るだけでなく、最終的には自分の意志で未来を選び取る。その姿を見て、私もこれからは他人の目や評価を気にするのではなく、自分の心の声に耳を傾け、信じた道を進んでいきたいと強く思った。虹色のコンパスは、アカリだけでなく、読んでいる私の心の中にも、未来を照らす希望の光を灯してくれたように感じる。この物語は、私にとって、これから何度も読み返したい、大切な一冊となった。
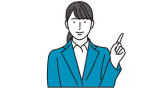
【説明文】読書感想文の例文
(ここでは、架空の説明文『ミクロの世界の冒険者たち:微生物の驚くべき力』を読んだという設定で例文を作成します)
題名:小さな巨人たちの大きな可能性
「微生物」と聞くと、皆さんは何を思い浮かべるだろうか。私は正直、この本を読むまで、微生物に対して「病気の原因になる怖いもの」という漠然としたイメージしか持っていなかった。しかし、『ミクロの世界の冒険者たち:微生物の驚くべき力』という本を読んで、その考えは180度変わった。この本は、私たちの目には見えない小さな生物たちが、地球環境や私たちの生活にとてつもなく大きな影響を与えていることを、分かりやすい言葉と迫力のある写真で教えてくれた。
この本の中で特に私の興味を引いたのは、微生物が持つ「分解する力」についての記述だ。例えば、海に流出した石油を分解してくれる微生物や、ゴミを土に還してくれる微生物がいるという。私は、人間が出したゴミや汚染物質は、自然の力だけではなかなか元に戻らないものだと思っていた。しかし、この小さな「冒険者」たちが、黙々と地球を綺麗にするために働いてくれていることを知り、大きな衝撃を受けた。「微生物がいなければ、地球はゴミだらけになってしまうかもしれない」。この一文を読んだ時、私は微生物に対する見方が完全に変わった。彼らは決して怖いだけの存在ではなく、むしろ地球環境を守るために不可欠な、頼もしいパートナーなのだと気づかされた。
この本を読んで、私は科学の面白さと奥深さを改めて感じるとともに、目に見えない小さな存在の大切さを学んだ。私たちの周りには、まだ解明されていない不思議なことがたくさんあり、微生物の世界もその一つだ。これからは、道端の草花や土の中にいる小さな生き物たちにも、少し優しい目を向けられるような気がする。そして、この本で学んだ知識を活かして、環境問題についてもっと深く考え、自分にできる小さなことから行動していきたい。この本は、私に新しい視点と知的好奇心を与えてくれた、まさに「冒険の書」だった。
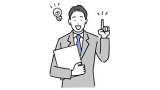
良い例文と惜しい例文の比較
ここでは、同じテーマで書かれた「良い例文」と「惜しい例文」を比較してみましょう。
テーマ:友情の大切さを教えてくれた本
- 惜しい例文
「私は『〇〇』という本を読みました。主人公と友達が喧嘩したり仲直りしたりする話で、面白かったです。友情は大切だと思いました。」- 惜しいポイント
- 書き出しが平凡。
- あらすじの説明がほとんどない。
- 「面白かった」「大切だと思った」という感想が抽象的で、なぜそう思ったのかが書かれていない。
- 自分の体験や具体的なエピソードがない。
- 惜しいポイント
- 良い例文
「『もし親友が大きな嘘をついていたとしたら、許せるだろうか?』。この本『〇〇』は、私にそんな難しい問いを投げかけてきた。主人公のユキは、大親友のミカからある秘密を打ち明けられ、友情が試されることになる。特に、ユキがミカの嘘を知りながらも、彼女を信じようと葛藤する場面は、読んでいて胸が苦しくなった。私も以前、友達に裏切られたと感じる出来事があり、その時の辛い気持ちを思い出したからだ。しかし、ユキはミカと真正面から向き合い、お互いの本音をぶつけ合うことで、より強い絆で結ばれていく。その姿を見て、本当の友情とは、ただ仲が良いだけでなく、時には傷つけ合いながらも理解し合おうと努力することなのだと気づかされた。この本を読んで、私も友達ともっと素直に向き合っていこうと強く思った。」- 良いポイント
- 問いかけから始まる魅力的な書き出し。
- 必要なあらすじが簡潔に書かれている。
- 心に残った場面と、それに対する自分の感情が具体的に書かれている。
- 自分の体験と結びつけて感想を深めている。
- 本から学んだこと、今後の行動への決意が明確に述べられている。
- 良いポイント
比較することで、どこをどう改善すれば良いのかが見えてきますね。
Q&A:中学生の読書感想文の書き方に関する質問(原稿用紙・枚数・盗作)
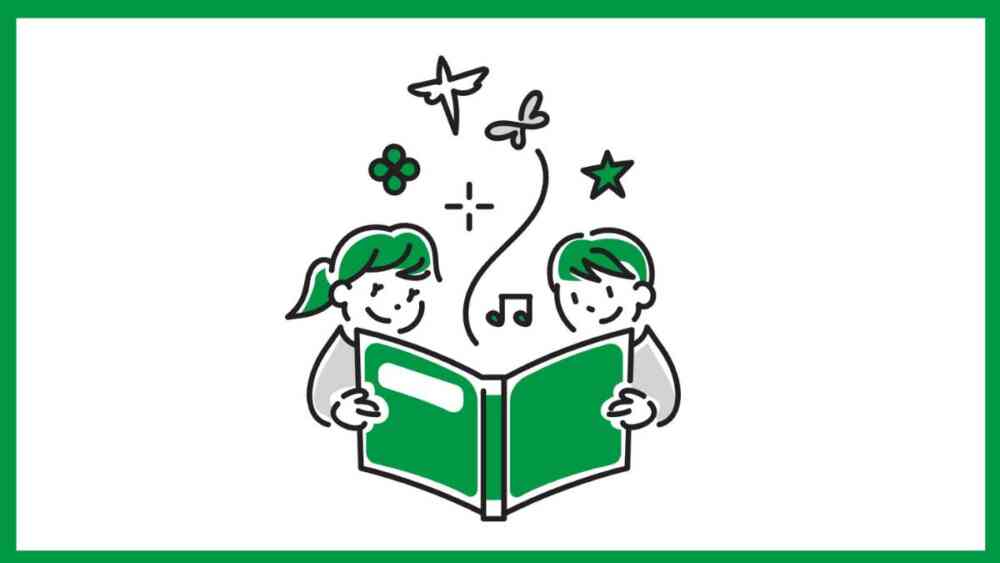
読書感想文を書く上で、多くの人が疑問に思うことや困ることをQ&A形式でまとめました。
- 原稿用紙の正しい使い方ルール
- 文字数調整のコツ(3枚・5枚)
- 読書感想文お助けテンプレート
- 盗作にならないための注意点
- 読書感想文に関するよくある質問
原稿用紙の正しい使い方ルール
原稿用紙には、いくつか基本的な書き方のルールがあります。これらを守ることで、読みやすく整った感想文になります。
- 題名
通常、1行目または2行目に書きます。書き始めは2~3マス空けるのが一般的です。 - 学校名・学年・組・氏名
題名の次の行に書きます。行の右側に寄せて書いたり、最後の行に書いたり、学校によって指示が異なる場合があるので確認しましょう。氏名の下は1マス空けます。 - 本文の書き始め
段落の初めは1マス空けて書き始めます。 - 句読点(、。)や括弧(「 」『 』)
それぞれ1マス使って書きます。ただし、句読点や閉じ括弧が行の先頭に来ないように注意しましょう。前の行の最後のマスに、文字と一緒に入れます。 - 小さい「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」(促音・拗音)
マス目の右上に小さく書きます。 - 数字の書き方
縦書きの場合、漢数字(一、二、三…)を使うのが基本です。横書きの場合は算用数字(1、2、3…)でも構いませんが、学校の指示に従いましょう。 - 会話文
「 」で囲み、改行して新しい行の1マス目から書き始めます。会話文の終わりの句点(。)は、「 」の前に打ちます。
原稿用紙の使い方は、慣れるまで少し難しく感じるかもしれませんが、基本を押さえれば大丈夫です。
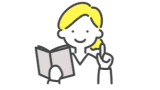
文字数調整のコツ(3枚・5枚)
「原稿用紙〇枚以上」という指定がある場合、文字数を調整するのに苦労することがありますよね。
指定枚数に足りない場合
- 各エピソードをより具体的に、詳しく書く
「感動した」だけでなく、どんな場面で、どんな言葉に、どのように感動したのかを詳細に描写します。 - 自分の考えや気持ちをさらに深く掘り下げてみる
「なぜそう思ったのか?」「そこから何を感じたのか?」と自問自答し、思考のプロセスを丁寧に記述します。 - 心に残った場面やセリフを複数取り上げ、それぞれに対する感想を書く
一つのエピソードだけでなく、複数の視点から本を捉え直してみましょう。 - 本を読む前と後での自分の変化を具体的に書く
どんな考え方がどう変わったのか、ビフォーアフターを明確にします。 - 比喩表現や情景描写を豊かにする
ただし、内容と関係ないことで文字数を稼ぐのは避けましょう。
指定枚数をオーバーしてしまう場合
- あらすじ部分を短く、簡潔にする
感想を述べるのに最低限必要な情報に絞り込みます。 - 繰り返し同じことを言っている部分を削る
表現を変えて同じ内容を繰り返していないか確認しましょう。 - 表現をより簡潔なものに言い換える
回りくどい言い方や冗長な表現を避け、ストレートな言葉を選びます。 - 重要度の低いエピソードや感想を思い切って削る
全体の構成を見直し、最も伝えたいことに焦点を絞ります。
文字数調整は、自分の考えを整理し、より的確に表現する良い練習にもなります。

読書感想文お助けテンプレート
「どうしても何から書けばいいか分からない!」という人のために、簡単な穴埋め式のテンプレートを用意しました。
これをヒントに、自分の言葉で肉付けしてみてください。
読書感想文お助けテンプレート
- はじめ(本との出会い・読む前の印象)
- 私がこの本(『本の題名』)を選んだ理由は、◎◎です。
- 読む前は、●●だろうと(思って・期待して)いました。
- なか(あらすじ・心に残ったこと・自分の考え)
- この本の簡単なあらすじは、◎◎です。
- 特に心に残ったのは、登場人物の名前や場面、セリフなど:◎◎です。
- なぜなら、◎◎だからです。
- 自分の体験談など:私も以前、 ◎◎を体験しました。
- このことから、私は◎◎と考えました。
- おわり(学んだこと・今後の抱負)
- この本を読んで、私は◎◎ことを学びました。
- これからは、◎◎していきたいです。
このテンプレートはあくまで骨組みです。
これにあなたの言葉で肉付けし、オリジナルの感想文を完成させてください。
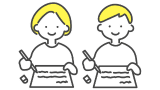
盗作にならないための注意点
読書感想文を書く上で、絶対にやってはいけないのが「盗作」です。盗作とは、他人の文章やアイデアを、まるで自分のもののように発表することです。
- インターネット上の感想文や解説サイトの丸写しは絶対にダメ!
先生は簡単に見抜きますし、何よりも自分のためになりません。 - 友達の感想文をそのまま写すのもNG!
たとえ許可を得ていたとしても、それはあなたの感想ではありません。 - 本や解説書の文章をそのまま抜き出してつなぎ合わせるのも盗作にあたります。
- 参考にするのはOK、でも必ず自分の言葉で書き直すこと!
他の人の感想を読んで「なるほど、そういう考え方もあるのか」とヒントを得るのは良いことです。しかし、それを表現する際は、必ず自分の言葉で、自分の体験や考えを交えて書きましょう。
読書感想文は、あなた自身の考えや感じたことを表現する場です。
自信を持って、自分の言葉で書きましょう。
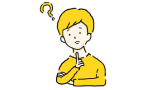
読書感想文に関するよくある質問
最後に、中学生の皆さんからよく寄せられる読書感想文に関する質問にお答えします。
Q. どんな本を選べばいいか、どうしても分かりません…。
A. まずは自分が少しでも「読んでみたい」「面白そう」と思える本を選ぶのが一番です。無理に難しい本や分厚い本を選ぶ必要はありません。漫画やライトノベルがきっかけで読書が好きになる人もいます(ただし、感想文の題材として認められるかは学校の先生に確認しましょう)。図書館の司書さんや国語の先生、本好きな友達におすすめを聞いてみるのも良い方法です。表紙やあらすじを見て、直感で「これだ!」と思う本に出会えることもありますよ。
Q. あらすじばかり長くなってしまい、感想が少ししか書けません。どうすればいいですか?
A. あらすじは、感想を述べるために「最低限必要な情報」に絞りましょう。 感想文の主役は、あくまであなたの「感想」です。「この場面で主人公はこう言った。それに対して私はこう思った。なぜなら…」というように、あらすじをきっかけにして自分の考えを展開していくことを意識してみてください。全体のバランスを見て、あらすじが長すぎるようなら思い切って削る勇気も必要です。
Q. 何を書けばいいか、全く思いつきません。頭が真っ白です…。
A. まずは、本を読んでいる時に取った「読書メモ」を見返してみましょう。 心に残ったセリフ、感動した場面、疑問に思ったことなど、どんな小さなことでも構いません。その中から一つでも「これについてもう少し考えてみたい」と思えるものがあれば、そこを深掘りしていくと、書きたいことが見つかるかもしれません。また、誰かに本の内容や感想を話してみるのも効果的です。話しているうちに、自分の考えが整理されたり、新しい発見があったりします。
Q. 読書感想文を書くのが苦手で、どうしても好きになれません。
A. 無理に好きになる必要はありませんが、「書かなければいけない」というプレッシャーを少しでも減らす工夫をしてみましょう。例えば、まずは短い文章で良いので、箇条書きで感じたことを書き出してみる。あるいは、絵や図を使って本の内容や感想を表現してみる(そこから文章に起こす)。完璧を目指さず、「まずは提出できる形にする」ことを目標にするのも一つの手です。そして、もし少しでも「書けた!」という達成感を味わえたら、それが次のステップに繋がるかもしれません。
読書感想文は、あなた自身の成長の記録でもあります。
焦らず、自分のペースで取り組んでみてください。
東大生家庭教師
現役の東大生が指導するオンライン家庭教師!
当サイト人気ランキングTOP3
第1位:東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
第2位:オンライン家庭教師「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
第3位:オンライン東大家庭教師友の会
※東大生をはじめとする難関大生がマンツーマンでオンライン指導!講師の2人に一人が厳しい採用基準を突破した現役東大生!
まとめ:中学生の読書感想文の書き方はコレで完ペキ!書き出し例文&テンプレート

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
以上、「中学生の読書感想文の書き方はコレで完ペキ!書き出し例文&テンプレート」でした。
まとめ:読書感想文!中学生向け書き方のコツ!
まとめ
ここまで、中学生向けの読書感想文の書き方について、構成の基本から具体的なコツ、例文まで詳しく解説してきました。
最後に、読書感想文を上手に書くための大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 基本構成「はじめ・なか・おわり」を意識する。
- 本選びは「自分が読みたい本」を優先する。
- 読書メモを活用して、感じたことや考えたことを記録する。
- 書き出しは読者の心をつかむ工夫をする。
- 本文では「なぜそう思ったか」を深く掘り下げ、自分の体験と結びつける。
- 結論では、本から学んだことを今後の生活にどう活かすかを示す。
- 例文は参考にしつつ、必ず自分の言葉で書く(盗作は絶対にダメ!)。
読書感想文は、決して難しいものではありません。本と真剣に向き合い、あなたが感じたこと、考えたことを素直に、そして自分の言葉で表現することが何よりも大切です。
この記事が、皆さんの読書感想文作成の一助となり、「書けた!」という達成感を味わうきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
さあ、自信を持って、あなただけの素晴らしい読書感想文を完成させてくださいね!応援しています!
国語の成績が上がる記事
ポイント

