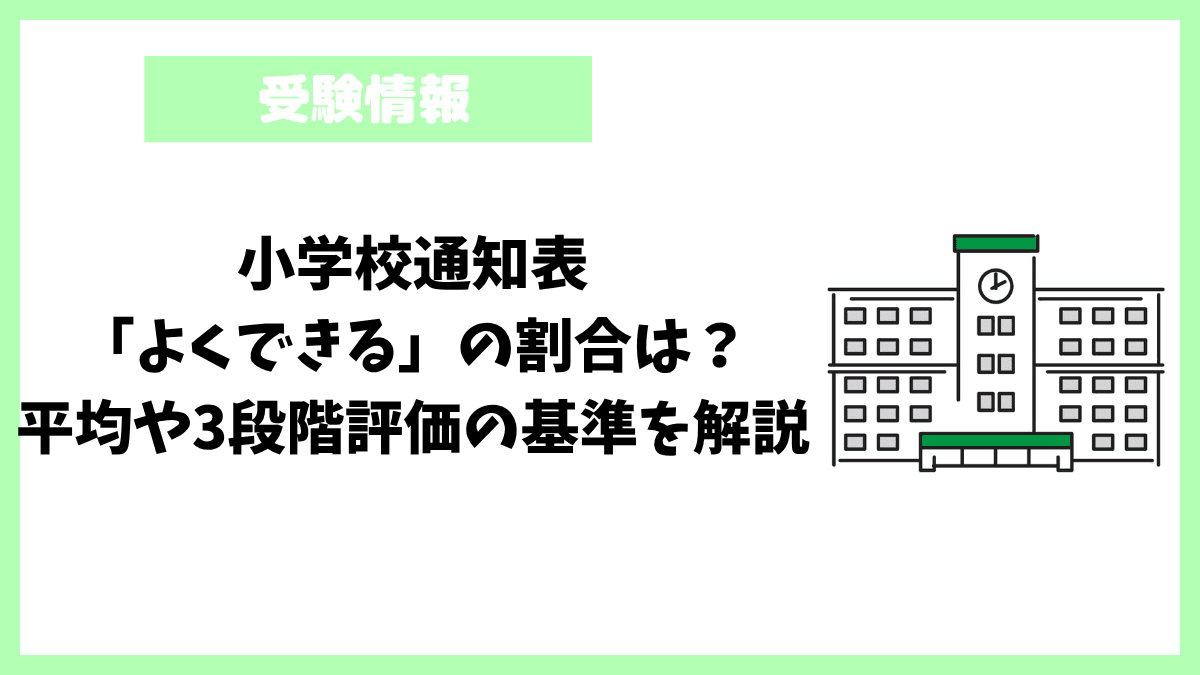
「※この記事には一部PRが含まれます」
お子さんが小学校から通知表(あゆみ)をもらってきたとき、「よくできる」の数がいくつあるか、つい気になってしまいますよね。
「うちの子の成績は、他の子と比べてどうなんだろう?」 「『よくできる』が少ないけど、大丈夫かな…?」
そんな不安や疑問を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、小学校の通知表における「よくできる」の評価について、現役の親世代が知らない評価制度の仕組みから、具体的な割合の目安、そして通知表を子どもの成長に繋げるための見方まで、分かりやすく解説しますます。
私自身は長年、個別指導の学習塾で小学生の指導にあたり、保護者の方々とは学期ごとに成績に関する面談を重ねてきました。
その中で見てきた具体的な事例や保護者の皆様の疑問、そして私が培った知見を交えながら、通知表の「今」をお伝えします。
この記事を読めば、通知表の評価に一喜一憂することなく、お子さんの頑張りを正しく認め、次のステップへ向けて前向きにサポートできるようになります。
リーナブルな料金で生徒数No.1のオンライン個別指導塾はこちらから
記事のポイント
「よくできる」の割合は平均10~20%が目安
小学校の通知表は絶対評価で決まる
「よくできる」の数で見る評価の目安
「よくできる」が少ない・ない時の考え方
「がんばろう」が多い時の受け止め方
通知表で本当に見るべき3つのポイント
おすすめ塾
参考記事:【そら塾】中学生の料金は高い?他のオンライン塾と料金比較してみた!
Contents
小学生の通知表「よくできる」の割合は平均10~20%が目安

結論から言うと、小学校の通知表で「よくできる」が付く割合は、評価項目全体の10%~20%が一般的な目安とされています。
ただし、この数字はあくまで目安です。
学校の方針や地域、学年、クラスの状況によって割合は変動するため、「この割合でなければならない」という決まりはありません。
私自身の長年の経験から言えば、この10%~20%という目安は肌感覚と非常に近い数字です。
特に高学年になるにつれて「よくできる」の割合がこの範囲に収まることが多く、保護者面談でもこの目安をお伝えすることがよくありました。
大切なのは、この数字を基準にお子さんの成績を判断するのではなく、評価の背景にある仕組みを理解することです。
- 評価の根拠は学習指導要領の目標達成度
- 学年が上がると「よくできる」は減る傾向
- 教科によって評価の付きやすさは異なる
評価の根拠は学習指導要領の目標達成度
小学生の通知表の評価は、先生の主観やクラス内での順位で決まるわけではありません。
その根拠となっているのが、文部科学省が定める「学習指導要領」です。
学習指導要領とは、全国どの学校でも一定水準の教育が受けられるように定められた、教育課程(カリキュラム)の基準のことです。
通知表の各評価項目は、この学習指導要領に示された各教科の目標が、どの程度達成できたかを示しています。
「よくできる」は、その目標を「十分に達成できた」と判断された場合に付けられる評価なのです。
(参考:文部科学省「学習指導要領「生きる力」」)

学年が上がると「よくできる」は減る傾向
小学校低学年の頃は「よくできる」がたくさん付いていたのに、学年が上がるにつれて数が減っていくのはよくあることです。
なぜなら、学年が上がるごとに学習内容が高度になり、求められる目標のレベルも高くなるからです。
例えば、算数では単純な計算だけでなく、文章問題や図形など、より複雑な思考力が求められるようになります。
そのため、評価が下がったからといって、必ずしもお子さんの学習意欲や能力が低下したわけではありません。
むしろ、より難しい課題に挑戦している証と捉えることもできます。
学習塾で指導する中で、小学3~4年生頃から「今まで『よくできる』がたくさんあったのに…」と心配される保護者の方が増える傾向にあります。
しかしこれは、お子さんが新たな壁に挑戦している証拠だと、私はいつもお伝えしています。
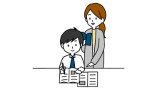
教科によって評価の付きやすさは異なる
国語や算数といった知識の積み重ねが重要な教科と、音楽や図工、体育といった感性や技能が評価される教科とでは、評価の観点が異なります。
そのため、お子さんの得意・不得意によって「よくできる」の数が教科ごとに偏るのはごく自然なことです。
すべての項目で「よくできる」を目指すのではなく、お子さんがどの分野に興味や強みを持っているのかを見つけるきっかけとして通知表を活用しましょう。
算数で「よくできる」を目指すための家庭学習法はこちらの記事で詳しく解説しています。小学6年生│算数の勉強法│親が算数を教えるコツを知ると成績アップ
小学校の通知表「よくできる」は絶対評価で決まる!3段階評価とは?
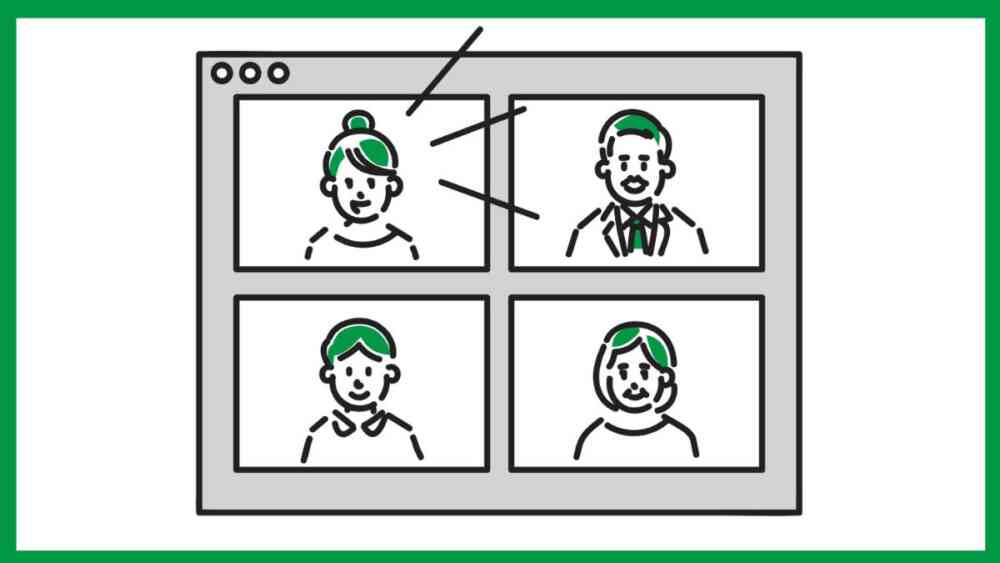
現在の小学校の通知表は、「絶対評価」という方法で付けられています。
これは、保護者世代が経験した「相対評価」とは大きく異なるため、まずこの違いを理解することが重要ですです。
私が学習塾で働き始めた頃はまだ相対評価が主流でしたので、保護者の皆様が「昔と違う」と感じるのは当然です。
しかし、この絶対評価を正しく理解することが、お子さんの通知表の見方を変える第一歩になります。
絶対評価とは、周りの子供との比較ではなく、子供一人ひとりが「学習指導要領」に示された目標をどのくらい達成できたかを見る評価方法です。
評価は主に以下の3段階で示されます。
- ①「よくできる」十分満足できる状況
- ②「できる」おおむね満足できる状況
- ③「がんばろう」努力を要する状況
- クラス順位で決まる相対評価との違い
「よくできる」十分満足できる状況
学習の目標を十分に達成できている状態を示します。
単にテストで良い点を取るだけでなく、授業での発表や課題への取り組みなど、学習意欲や態度も評価の対象となります。

「できる」おおむね満足できる状況
学習の目標をおおむね達成できている状態です。
ほとんどの小学生がこの評価に該当し、基本的な学習内容が身についていることを示しています。
小学校の学習においては、まずこの「できる」を目指すことが一つの目安となります。
私が指導する生徒たちも、まずは「できる」を確実に増やしていくことを目標にすることで、基礎学力の定着に繋がることが多くありました。

「がんばろう」努力を要する状況
学習の目標達成に向けて、もう少し努力が必要な状態を示します。
「成績が悪い」というネガティブな意味ではなく、「ここが伸びしろですよ」という先生からのメッセージと捉えることが大切です。

クラス順位で決まる相対評価との違い
一方、かつて主流だった「相対評価」とは、集団の中での位置(クラス内での順位など)によって評価が決まる方法です。
例えば、「上位10%が『5』、次の20%が『4』」というように、あらかじめ評価の割合が決められていました。
絶対評価では、クラス全員が目標を十分に達成していれば、全員が「よくできる」になる可能性もあります。
つまり、他人との比較ではなく、お子さん自身の成長を見ることが大切なのです。
「うちの子はクラスで何番目くらいですか?」というご質問を保護者面談でいただくことがよくありますが、絶対評価の現在では、この問い自体が意味をなしません。
お子さん自身の「伸び」に目を向けてあげてください。
「よくできる」の数で見る評価の目安
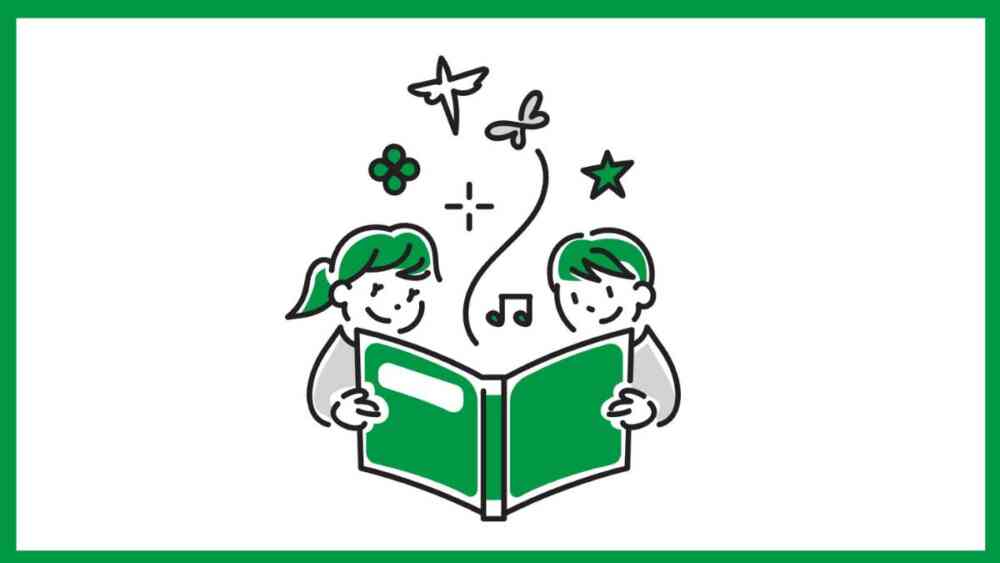
「結局、うちの子の『よくできる』の数は平均と比べてどうなの?」という疑問にお答えします。
- 平均的な個数は学校や学年で変動する
- 全部「よくできる」はクラスに数人程度
- 学校独自の二重丸評価との関係性
平均的な個数は学校や学年で変動する
「よくできる」の平均個数について、明確なデータや基準は存在しません。
なぜなら、前述の通り、評価は学校や学年、クラスを担当する先生の方針によっても変わるからです。
例えば、基本的な知識の定着を重視する学校と、応用力や表現力を重視する学校とでは、「よくできる」」が付く基準も異なります。
そのため、平均的な個数を過度に気にする必要はありません。
私自身、様々な学校の生徒を見てきましたが、同じ学年でも通知表の「よくできる」の数には学校ごとの傾向があると感じています。
これは、学校がどんな学習目標を重視しているか、という先生方の「教育方針」が反映されているからだと理解していました。
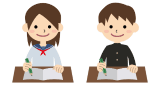
全部「よくできる」はクラスに数人程度
すべての評価項目で「よくできる」(いわゆるオールA)を取ることは、非常に難しいことです。
もしクラスにいたとしても、1人か2人程度、あるいは全くいないというケースも珍しくありません。
「全部よくできる」を目指すことよりも、お子さんが苦手な項目を少しでも克服したり、得意なことをさらに伸ばしたりすることに目を向ける方が、よほど建設的です。
実際に「オールA」のお子さんを指導した経験はありますが、それは本当に稀なケースです。
むしろ、得意な科目で「よくできる」を取りつつ、苦手な科目も「できる」に近づける努力をしているお子さんの方が、着実に成長していると感じることが多かったです。
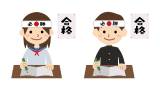
学校独自の二重丸評価との関係性
学校によっては、「よくできる」「できる」「がんばろう」の代わりに、「◎(二重丸)」「○」「△」といった記号で評価を示す場合があります。
これは呼び方が違うだけで、評価の考え方は同じです。
一般的に「◎」が「よくできる」、「○」が「できる」、「△」が「がんばろう」に相当すると考えてよいでしょう。
「よくできる」が少ない・ない時の考え方
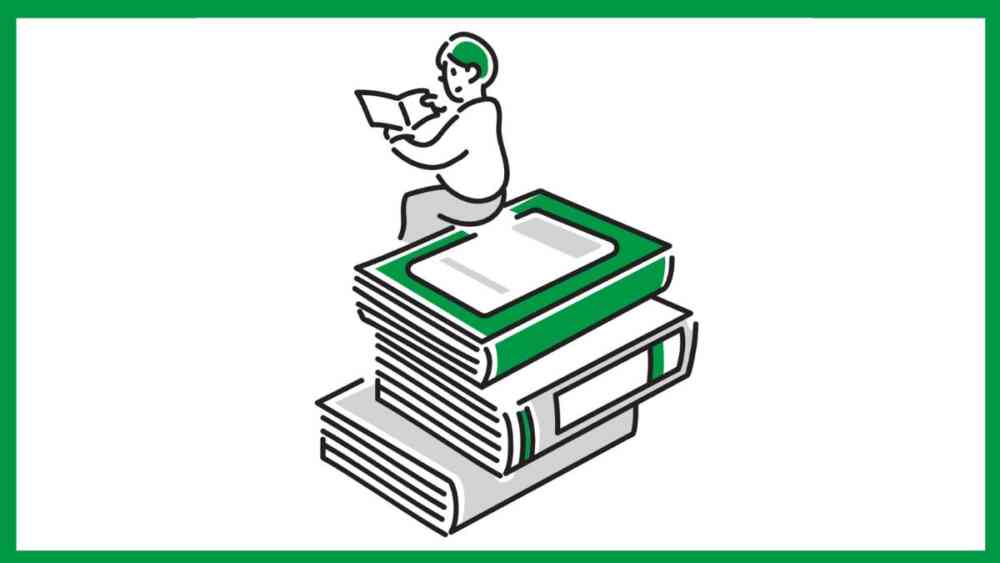
「よくできる」が一つもなかったり、数が少なかったりすると、保護者としては心配になるかもしれません。
そんな時こそ冷静に受け止め、前向きな行動につなげることが大切ですです。
保護者面談では、「うちの子、『よくできる』が一つもなくて…」と、本当に落ち込んだ表情でお話しされる方もいらっしゃいました。
しかし、そんな時こそ、通知表を客観的に見て、お子さんの「伸びしろ」を探すチャンスだとお伝えしています。
- 評価は子供の能力の全てではない
- 苦手分野を特定するチャンスと捉える
- 家庭でできる学習サポートの具体例
評価は子供の能力の全てではない
まず心に留めておいてほしいのは、通知表の評価は、お子さんの学校生活の一側面に過ぎないということです。
通知表には現れない優しさ、ユニークな発想、好きなことへの集中力など、お子さんにはたくさんの素晴らしい個性があります。
評価の数だけでお子さんの価値を判断しないようにしましょう。

苦手分野を特定するチャンスと捉える
「よくできる」が少ない、あるいは「がんばろう」が付いている項目は、見方を変えれば「お子さんの苦手な部分」や「これから伸びる可能性のある部分」を具体的に示してくれる貴重な情報です。
どこでつまずいているのかが分かれば、的を絞ったサポートができます。
漠然と「勉強しなさい」と言うよりも、ずっと効果的です。
「算数の図形で『がんばろう』が付いているなら、まずはそこから集中して取り組んでみようか」と、目標を具体的にすることで、お子さんも前向きに学習に取り組めるようになります。
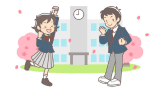
もしお子さんが勉強そのものに抵抗があるようでしたら、こちらの記事で勉強嫌いの克服法と親ができる対策を紹介しています。小学生の勉強嫌いを克服!勉強しない子の原因と対策!今すぐ親ができること
家庭でできる学習サポートの具体例
苦手分野を克服し、「できる」を「よくできる」に引き上げるために、家庭でできるサポートの例をいくつかご紹介します。
- 学習習慣を整える:まずは勉強する環境を整えましょう。毎日決まった時間に宿題をする、静かな場所で集中できるようにするなど、基本的な生活習慣が学習の土台になります。これは塾で指導する上で最も大切にしていることです。どんなに素晴らしい教材があっても、家庭での学習習慣がなければ定着しません。
- 教科書やドリルで復習する:「できる」と評価された項目は、基礎が理解できている証拠です。その単元の教科書をもう一度読み返したり、ドリルの応用問題に挑戦したりすることで、「よくできる」に必要な深い理解につながります。
- 子供の興味を引き出す:例えば、理科が苦手なら一緒に科学館へ行ったり、社会が苦手なら歴史漫画を読んだりするなど、学習内容と実生活を結びつけて興味を引き出す工夫も有効ですです。「理科が苦手だった子が、家庭で簡単な実験を体験してから急に興味を持ち、『よくできる』に変わった」という嬉しい報告を受けたこともあります。
小学生から中学生へのスムーズな移行には、学習習慣の準備も重要です。こちらの記事も参考にしてください。小学生と中学生の違い!勉強・生活もこんなに違う!親子で準備
「がんばろう」が多い時の受け止め方
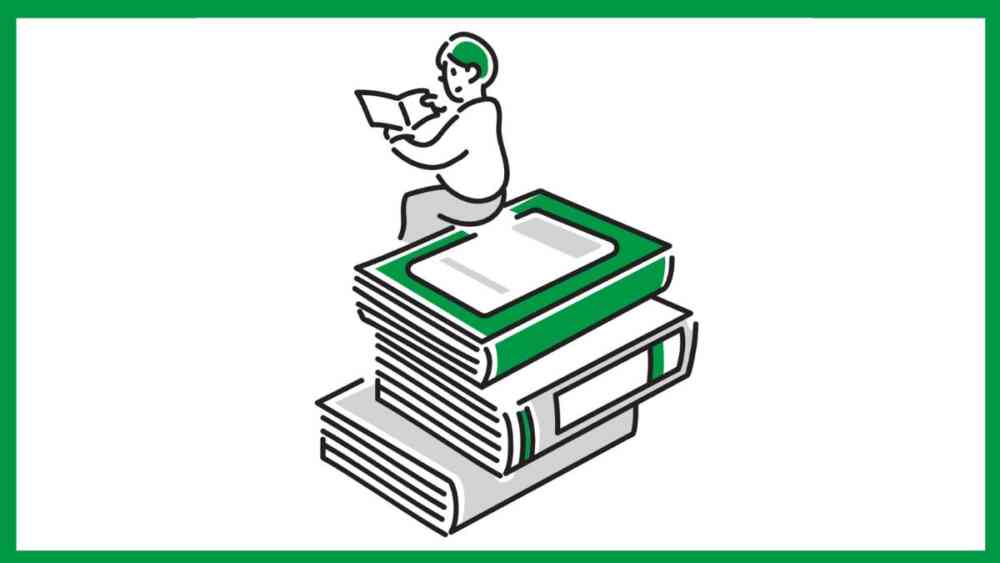
「がんばろう」の評価が多いと、つい叱ってしまいたくなるかもしれません。
しかし、それは逆効果です。ここでは、「がんばろう」を成長のバネにするための受け止め方をお伝えします。
- 伸びしろを示しているポジティブなサイン
- まずは子供の話を聞き原因を探る
- 先生に具体的な学習状況を相談する
伸びしろを示しているポジティブなサイン
「がんばろう」は、決して「できない子」という烙印ではありません。
むしろ、「ここを乗り越えればもっと成長できるよ」という先生からの期待が込められたエールです。
お子さんの「伸びしろ」を示してくれるポジティブなサインと捉え、親子で一緒に乗り越える課題として向き合いましょう。
私自身、たくさんの生徒と接してきましたが、「がんばろう」が付いたことをきっかけに、苦手分野を克服して大きく伸びた生徒を何人も見てきました。これは本当にポジティブなサインなのです。
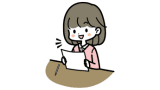
まずは子供の話を聞き原因を探る
なぜ?その評価になったのか、頭ごなしに問い詰めるのはやめましょう。
まずは「授業でどこが難しかった?」「何に困っているの?」と、お子さんの目線に立って優しく話を聞いてあげてください。
原因は、「授業のペースが速い」「先生に質問するのが恥ずかしい」「特定の友達との関係」など、勉強そのもの以外にあるかもしれません。
私の保護者面談では、まずはお子さんの話をじっくり聞いて、その上で原因を一緒に探るようアドバイスしていました。意外なところに原因があることも少なくありません。
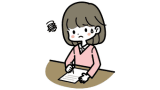
先生に具体的な学習状況を相談する
個人面談などの機会を積極的に活用し、先生に学校での具体的な様子や、家庭でできるサポートについて相談することを強くお勧めします。
先生は多くの子供たちを見ている教育のプロです。
つまずきの原因や、お子さんに合った効果的な学習方法について、的確なアドバイスをもらえるはずです。
私の学習塾経験の中で、担任の先生と密に連携を取れたご家庭ほど、お子さんの学習状況が劇的に改善するケースを数多く見てきました。先生方も、家庭でのサポートを非常に心強く思っています。
通知表で本当に見るべき3つのポイント
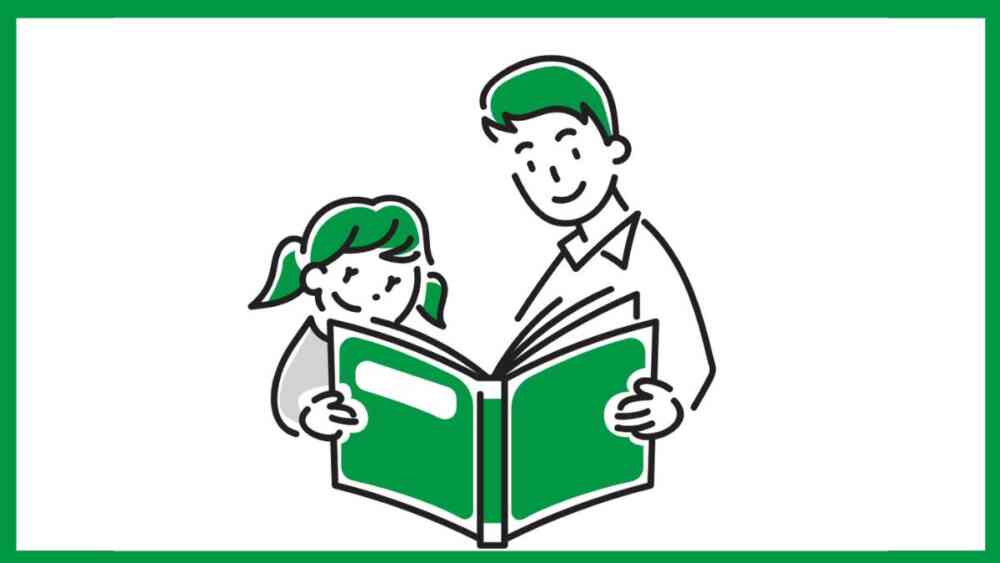
最後に、評価の数に一喜一憂するのではなく、通知表を最大限に活用するために本当に見るべきポイントを3つご紹介します。
- 評価の数より先生からの所見欄
- 子供が頑張った過程を具体的に褒める
- 親子で次の学期の目標を立てる
評価の数より先生からの所見欄
通知表の中で最も重要なのは、評価の記号や数字ではなく、先生が文章で記述してくれる「所見欄」です。
ここには、評価だけでは分からないお子さんの学校での具体的な頑張り、友達との関わり方、授業中の様子、そして成長した点などが書かれています。
この所見欄こそ、お子さんの個性を理解するための宝の山です。
私自身、保護者面談では、まず所見欄に書かれている先生のメッセージに注目するようお伝えしていました。ここにこそ、お子さんの「本当の姿」が隠されています。
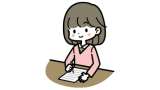
子供が頑張った過程を具体的に褒める
通知表を見ながらお子さんを褒めるときは、結果だけでなく過程を褒めることが大切です。
「『よくできる』が5個ですごいね!」ではなく、「漢字の練習を毎日頑張ったから、字がとても丁寧になったね」「苦手な計算問題から逃げずに挑戦したのが素晴らしいね」というように、具体的な行動や努力を褒めてあげましょう。
それがお子さんの自己肯定感を育みます。「結果だけでなく、そこに至るまでの頑張りを認めると、お子さんの次の意欲に繋がる」ということを、数多くの親子を見てきて痛感しています。
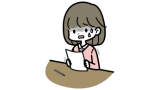
親子で次の学期の目標を立てる
通知表は、過去を振り返るだけでなく、未来へ目を向けるためのツールです。
「がんばろう」だった項目について「次の学期は、まず『できる』を目指して一緒に頑張ろうか」と、親子で前向きな目標を立ててみましょう。
通知表をきっかけにした対話が、お子さんの学習意欲を引き出す最高のきっかけになります。
通知表の「よくできる」の数を増やす!小学生向けタブレット学習教材厳選6つ

塾オンラインドットコムがおすすめする、小学生向けおすすめのタブレット教材を紹介。
興味があれば、積極的に資料請求すると良いでしょう。
進研ゼミ:小学講座

小学生利用者NO.1!進研ゼミ
| 月謝 | 【月謝例】 小学1年生:3,250円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、算数、理科、社会、英語 |
| 学習機能 | 教科書対応のテキストで、予習も復習もバッチリ! お使いの教科書に合わせたテキストなので、予習はもちろん復習にも効率的に |
| 管理機能 | AIのレッスン提案で迷わない実力に合わせて学習スタート 学習達成後のごほうびでやる気が続く |
| サポート体制 | 月1回、赤ペン先生がお子さま一人ひとりを添削し、丁寧に指導。担任制なので、毎回同じ先生に提出する楽しみがうまれ、毎月の学習の仕上げとしてしっかり取り組めます。 |
すらら:無学年方式オンライン教材

「すらら」の基本情報
| 受講費用の安さ | ■入会金 ・小中・中高5教科コース:7,700円 ・小中・中高3教科、小学4教科コース:11,000円 ■3教科(国・数・英)コースの月謝例 ・小中コース 月額:8,800円〜 小学1年生~中学3年生までの3教科(国・数・英)の範囲が学び放題 ・中高コース 月額:8,800円〜 |
| 対応科目・コース | 4教科(国・数・理・社)コース 5教科(国・数・理・社・英)コース 無学年方式で中学英語も先取り学習できる |
| 学習機能 | キャラクターによるレクチャーからドリル機能が充実 「すらら」は読み解くだけではなく、見て、聞いて学べる |
| 管理機能 | 「すらら」はAI搭載型ドリルだから自分のつまずきポイントがわかる! |
| サポート体制 | 学習習慣の身に付け方を始めとした学習に関する悩みや、基礎学力、成績を上げるための学習設計をサポートします。 |
スマイルゼミ:最適な学びが継続するタブレット教材
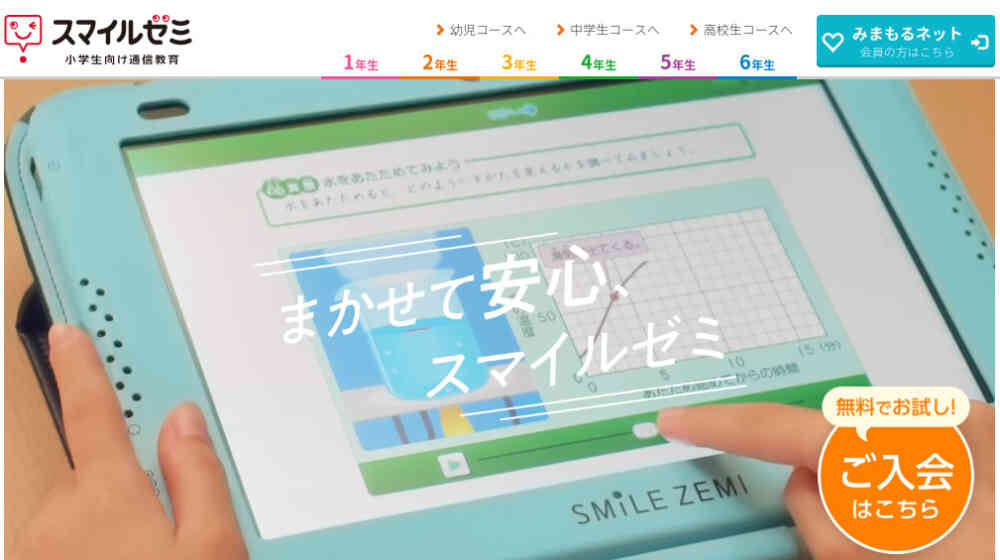
スマイルゼミの基本情報
| お手軽な受講費用 | 【小学1年生】月謝例 <標準クラス> ・3,278円:12か月一括払い/月あたり ・3,718円:6ヵ月一括払い/月あたり ・4,268円:毎月払い |
| 対応科目・コース | 国語・算数・理科・社会はもちろんのこと、英語やプログラミングも1年生から学習できる |
| 学習機能 | アニメーションによる解説で公式の持つ意味を正しく理解できる 手をついて書ける学習専用タブレットを使用 |
| 管理機能 | スマイルゼミのタブレットは、利用時間を「1日〇時間」という形で制限可能 |
| サポート体制 | 全額返金保証制度あり |
小学生に最適なタブレット教材:デキタス
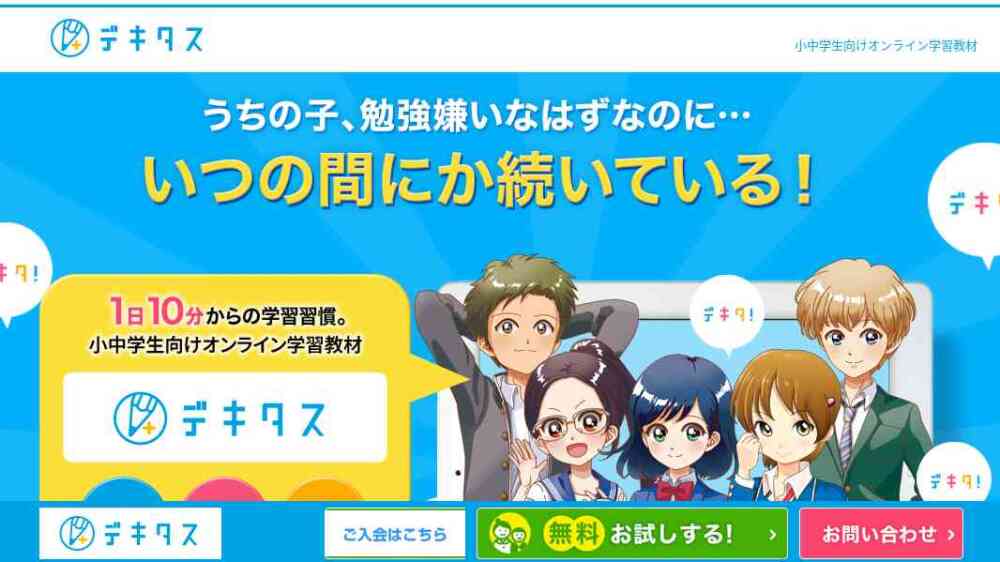
中学生におすすめ!デキタスの基本情報
| 項目 | デキタスの公式サイト |
| 料金 | 小学生:3,960円 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、地理、歴史、公民、国文法、英語検定 |
| 学習機能 | ポップなキャラクター&わくわくする授業! |
| 管理機能 | テストモード搭載 |
| サポート体制 | 学習結果は表・グラフ・カレンダー等でひと目で確認することができます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
教科書の内容を確実に理解
↓↓↓
デキタスの公式サイトチェック!
RISU算数:タブレット算数学習+個別フォロー

RISU算数の基本情報
| 安心の月謝体系 | 1か月あたりの平均クリアステージ数に応じて段階的に利用料が変動 1.0未満:0円 1.0以上~1.3未満:1,000円(税込1,100円) 1.3以上~1.5未満:1,500円(税込1,650円) 1.5以上~2.0未満:3,000円(税込3,300円) 2.0以上~2.5未満:5,000円(税込5,500円) 2.5以上~3.0未満:7,000円(税込7,700円) |
| 対応科目・コース | 算数・英語 |
| 学習機能 | RISUでは、お子様1人1人のデータを分析し、ピッタリの問題とレッスン動画を配信。 復習する部分を自動出題することで、むやみやたらに全部の問題を何度もやり直すことなく、的確に地に足の着いた学習ができる |
| 管理機能 | マイページで学習状況をチェック |
| サポート体制 | ・24時間365日スタッフへ相談可能 ・難関大生のトップチューターがデータ分析をもとに学習状況をフォロー(ビデオ解説など) |
東大生家庭教師
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
当サイトで人気の「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求が勉強が変わること間違いなし!
オンライン東大家庭教師友の会
※東大生をはじめとする難関大生がマンツーマンでオンライン指導!講師の2人に一人が厳しい採用基準を突破した現役東大生!
オンライン家庭教師e-live
※東大生や英学部生の講師が選べるオンライン家庭教師!オンライン家庭教師の実績は15年以上!信頼と実績のあるオンライン家庭教師
MeTULAB(ミートゥーラボ)
※講師は全員現役の東大生!大学受験、高校受験合格を目指す生徒に向けて、現役の東大生から親切・丁寧な個別指導が特徴
スタディコーチ
※講師のほとんどが東大生と早慶生!勉強の計画作成や進捗管理をおこなうコーチンが特徴!スタッフの丁寧な対応が印象的なオンライン家庭教師
STRUX
※東大出身の塾長が生徒を合格に導いてくれる!勉強の仕方を生徒に合わせて指導してくれるオンライン家庭教師!
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
まとめ:小学校の通知表「よくできる」は平均何%?評価基準・割合と改善方法

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
「小学校の通知表「よくできる」は平均何%?評価基準・割合と改善方法」でした。
小学校通知表「よくできる」の割合は?平均や3段階評価の基準を解説
まとめ
この記事では、小学校の通知表における「よくできる」の割合や評価の仕組みについて解説しました。
- 「よくできる」の割合は全体の10%~20%が目安だが、絶対的な基準ではない。
- 現在の評価は、他人と比較しない「絶対評価」が基本。
- 評価の数は、子供の苦手や得意を把握するヒントになる。
- 「がんばろう」は「できない」ではなく「伸びしろ」のサイン。
- 本当に見るべきは評価の数より、先生の所見欄と子供の努力の過程。
通知表は、お子さんの成績を他人と比べるためのものではありません。
お子さん自身の成長を振り返り、頑張りを認め、次への意欲を引き出すための、親子にとって大切なコミュニケーションツールです。
この記事を参考に、ぜひ通知表を前向きに活用し、お子さんの健やかな成長をサポートしてあげてください。
小学生の成績を上げる記事
小学生の成績を上げる記事
【小学生の算数】割合を簡単に理解する!割合のちょっとしたヒント!
算数の文章問題を解くコツを完全マスター!答え方のポイントを例題で解説
宿題を早く終わらせる方法!小学生のための宿題時短テクニック10
漢字が苦手な子供の勉強の仕方!小学生の漢字嫌いを克服しよう!
小学生の漢字ドリルおすすめ10冊!漢字の苦手克服に最適な学習法!
小学生と中学生の勉強の違いを分かりやすくポイントにまとめて徹底解説!
小学生の勉強嫌いを克服!勉強しない子の原因と対策!今すぐ親ができること
子供が勉強しない理由は100%親にある?親御さんが知るべき原因と解決策
中学生になる前にやっておくこと|算数編|小学生が復習する単元!



