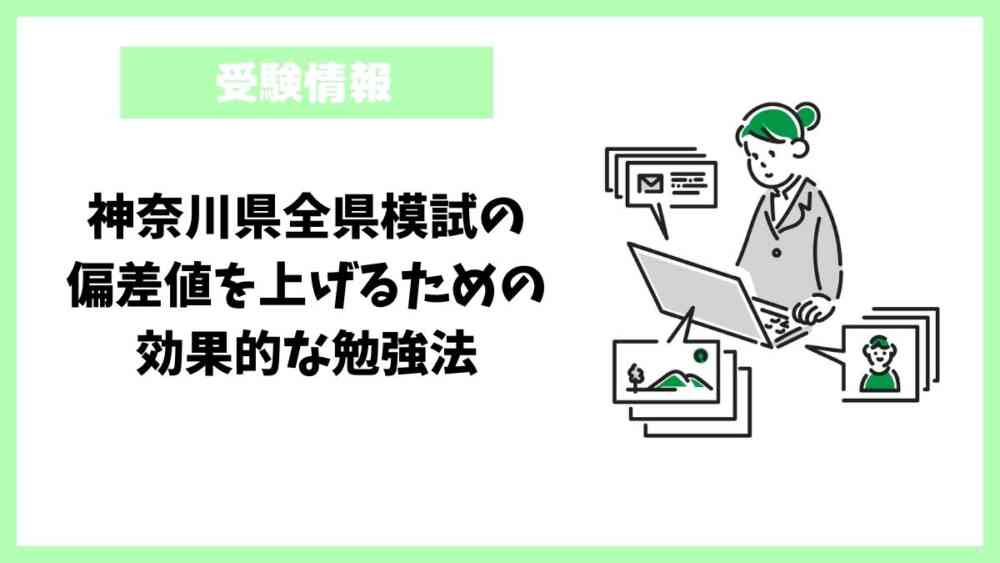
「※この記事には一部PRが含まれます」
塾オンラインドットコム「合格ブログ」です。
小学生と中学生の勉強に役立つ情報を発信している教育メディアです。
今回のお悩みはこちら。

神奈川県の全県模試の偏差値を上げる勉強法について教えて下さい。
今回は、神奈川県全県模試の活用法や偏差値を上げる勉強法を解説します。

神奈川県の公立高校の入試対策として模擬試験の活用法についてまとめてみました。
この記事で紹介する「神奈川県全県模試の偏差値を上げるための効果的な勉強法」を読めば、模擬試験や神奈川県全県模試について理解できる内容となっています。
なぜなら、神奈川県全県模試に詳しい進路アドバイザーが書いた記事だからです。
この記事では、模擬試験を受験する理由や神奈川県全県模試の偏差値を上げる勉強法について具体的に紹介しています。
記事を読み終えると、模擬試験についての理解が深まる内容となっています。
読み終えるとわかること
神奈川県の公立高校入試に模擬試験が必要な理由
模擬試験の活用ポイント
神奈川県全県模試の偏差値を上げる勉強法
神奈川県の高校入試の仕組み
神奈川県の高校入試に強い塾
個別指導なら森塾|定期テスト対策・内申点対策に強い塾
※成績保証制度は授業に自信があるからでいること!しかも低料金!
個別指導WAM|難関大学の講師が親切・丁寧に合格まで導く!
※成績保証制度・月謝無料などの各種キャンペーン実施中!
Contents
神奈川県:公立高校入試に模擬試験が必要な理由


神奈川県の公立高校の入試対策として模擬試験が必要な理由についてまとめてみました。
以下のポイントについて説明しています。
- 模擬試験とは
- 模擬試験の種類
- 模擬試験は進路に必要
- 試験に慣れる
模擬試験とは
高校受験対策のための模擬試験とは、高校入試の本番と同様に試験会場に足を運び、過去の高校入試の問題をもとに出題形式や難易度を予想して作成され、受験者の能力を客観的に測るための試験のことです。
一般的に模擬試験はテスト業者が実施しているので「業者テスト」とも呼ばれることがあります。
テスト業者がこれまでに蓄積した受験生の試験結果などのデータを分析・活用し、受験の専門家という観点から高校入試を模した試験を作成しているため、高校受験する受験生にとっては、避けては通れないのが模擬試験です。
現在行われている高校受験のための模擬試験は、都道府県単位で実施されるのが一般的。
これは各都道府県の高校受験に対応するためであり、高校受験のための模擬試験では、実際の高校受験の入試問題をもとにした出題傾向や問題数、出題パターンを的確に再現しており、中には問題用紙や解答用紙に至るまで、入学試験本番に近い形の模擬試験もあります。
受験を成功させるためにも模擬試験は大切な役割を果たします。
神奈川県の公立高校を目指す場合、「Wもぎ」・「神奈川県全県模試」の2つの模擬試験があります。
どの模擬試験を受験しても神奈川県の公立高校の入試対策になります。

参考記事:【神奈川県】の内申点の計算方法と高校入試の概要を10分で理解する。
神奈川県の模擬試験の種類
| wもぎ | 受験料は、4,600円 | 新教育のWもぎ「神奈川県入試そっくりもぎ」は、神奈川県全体の中での自分の学力の位置を正確に判定できる首都圏最大規模の会場テスト。 多くの公立高校・私立高校の合格可能性基準となっています 。 1.偏差値・合格基準が活用できる。 Wもぎは、首都圏最大規模の参加者を誇るため、膨大なデータに基づいて正確な合格可能性の判定が可能。 2.評価(内申点)を加味した総合判定も実現。 都立・公立は内申点を加味した精度の高い総合判定が出るため、合格ラインまで、あとどれだけ頑張れば良いかが具体的にわかります。 |
| 神奈川全県模試 | 受験料は、4,840円 | 神奈川全県模試(全県模試)は、神奈川県内28,500人の中学3年生が参加する県内最大級の合格判定模試です。神奈川県内多数の中3生が受験していますので、豊富なデータに基づいた信頼の合格判定が可能となっています。 さらには弱点単元が一目で分かる学力診断表も志望校合格に向けた対策や学習計画にも役立ちます。参加者に無料で“未来へのパスポート”や“学校説明会一覧(文化祭・体育祭)”の他、各種教材や受験情報誌の出版など、充実したサービスで受験生の皆様をしっかりとサポートしているのが特徴です。 |
最新の情報については各ホームページでご確認願います。
神奈川全県模試では、共通選抜(入試)において学力検査に加え記述式特色検査を実施する高校に対応した【特色検査対策模試】を神奈川全県模試と同時開催し、公立難関校で実施される教科横断型総合問題に挑戦する受験生を強力にサポートしています。
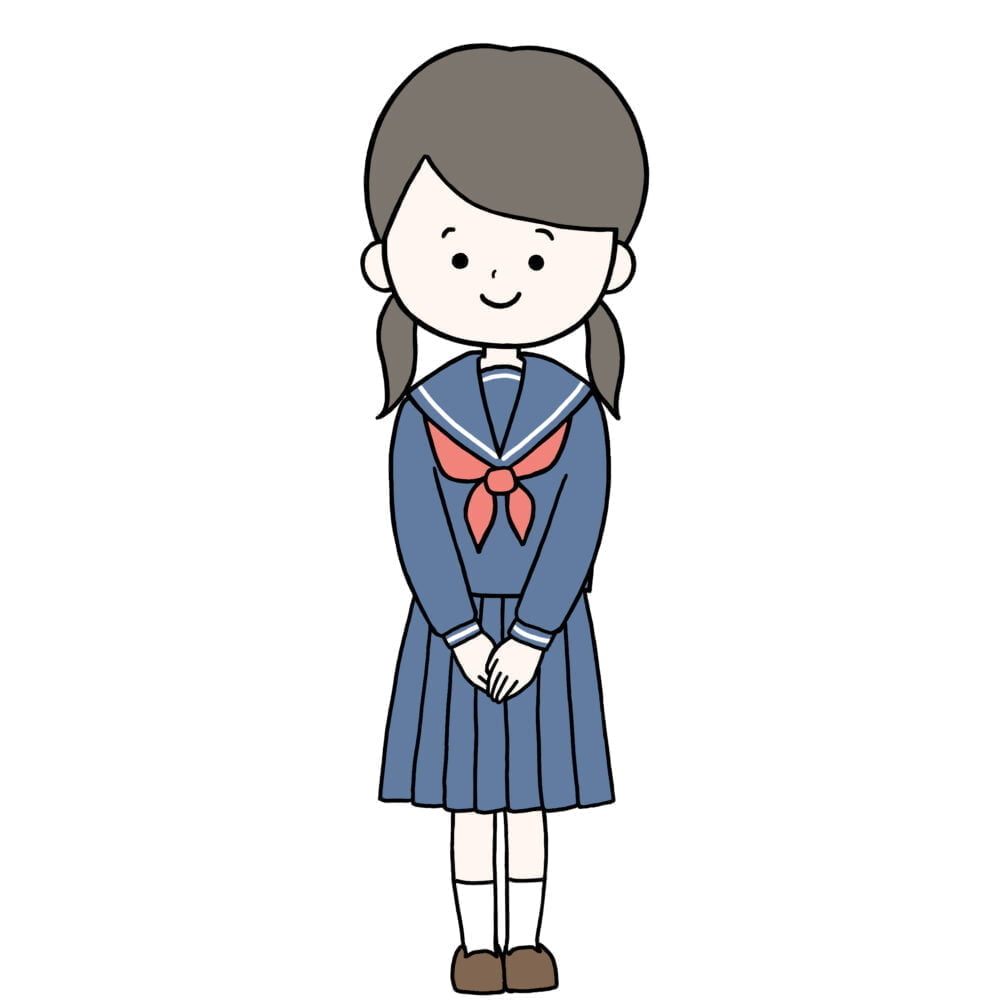
参考記事:高校の学校説明会に参加して志望校を決める7つのポイントを紹介!
模擬試験は進路に必要
神奈川全県模試などの模擬試験を受験すると偏差値や志望校が判定されるので、公立高校の入試対策としては模擬試験を受験することをおすすめします。
理由は、偏差値を知ることで自分の学力を知ることで、今後の学習計画に反映させるためと、志望校の判定されるので進路を決定するためにとても参考になるからです。
中学校によっては、進路指導する際には、模擬試験の結果を持参することを依頼されることもありますし、受験を促されることもあります。
したがって、受験までの学習計画や精度の高い進路指導をするためにも、模擬試験は必要となってくるのです。
しかも、1回だけの受験ではなく複数回の受験がおすすめです。
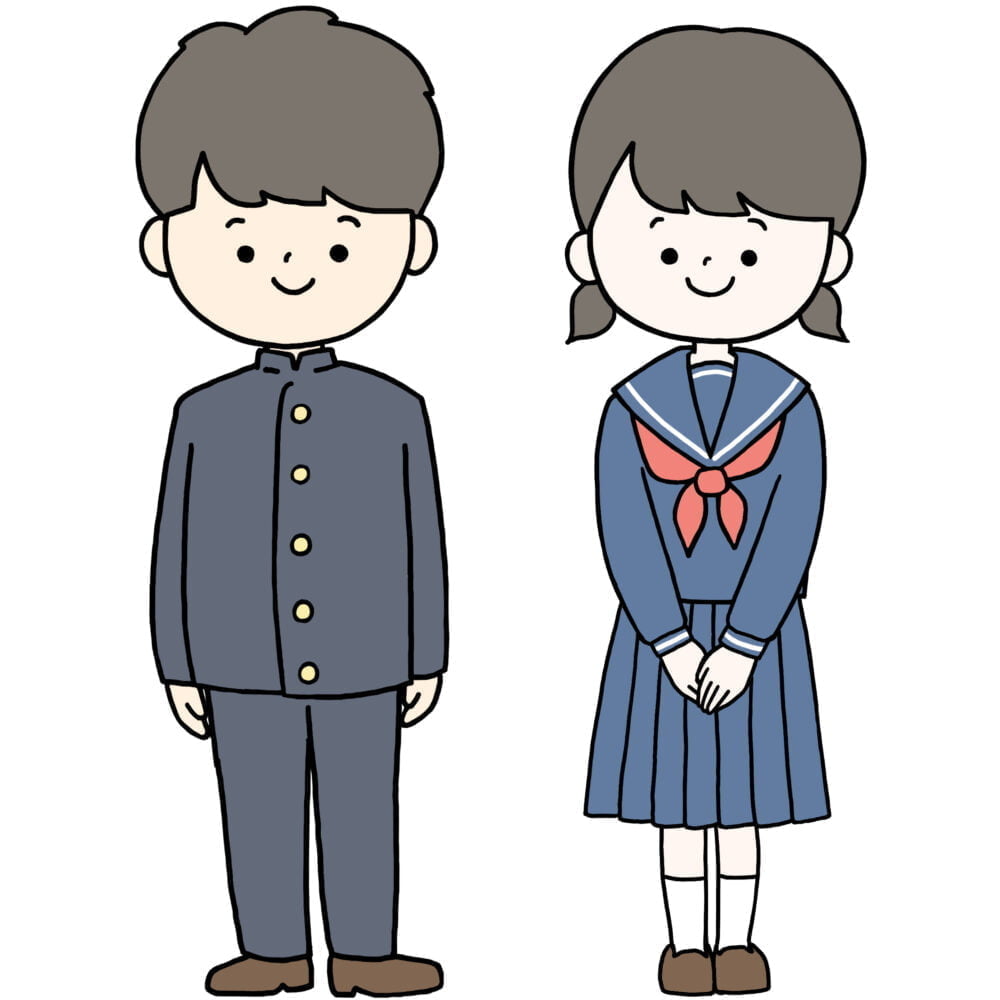
参考記事:定期テストの勉強法【中学生編】内申点がアップする【教科別勉強法】
試験に慣れる
模擬試験の実施会場は、大学・私立高校・専門学校などの会場に足を運んで受験生が集まり、本試験と同じスタイルで受験できます。
本番としての臨場感を味わえるのも模擬試験の良いところです。
模擬試験の会場では、周りに誰も知らない生徒ばかりだと周りの生徒が賢く見えて緊張したりしてストレスとなることも。
また、問題を解くにあたって時間配分などで失敗すると次の教科の試験にまで影響が及ぶ可能性もあります。
本番の試験で実力を発揮するためには、模擬試験などを数回受験して慣れることが大切なのです。
試験に慣れることで試験の本番で実力を発揮できるのです。
参考記事:森塾の授業料はいくら?学年別に徹底解説!リーズナブルな授業料?
神奈川全県模試の活用ポイント

(神奈川全県模試のホームページを参照)

神奈川全県模試を受験すると成績表が送られてきます。
成績表のポイントについてまとめてみました。
- 自分の偏差値を知る
- 志望校の合格判定ができる
- 成績の推移がわかる
- 苦手な科目がわかる
- 内申点も計算して志望校判定
- 私立高校の判定もできる
自分の偏差値を知る
偏差値とは、「神奈川全県模試を受けた人の中で、自分がどのくらいの学力があるのか」を表す数値。
神奈川全県模試の得点で平均点を取るとちょうど偏差値が50になります。
平均点より得点が高くなるにつれて、偏差値も51・52・53・・・・と上がっていきます。
逆に平均点よりも低くなるにつれて、偏差値も49・48・47・・・と下がっていきます。
神奈川全県模試の偏差値はみなさんの得点に応じて「25~75」の範囲で表されるので最高得点をとった人が75、最低得点の人が25となります。
神奈川全県模試では、各教科の偏差値と3教科の偏差値、そして5教科の偏差値が表示されますので、しっかりと自分の偏差値を確認してください。

参考記事:【中学生】無料で受けられる模試と模試の復習の仕方を解説
志望校の合格判定ができる
模擬試験を受験する目的のひとつに、志望校の合格判定があります。
神奈川県全県模試の成績表にも志望校の合格判定の結果が表示されますのでしっかりと確認してください。
結果については、一喜一憂しないことがポイント。
なぜなら、模擬試験は自分が目標を達成するために克服・強化すべきことが何かを知る場であるため、点数に踊らされて終わりではこれもまた、模試を受験した価値が大きく減ってしまうからです。
神奈川全県模試では現段階でのあなたの内申・入試予想得点をもとに各高校の選抜方法(選考基準)に基づいて判定し、どの位置で合格すると予想されるかを、表示しています。

成績の推移がわかる
神奈川県全県模試の成績表には、過去の成績の推移がグラフで表示されています。
自分の学力の推移がひと目で分かるようになっていますので、神奈川県全県模試は複数回受験することがおすすめ。
グラフが右肩上がりなのか?横ばいなのか?右肩下がりなのか?を把握することで勉強のアドバイスにもつながります。
右肩上がりのグラフになるように対策して、神奈川県全県模試を複数回、受験してください。
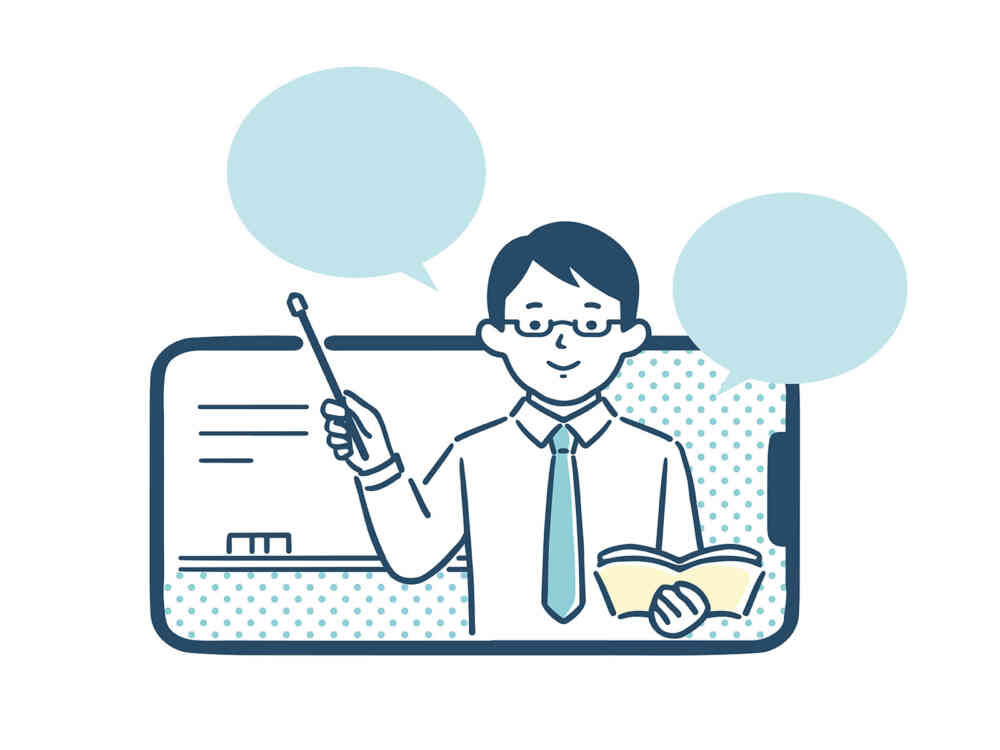
参考記事:高校の学校説明会に参加して志望校を決める7つのポイントを紹介!
苦手な科目がわかる
5教科の偏差値がレーダーチャートで表示されますので、苦手教科や得意教科がひと目でわかります。
過去の偏差値とも比較されて表示されますので苦手教科を見つけて克服する参考になります。
内申点も計算して志望校判定
神奈川県全県模試受験当日は、用紙に内申点を記入すると、より正確な志望校判定が出せるので、内申点を把握しておくことが大切です。
内申とは学校の通知表の5段階の成績(1~5)のことです。神奈川県全県模試当日は通知表の成績をメモしたものを持参してください。
また、神奈川県全県模試では、みなさんの偏差値を公立入試当日の学力検査の得点に換算し、偏差値を基に実際の入試当日の学力検査で何点くらいとれるのかを予測します。
精度の高い志望校判定ができるのも特徴です。

参考記事:【高校受験】数学の勉強法を徹底解説│誰でもできる!高校入試対策
私立高校の判定もできる
神奈川県全県模試の偏差値から私立高校の志望校の判定も行えます。
模擬試験の偏差値から、各高校の選抜方法に基づいて判定し、合格可能性(%)をグラフで表示。
私立高校の学校情報も表示されますので、私立高校の進路をきめる判断材料としても神奈川県全県模試は活用できます。
高校入試に強いオンライン塾
森塾のオンライン部門!オンライン個別指導生徒数No.1のそら塾
※保護者が選ぶオンライン学習塾NO.1を獲得!しかも低料金!
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師は全員東大生・東大院生!最高レベルの授業がこの価格で実現!
圧倒的な合格実績!オンラインプロ教師のメガスタ!
※全国に40,000人の講師が在籍!きっとあなたにピッタリの講師が見つかる!
参考記事:オンライン個別指導「そら塾」のメリット・デメリット!成績は伸びるの?
神奈川県全県模試の偏差値を上げる勉強法
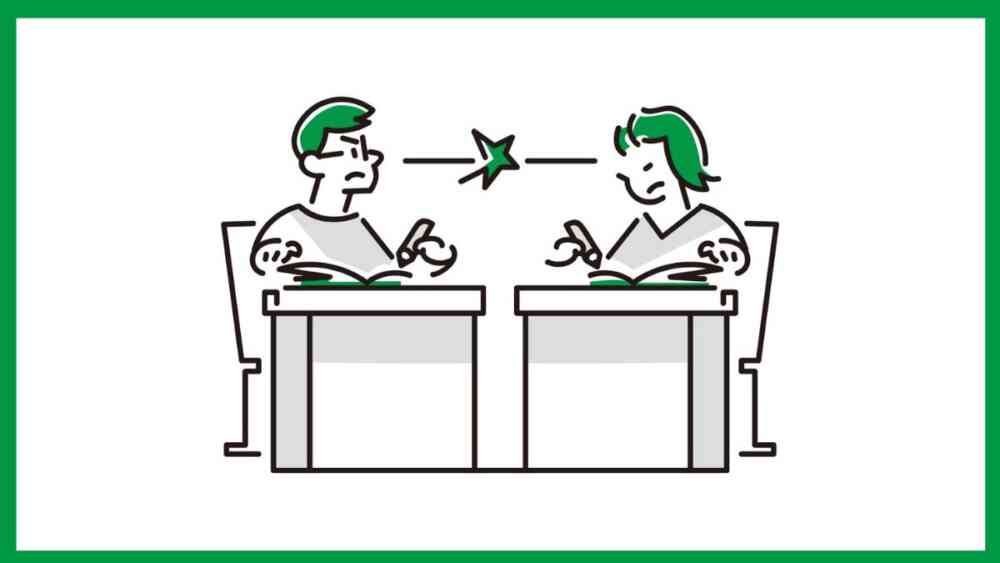

神奈川県全県模試の偏差値を上げる勉強法を紹介。
参考にしてください。
- 神奈川県全県模試の出題範囲を確認
- 基本を徹底的に理解する
- 苦手分野を重点的に勉強
- 神奈川県全県模試対策:塾に通う
神奈川県全県模試の出題範囲を確認
神奈川県全県模試の偏差値を上げるために出題範囲を確認することは、非常に重要。
出題範囲を把握することで、以下のようなメリットがあります。
- 苦手分野を的確に把握できる
- 効率的な学習計画が立てられる
- 模試の結果を正しく分析できる
神奈川県全県模試の出題範囲は、公式ホームページで確認できます。
出題範囲を確認したら、以下の手順で学習を進めていきましょう。
・出題範囲を分類する
出題範囲を教科や単元ごとに分類しましょう。これにより、苦手分野や弱点が見えやすくなります。
・苦手分野や弱点を重点的に学習する
苦手分野や弱点を重点的に学習しましょう。教科書や問題集を丁寧に読み込み、理解できない箇所は先生や先輩に質問するなどして、わからないことをそのままにしないことが重要です。
・模試や過去問を解いて、学習の成果を確認する
模試や過去問を解いて、学習の成果を確認しましょう。間違えた問題は、解き直して理解を深めましょう。
神奈川県全県模試の偏差値を上げるために、出題範囲の確認は欠かせません。
ぜひ、上記の手順を参考にして、効果的に学習を進めていきましょう。

基本を徹底的に理解する
神奈川県全県模試の偏差値を上げるためには、まず基本的な知識や考え方をしっかりと理解することが大切。
そのためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
・教科書や問題集を丁寧に読み込む
教科書や問題集を丁寧に読み込み、基本的な知識や考え方をしっかりと理解しましょう。わからない箇所は、先生や先輩に質問するなどして、わからないことをそのままにしないことが重要です。
・基本問題を繰り返し解く
基本問題を繰り返し解いて、基本的な知識や考え方の定着を図りましょう。間違えた問題は、解き直して理解を深めましょう。
・応用問題にも取り組む
基本的な知識や考え方が理解できたら、応用問題にも取り組みましょう。応用問題を解くことで、実戦力を養えます。
具体的な勉強法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 教科書や問題集の例題や練習問題を解く
- 基本問題集やミニテストを活用する
- 模試や過去問を解く
これらの勉強法をしっかりと実践することで、神奈川県全県模試の偏差値が上がるはずです。

苦手分野を重点的に勉強
苦手分野を重点的に勉強することは、神奈川県全県模試の偏差値を上げる上で非常に効果的。
苦手分野をそのままにしておくと、偏差値アップを阻害する原因となります。
苦手分野を重点的に勉強するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
・苦手分野を明確にする
まずは、自分の苦手分野を明確にしましょう。模試や過去問を解いて、間違えた問題や解くのに時間がかかった問題を参考にするとよいでしょう。
・苦手分野の原因を分析する
苦手分野の原因を分析しましょう。知識不足なのか、理解不足なのか、解法が身についていないのか、など原因を明確にすることで、適切な対策が立てられる。
・苦手分野を徹底的に理解する
苦手分野を徹底的に理解しましょう。教科書や問題集を丁寧に読み込み、理解できない箇所は先生や先輩に質問するなどして、わからないことをそのままにしないことが重要。
・苦手分野の復習を忘れない
一度理解したからといって、そのままにしておくとすぐに忘れてしまいます。苦手分野は、定期的に復習して定着を図りましょう。
具体的な勉強法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 教科書や問題集の苦手分野の部分を重点的に学習する
- 苦手分野に特化した参考書や問題集を活用する
- 苦手分野の模擬問題や過去問を解いて、実践力を養う
これらの勉強法をしっかりと実践することで、苦手分野を克服し、偏差値アップが目指せます。

神奈川県全県模試対策:塾に通う
塾に通うことは、神奈川県全県模試の偏差値を上げる上で非常に効果的。
塾では、プロの講師による指導を受けることで、効率的に学習できます。
塾に通うメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
・プロの講師による指導を受けられる
塾では、プロの講師による指導が受けられるでしょう。講師は、豊富な知識と経験を活かして、一人ひとりの学力やレベルに合わせて指導を行います。
・効率的な学習法が身につく
塾では、効率的な学習法が身につきます。講師は、学習の進め方や勉強のツボなど、効率的な学習法を指導してくれます。
・モチベーションを維持できる
塾に通うことで、モチベーションを維持できます。同じ目標に向かって努力する仲間や、切磋琢磨できる環境が、モチベーションを維持するのに役立ちます。
塾に通うことで、神奈川県全県模試の偏差値アップに大きく貢献します。
ぜひ、自分に合った塾を見つけて、通ってみることを検討してみてはいかがでしょうか。
おすすめオンライン塾
森塾のオンライン部門!オンライン個別指導生徒数No.1のそら塾
※保護者が選ぶオンライン学習塾NO.1を獲得!しかも低料金!
圧倒的な合格実績!オンラインプロ教師のメガスタ!
※全国に40,000人の講師が在籍!きっとあなたにピッタリの講師が見つかる!
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師は全員東大生・東大院生!最高レベルの授業がこの価格で実現!
参考記事:【そら塾】中学生の料金は高い?他のオンライン塾と料金比較してみた!
参考記事:トウコベの料金(入会金・月謝)は高い?他のオンライン塾と徹底比較!
神奈川県公立高校入試の仕組みについて知る


最後に神奈川県の公立入試の仕組みについてまとめてみました。
- 公立入試の試験教科
- 公立入試合否の決め方
- 内申点の計算方法
公立入試の試験教科
実施教科:国語・数学・英語・社会・理科。
全校、同じ内容の共通問題を使用している。思考力・判断力・表現力を見る難しい内容で、記述問題も多いのが特徴。
また、選択問題でマークシート方式が導入されていますが、記述問題も出題されています。
・原則5教科だが、特色検査する学校では3~4教科の場合もあります。
・各100点満点だが、2教科まで各2倍以内の範囲で傾斜配点をつける学校もあります。
受験生1人につき、10分程度の個人面接。
面接は2名以上の教員が担当して実施されます。
出願時に、面接シートを提出し、その面接シートと内申書の内容を参考にして行われています。
面接の評価ポイントは、主に以下の2つの観点に分けられる。
①共通の観点
「入学希望の理由」、「中学校での学習意欲」や「学習以外の活動に対する意欲」など、面接シートの内容を参考に、すべての学校で質問される項目です。
②学校ごとの観点
高校に入学してからの学習意欲や将来の展望、自分の長所・特性についてなど、質問内容は学校・学科によって異なります。
神奈川公立高校入試特色検査について
共通の検査(学力検査と面接)以外に、各高校の特色に応じた検査を実施できます。これを「特色検査」といいます。
・特色検査には、「実技検査」と「自己表現検査」の2種類があります。
・特色検査を実施する高校は、学力検査の教科数を3教科まで減らせます。

参考記事:神奈川県の内申点の計算方法│完全ガイド!内申点を上げる7つのコツ
公立入試合否の決め方
神奈川県公立高校の入試の仕組みについて説明します。
特徴的なのは、2段階で選考が行われることです。
第1次選考と第2次選考で選考方法が違うので簡単に説明します。
第1次選考では「内申点」「学力検査の得点」「面接の得点」「特色検査の得点(実施校のみ)」の4つの指標を基に算出した数値で募集人員の90%の合格が決定。
合否判定に用いられる資料は内申書、学力検査、面接、特色検査(実施した高校のみ)で総合的に合否判定されます。
内申書・学力検査・面接の比率は、それぞれ2以上で合計10になるよう学校ごとに配分。
第2次選考では「学力検査の得点」「面接の得点」(「特色検査の得点」)の3つの指標を基に算出した数値で残りの10%の合格が決定。
第2次選考では内申点を判定に使用しません。※1次選考・2次選考とともに調査書や学力検査において重点化する学校もあります。
ただし、両選考とも各資料の配分比率は各学校で決められています。

参考記事:国語が苦手な中学生の成績を上げる方法!分野別の勉強法を徹底解説
内申点の計算方法
内申点とは通知表に記載された5段階評価の成績のことです。
中間テストや期末テストの点数の他、授業態度や提出物などをもとに評価。
高校入試の出願の際に必要となる調査書にも記載され、入試の合否にも影響を与えます。
神奈川県の公立の入試における内申点は、中学2年生の9教科の合計+(中学3年生の9教科の合計×2)=135点となります。
中学2年生の成績から内申点に加わるのが特徴。
例)
中学2年生の成績がオール3の場合、3×9教科=27点・・・①
中学3年生の成績がオール3の場合、3×9教科×2倍=54点・・・②
内申点の合計点は、①+②=81点となります。
神奈川県の高校入試に強い塾
※成績保証制度は授業に自信があるからでいること!しかも低料金!
※成績保証制度・月謝無料などの各種キャンペーン実施中!
模試の豆知識:模試によって偏差値が違う理由
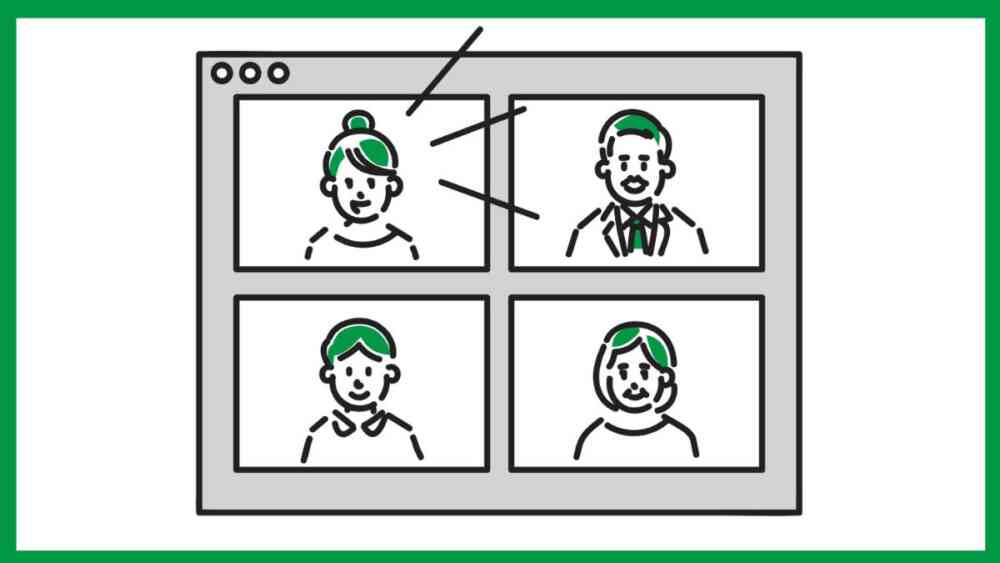
一般的な模試やオープン模試の偏差値が異なる理由は、母集団(受験者の集まり)やテストの性質によるものです。
例えば、神奈川県全体で行われる一般的な模試には、広範な学力層の受験者が参加します。
つまり、塾に通っていない生徒も含まれます。
一方、オープン模試は特定の塾の生徒が受験することが多いため、母集団は一般的な模試よりも特定の学力層が揃っています。
そのため、同じ難易度のテストを受けても、母集団が異なるため、平均点が異なります。偏差値は平均点からの個々の得点の差を示す指標であり、平均点が高い母集団では高い偏差値が出やすく、逆に平均点が低い母集団では低い偏差値が出やすい。
したがって、異なる母集団の模試の偏差値を比較するのは難しい。
つまり、模試の偏差値はテストの難易度だけでなく、受験者の母集団にも影響を受けるため、異なる模試の偏差値を直接比較するのは適切ではありません。
まとめ:神奈川県全県模試の偏差値を上げるための効果的な勉強法

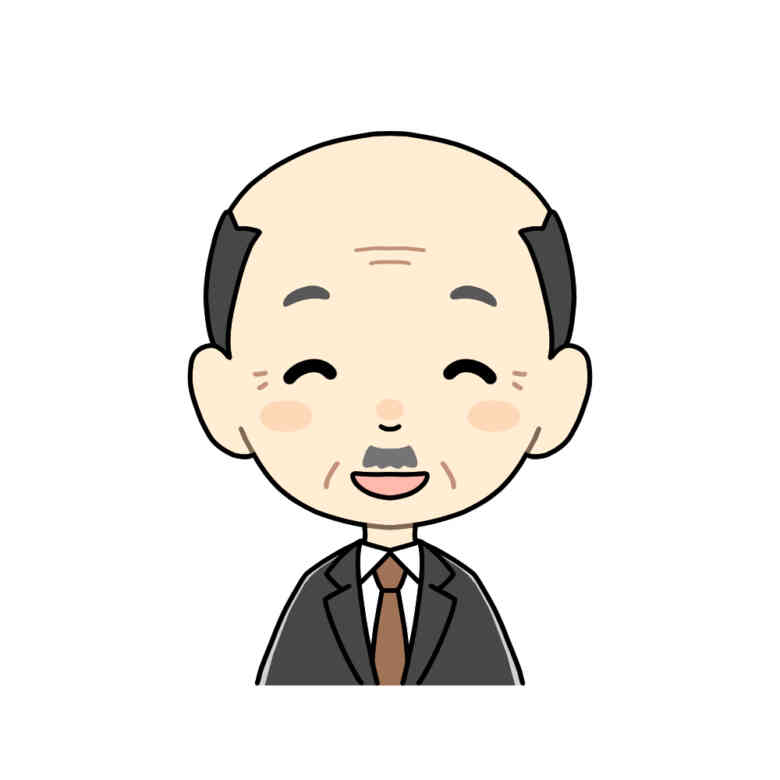
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「神奈川県全県模試の偏差値を上げるための効果的な勉強法」参考になりましたか?
神奈川県全県模試の勉強法を理解しました。

以上、「神奈川県全県模試の偏差値を上げるための効果的な勉強法」でした。
まとめ:神奈川県全県模試の偏差値を上げるための効果的な勉強法
まとめ
神奈川県全県模試の偏差値を上げるためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
・基本を徹底的に理解する
まずは、基本的な知識や考え方をしっかりと理解しましょう。教科書や問題集を丁寧に読み込み、理解できない箇所は先生や先輩に質問するなどして、わからないことをそのままにしないことが重要です。
・苦手分野を重点的に勉強する
苦手分野をそのままにしておくと、偏差値アップを阻害する原因となります。模試や過去問を解いて、間違えた問題や解くのに時間がかかった問題を参考にして、自分の苦手分野を明確にしましょう。苦手分野の原因を分析して、適切な対策を立てて、徹底的に理解しましょう。
・計画的に勉強する
毎日の勉強時間や学習内容を決め、それを確実にこなしていくようにしましょう。定期的に模試やテストを受けて、自分の学力を客観的に評価することも大切です。
また、塾に通うことも効果的です。塾では、プロの講師による指導を受けることで、効率的に学習できます。
これらのポイントを押さえて、効果的な勉強法を実践することで、神奈川県全県模試の偏差値アップを目指しましょう。
具体的な勉強法としては、以下のようなものが挙げられます。
・教科書や問題集を丁寧に読み込む
・苦手分野に特化した参考書や問題集を活用する
・模試や過去問を解いて、実戦力を養う
塾に通って、プロの講師による指導を受ける
これらの勉強法をしっかりと実践することで、神奈川県全県模試の偏差値アップが目指せます。

