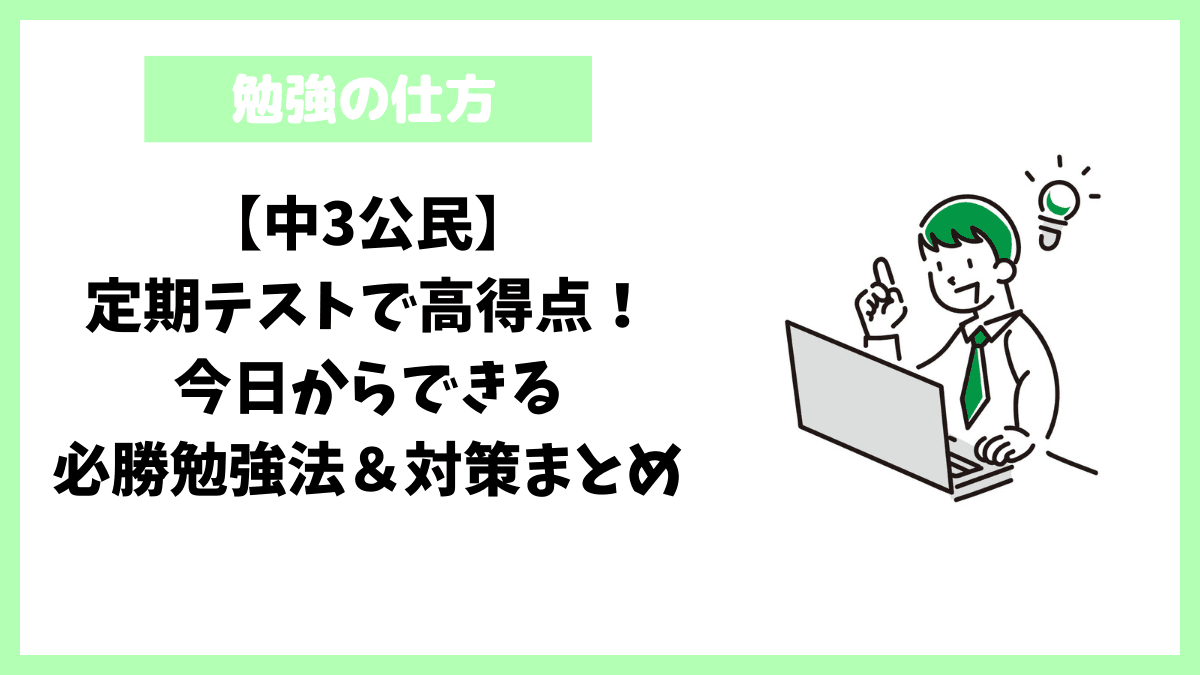
「※この記事には一部PRが含まれます」
「国語の文章問題になると、いつも時間が足りない…」
「設問で何を聞かれているのか、よく分からない…」
「読解力を上げたいけれど、何から手をつけたらいいのか…」
こんなふうに悩んでいませんか?
部活や他教科の勉強で忙しい中学生にとって、国語の長文読解は大きな壁になりがちです。
特に高校受験が近づいてくると、「国語が足を引っ張るかもしれない…」と不安になる人も多いでしょう。
でも、安心してください。読解力は「才能」ではなく、「正しい方法」でトレーニングすれば、誰でも必ず伸ばせます。
この記事では、国語が苦手な中学生でも明日から実践できる「読解力を上げる具体的な勉強法」や「テストで点数を取るコツ」を、専門家の視点から分かりやすく紹介します。
【塾オンラインドットコム編集部より】
27年以上学習塾に携わってきた経験から、多くの生徒が「国語が苦手」だと感じる一番の原因は、正しい勉強法を知らないことだと考えています。この記事で紹介する方法は、塾オンラインドットコム編集部の経験において、実際に多くの生徒の読解力向上に寄与してきました。
ぜひ、一つでも試してみてください。
この記事を読み終える頃には、国語の文章問題が「苦手」から「得意」へ変わるきっかけがつかめるはずです。
記事のポイント
中学生が読解力でつまずく原因は3つある
中学生のテストの点数を上げる5つのコツ
中学生が読解力を鍛える4つの具体的な勉強法
学習を継続するための習慣とヒント
参考記事:ヨミサマ【国語塾】の口コミ・評判は?良い・悪い声を本音で専門家が徹底分析
Contents
国語の読解力を上げる方法!中学生がつまずく3つの原因
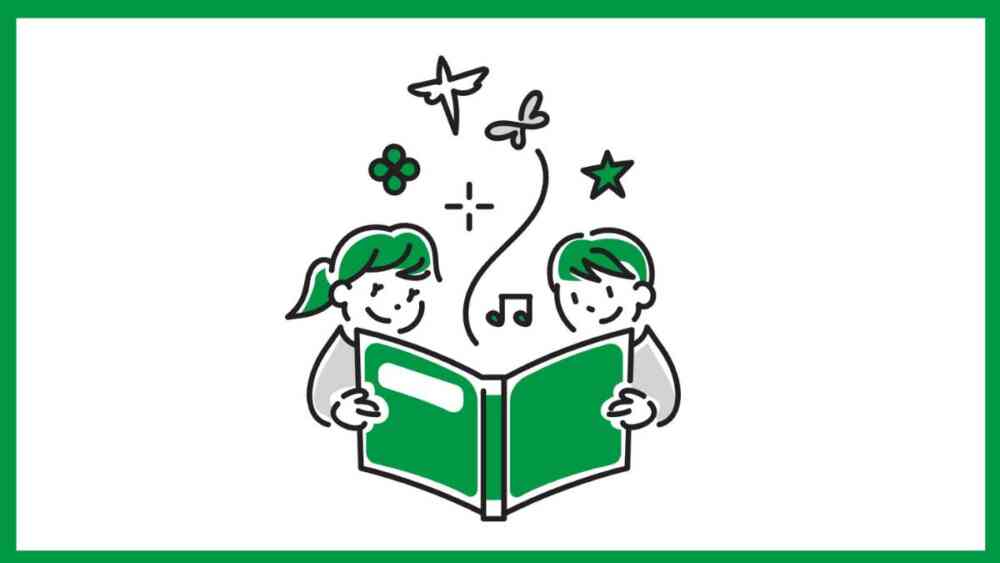
なぜ国語の文章問題が解けないのでしょうか?
まずは、多くの中学生が陥りがちな3つの原因から見ていきましょう。
自分に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
- 語彙力と背景知識の不足
- 文章の構造を正確に把握できていない
- 設問の意図を正しく読み取れていない
語彙力と背景知識の不足
文章を正しく読むための土台は、言葉を知っていることです。
知らない単語や慣用句が多いと、文章の意味を正確に理解することはできません。
例えば、「示唆(しさ)」「普遍的(ふへんてき)」「形而上(けいじじょう)」といった言葉が出てきたときに、意味が分からないまま読み進めてしまうと、筆者の主張を大きく取り違えてしまう可能性があります。
環境問題や情報社会といったテーマに関する基本的な知識(背景知識)がないと、文章の内容が頭に入ってきにくいことも、読解を難しくする一因です。

文章の構造を正確に把握できていない
なんとなく目で文字を追っているだけでは、文章を「読んだ」ことにはなりません。
国語が得意な人は、文章の設計図である「構造」を意識しながら読んでいます。
- 「しかし」の後には、前の内容と反対のことが書かれている
- 「つまり」の後には、前の内容をまとめた重要な結論がくる
- 「これ」「その」といった指示語が、具体的に何を指しているのか
こうした文章のルールを無視して読み進めると、話の流れを見失い、「結局、何が言いたかったの?」という状態に陥ってしまいます。
【オンライン学習塾運営者の声】 オンラインで生徒とやり取りをしていると、「つまり」「したがって」といった接続詞や指示語が出てきた際に、読み飛ばしてしまう生徒が非常に多いことに気づきます。個別指導でその都度「この『つまり』の後は何が来ると思う?」と問いかけるだけで、生徒は論理的な文章の読み方を徐々に身につけていきました。
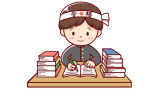
設問の意図を正しく読み取れていない
テストの問題は、出題者があなたに「本文のこの部分を理解できていますか?」と問いかけているメッセージです。
このメッセージ、つまり設問の意図を正しく読み取れていないと、見当違いな答えを書いてしまいます。
例えば、「筆者の考えを答えなさい」と聞かれているのに、自分の感想を書いてしまったり、「本文中から抜き出しなさい」という指示を見落として、自分の言葉で要約してしまったりするのは、典型的な失敗例です。
「何が問われているのか」を正確に把握することが、正解への第一歩です。
参考記事:ヨミサマ【国語塾】の口コミ・評判は?良い・悪い声を本音で専門家が徹底分析
中学生向け!国語のテストで文章問題の読解力を上げる方法
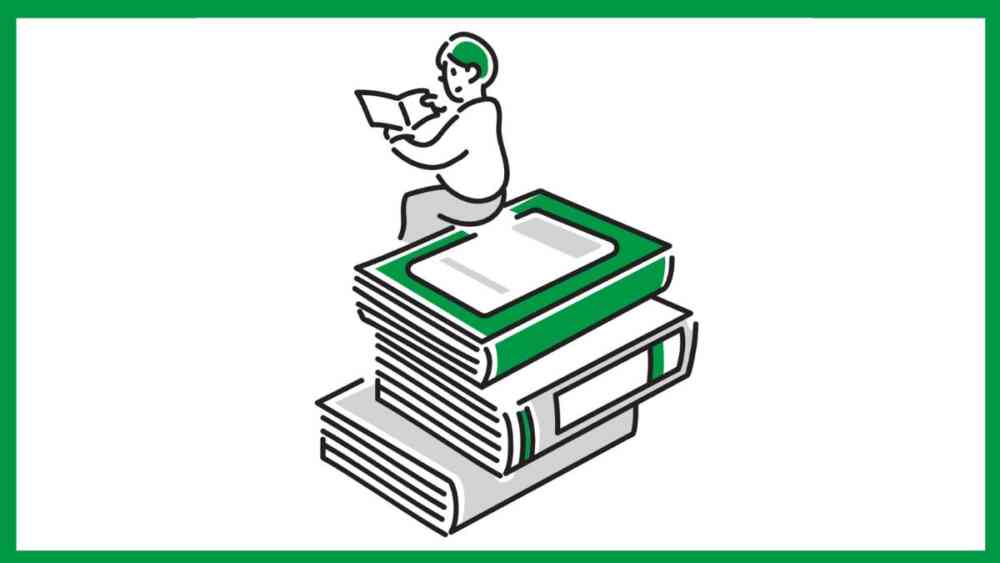
読解力は一朝一夕には身につきませんが、テスト本番で使えるちょっとしたコツを知っているだけで、点数は大きく変わります。
ここでは、明日からすぐに実践できる国語の文章問題で点数を上げるための5つのコツを紹介します。
- 設問を先に読み、本文のどこに注目すべきか把握する
- 指示語(こそあど言葉)が指す内容を明確にする
- 接続詞に印をつけ、文章の論理展開を追う
- 選択肢問題は消去法で不正解の理由を考える
- 記述問題は本文中のキーワードを使って答える
設問を先に読み、本文のどこに注目すべきか把握する
文章を読む前に、まず設問に目を通しましょう。
これは、時間内に問題を解ききるための最も効果的なテクニックの一つです。
【塾オンラインドットコム編集部】 800以上の学習塾を調査した結果、国語指導に定評のある塾の多くが、「設問の先読み」を指導の初期段階で徹底させていることが分かりました。この習慣を身につけることで、文章を読むスピードと正答率の向上に貢献することが期待されます。
設問を先に読むことで、文章のテーマや、どこを重点的に読めばよいのか、いわば「宝の地図」を手に入れた状態で本文を読み始められます。
特に、傍線部に関する問題やキーワードを問う問題は、先にチェックしておくと、本文中でその箇所が出てきたときに意識して読むことができます。

指示語(こそあど言葉)が指す内容を明確にする
「これ」「それ」「あれ」「どれ」といった指示語が出てきたら、必ずそれが何を指しているのかを明確にする癖をつけましょう。
問題文に直接、矢印を引っ張って書き込むのがおすすめです。指示語の内容を取り違えると、文全体の意味を誤解してしまいます。
特に記述問題では、指示語が指す内容を正しく理解できているかが、点数の分かれ目になることも少なくありません。

接続詞に印をつけ、文章の論理展開を追う
接続詞は、文と文の関係を示す「道路標識」のようなものです。
接続詞に丸や四角などの印をつけながら読むと、文章の論理的な流れが格段に分かりやすくなります。
- 順接(だから、したがって) :原因と結果の関係を示します。後に結論が来ることが多い重要な部分です。
- 逆接(しかし、だが、けれども): 前の内容と反対の意見や、筆者が本当に主張したいことが後に来ます。最重要の目印です。
- 並立・追加(また、そして、さらに): 同じ種類の情報が並べられます。
- 対比・選択(一方、あるいは) :二つの事柄を比べたり、どちらかを選ばせたりします。
- 具体例(たとえば) :抽象的な内容を分かりやすく説明する部分です。
特に「しかし」などの逆接の接続詞の後は、筆者の主張が述べられている可能性が非常に高いため、絶対に読み飛ばさないようにしましょう。

参考記事:中学生が定期テストを休むと見込み点はつくの?内申点に悪影響なの?
選択肢問題は消去法で不正解の理由を考える
選択肢問題で迷ったとき、正解を探すのではなく、「明らかに間違っている選択肢」から消していく「消去法」を使いましょう。
その際、なぜその選択肢が不正解なのか、「本文にはこう書かれているから違う」「言い過ぎている」「全く触れられていない」といったように、不正解の理由を明確に考えることが重要です。
根拠を持って選択肢を消していくことで、正解率がぐっと上がります。
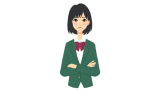
参考記事:国語の文章問題を解くコツを中学生にアドバイス!国語の苦手を克服
記述問題は本文中のキーワードを使って答える
記述問題は、自分の感想文を書くのではなく、本文に書かれていることを根拠に答えるのが鉄則です。
解答の骨格は、本文中にあるキーワードやキーフレーズです。
まずは設問で問われていることに対応する箇所を本文から探し、その部分の言葉を使いながら、設問の形式(「~から。」「~こと。」など)に合わせて文章を組み立てましょう。
オリジナリティは必要ありません。いかに本文の内容を忠実に再現できるかが問われています。
読解力を上げるための具体的な勉強法

テストのコツと合わせて、日々の学習で読解力の土台を鍛えることも大切です。
ここでは、中学生が国語の読解力を根本から鍛えるための勉強法を4つ紹介します。
【国語の指導における体験談】 以前、高校受験を控えた中学3年生の男子生徒を指導していました。生徒は、模試の国語でいつも偏差値が50以下でした。単語力や文法は悪くなかったのですが、文章全体の要点を掴むのが苦手でした。そこで、私は生徒に、問題集の文章を段落ごとに20字以内で要約するというトレーニングを毎日続けさせました。読解力は継続的な学習で向上し、多くの場合、3ヶ月程度の継続で文章を読むスピードや設問の意図把握において変化を感じ始めることができるとされています。
- 文章を段落ごとに要約するトレーニング
- 音読で文章のリズムと意味を体で覚える
- 新聞の社説やコラムを毎日読む習慣をつける
- 語彙力強化のためのノート作りと反復学習
文章を段落ごとに要約するトレーニング
文章の要点を掴む力を養うには、要約が最も効果的なトレーニングです。
問題集の文章などを読んだ後、段落ごとに「この段落では何が書かれているか」を30~50字程度でまとめる練習をしてみましょう。
初めは難しく感じるかもしれませんが、続けるうちに、文章の重要な部分とそうでない部分を素早く見分ける力がついてきます。
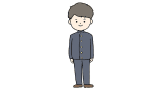
参考記事:【高校受験】漢字の勉強法と高校入試によく出る漢字100個で得点UP!
音読で文章のリズムと意味を体で覚える
文章を読むとき、黙読だとつい目だけで追ってしまい、内容をしっかり理解できないまま読み進めてしまうことがあります。
「音読」をすれば、一語一語をはっきり声に出すことで、自然と意味を考えながら読む習慣がつきます。
その結果、文章の内容が頭に入りやすくなり、理解力がぐんと高まります。
特に意識してほしいのは、接続詞(しかし・だから など)や文末の表現、句読点の位置です。
接続詞を意識して読むと、文章の構造や流れ、リズムを体で覚えることができます。
最初はつっかえてもかまいません。同じ文章をスラスラ読めるようになるまで繰り返し音読してみましょう。
1日たった5〜10分でも続けることで、読解力アップに大きな効果があります。
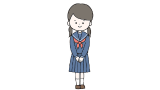
新聞の社説やコラムを毎日読む習慣をつける
新聞の社説やコラムは、論理的な文章構成を学ぶための最高の教材です。
1つのテーマについて、問題提起→具体例→結論という流れでコンパクトにまとめられており、良質な評論文のお手本と言えます。
毎日1本読む習慣をつければ、時事問題に関する背景知識も増え、語彙力も自然と強化されます。
中学生向けの新聞や、Webで読めるニュースサイトの解説記事から始めてみるのも良いでしょう。
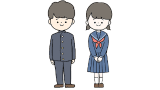
語彙力強化のためのノート作りと反復学習
読解力の土台となる語彙力は、地道な努力で確実に伸ばせます。
知らない言葉に出会ったら、そのままにせず、専用のノートに書き留める習慣をつけましょう。
ノートには、言葉とその意味だけでなく、その言葉が使われていた例文も一緒に書いておくのがポイントです。
意味と使われ方をセットで覚えることで、記憶に定着しやすくなります。
週末などにノートを見返し、覚えているかチェックする反復学習を取り入れましょう。
国語の苦手を克服するための学習習慣

最後に、国語の苦手意識をなくし、得意科目にするための学習習慣についてお伝えします。
- 読書が苦手なら短い解説文や評論文から始める
- 漢字・語句・文法の問題集を1冊完璧に仕上げる
- 解き終わった問題の解説を熟読し、解法を学ぶ
読書が苦手なら短い解説文や評論文から始める
「読解力を上げるには読書」とよく言われますが、本を読むのが苦手な人が無理に長編小説を読む必要はありません。
まずは、あなたが興味を持てる分野の解説記事や、問題集に載っている短い評論文などから始めてみましょう。
大切なのは、文章を読んで「何が書いてあるか」を考える習慣をつけることです。
短い文章でも、集中して論理展開を追う練習をすれば、読解力は十分に鍛えられます。
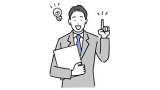
参考記事:高校受験:古文の勉強法!中学生にわかりやすく解説!高校入試を突破
漢字・語句・文法の問題集を1冊完璧に仕上げる
読解問題ばかりに目が行きがちですが、漢字・語句・文法といった知識問題は、国語の成績を安定させるための生命線です。
漢字の分野は、勉強すればするだけ確実に点数に結びつきます。
まずは学校で使っている問題集や市販の教材を1冊選び、「どのページから問題を出されても満点が取れる」という状態になるまで、繰り返し解きましょう。
基礎が固まることで、文章全体を読む余裕も生まれます。
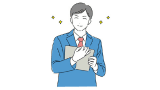
参考記事:漢字の勉強ができる中学生がやっている勉強法と漢字ドリル10選
解き終わった問題の解説を熟読し、解法を学ぶ
国語の勉強で最も重要なのは、問題を解いた後の「答え合わせ」と「復習」です。
丸付けをして点数に一喜一憂するだけでは、力はつきません。
なぜその答えになるのか、解説をじっくりと読み込み、正解に至るまでの「考え方」や「解き方のプロセス」を理解することが何よりも大切です。
特に間違えた問題は、「なぜ間違えたのか」「どう考えれば正解できたのか」を自分の言葉で説明できるようになるまで、徹底的に復習しましょう。
読解力トレーニングにおすすめの問題集・参考書

ここでは、読解力を鍛えるためにおすすめの市販問題集・参考書をレベル別に紹介します。
自分に合ったものから始めてみてください。
- 基本:学校のワーク
- 標準レベル:中学国語 出口のシステム読解
- 応用レベル:全国高校入試問題正解 国語
基本:学校のワーク
まずは学校で配られている国語のワーク(問題集)から取り組むのがおすすめです。
授業で習った内容とつながっているため理解しやすく、基礎的な読解力を身につけるのに最適です。
定期テストにも出やすい内容なので、繰り返し解いておくとテスト対策にもなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書籍名 | 中学教科書ワーク 国語 3年 光村図書版 |
| 出版社 | 文理 |
| 発売日 | 2025年3月12日 |
| 本の長さ | 192ページ |
| 特徴 | ・教科書と同じ単元構成・文章で学習できる ・要点確認→練習問題→テスト形式と段階的に実力アップ ・漢字・語句・文法など基礎知識を効率よく習得 ・聞き取り問題や定期テスト予想問題付き |
| こんな人におすすめの参考書 | ・授業内容に合わせて効率よく予習・復習したい中学3年生 ・定期テストで確実に点を取りたい中学生 ・基礎から応用まで段階的に国語力を伸ばしたい人 |
標準レベル:中学国語 出口のシステム読解
カリスマ現代文講師として有名な出口汪先生による、中学生向けの読解問題集です。
「論理的に文章を読むとはどういうことか」を体系的に、分かりやすく解説してくれます。
解説が非常に丁寧なので、自学自習でも無理なく進めることができます。
定期テスト対策から高校受験の基礎固めまで、幅広く対応できる一冊です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書籍名 | 中学国語 改訂版 出口のシステム読解 |
| 著者 | 出口 汪 |
| 出版社 | 水王舎 |
| 発売日 | 2025年8月5日 |
| 本の長さ | 100ページ |
| 特徴 | ・中学向け国語参考書としてロングセラー(学参売上1位)・国語読解に「公式」があるという視点で論理的読解法を解説 ・3部構成(①読解の基本ルール ②演習問題の解き方と答え ③総合問題の解き方と答え)・論説・ 小説・随筆それぞれのポイントを体系的に学べる |
| こんな人におすすめの参考書 | ・国語の読解問題で「なんとなく」解いてしまっている中学生 ・論理的な読み方・考え方を身につけたい人 ・国語のテストで安定して点を取れる力をつけたい人 ・高校入試に向けて国語の読解力を基礎から固めたい人 |
応用レベル:全国高校入試問題正解 国語
全国の公立・私立高校の実際の入試問題を集めた問題集です。
さまざまな形式やレベルの問題に触れることで、実践力を高め、自分の現在の実力を測ることができます。
志望校の過去問に取り組む前の腕試しや、よりハイレベルな問題に挑戦したい人におすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書籍名 | 2026年受験用 全国高校入試問題正解 国語 |
| 出版社 | 旺文社 |
| 発売日 | 2025年6月26日 |
| 本の長さ | 580ページ |
| 特徴 | ・47都道府県の公立高校+主な国立・私立・高等専門学校の入試問題を掲載 ・都道府県別・高校別に「出題傾向と対策」を解説・問題ごとに詳しい「解き方」を掲載 ・思考力を問う問題に「思考力マーク」を表記 |
| こんな人におすすめの参考書 | ・最新の高校入試国語の出題傾向を把握したい中学3年生 ・志望校対策として全国の過去問を幅広く演習したい受験生 ・思考力を問う記述問題や読解問題の対策を強化したい人 ・実戦形式で国語の得点力を伸ばしたい人 |
中学生の読解力を上げる方法に関するQ&A
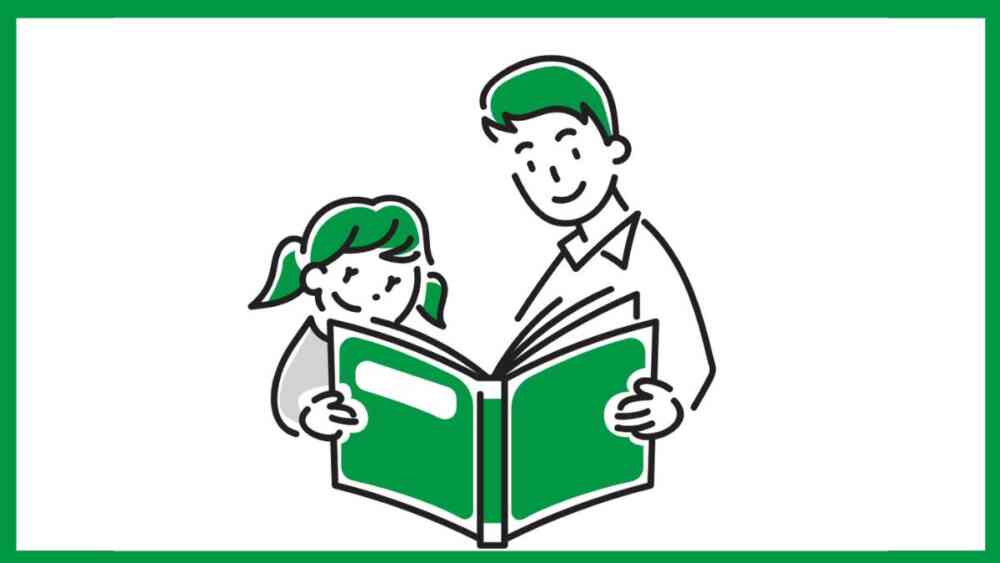
最後に、中学生や保護者の方からよく寄せられる読解力に関する質問にお答えします。
- Q.本を読むのが苦手でも読解力は上がりますか?
- Q. どれくらいの期間で勉強の効果は出ますか?
- Q. 塾に行かなくても高校受験は大丈夫ですか?
- Q. 読解力と語彙力、どちらを先に勉強すべきですか?
- Q. 読解力は他の教科にも役立ちますか?
- Q. 読解力向上のために、どんな種類の本を読めばいいですか?
本を読むのが苦手でも読解力は上がりますか?
A.はい、上がります。
もちろん読書習慣があるに越したことはありませんが、必須ではありません。
この記事で紹介したように、問題集の文章を丁寧に読み解いたり、新聞のコラムを要約したりするトレーニングでも、読解力は十分に鍛えられます。
大切なのは、文章の内容を正確に理解しようと意識することです。
無理に読書を始めるよりも、まずは自分が続けやすい方法で、毎日少しずつ文章に触れる機会を作ることから始めてみましょう。
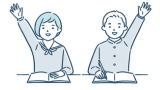
Q. どれくらいの期間で勉強の効果は出ますか?
【受験メンタルトレーナーからのアドバイス】 読解力は、筋トレと同じで、すぐに効果が表れるものではありません。しかし、正しい方法で毎日コツコツ続ければ、3ヶ月ほどで文章を読むスピードが上がったり、設問の意図が掴みやすくなったりといった変化を感じられるでしょう。大切なのは、焦らずに継続することです。目に見える点数アップには少し時間がかかるかもしれませんが、あなたの「読む力」は着実に向上しています。
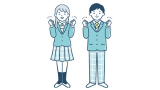
Q. 塾に行かなくても高校受験は大丈夫ですか?
A. はい、塾に行かなくても合格は可能です。
大切なのは、塾に行くかどうかではなく、「自分に合った正しい勉強法で、計画的に学習を進められるか」です。
この記事で紹介した勉強法や問題集を活用し、自分で学習計画を立てて実行できれば、読解力は十分に伸ばせます。
ただし、「一人だとサボってしまう」「分からない問題を質問できる相手がほしい」という場合は、塾や家庭教師を利用するのも有効な選択肢です。
自分に合った学習環境を見つけることが大切です。

Q. 読解力と語彙力、どちらを先に勉強すべきですか?
A. 両方を並行して進めるのが理想です。
しかし、語彙力強化を優先することを推奨します。語彙は読解の土台であり、知らない単語が多いと文章の内容を理解すること自体が難しくなります。
語彙力がある程度身につけば、文章を読むことへの抵抗も減り、読解トレーニングもより効果的になります。

Q. 読解力は他の教科にも役立ちますか?
A. もちろん役立ちます。
読解力は「すべての教科の土台となる力」です。
数学の問題文を正確に読み解く力、理科や社会の教科書の要点を把握する力は、すべて読解力に基づいています。
読解力が向上すれば、他の教科の成績も自然と上がるケースが非常に多いです。
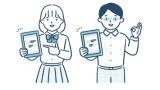
Q. 読解力向上のために、どんな種類の本を読めばいいですか?
A. 結論から言うと、自分が「面白い」と思える本で大丈夫です。
ただし、論理的な思考力を鍛えるなら、論説文や新書、新聞のコラムなどが効果的です。
物語文を読む場合は、登場人物の心情や行動の理由を深く考えることで、筆者の意図を読み取る練習になります。
参考記事:ヨミサマ【国語塾】の口コミ・評判は?良い・悪い声を本音で専門家が徹底分析
まとめ:中学生の国語読解力を上げる7つの方法!テストのコツも解説

今回は、中学生が国語の読解力を上げるための具体的な方法について解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
中学生の国語読解力を上げる7つの方法!テストのコツも解説
ポイント
- 読解でつまずく原因は「語彙力不足」「構造の未把握」「設問意図の誤解」
- テストでは「設問先読み」「指示語・接続詞のチェック」などのコツが有効
- 日々の勉強では「要約」「音読」「語彙ノート」などのトレーニングを実践する
- 勉強で最も大切なのは、解きっぱなしにせず「解説を熟読」して解法を学ぶこと
- 読書が苦手でも、短い文章の精読や問題集の活用で読解力は上がる
国語の読解力は、すべての教科の土台となる重要な力です。
そして、それは正しいトレーニングによって、誰でも、いつからでも伸ばすことができます。
まずはこの記事で紹介した方法の中から、「これならできそう!」と思えるものを一つ選んで、今日から早速始めてみませんか?その小さな一歩が、あなたの国語の成績を、そして未来を大きく変えるはずです。
応援しています!
国語の勉強法関連の記事
国語の勉強法
執筆者のプロフィール
【執筆者プロフィール】

塾オンラインドットコム【編集部情報】
塾オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営経験者、ファイナンシャルプランナー、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。小学生・中学生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
塾オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram

