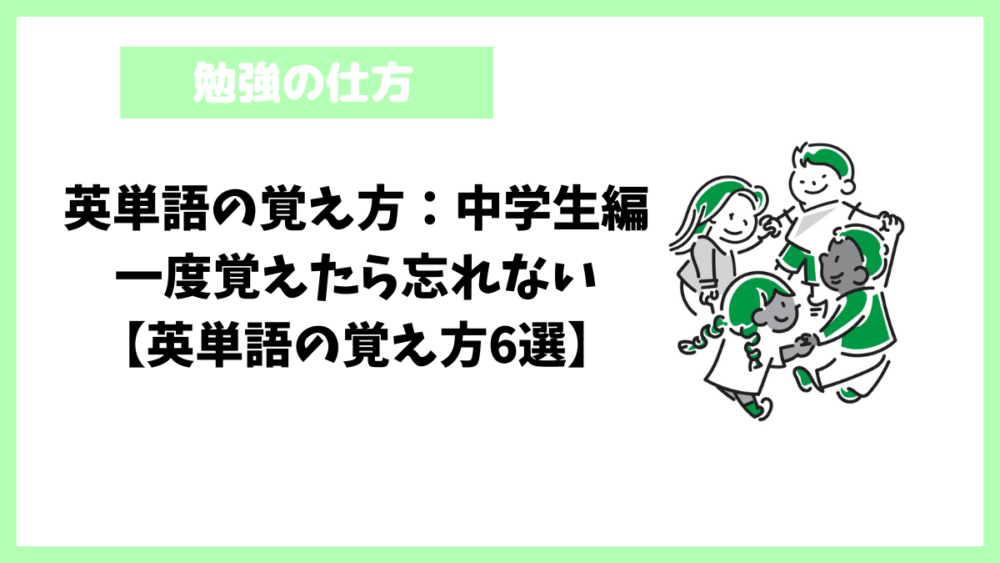
「※この記事には一部PRが含まれます」
こんにちは、塾オンラインドットコム「合格ブログ」です。
小学生と中学生向けに、勉強に役立つ情報を発信しています。
高校受験の小論文に初めて挑戦する中学生のみなさん、「何を書けばいいの?」「どうやって書き始めればいいの?」と不安に感じていませんか?
このガイドでは、小論文を書いたことがない初心者でも、基本から応用まで段階的に学べるよう解説します。
正しい書き方のコツを知れば、あなたも自信を持って小論文に取り組めるようになりますよ。
読み終えるとわかること
小論文と作文の違いがはっきり分かり、高校受験の小論文で評価されるポイントが理解できます。
初心者でもステップ通りに書ける!小論文の基本的な「書き方」と「構成」が身につきます。
他の受験生と差をつける!小論文で合格点を取るための実践的な「コツ」や「テクニック」が分かります。
これで迷わない!試験までの期間で何をすれば良いか、具体的な小論文の「対策方法」が見つかります。
Contents
高校受験の小論文、どう書けばいいの?不安なあなたへ

小論文に初めて挑戦する中学生にとって、「何を書けばいいの?」「どうやって自分の考えをまとめればいいの?」という不安はとても自然なことです。
特に、作文との違いがわからなかったり、評価のポイントが見えなかったりすると、さらに不安は大きくなりますよね。
でも大丈夫です。
小論文には基本的な「型」があり、それに沿って書けば、誰でも論理的な文章が書けるようになります。
このガイドで小論文がスラスラ書けるようになる理由
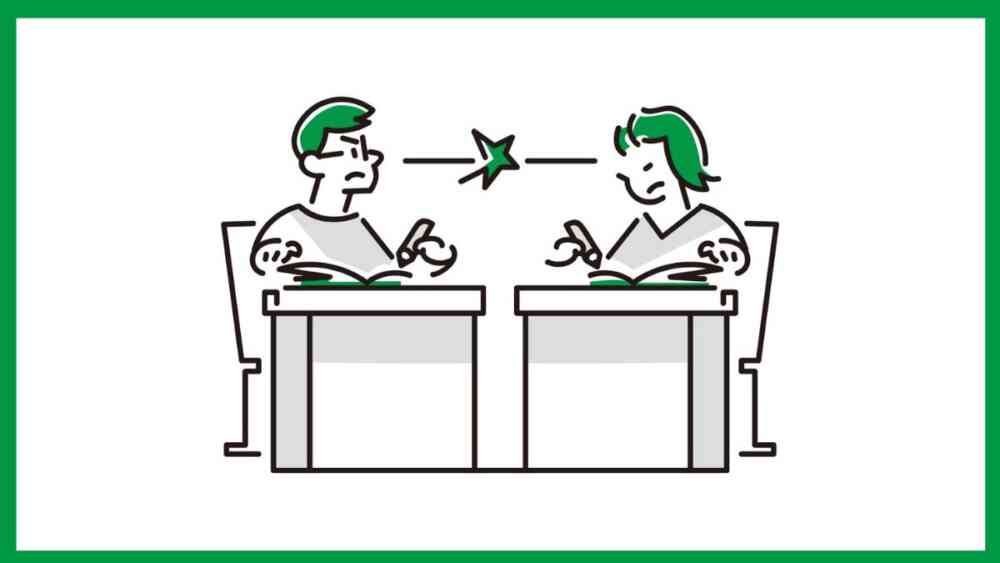
このガイドでは、小論文を「5つのステップ」に分けて、それぞれのポイントを詳しく解説します。
初心者の方でも理解しやすいよう、具体例を交えながら説明していくので、手順通りに進めれば自然と小論文が完成します。
高校受験で評価されるポイントもしっかり押さえているので、単に「書ける」だけでなく、「合格につながる小論文」を書けるようになります。
作文と小論文、どう違う?高校受験で必要なのはどっち?

- 作文は「感想」、小論文は「意見」を述べる
- 高校受験の小論文で評価されるポイント
作文は「感想」、小論文は「意見」を述べる
作文と小論文の最大の違いは、主観的な感想を述べるか、論理的な意見を述べるかという点にあります。
作文では「私はこう感じた」という個人的な感想や体験を自由に表現します。
小論文では「私はこう考える」という意見を、根拠や具体例を示しながら論理的に説明することが求められます。
たとえば、「環境問題」というテーマなら、作文では「海岸のゴミを見て悲しくなりました」と感想を書きますが、小論文では「環境問題解決には個人の意識改革が必要だ」と主張し、その理由を論理的に説明します。
| 項目 | 作文 | 小論文 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 感想や体験を自由に表現する | 意見を論理的に述べる |
| 表現の特徴 | 主観的・感情的 | 客観的・論理的 |
| 書き方の例 | 「私はこう感じた」「○○が悲しかった」など | 「私はこう考える」「○○が必要だ」など |
| 構成のしかた | 感じたことや思い出を中心に書く | 主張 → 理由 → 具体例 → 結論の順で書く |
| テーマ例:「環境問題」 | 「海岸のゴミを見て悲しくなりました」 | 「環境問題解決には個人の意識改革が必要だ」と主張し、その根拠を説明する |
高校受験の小論文で評価されるポイント
高校受験の小論文では、主に以下のポイントが評価されます。
- 課題の理解力: 与えられたテーマを正確に把握できているか
- 論理的思考力: 意見と根拠の関係が明確で筋道立てて説明できているか
具体的には、文章全体の構成が整っているか、自分の意見を明確に述べているか、適切な根拠や例を示しているかなどが重要です。
誤字脱字がないか、原稿用紙の使い方は正しいかなど、基本的なルールを守ることも評価の対象となります。
作文の書き方は:【小学生向け】作文の書き方&原稿用紙のルール10選+例文付きで解説
参考記事:ヨミサマ【国語塾】の口コミ・評判は?良い・悪い声を本音で専門家が徹底分析
【超基本】高校受験の小論文 書き方ガイド【5つのステップ】

小論文を書くための基本的な流れを5つのステップで解説します。
このステップに沿って準備し、練習することで、小論文への苦手意識を克服できるでしょう。
各ステップをしっかり理解して、実践してみてくださいね。
- ステップ1:テーマ(課題文)を正しく理解しよう
- ステップ2:自分の意見・主張を明確にしよう
- ステップ3:小論文の「型」で構成を決めよう(序論・本論・結論)
- ステップ4:構成に沿って文章を書いてみよう
- ステップ5:書いた小論文を必ず見直そう
ステップ1:テーマ(課題文)を正しく理解しよう
小論文の第一歩は、与えられたテーマを正確に理解することです。
テーマには「問われていること」が必ず含まれています。
たとえば、「SNSの利用について、あなたの考えを述べなさい」というテーマなら、SNSの良い点・悪い点を踏まえた上で、自分はどう考えるかが問われています。
テーマを読んだら、次のポイントを確認しましょう!
- 何について(主題)述べるよう求められているか
- どのような観点(視点)から考えるべきか
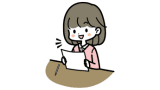
ステップ2:自分の意見・主張を明確にしよう
テーマを理解したら、そのテーマに対する自分の意見や主張を明確にします。
これが小論文の「軸」となるものです。意見は「〜だと思う」「〜すべきである」など、明確かつ具体的に表現しましょう。
たとえば、「SNSの適切な利用には、使用時間の自己管理と情報リテラシーの向上が必要だ」というように、具体的な意見を持つことが大切です。自分の意見と、それを支える2〜3の理由を考えておきましょう。
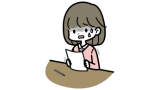
ステップ3:小論文の「型」で構成を決めよう(序論・本論・結論)
小論文は基本的に「序論」「本論」「結論」の三部構成で書きます。
この構成を意識することで、論理的な文章になりやすくなります。
それぞれのパートで何を書くべきか、しっかり押さえておきましょう。
序論で問題提起と結論を示す
序論では、テーマに関する問題提起と、自分の考え(結論)を簡潔に示します。
分量は全体の約20%程度です。
例文:「近年、SNSの普及により便利になった一方で、様々な問題も生じています。私は、SNSの適切な利用には、使用時間の自己管理と情報リテラシーの向上が必要だと考えます。」
本論で理由・根拠・具体例を展開する
本論では、序論で示した自分の意見の理由や根拠、具体例を展開します。
「なぜそう考えるのか」を論理的に説明する部分で、分量は全体の約60%を占めます。
展開例
- 第一の理由:SNS依存の問題と使用時間管理の重要性
- 具体例:時間制限アプリの活用事例
- 第二の理由:情報リテラシーの必要性
- 具体例:フェイクニュースの拡散問題
結論で全体のまとめと今後の展望を述べる
結論では、本論で展開した内容を簡潔にまとめ、今後の展望や提案を述べます。
分量は全体の約20%程度です。新しい内容を追加するのではなく、これまでの議論を統合してください。
例文:「以上のように、SNSを適切に活用するには、使用時間の自己管理と情報リテラシーの向上が不可欠です。私たち一人ひとりが意識して利用することで、SNSの利点を最大限に活かせる社会になるでしょう。」
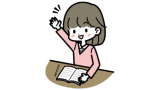
ステップ4:構成に沿って文章を書いてみよう
構成が決まったら、実際に文章を書き始めます。まずは下書きとして、考えたことを箇条書きでメモしてから、それを文章化するとスムーズです。
特に最初は、「型」に当てはめることを意識して書いてみましょう。
書き始めるポイント
- 各段落の冒頭に、その段落で述べる内容を要約する一文を置く
- 一つの段落では一つの内容に絞る
- 適切な接続詞を使って文と文のつながりを明確にする
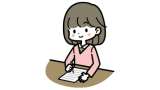
ステップ5:書いた小論文を必ず見直そう
小論文を書き終えたら、必ず見直しの時間を取りましょう。
以下のポイントをチェックします。
- 課題に沿った内容になっているか
- 自分の主張と根拠が明確か
- 誤字脱字はないか
- 文字数制限を守っているか
特に誤字脱字は減点対象になりやすいので、丁寧にチェックしましょう。
文章の流れも確認し、論理の飛躍がないかも見直します。
スラスラ書くための実践的なコツと表現のポイント

小論文をスラスラ書くためには、論理的な文章構成や分かりやすい表現が重要です。
ここでは、小論文を書く際の具体的なコツと表現のポイントを紹介します。
これらのテクニックを身につければ、より説得力のある小論文が書けるようになります。
- 論理的な文章構成にする接続詞の使い方
- 分かりやすい表現で自分の考えを伝えるには
- 制限時間内に書き終えるための時間配分テクニック
論理的な文章構成にする接続詞の使い方
接続詞は文と文をつなぐだけでなく、論理的な関係性を示す重要な役割を持ちます。
適切な接続詞を使うことで、読み手に伝わりやすい文章になります。
効果的な接続詞の例
- 順接(原因と結果):「したがって」「そのため」
- 逆接(反対の内容):「しかし」「一方で」
- 追加(情報の追加):「また」「さらに」
たとえば、「SNSの利用時間が増えている。生活習慣の乱れが問題になっている」という2文があれば、「SNSの利用時間が増えている。そのため、生活習慣の乱れが問題になっている」とすることで、因果関係が明確になります。

分かりやすい表現で自分の考えを伝えるには
小論文では、難しい言葉を使うよりも、自分の考えを明確に伝えることが大切です。
以下のポイントを意識しましょう!
- 一文を短めにして、一つの文で一つの内容を伝える
- 抽象的な表現より、具体的な例を挙げる
- 「私は〜と考える」など、主語と述語を明確にする
たとえば、「現代社会における環境問題は深刻である」という抽象的な文よりも、「海洋プラスチックごみが年間800万トン発生し、海の生態系に深刻な影響を与えている」と具体的に書く方が伝わりやすくなります。
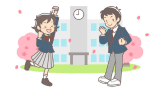
制限時間内に書き終えるための時間配分テクニック
本番では限られた時間内に小論文を完成させる必要があります。
効率よく書くための時間配分を紹介します。
50分の試験を例にした時間配分
- テーマ理解と構想:10分
- 序論・本論・結論の下書き:25分
- 清書:10分
- 見直し:5分
特に重要なのは、最初に全体の構成を考える時間をしっかり取ることです。
構成が決まっていれば、本文を書くときにスムーズに進められます。
必ず見直しの時間を確保しましょう。
知っておきたい!高校受験の小論文のルールと注意点

小論文を書く際には、内容だけでなく形式面のルールも重要です。
基本的なルールを守ることで、減点を避け、内容に集中して評価してもらえます。
ここでは、高校受験の小論文で知っておくべきルールと注意点をまとめました。
- 指定された文字数を守る
- 原稿用紙の正しい使い方
- 話し言葉や略語は使わない
- 誤字脱字・表記ゆれをチェックしよう
指定された文字数を守る
小論文では、文字数制限が必ず指定されます。
たとえば「600字以内」「800字程度」などです。この制限を大幅に超えたり、不足したりすると減点対象となります。
【文字数の目安】
- 「以内」の場合:指定の90〜100%を目指す
- 「程度」の場合:指定の±10%を目安にする
練習の段階から、指定文字数で書く訓練をしておくと良いでしょう。
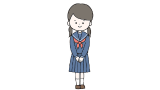
原稿用紙の正しい使い方
原稿用紙には独自のルールがあります。
以下のポイントを押さえましょう!
- 段落の最初は1マス空ける
- 句読点やカギカッコは1マスに書く
- 数字は1文字1マスで書く
- 最後の行が1字だけにならないよう調整する
特に段落の始めは忘れやすいポイントなので、意識して空けるようにしましょう。
原稿用紙の使い方に慣れておくことで、本番でも余計なことを考えずに済みます。
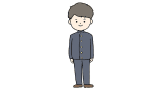
話し言葉や略語は使わない
小論文は「論理的な文章」ですので、話し言葉や略語は使いません。
以下のような表現は避けましょう!
- 「〜だよね」「〜じゃない」などの話し言葉
- 「SNS」などの略語(初出時は正式名称を書く)
- 「すごく」「とても」などの曖昧な表現
たとえば、「スマホでLINEするのってすごく便利だよね」ではなく、「スマートフォンでのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)利用は、私たちの生活に大きな利便性をもたらしている」というように書きます。
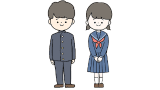
誤字脱字・表記ゆれをチェックしよう
誤字脱字や表記ゆれは、内容の良さにかかわらず減点対象になります。
【特に注意すべきポイント】
- 漢字の書き間違い
- 同じ言葉の表記ゆれ(「行なう」と「行う」など)
- 句読点の打ち忘れ
見直しの際は、一文ずつゆっくり読み返すことで、誤りを見つけやすくなります。
不安な漢字は練習時に確認し、本番では平易な漢字に置き換えるのも一つの方法です。
合格に近づく!今日からできる小論文対策
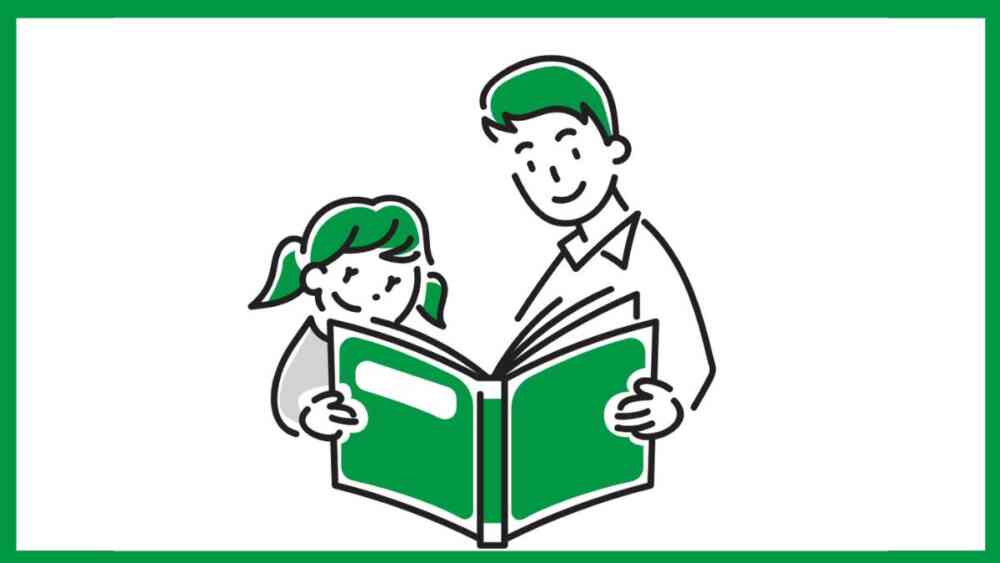
小論文の力を高めるには、日頃からの計画的な練習が欠かせません。
ここでは、効果的な練習方法や対策のポイントをご紹介します。
これらの対策を積み重ねることで、本番で実力を発揮できる力が身につきます。
- 志望校の過去問で出題傾向とレベルを把握する
- いろいろなテーマについて考え、書いてみる
- 学校や塾の先生に添削してもらおう
志望校の過去問で出題傾向とレベルを把握する
志望校の過去の小論文問題を集めて、どのようなテーマが出題されているか、どのレベルの回答が求められているかを分析しましょう。
学校によって傾向が大きく異なるため、志望校に特化した対策が効果的です。
【調べるポイント】
- よく出題されるテーマ(環境、教育、情報社会など)
- 文字数制限
- 試験時間
志望校の過去問を入手できない場合は、学校のホームページや説明会で情報収集しましょう。

いろいろなテーマについて考え、書いてみる
様々なテーマについて考え、実際に書く練習をしましょう。
特に以下のような身近なテーマから始めると取り組みやすいです。
- 学校生活に関すること(制服、校則など)
- 社会問題(環境問題、少子高齢化など)
- 情報化社会(SNS、AIなど)
まずは週に1テーマ、800字程度の小論文を書く習慣をつけましょう。
書き終えたら、自分で読み返して論理的に書けているか確認します。
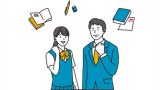
参考記事:【都立高校入試】過去問はいつからやるのか?何年分やるの?徹底解説
学校や塾の先生に添削してもらおう
自分で書いた小論文は、できれば学校の先生や塾の先生に添削してもらいましょう。
プロの視点からのフィードバックは非常に価値があります。
【添削を受ける際のポイント】
- 自分が特に確認してほしい点を伝える
- 「どこが良かったか」も聞く
- 改善点は必ずメモして次回に活かす
添削を受けられない場合は、家族や友人に読んでもらい、「分かりにくい部分はないか」「主張は明確か」などの感想を聞くのも良い方法です。
小論文への苦手意識を克服するには

小論文に苦手意識を持つ人は少なくありません。
ここでは、その苦手意識を克服するための心構えや具体的なアドバイスをご紹介します。
小さな一歩からはじめて、徐々に自信をつけていきましょう。
- 完璧を目指さず、まずは書いてみよう
- 困ったときは周りの大人に相談しよう
完璧を目指さず、まずは書いてみよう
小論文の上達には、とにかく書くことが一番の近道です。
最初から完璧な文章を書こうとせず、まずは思いついたことを書き出してみましょう。書き始めるとアイデアが浮かびやすくなります。
【実践のポイント】
- 時間を決めて(30分など)、思いついたことを書き出す
- 最初は自分の興味のあるテーマから始める
- 書けたらまず自分を褒める習慣をつける
小論文は「練習した分だけ上達する」分野です。完璧な文章より、継続して書く習慣のほうが大切です。

参考記事:高校受験でメンタル崩壊(ボロボロ・やばい) 受験生の不安解消&親のNG行動
困ったときは周りの大人に相談しよう
小論文について分からないことがあれば、遠慮せずに先生や保護者に質問しましょう。
「どう書き始めれば良いか分からない」「自分の意見がまとまらない」など、具体的に悩みを伝えることで的確なアドバイスがもらえます。
【相談の仕方】
- 「ここが分からない」と具体的に伝える
- 自分なりに考えたことも伝える
- メモを取って、次に活かす
周りの大人は、あなたの力になりたいと思っています。
一人で抱え込まずに、積極的に相談してみましょう。
高校受験小論文 Q&A 推薦入試・面接対策・短期上達法
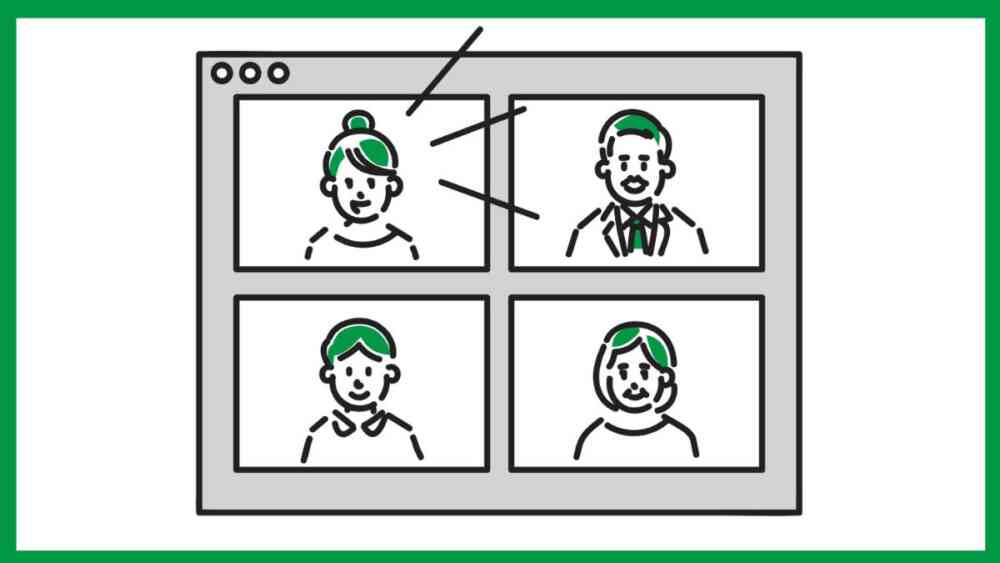
- Q1:推薦入試・特色選抜の小論文、対策は何が違う?
- Q2:面接で小論文の内容について聞かれたらどうする?
- Q3:試験まで時間がない!短期間で小論文をレベルアップさせる方法は?
- Q4:小論文でよくある細かい疑問を解消!(文字数、原稿用紙など)
Q1:推薦入試・特色選抜の小論文、対策は何が違う?
推薦入試や特色選抜の小論文は、一般入試と目的が少し違います。
なぜなら、高校側はあなたの学力だけでなく、「あなたがどんな人で、なぜこの学校に入りたいか」を特に知りたいからです。
一般入試では幅広いテーマが多いですが、推薦・特色では、あなたの経験や、その高校でどう学びたいか、将来どうなりたいかといった「あなた自身」に関わるテーマが出やすい傾向があります。
たとえば、「中学校で頑張ったことと、それを高校でどう活かしたいか」といったテーマです。
自分の経験や考えを具体的に、熱意をもって書く練習が必要です。
事前に志望校の教育方針や特色をしっかり調べて、自分の経験と結びつけることが、オリジナリティを出す鍵になります。
推薦・特色の小論文対策では、自己分析と志望校研究を特に力を入れましょう。

参考記事:都立推薦で受かる子・落ちる子の違いとは?受かるためのポイント!
Q2:面接で小論文の内容について聞かれたらどうする?
面接で小論文について聞かれても、慌てる必要はありません。
なぜなら、面接官はあなたが書いた内容を理解しているか、自分の言葉で説明できるかを見ているからです。
小論文では書ききれなかった思いや、書いた後に改めて気づいたことなどを話すチャンスでもあります。
たとえば、「小論文の○○について、詳しく聞かせてください」と聞かれるかもしれません。
あなたが小論文で書いた意見やエピソードを、もう一度頭の中で整理しておきましょう。
具体的にどんなことを書いたか、なぜそう考えたのかをスムーズに話せるように練習しておくと安心です。
面接と小論文はセットだと考えて、書いた内容を自分の言葉で説明できるように準備しておきましょう。
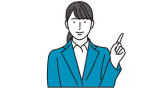
参考記事:高校受験の面接でやってはいけないこと10選!NGな行為はこれだ!
Q3:試験まで時間がない!短期間で小論文をレベルアップさせる方法は?
「試験まで時間がない…」と焦っている人も大丈夫、ポイントを押さえれば短期間で小論文の実力をぐっと上げられます。
なぜなら、小論文には合格につながる基本的な「型」や頻出テーマの傾向があるからです。
合格に直結するエッセンスに絞り、集中的に対策することで効率よくレベルアップできます。
たとえば、まず序論・本論・結論の「型」を完璧に覚え、過去問でよく出るテーマをいくつか選び、型通りに書いてみる練習を繰り返します。
時間は計って本番を意識しましょう。
信頼できる先生や添削サービスに一度見てもらい、自分の弱点を把握して改善するのも効果的です。
短期間でも「型を覚える」「頻出テーマに絞る」「実践練習と添削」に集中すれば、確実に得点アップが可能です。
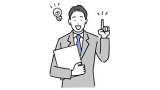
Q4:小論文でよくある細かい疑問を解消!(文字数、原稿用紙など)
小論文には文字数や原稿用紙の使い方など、細かいけれど大切なルールがあります。
なぜなら、これらのルールを守れているかも評価の対象になるからです。
せっかく良い内容を書いても、ルール違反で減点されるのはもったいないです。
初心者の方が特に間違えやすいポイントを事前に知っておけば、安心して書けます。
たとえば、指定された文字数は8割以上、できれば9割を目指しましょう。
原稿用紙では、段落の初めに一マス空け、句読点も一マス使う、ただし行の最初に句読点や閉じカッコが来ないように前のマスに詰める、といったルールがあります。
不安な場合は、一度正しい使い方を確認しておきましょう。細かいルールもマスターして、内容だけでなく形式面でも減点を防ぎましょう。
まとめ:【高校受験対策】小論文の書き方ガイド!初心者の中学生もスラスラ書けるコツ

まとめ:さあ、今日から高校受験の小論文対策を始めよう!
まとめ
ここまで小論文の基本から実践的なコツまで解説してきました。
これらのポイントを押さえれば、初心者でも自信を持って小論文に取り組めるはずです。
大切なのは、今日から実際に書き始めることです。
まずは簡単なテーマから始めて、徐々に難しいテーマにチャレンジしていきましょう。
毎日少しずつでも練習を重ねることで、確実に力がついていきます。
小論文は「考える力」と「表現する力」を養う絶好の機会です。
この機会を活かして、高校受験を乗り越えるだけでなく、将来役立つ論理的思考力も身につけていきましょう。
あなたならきっとできます!今日からの努力が、明日の合格につながります。応援しています!
以上、「【高校受験対策】小論文の書き方ガイド!初心者の中学生もスラスラ書けるコツ」でした。

