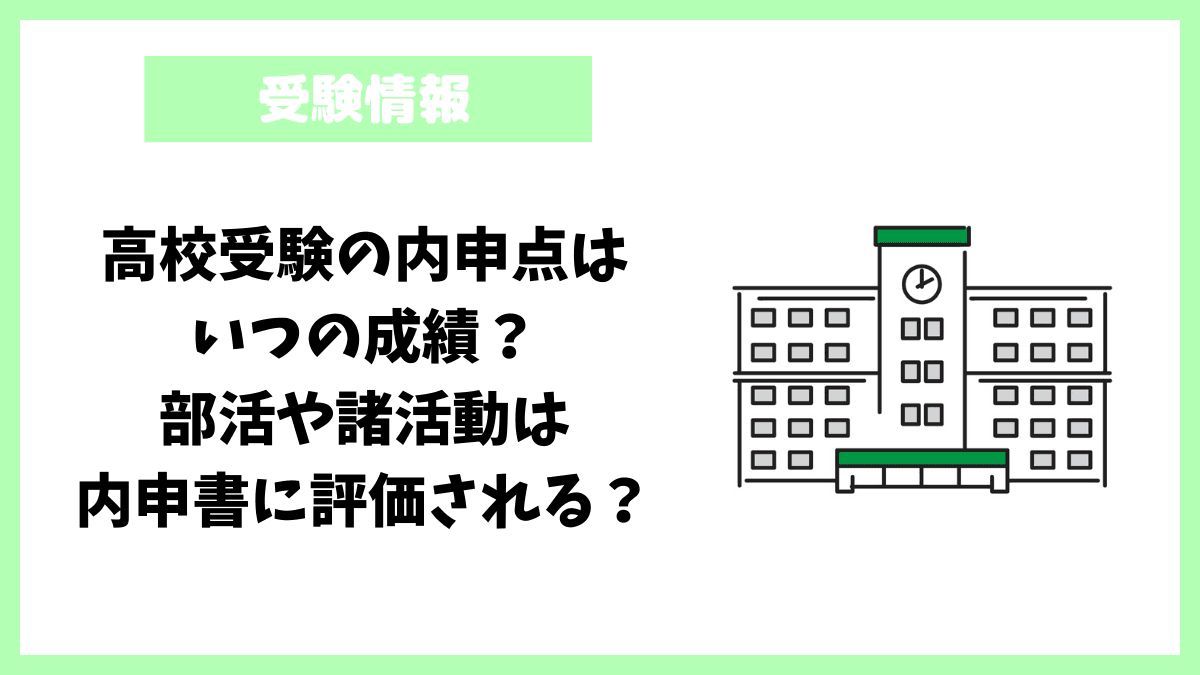
「※この記事には一部PRが含まれます」
塾オンラインドットコム「合格ブログ」です。
小学生と中学生向けに、勉強に役立つ情報を発信している教育メディアです。
今回のお悩みはこちら。

高校受験の内申点はいつの成績ですか?
内申点について詳しく教えてください。
高校受験において内申点はとても大切!
今回は、中学生向けに内申点について説明します。

「高校受験の内申点って、実際どの時期の成績が評価に反映されるの?」と気になる中学生や保護者の方も多いでしょう。
部活動や生徒会といった学校での活動が内申点にどう影響するのか、どのように評価されるのかも知っておきたいポイントです。
この記事では、内申点に反映される成績の時期や、部活動・諸活動の評価の仕組みを分かりやすく解説します。
早い段階から効果的に準備を進めるために、内申点の仕組みをしっかり理解しておきましょう!
読み終えるとわかること
高校受験の内申点とは?いつの成績が大事なの?
高校受験の内申点はいつの成績?ギモンを解決
高校受験に内申点は関係ない?重要なの?
高校受験の内申書は何が書かれているの?
評価方法は?諸活動の記録に優先順位はあるの?
高校受験で内申点が足りない時はどうする?
おすすめ塾
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
オンライン個別指導そら塾
※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師マナリンク
※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!
オンラインプロ教師のメガスタ!
※圧倒的な合格実績を誇る!学生講師からプロ講師まで多数在籍!きっと生徒にピッタリの講師が見つかるはずです。
トライのオンライン個別指導塾
※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!
オンライン家庭教師WAM
※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!
オンライン家庭教師ナイト
※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!
家庭教師の銀河
※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
Contents
高校受験の内申点とは?いつの成績が大事なの?
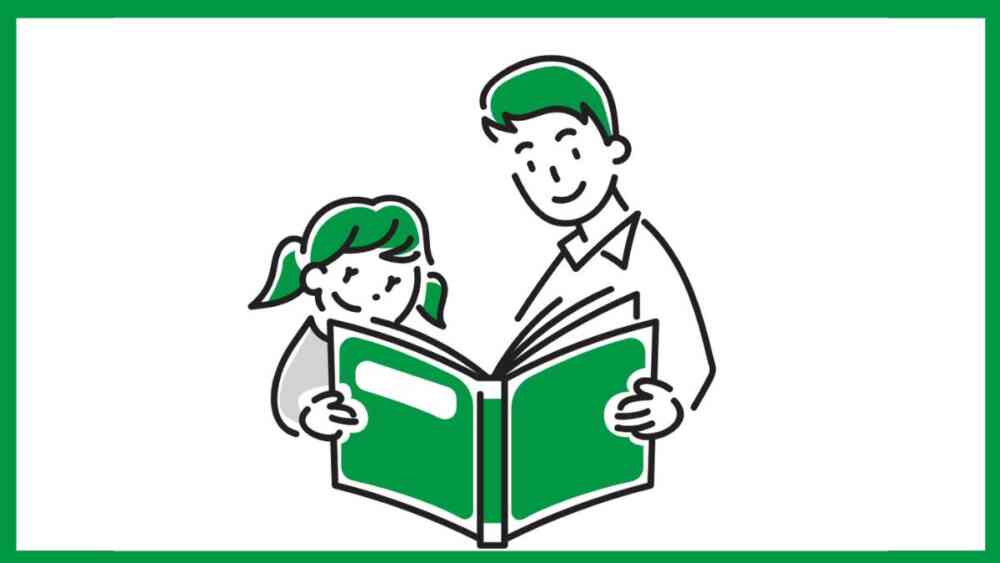

高校受験に大切な内申点についてまとめてみました。
以下のポイントについて説明しています。
- 通知表とは
- 高校受験の内申書(調査書)とは
- 高校受験の評定とは
- 高校受験の内申点(調査書点・調査書素点)とは
- 内申書に記載される成績(内申点)
通知表とは
通知表は、学期ごとの成績をまとめた表で、授業の理解度や学力が記載される大切な書類です。
各教科ごとに「5段階評価」や「観点別評価」がつけられ、学習の成果が数字や先生のコメントで示されます。
例えば、国語が5、数学が4というように、教科ごとに成績がつきます。
担任の先生からのコメント欄があり、学習態度や学校生活での様子が記録されます。
この通知表は、日々の授業の成果や態度が反映され、保護者にとっても子どもがどのように学校生活を送っているか確認できる貴重な資料です。
高校受験では、最終学年の通知表の成績が特に重要視され、合否に影響する「内申書」の基礎資料として使われます。

参考記事:内申点の付け方がわかる!知っておきたい内申点の仕組みや決め方
高校受験の内申書(調査書)とは
内申書(調査書)は、高校受験に提出するための書類で、これまでの学校生活や成績がまとめられています。
通知表と異なる点は、学年ごとの総合評価が記載される点です。
中3の内申書には、中学生活全体の成績や授業態度、出席状況、部活動の実績、行事への参加なども反映され、高校が「どのような生徒か」を知るための重要な資料となります。
例えば、東京都の公立高校では中3の成績のみが評価されますが、神奈川県や埼玉県では中1からの成績も含まれるため、学年を通して安定した成績を保つことが大切です。
内申書は、通知表よりも受験の合否に直接影響を及ぼすため、日々の積み重ねが大切です。

参考記事:【中学生の国語】定期テスト対策!前日でも間に合う!点数をUPする勉強法(現代文・古文・漢字別)
高校受験の評定とは
評定は、通知表や内申書で教科ごとに付けられる「5段階評価」のことを指し、「1」から「5」までの数字で成績が示されます。
例えば、英語で「5」、数学で「4」のように評定が記され、成績の合計が内申点として使われます。
この評価は、学力だけでなく、授業への参加態度や提出物の状況も反映されているため、ただテストで良い点を取るだけではなく、授業での積極的な姿勢も大切です。
特に実技教科は評価が2倍になる地域もあり、音楽や体育、美術の成績も志望校に届くためには重要です。
評定が高ければ内申点も上がるため、学習全般への取り組み方が成績に大きく影響します。
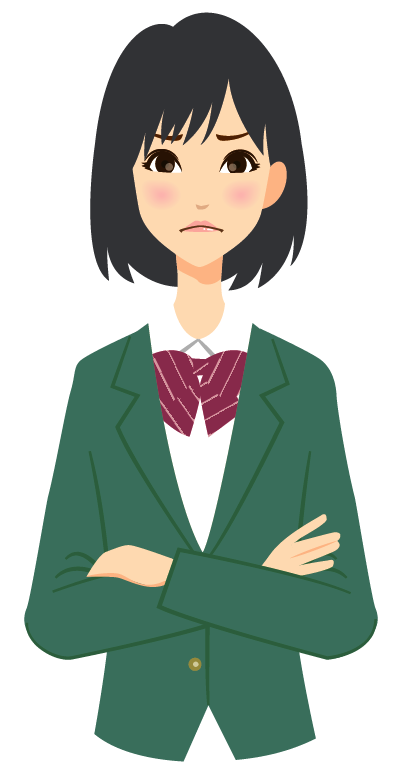
高校受験の内申点(調査書点・調査書素点)とは
内申点とは、高校入試で活用される成績の数値で、通知表の評定をもとに各都道府県で定めた計算方法で算出されます。
例えば、東京都の高校受験では主要5教科はそのまま計算されますが、実技4教科は2倍して加算され、合計が65点満点となります。
一方、神奈川県や埼玉県では異なる基準で計算され、地域ごとに内申点の扱いが違うのが特徴です。
内申点は「調査書点」とも呼ばれ、単なる学力だけでなく、日々の積極的な学習態度も影響します。
中学3年生になってからの対策が重要ですが、早い段階から日常の努力を積み重ねることが、高校受験での内申点アップの鍵です。

内申書に記載される成績(内申点)
内申書には、学年ごとの成績や学校生活の様子が詳細に記録されます。
具体的には、「評定」と呼ばれる5段階評価の成績が9教科について記載されます。
欠席や遅刻の状況、部活動での実績や生徒会活動の役割も内申書に含まれることがあります。
例えば、学期ごとの成績だけでなく、部活動の大会出場や、行事での活躍なども評価され、総合的な人物像が示されることが特徴です。
高校側が内申書を通じて見ているのは、単なる学力だけでなく、授業態度や社会性なども含めた総合評価です。
中学校での経験や努力がそのまま受験に反映されるため、幅広く学校生活に取り組む姿勢が求められます。
おすすめ塾
自宅で集中して勉強できる!
中学校教員・大学教授が推薦する塾
入会すると勉強の習慣が身につく!
中学生:1コマ¥1,375円〜
\無料体験実施中/

生徒の成績がグングン伸びる!
↓↓↓
家庭教師の銀河公式HPはこちらから
参考記事:家庭教師銀河の口コミ・評判!やばい?教材費は高い!リアルな体験談を検証
高校受験の内申点はいつの成績?ギモンを解決


高校受験の内申点はいつの成績が記載されるのでしょうか?
質問形式で詳しく解説します。
- 高校受験の内申点はいつまでの成績?
- 私立高校の内申は、いつの成績で決まりますか?
- 内申点は何学期の成績が記載されますか?
- 内申点はいつ決まるのですか?
- 2学期制の場合はいつ決まるのですか?
- 都道府県内申点の記載学年は違いますか?
高校受験の内申点はいつまでの成績?
高校受験で使われる内申点は、通常、中学1年生から中学3年生の2学期までの成績が反映されます。
出願の時期が1月頃から始まるため、中学3年生の3学期の成績は入試に間に合わず、2学期の成績が最終的な内申点として記録されます。
具体的には、通知表の評定が基準となり、12月の2学期終業式の頃に内申点が確定されます。
例えば、東京都の都立高校では中学3年生の2学期の成績が評価に使用され、埼玉県では中学1年生からの成績が対象となるなど、地域によって対象となる期間が異なります。
早い段階からの成績も重要視される地域も多いため、日々の学習態度が影響することを意識して過ごすことが大切です。

私立高校の内申は、いつの成績で決まりますか?
多くの私立高校では、中学3年生の2学期の成績が内申基準として使われます。
中学校では、2学期の期末テストが終了すると成績会議が行われ、そこで内申が確定します。
この内申が推薦基準に達していれば、推薦入試での受験資格が得られる場合が多いです。
例えば、推薦入試を実施する私立高校では、「中学3年生の2学期の成績が4以上」など、具体的な成績基準が設定されている場合が多くあります。
一般入試でも同様に2学期の成績が基準となり、確定した内申点が合否の一部に反映されます。
したがって、2学期の成績が決まる期末テストや提出物が大きな影響を持つので、この時期に集中して取り組むことが大切です。

内申点は何学期の成績が記載されますか?
内申点には、通常、3学期制の場合は各学年の3学期の成績が記載されます。
ただし、中学3年生については3学期の成績が入試に間に合わないため、2学期の成績が内申点として採用されます。
例えば、東京都立高校の一般入試では中3の2学期の通知表の成績がそのまま内申点として記載されます。
2学期制の学校では後期中間テストまでの成績が内申点に反映されます。
したがって、学年末の成績が重要な基準となりますが、受験年度の中3では2学期までの結果が反映されることを意識し、日々の学習に取り組むことが大切です。
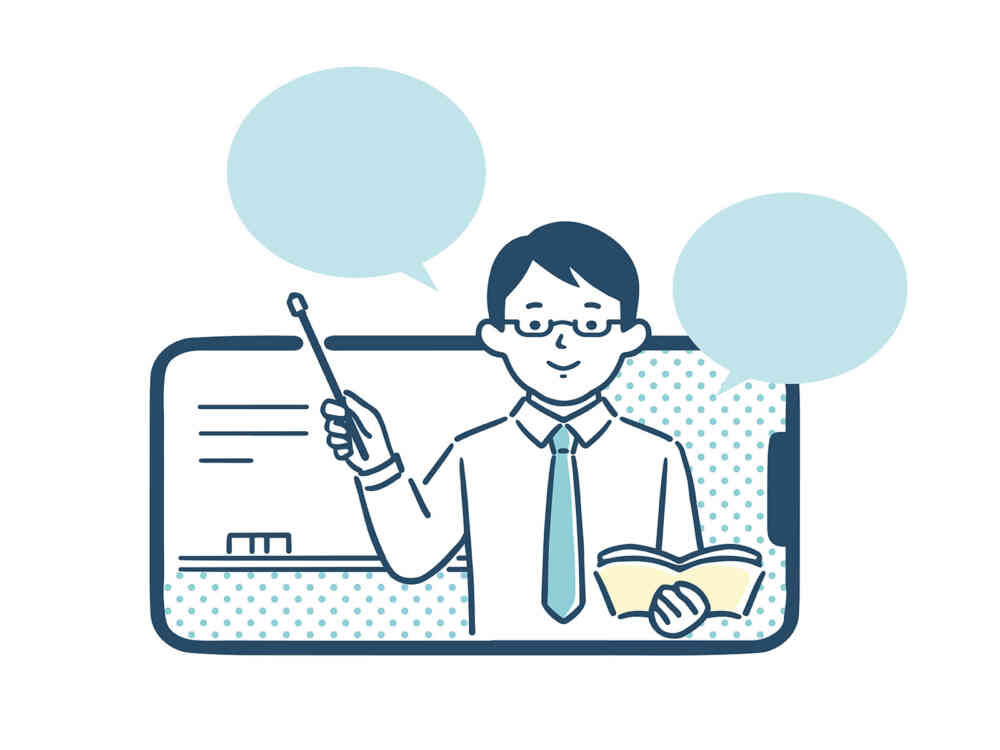
内申点はいつ決まるのですか?
内申点は、中学3年生の2学期が終わる頃、12月に確定されます。
3学期制の学校では3学期に通知表がもらえますが、中学3年生は入試に間に合わないため、2学期末までの成績が最終の内申点として決定されます。
2学期末には面談などで一部の学校では内申点の途中経過が伝えられることもあります。
こうした途中経過は、学習の進捗や必要な対策を考えるために役立ちます。
最終的な内申点は、期末テストの結果、授業での態度、提出物の状況などがすべて考慮されて決定されるため、しっかりと準備をして臨むことが求められます。

2学期制の場合はいつ決まるのですか?
2学期制の場合、内申点は後期の中間テストの成績までが反映され、12月頃に確定されます。
2学期制では前期と後期に分かれ、各学期の最終成績が通知表に記載されますが、中学3年生は後期の途中までの成績が内申点に使用されます。
例えば、後期の中間テストやその後の提出物の評価が影響し、最終内申点が決定されます。
こうした点で、2学期制の学校でも、中3の後期の始まりから意識して成績を上げる取り組みが重要です。
内申点確定前の取り組みが進路に直接影響するため、計画的に準備を進めることが大切です。

都道府県内申点の記載学年は違いますか?
内申点に使われる成績の学年は、都道府県によって異なるため、地域ごとに確認が必要です。
例えば、東京都の公立高校入試では中学3年生の2学期の成績が評価の対象ですが、神奈川県では中学2年生と中学3年生の成績が内申点として反映されます。
埼玉県や千葉県では中学1年生から中学3年生までの成績が内申点に含まれます。
地域によって内申点に含まれる学年が異なるため、早い段階から全学年の成績が重要となる地域も多く、特に中学1年生からの積み重ねが重要です。
自分の住む地域や志望校のルールをよく確認し、各学年で安定した成績を保つことが高校受験を有利に進めるポイントです。
おすすめ塾
自宅で集中して勉強できる!
中学校教員・大学教授が推薦する塾
入会すると勉強の習慣が身につく!
中学生:1コマ¥1,375円〜
\無料体験実施中/

生徒の成績がグングン伸びる!
↓↓↓
家庭教師の銀河公式HPはこちらから
参考記事:家庭教師の銀河の料金や教材費は高い?他のオンライン家庭教師と比較
高校受験に内申点は関係ない?重要なの?


高校受験に内申点は関係ない?重要なの?について解説します。
結論から言うと、内申点は高校受験でとても重要な要素です。
なぜなら、高校受験では、内申点が合否に大きく関係するからです。
内申点とは、中学校での成績や授業態度、課外活動の成果などをまとめたものです。
高校側は、筆記試験だけでなく、日々の学習態度や活動からも生徒の人柄や意欲を評価したいと考えており、そのために内申点が使われます。
内申点の比重は地域や高校ごとに異なりますが、一般的に公立高校の入試では筆記試験と内申点が一定の比率で評価されます。
例えば、東京都の都立高校では、内申点と学力検査の配分が「3:7」や「4:6」となることが多いですが、神奈川県の高校では内申点の比重が比較的高い場合もあります。
そのため、内申点が高いほど、当日の試験でのアドバンテージが得られ、受験生にとって精神的な余裕が生まれます。
高校受験の内申書は何が書かれているの?評価方法は?
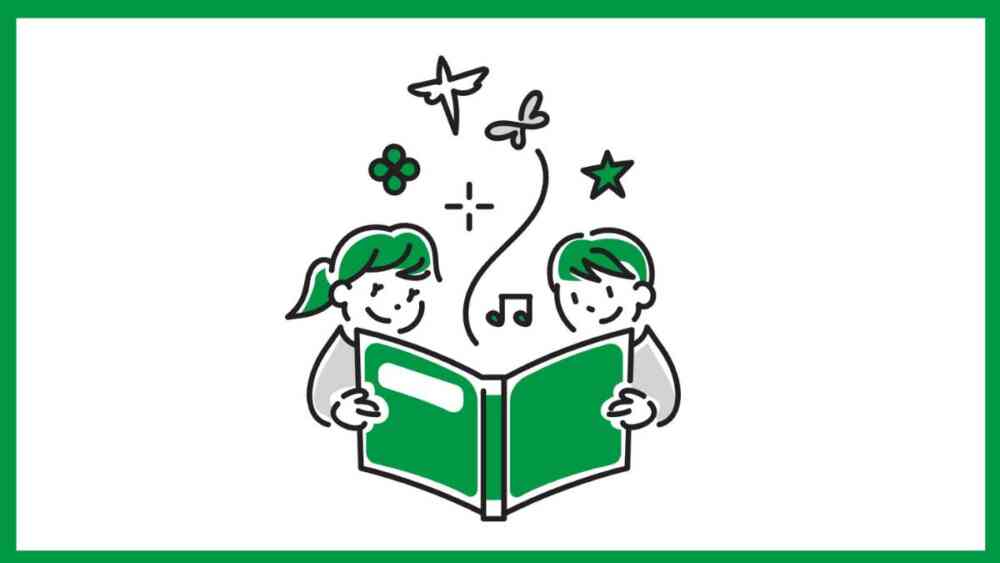

内申点の評価方法について解説します。
- 内申書の内容について知る
- 内申点の評価:知識・技能
- 内申点の評価:思考力・判断力・表現力等
- 内申点の評価:主体的に取り組む態度
内申書の内容について知る
内申書は、生徒が中学生時代に過ごした内容が一目でわかるよう記載されています。
例えば、学力や成績はもちろん、部活動のこと、英語検定や漢字検定などの検定結果、生徒会や学校行事における活動や課外活動による功績も、内申書に記載されているのです。
【東京都の内申点の項目例】
- 氏名
- 生年月日
- 出席しなければならない日数
- 欠席日数
- 各教科の学習の記録
- 観点別学習状況と評価(A・B・C)、評定(5段階)
- 総合的な学習の時間の内容および評価
- 諸活動の記録
内申点は、各学校が教科ごとに定める観点から評定されています。
評定する際は、学力だけでなく、総合的な物事の考え方や勉強に取り組む際の姿勢も評価に含めます。
また、2021年度から中学校学習指導要領が改訂され、内申のつけられ方そのものが以前とは違うものになりました。
新しい評価基準では、生徒の資質・能力を評価する「3つの柱」が主体となります。
ここからは、内申の評価方法について詳しく見ていきましょう。

内申点の評価:知識・技能とは
知識・技能とは、勉強の習熟度です。
中学校の学習内容を理解し、何ができるようになったのかが評価基準になります。
例えば、習った単語や公式を理解しているのか?それを使っても問題が解けるのか?しっかりと理解して学力として定着しているのかが問われます。
そのため知識・技能では、各教科で学習した内容について体系的に理解し、応用できるかたちで身につけることが求められるのです。
技能についても同様に、体育や美術などの実技科目において必要な技術を理解し、スキルを身につけることが目標となります。

評判の良い塾について知りたい方:中学生に人気のオンライン塾!口コミ評価の高いおすすめ14選を徹底比較
内申点の評価:思考力・判断力・表現力とは
思考力・判断力・表現力は、生徒自身の考える力を評価する。
生活するうえで重要視される「生きる力」とされる「問題解決能力」に関する項目とされ、理解していることやできることをどう使うかが評価基準となります。
いろいろな問題に対し、学んだ知識や技能を活かしながら自ら考えたうえで答えを導き出せるかを、テストを通じて評価します。
また、授業などにおいて問題となる事柄を見つけ出し、仲間と協力して解決できる表現力も求められます。

参考記事:中学生の内申点!平均点はズバリ◯点!内申点が足りない時の対策とは
内申点の評価:主体的に取り組む態度とは
主体的に取り組む態度とは、勉強に対する向き合い方を評価すること。
主体的に取り組む態度において、重要なのが授業の際に忘れ物をしていないか、提出物をきちんと出しているか、自分から発言しようとしているかなど、普段の授業態度が評価基準になります。
指導要領の改訂では、現代社会を「生きる力」を育てることが目的の1つとなっています。
そのため、この項目では「どのように社会や世界と関わっているか」「よりよい人生を送る努力をしているか」という、学習への主体的な姿勢が求められるのです。

内申点の評価について
3つの観点別の学習状況を評価して内申点は評価されていますが、教科によって重視する項目も異なっています。
私の経験上、内申点の評価については、主に5教科では定期テストの点数が重視され、実技教科では授業態度などの平常点が重視される傾向にあると思われます。
文部科学省では、評定の統一性を保つ努力をすることを推奨していますが、地域や学校、教科によって差が出てしまうことは完全には避けられないのが現状です。
観点別学習のポイントをよく理解して、内申点対策するのが内申点の評価を上げる王道と言えます。
おすすめ塾
講師のほとんどが東大・東大院生
しかも、圧倒的低価格を実現した!
オンライン個別指導
部活が忙しい生徒にも対応!
自宅で勉強できるから、集中力UP!
成績アップの近道!
30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/
↓↓↓
トウコベの公式HPをチェック!
参考記事:【トウコベ】口コミ・評判を徹底解説!知っておきたい口コミの真実
諸活動の記録に優先順位はあるの?


諸活動の記録の内申点について解説します。
- 諸活動の記録の優先順位はあるの?
- 部活動や生徒会活動は内申点に影響するのか?
- 内申点に加算される資格はあるの?
諸活動の記録の優先順位はあるの?
高校受験の内申点では、学力だけでなく、部活動や生徒会活動などの「諸活動」も評価の対象となることがあります。
しかし、どの活動が優先されるのか、疑問に思う人も多いでしょう。
結論から言うと、明確な優先順位は存在しません。
一般的に、内申書には以下の項目が記載されます。
- 学力:各教科の成績
- 出欠状況:欠席日数や遅刻回数
- 諸活動:部活動、生徒会活動、ボランティア活動など
- 総合的な評価:先生による総合的な評価
これらの項目の中で、学力が最も重視されることは間違いありません。
しかし、諸活動も、あなたの学校生活を総合的に評価する上で重要な要素となります。
例えば、
- リーダーシップを発揮している:部活動のキャプテンを務めたり、生徒会で中心的な役割を担ったりしている場合
- 継続性がある:長期にわたって同じ活動に取り組んでいる場合
- 社会貢献活動:ボランティア活動など、社会貢献に積極的に取り組んでいる場合
このような活動は、あなたの積極性や責任感、協調性などを示す証拠となり、総合的な評価を上げることにつながります。

部活動や生徒会活動は内申点に影響するのか?
直接的に内申点に数値として加算されることは、ほとんどありません。
しかし、内申書の「諸活動」の欄に記載され、あなたの総合的な評価に影響を与える可能性は十分にあります。
メリット
- 学校生活の充実:部活動や生徒会活動は、学校生活を豊かにし、人間関係を築く上で貴重な経験となります。
- 自己成長:リーダーシップや協調性、責任感などを養うことができます。
- 内申書のプラス評価:積極的に活動することで、内申書での評価が上がる可能性があります。
デメリット
時間的な負担:部活動などに熱中しすぎて、勉強時間が減ってしまう可能性があります。
体力的な負担:過度な練習は、健康を害する可能性もあります。

内申点に加算される資格はあるの?
英検、漢検などの資格取得は、直接内申点に加算されることはありません。
しかし、内申書の「諸活動」の欄に記載されることで、あなたの学力や学習意欲の高さを示すことができます。
資格取得は、以下の点で評価されます。
- 学習意欲:自ら進んで学習に取り組んでいることを示します。
- 目標達成能力:目標を設定し、それを達成するための努力をしていることを示します。
- 能力の証明:資格を取得したという事実は、あなたの能力を客観的に証明します。
諸活動は、内申点に直接的に影響を与えるわけではありませんが、あなたの学校生活を総合的に評価する上で重要な要素です。
おすすめ塾
講師のほとんどが東大・東大院生
しかも、圧倒的低価格を実現した!
オンライン個別指導
部活が忙しい生徒にも対応!
自宅で勉強できるから、集中力UP!
成績アップの近道!
30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/
↓↓↓
トウコベの公式HPをチェック!
参考記事:トウコベの料金(入会金・月謝)は高い?他のオンライン塾と徹底比較!
内申点を効果的に上げる7つの内申点対策


内申点を効果的に上げる7つの内申点対策について解説します。
- 内申点の評価項目を理解する
- 定期テストを頑張る
- 実技4教科を頑張る
- 小テストを頑張る
- 授業に積極的に参加する
- 提出物は必ず提出する
- 忘れ物をしない
内申点の評価項目を理解する
内申点の評価項目を理解しておくと、内申点対策になります。
内申点の評価項目
・「知識・技能」
・「思考力・判断力・表現力など」
・「学習に取り組む態度(主体性・人間性)」
| 「知識・技能」 | 教科等を通して身につける、知識や技能のこと、例えば、国語の知識や計算の技能など |
| 「思考力・判断力・表現力など」 | 知識や技能を活用して、自ら考え、判断し、表現する力、例えば、論理的思考力、創造力、コミュニケーション力など |
| 「学習に取り組む態度(主体性・人間性)」 | 主体的に学習に取り組む態度、例えば、探究心、粘り強さ、協調性など、学びに向かう力や人間性 |
上記の3つの観点から、中学生の内申点がつけられています。
この3つの観点は、単に知識や技能を習得するだけでなく、それらを活用しながら、自ら学び続ける力を身につけることが、大きな目標となっているのです。
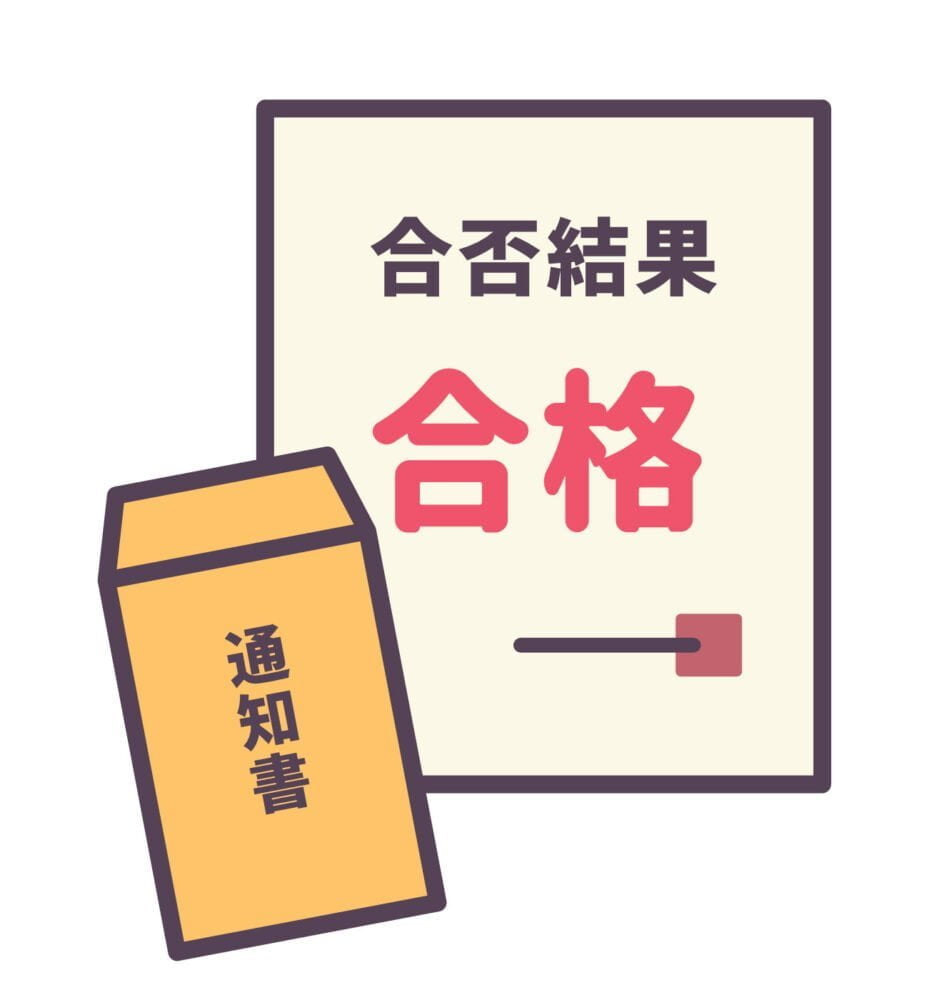
参考記事:内申点の付け方がわかる!知っておきたい内申点の仕組みや決め方
内申点対策:定期テストを頑張る
内申点を上げる一番のポイントは、定期テストで良い結果を出すことです。
なぜなら、定期テストの成績は内申点に直結するため、良い成績を取ることで内申点を上げることができるからです。
親ができるサポートとしては、子どもが定期テストに向けて効果的な学習計画を立てるアドバイスや、学習環境の整備、モチベーションアップをサポートをすることが大切です。
また、定期テストで良い点数を取るために、学習塾、家庭教師、オンライン塾、タブレット教材の利用を検討するのも良い方法です。

参考記事:【オンライン塾】定期テスト対策に強い!中学生におすすめする13選!
内申点対策:実技4教科を頑張る
内申点対策として、実技4教科をおろそかにしないことは非常に重要です。
なぜなら、実技4教科の定期テストは、テスト範囲も多くなく、暗記中心なので、良い点数が取りやすいからです。
もちろん、実技なので、能力や技術を評価されるため、授業にも積極的に取り組まないといけません。
実技4教科の定期テストは、一生懸命に取り組む姿勢が評価されるため、決しておろそかにしてはいけません。

参考記事:体育・音楽・美術・技術家庭の実技4教科の内申点を上げる!
内申点対策:小テストを頑張る
内申点を上げるコツとして、小テストを頑張ることは非常に重要です。
なぜなら、小テストの成績は日々の学習の結果であるため、内申点を上げるための大きな要素となります。
具体的には、漢字テスト、単語テスト、計算テストで良い点数を取ることです。
親ができるサポートとしては、子どもが小テストで良い結果を出すためのサポートをすることが重要です。

内申点対策:授業に積極的に参加する
授業に積極的に参加することは、内申点対策としてとても重要です。
理由は、内申点の評価項目である、「学習に取り組む態度」に直結しているからです。
具体的には、授業に積極的に参加し、授業中に質問をしたり、話し合いに参加したりすることが重要です。
積極的な姿勢を見せることで、教師からの評価が高まります。
良い印象
・積極的に手を挙げる
・先生の説明にうなずく
・他の生徒の発表を真剣に聞く
悪い印象
・あくび
・私語をする
・話し合いに参加しない
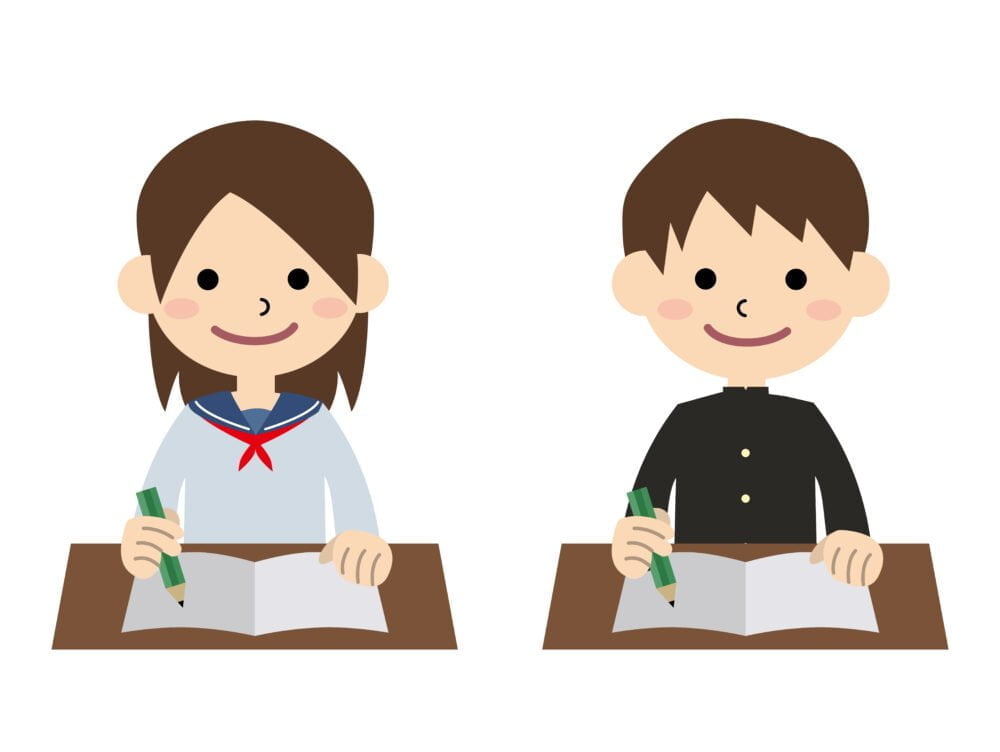
内申点対策:提出物は必ず提出する
学校からの宿題、プリントなどの提出物は必ず期限内に提出してください。
提出物を出すことは内申点を上げるためのポイントです。
提出物が期限内に提出されない場合、評価されないため、内申点が下がる可能性があるでしょう。
親としては、提出物のスケジュールをカレンダーにメモしたりして、サポートすることが大切です。
期限を守り、丁寧に取り組むことで、内申点アップにつながります。
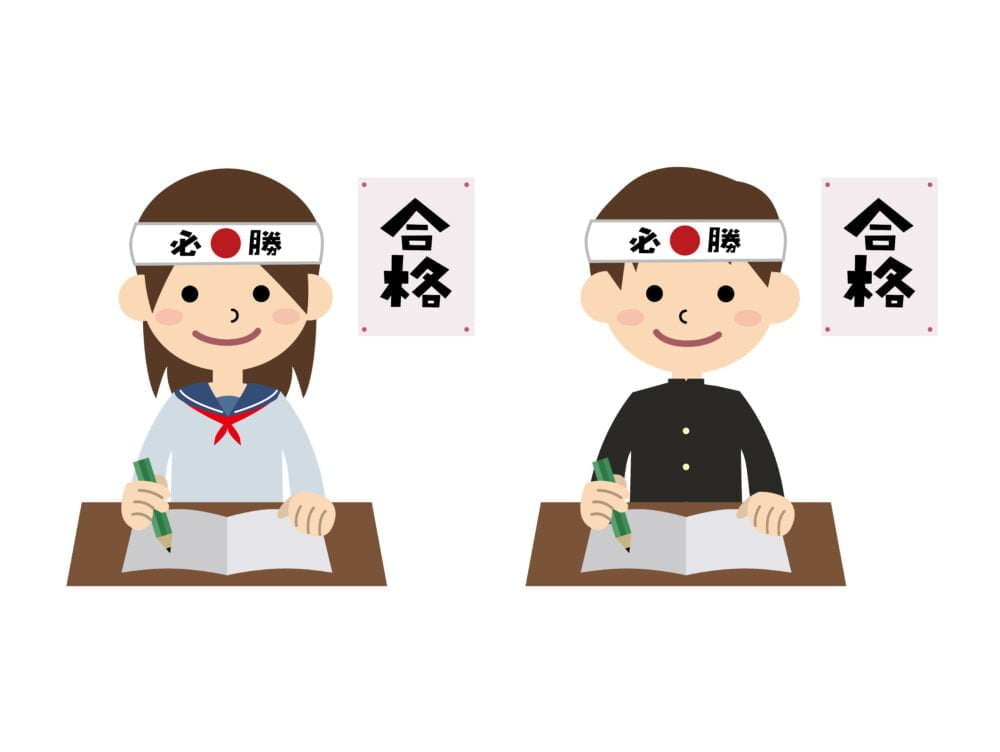
参考記事:中学生が提出物を出さないとどうなる?リアルな影響!親ができるサポート
内申点対策:忘れ物をしない
忘れ物をしないことも、内申点対策のポイントの一つです。
定期テストの点数が良くても、忘れ物が多いと内申点が下がってしまいます。
特に実技4教科においては、体操服、リコーダー、絵の具、縫製セットなどを忘れると、授業に参加できません。
親としては、チェックリストを作り、毎朝、忘れ物がないかしっかりと確認することが大切です。
忘れ物をなくすための対策を立て、実践することで、内申点の向上につなげることができます。
特に自分の弱点となっている教科の忘れ物には気をつけましょう。
参考記事:内申点どこから高い?気になる中学生のための内申点完全ガイド
参考記事:学研の家庭教師の口コミ・評判は悪い?料金も高い?徹底検証してみた
高校受験で内申点が足りない時はどうする?
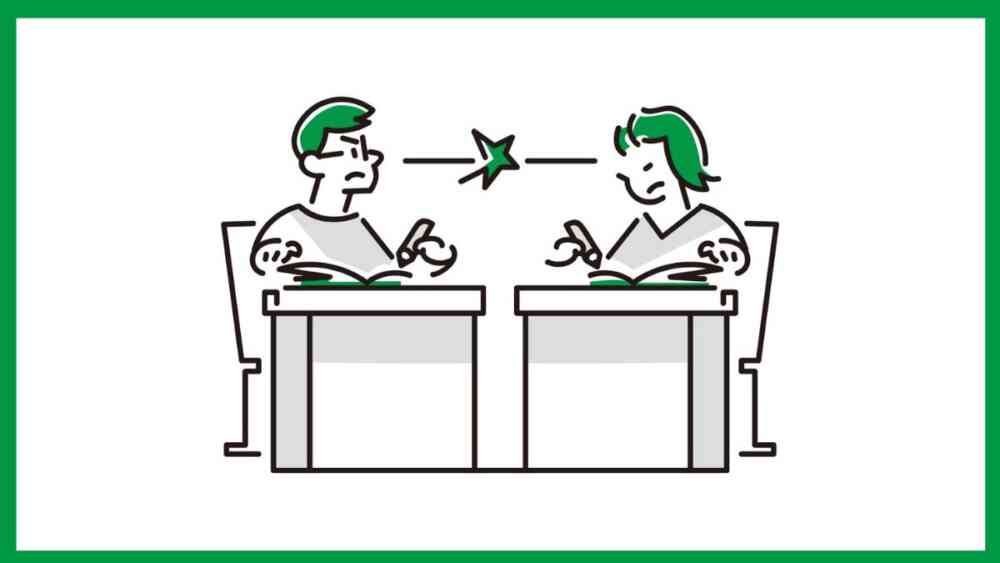

内申点が足りない時の対策を紹介します。
- 入試当日の筆記試験で高得点を獲得する
- 志望校を変更する
- 面接で高評価を獲得する
- 内申点以外の項目を頑張る
入試当日の筆記試験で高得点を獲得する
内申点が十分でない場合、入試当日の学力試験(筆記試験)で高得点を取ることが重要になります。
多くの高校では、内申点と学力試験の得点を合計して合否判定を行うため、試験の得点で内申点の低さを補うことができます。
なぜなら、内申点がやや低めでも、当日の試験で大きく点数を稼げば合格のチャンスが残されているからです。
試験勉強に力を入れ、満点を目指して臨む必要があります。

参考記事:体育・音楽・美術・技術家庭の実技4教科の内申点を上げる!
志望校を変更する
内申点が足りない時の対策として、志望校のラインを下げることです。
内申点が目標とする志望校の基準に達していない場合、やむを得ず志望校のレベルを下げて受験することを検討する必要があります。
例えば、第一志望の難関私立高校が内申点の関門で無理そうだと判断したら、併願していた次点の公立高校や中堅私立高校にシフトするといった具合です。
内申点の評価基準は高校ごとに異なるため、目標を少し下げれば十分にクリアできる可能性が高まります。
もちろん志望校を下げるのは本意ではありませんが、現実的に内申点が足りない場合は、チャレンジできる受験機会を残すためにも賢明な選択肢と言えるでしょう。
将来性を考えた上で、しっかりと選択肢を見直し、自分の力に見合った進学先を選ぶことが何よりも大切です。
内申点に捉われすぎず、柔軟に対応することが重要なのです。
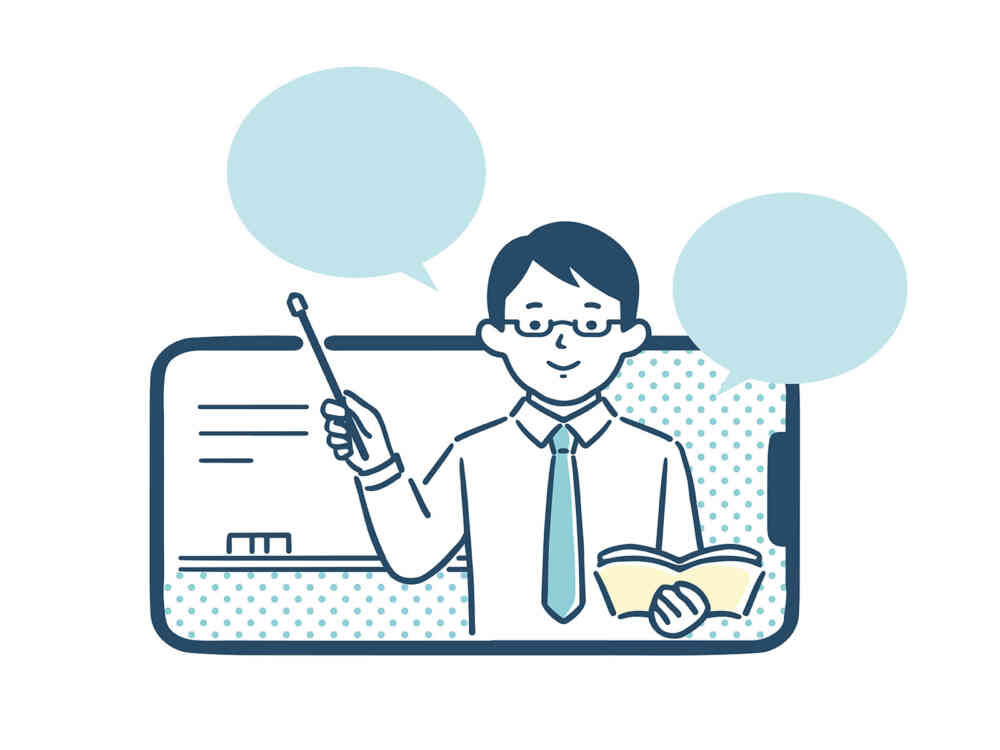
参考記事:高校受験で志望校が決まらない中3生!行きたい高校がない場合を解決
面接で高評価を獲得する
一部の高校では、面接試験の結果が合否に大きく影響します。
この面接では、学力だけでなく人物評価が重視されます。
内申点が低めでも、面接官を前に自分の長所を存分にアピールできれば、高い評価を得ることが可能です。
事前に自己PR、志望動機、将来の夢などをしっかり準備し、その上で、品行方正な姿勢と明るい印象を面接官に与えることがポイントです。
知識だけでなく人間性の高さを伝えられれば、内申点の低さを十分にカバーすることができるでしょう。

参考記事:【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)
内申点以外の項目を頑張る
内申点が志望校の基準を満たせない場合は、内申書の他の項目で評価を上げることが重要です。
内申書とは、生徒の中学校生活全体を詳しく記録した書類のことです。
先生が、学習面だけでなく、出席状況や課外活動、生徒会活動、行動面なども評価して作成します。
この内申書には、内申点だけでなく以下の項目が記載されています。
・基本情報(名前、生年月日など)
・教科ごとの学習記録
・出席状況の記録
・部活動や生徒会活動などの課外活動の記録
・規律違反などの行動面の記録
・総合所見(生徒への総合的な評価)
中でも、3年生になってから取り組めば内申書の評価を上げられる項目が以下の3つです。
【1】出席状況:3年次に遅刻や欠席がないよう気をつける
【2】課外活動:文化祭や体育祭で班長など、リーダー的存在となる
【3】行動面:部活動で県大会出場するなど、目標に向かって頑張る
このように、内申点以外の項目で大きく評価を上げることで、内申書全体の評価をアップさせられます。
志望校合格への大きな助けとなるでしょう。
おすすめ塾
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
オンライン個別指導そら塾
※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師マナリンク
※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!
オンラインプロ教師のメガスタ!
※圧倒的な合格実績を誇る!学生講師からプロ講師まで多数在籍!きっと生徒にピッタリの講師が見つかるはずです。
トライのオンライン個別指導塾
※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!
オンライン家庭教師WAM
※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!
オンライン家庭教師ナイト
※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!
家庭教師の銀河
※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
まとめ:高校受験の内申点はいつの成績?部活や諸活動は内申書に評価される?

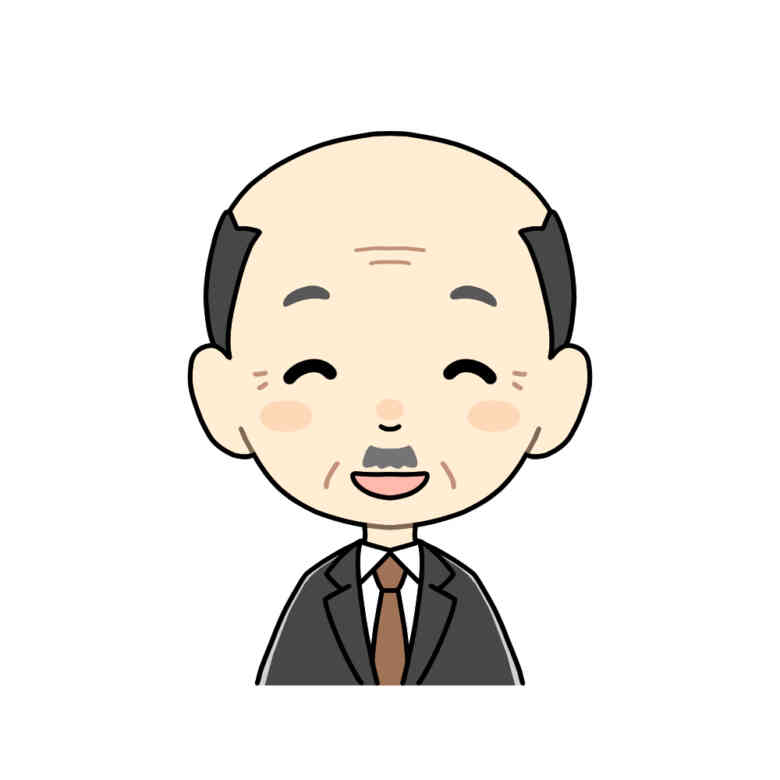
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「高校受験の内申点はいつの成績?部活や諸活動は内申書に評価される?」は参考になりましたでしょうか?
内申点について理解できました。

まとめ:高校受験の内申点はいつの成績?部活や諸活動は内申書に評価される?
まとめ
内申点は、高校受験において重要な要素の一つです。内申点を上げることで、志望校に合格する可能性が高まります。内申点を上げるためには、以下のようなポイントを押さえましょう。
【授業態度を良くする】
授業態度が悪いと、教師からの評価が低くなります。授業では、積極的に質問し、授業内容を理解するようにしましょう。また、遅刻や早退しないことも大切です。
【テストの点数を上げる】
テストの点数が良くないと、内申点は上がりません。テスト勉強をきちんとし、満点を目指しましょう。また、苦手な科目は早めに対策しましょう。
【部活動や委員会活動に積極的に参加する】
部活動や委員会活動に積極的に参加することで、学校生活への取り組み姿勢をアピールできます。また、部活動や委員会活動を通して、リーダーシップや協調性などの資質が身につきます。
【挨拶や礼儀をきちんとする】
挨拶や礼儀をきちんとすることで、教師や生徒からの信頼を得られます。また、挨拶や礼儀は、中学生としても大切なことです。
内申点を上げるためには、日々の積み重ねが大切です。これらのポイントを押さえ、コツコツと努力することで、内申点が上がるでしょう。

