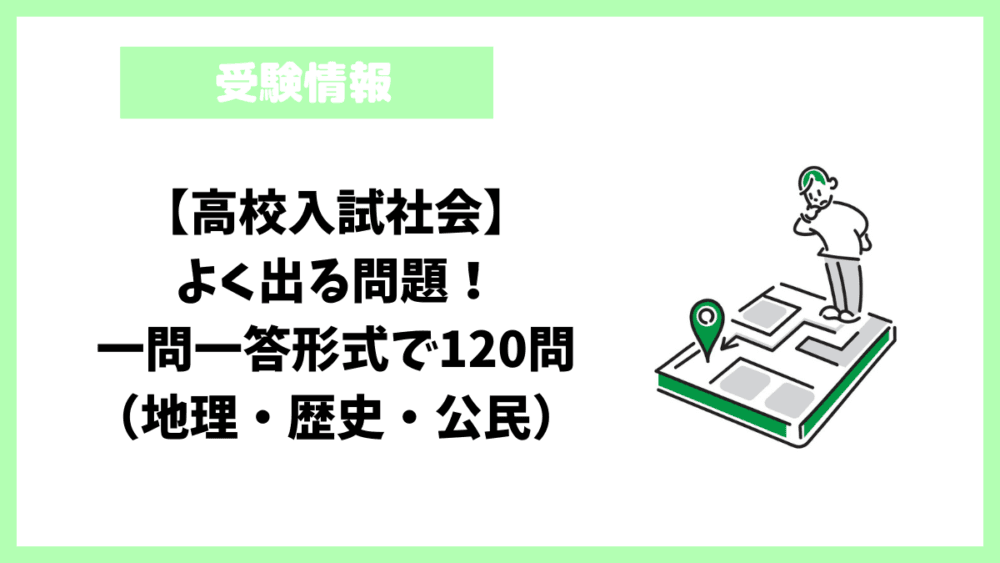
※この記事には一部PRが含まれます。
こんにちは、塾オンラインドットコム「合格ブログ」です。
小学生と中学生向けに、勉強に役立つ情報を発信しています。
今回のお悩みはこちら。

高校入試の社会を効率的に勉強したいです。
社会でよく出る問題を教えてください。
社会の勉強は効率的に暗記するのが大切!
今回は、高校入試によく出る社会の問題を一問一答にしてみました。

社会:高校入試の頻出事項をまとめてみました。
今回紹介する、「【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)」を読めば、社会の重要事項のチェックができます。
また、社会の勉強法も紹介しているため、とても参考になる記事です。
読み終えるとわかること
高校入試の社会では得点が伸ばせます!
高校入試の社会!よく出る問題:世界の地理
高校入試の社会!よく出る問題:日本の地理
高校入試の社会!よく出る問題:歴史
高校入試の社会!よく出る問題:公民
効率よく社会の勉強ができる!タブレット学習教材の紹介
短期間で成績を上げたいのであれば、東大生と東大院生の指導が受けられる!「トウコベ:東大生のオンライン個別指導」がおすすめです。
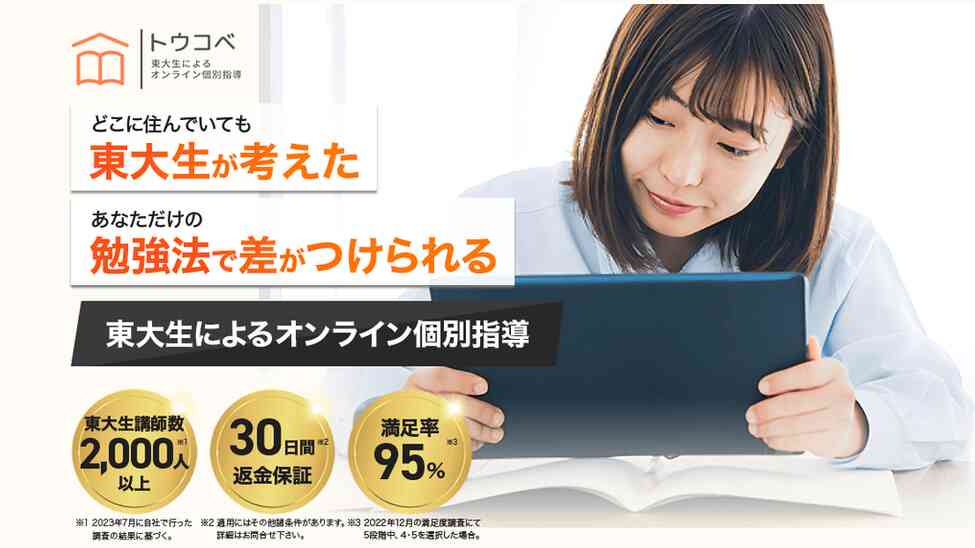
東大生と東大院生から教えてもらえると高額のイメージがありますが、なんと!月額9,900円〜から!低料金で高品質の授業が受けられます。
トウコベの公式サイトをチェック!
↓↓↓
参考記事:【トウコベ】口コミ・評判を徹底解説!知っておきたい口コミの真実
Contents
【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)


高校入試対策!社会で得点アップ!についてまとめてみました。
社会は得点が稼げる教科!しっかりと勉強して得点をゲットしましょう!
- 【高校入試対策】社会で得点アップ!
- 高校入試対策:社会の勉強法は教科書中心に
- 高校入試の社会を得点源にする
【高校入試対策】社会で得点アップ!
高校入試の社会科目は得点が伸ばせます。
なぜなら、社会科目は記憶力を駆使して事実や情報を覚えることが求められるからです。
つまり、効果的な学習法を用いれば高得点が狙えるのです。
また、社会科目は課題文の理解と情報の適切な活用が必要で、読解力や論理的思考力の向上にも寄与します。
さらに、多様な分野から出題されるため、知識の幅広さがポイントです。
最後に、社会科目は他の科目とのバランスをとりやすく、総合的な成績を向上させる助けになります。
これらの理由から、高校入試において、社会科目への適切な対策と学習が高得点を獲得するために重要です。

高校入試対策:社会の勉強法は教科書中心に
高校入試対策の社会の勉強法において、教科書は重要な役割を果たします。
教科書は、高校入試で問われる基本的な知識を網羅しているため、教科書をしっかりと理解しておくことが、社会を得点源にするためには欠かせません。
教科書を勉強する際には、以下の点に注意しましょう。
- 教科書を何度も読み返して、内容をしっかりと理解する
- 図や表、地図などを使って、視覚的に理解する
- 重要な用語や概念を覚えておく
- 教科書の内容をまとめるノートを作成する
また、教科書を勉強する際には、自分の考えをまとめる練習も大切です。
教科書の内容を読みながら、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。
以下に、教科書を勉強する際のコツをまとめます。
- 1回読んだだけでは覚えられないので、何度も読み返す
- 図や表、地図などを使って、視覚的に理解する
- 重要な用語や概念を覚えておく
- 教科書の内容をまとめるノートを作成する
- 自分の考えをまとめる練習
教科書をしっかりと勉強することで、高校入試対策社会の勉強の基礎が固まります。

高校入試の社会を得点源にする
高校入試の社会を得点源にするためには、以下の3つのポイントを押さえることが大切です。
- 過去問を解いて傾向を把握する
- 基本的な知識を身につける
- 思考力を鍛える
1.過去問を解いて傾向を把握する
高校入試の社会でよく出る問題を対策するためには、まずは過去問を解いて傾向を把握することが重要です。
過去問を解くことで、どのような問題が出題されるのか、どのような内容を押さえておく必要があるのかを把握できます。
過去問を解く際には、問題の形式や内容を分析し、自分が苦手な分野や問題形式を把握しましょう。
また、過去問を解いた後は、間違えた問題を徹底的に復習し、間違えた理由を理解して解き方を身につけましょう。
2.基本的な知識を身につける
高校入試の社会でよく出る問題を対策するためには、基本的な知識を身につけることも大切です。
歴史や地理、公民などの基本的な知識を身につけておけば、問題を解く際の思考の幅が広がります。
基本的な知識を身につけるためには、教科書や参考書をしっかり読み込むことが大切です。
また、教科書や参考書を読み込む際には、図や表、地図などを使って、視覚的に理解するのも効果的です。
3.思考力を鍛える
高校入試の社会でよく出る問題の中には、記述問題や計算問題など、思考力を問う問題も出題されます。
思考力を鍛えるために、普段からニュースや時事問題などにも目を向け、自分の考えを深めるようにしましょう。
また、思考力を鍛えるには、問題を解く際に、自分の考えを論理的に説明できるようにすることが大切です。
問題を解く際には、まずは問題文をしっかりと読み込み、問題の意図を理解しましょう。
そして、問題文の意図を理解した上で、自分の考えを論理的に説明できるように解答を作成しましょう。
高校入試の社会を得点源にするためには、早いうちから対策を始めることが大切です。
また、過去問を解いて傾向を把握し、基本的な知識を身につけて、思考力を鍛えることで、高校入試の社会で高得点を狙うことが可能です。
おすすめ塾
講師のほとんどが東大・東大院生
しかも、圧倒的低価格を実現した!
オンライン個別指導
部活が忙しい生徒にも対応!
自宅で勉強できるから、集中力UP!
成績アップの近道!
30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/
↓↓↓
トウコベの公式HPをチェック!
参考記事:トウコベの料金(入会金・月謝)は高い?他のオンライン塾と徹底比較!
【高校入試対策】社会でよく出る問題:世界の地理


世界の地理でよく出る問題を30個まとめてみました。
以下、大切なポイントです。
| 六大陸はユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、南極大陸ともう1つは何か? | オーストラリア大陸 |
| 三大洋は太平洋、大西洋ともう1つは何か? | インド洋 |
| 冷帯地域に拡がる針葉樹林地帯を何というか? | タイガ |
| 東アジアや南アジアの気候に影響を与える、夏と冬で向きが変わる風の事を何というか? | モンスーン |
| 中国の沿岸部に設けられた、外国企業を多く受け入れるために税金面などで優遇されている地域を何というか? | 特別経済区(SEZ) |
| 南アフリカ共和国で行われていた人種隔離政策を何というか? | アパルトヘイト |
| 世界最大の面積を持つ国家? | ロシア |
| オーストラリア東部でよく産出される鉱山資源は何か? | 石炭 |
| ヨーロッパ連合の略称? | EU |
| アジアで最も高い山は? | エベレスト |
| 中国の歴史的な防壁であり、国の北部を横断する巨大な防御施設 | 万里の長城 |
| ヨーロッパとアジアを結ぶ、陸上の交通路は何と呼ばれていますか? | シルクロード |
| アフリカ大陸の最高峰の山は? | キリマンジャロ山 |
| アジアで最大の面積を有している国? | 中華人民共和国 |
| アメリカ合衆国の首都はどこですか? | ワシントンD.C. |
| アフリカ大陸の最長の川の名称は? | ナイル川 |
| アジアとヨーロッパの境界に位置する国はどこですか? | トルコ |
| 首都はジャカルタで、赤道をまたぎ約18,000の島々からなる国は? | インドネシア |
| 世界で最も人口の多い国は? | インド |
| 中華人民共和国の首都はどこですか? | 北京 |
| オーストラリアの首都は? | キャンベラ |
| 産業革命発祥の地? | イギリス |
| 北アメリカに位置し、自然景観や国立公園が多く存在する国は? | カナダ |
| 太平洋に位置し、ニュージーランドと共にオセアニアを構成する国は? | オーストラリア |
| ヨーロッパ南東部に位置する半島で、主にバルカン山脈によって形成されている半島? | バルカン半島 |
| アメリカ合衆国のカリフォルニア州に位置し、テクノロジー産業の中心地として世界的に知られている地域の名称は? | シリコンバレー |
| EU最大の工業国? | ドイツ |
| ヨーロッパに位置し、エッフェル塔がある国は? | フランス |
| 北アメリカに位置し、自由の女神が存在する国は? | アメリカ合衆国 |
| 中東とアフリカ大陸の接点に存在し、古代文明が存在していた地域のひとつに数え上げられる。ピラミッドがある国は? | エジプト |
参考記事:東大先生は怪しい!口コミ・評判の真実とは?驚きの調査結果を解説
【高校入試対策】社会でよく出る問題:日本の地理
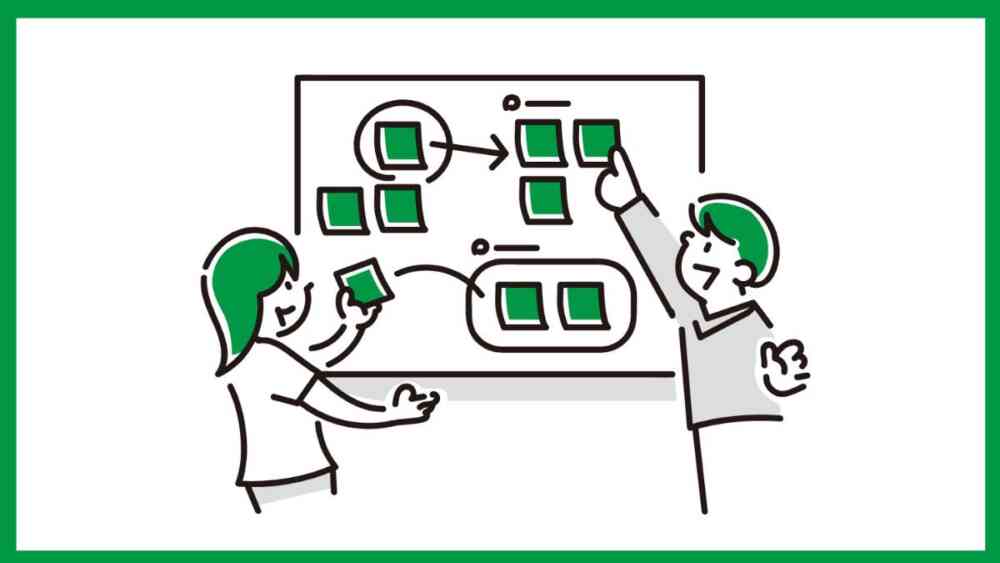

日本の地理でよく出る問題を30個まとめてみました。
以下、大切なポイントです。
| 地形図で、同じ高さに集まる点を結ぶ線を何というか? | 等高線 |
| 太陽光、風力、水力、地熱などを利用してつくられる、繰り返し使えて自然破壊や汚染の原因にならないエネルギーを何というか? | 再生可能エネルギー |
| 自国で消費する食料を国内生産でまかなえる率のことを何というか? | 自給率 |
| 阿蘇山などでみられるような、火山の噴火でできた大きなくぼ地を何というか? | カルデラ |
| 東京都と神奈川県の一部にまたがるエリアを中心に、多くの製造業や工場が集中している地域 | 京浜工業地帯 |
| 根釧台地で盛んな、乳牛を飼って生乳や乳製品を生産する牧畜を何というか? | 酪農 |
| 富士山の高さは何メートルですか? | 3,776メートル |
| 日本で一番高い山は? | 富士山 |
| 日本で最も大きな湖の名称は? | 琵琶湖 |
| 日本の最も長い川の名称は? | 信濃川 |
| 冬は北西、夏は南東から吹く風を何というか | 季節風(モンスーン) |
| 河川が運搬してきた土砂や堆積物が、河口や湖などの水域に堆積して形成される地形のこと(広島市内の河川の河口付近に形成) | 三角州 |
| 日本の最も北端に位置する都道府県は? | 北海道 |
| 海岸線に沿って行われる漁業のこと | 沿岸漁業 |
| 人口が急激かつ大幅に減少したため、地域社会の機能が低下し、住民が一定の生活水準を維持することが困難になった地域 | 過疎 |
| 温室やハウスなどの施設内で、気候や環境条件を人工的に調整しながら植物を栽培する方法 | 促成栽培 |
| 日本の都道府県の総数は? | 47 |
| 米の生産量が最も多い県 | 新潟県 |
| 落花生の生産量が日本一の県? | 千葉県 |
| 本州と北海道を結ぶトンネルの名称は? | 青函トンネル |
| 日本で最も人口の多い都道府県は? | 東京都 |
| 日本で最も少ない人口を持つ都道府県は? | 鳥取県 |
| 日本で最も面積が広い都道府県は? | 北海道 |
| 日本で最も人口密度の高い県は? | 神奈川県※(県で聞かれている引っ掛け問題)都道府県で聞かれた場合は、東京都 |
| 北海道の先住民族を何と呼ぶか。 | アイヌ民族 |
| 山陰地方にある日本有数の砂丘は何か。 | 鳥取砂丘 |
| 山の斜面などで階段状につくられた田を何というか。 | 棚田 |
| 九州の日本海側を流れる暖流を何というか。 | 対馬海流 |
| 九州の太平洋側を流れる暖流を何というか。 | 黒潮(日本海流) |
| 愛知県南部から三重県北部にまたがる工業地帯 | 中京工業地帯 |
おすすめ塾
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
オンライン個別指導そら塾
※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師マナリンク
※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!
オンラインプロ教師のメガスタ!
※圧倒的な合格実績を誇る!学生講師からプロ講師まで多数在籍!きっと生徒にピッタリの講師が見つかるはずです。
トライのオンライン個別指導塾
※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!
オンライン家庭教師WAM
※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!
オンライン家庭教師ナイト
※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!
家庭教師の銀河
※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
部活が忙しくても内申点対策できる:中学生オンライン個別指導塾おすすめ20選ハイレベル対策から苦手克服まで
【日本の歴史】高校入試の社会によく出る問題
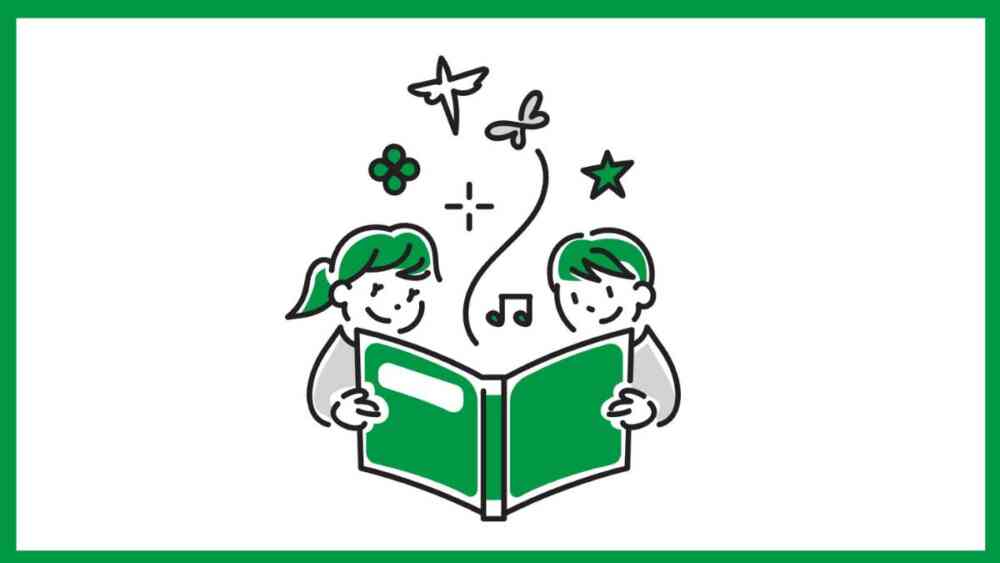

日本の歴史でよく出る問題を30個まとめてみました。
以下、大切なポイントです。
| 戦国時代、織田信長が本能寺で暗殺された年は? | 1582年 |
| 室町幕府が崩壊した後、戦国時代を経て天下統一を果たしたのは? | 豊臣秀吉 |
| 聖徳太子が制定した役人の心得 | 17条憲法 |
| 江戸時代、日本の国内で外国との交流を行った港は? | 出島 |
| 日本に初めてキリスト教を伝えた人 | フランシスコ・ザビエル |
| 1192年に征夷大将軍になった人物 | 源頼朝 |
| 豊臣秀吉や徳川家康が行った官制の貿易で、日本船に渡航許可証を与えて行った外国との貿易を何というか? | 朱印船貿易 |
| 630年に日本が唐に派遣した使節 | 遣唐使 |
| 島原の乱が起こった年 | 1637年 |
| 1867年、徳川慶喜が徳川幕府の政権を朝廷に返上したことを何というか? | 大政奉還 |
| 1881年に結成された自由党の党首は誰か? | 板垣退助 |
| 1910年、日本が韓国を併合したことを何というか? | 韓国併合 |
| 大正時代に日本国内で高まった、民主主義の風潮や運動を何というか? | 大正デモクラシー |
| 日中戦争の長期化に伴い、1938年に公布された、国家の全ての人的・物的資源を政府が統制して運用できるようにした法律を何というか? | 国家総動員法 |
| 江戸幕府が成立する年 | 1603年 |
| 静岡県静岡市駿河区登呂にある、弥生時代後期の集落遺跡 | 登呂遺跡 |
| 江戸幕府が諸大名の統制のために制定した基本法 | 武家諸法度 |
| 1774年に出版された、日本初の西洋医学書の翻訳書 | 解体新書 |
| 織田信長が京都の本能寺で家臣の明智光秀に謀反を起こされて殺害された事件 | 本能寺の変 |
| 1467年から1477年にかけて京都を中心に繰り広げられた内乱 | 応仁の乱 |
| 鉄砲が伝来した島 | 種子島 |
| 江戸時代の幕府による、江戸から大坂への物資輸送を円滑に行うための太平洋沿いの道路を何というか? | 東海道 |
| 関ヶ原の戦いが起きた年 | 1600年 |
| 江戸幕府の第5代将軍・徳川綱吉によって制定された、動物保護を目的とした法令 | 生類憐れみの令 |
| 戦後、日本の憲法が制定された年は何年か? | 1947年 |
| 幕末の動乱期に活躍し、薩摩藩から長州藩に亡命した人物は誰か? | 坂本竜馬 |
| 江戸城桜田門外で、水戸藩士を中心とする尊皇攘夷派の浪士たちが、幕府の大老・井伊直弼を暗殺した事件 | 桜田門外の変 |
| 明治時代に行われた、新しい国号を制定し、皇室の神聖性を強調した出来事を何というか? | 明治維新 |
| 明治時代に日本が近代化を推進するために行った、西洋からの専門家を招聘し、技術や制度を導入した政策を何というか? | 文明開化 |
| 1905年(明治38年)、日露戦争の講和条約として、日本とロシアとの間で締結された条約 | ポーツマス条約 |
参考記事:【高校入試理科】よく出る問題!一問一答形式で120問(生物・地学・物理・化学)
おすすめ塾
参考記事:【必見】オンライン塾の選び方|失敗しない7つのポイントを徹底解説
【公民】高校入試の社会によく出る問題
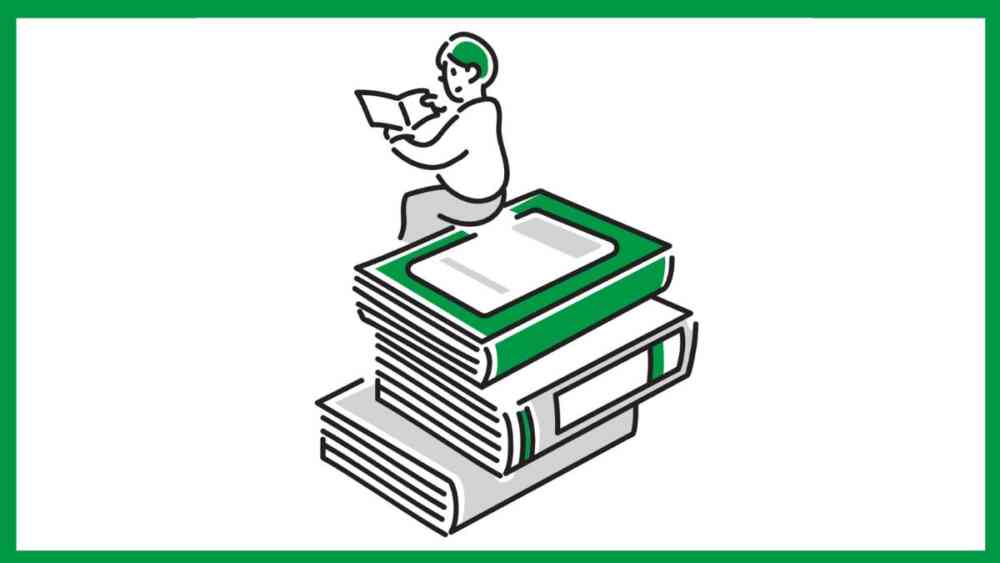

公民でよく出る問題を30個まとめてみました。
以下、大切なポイントです。
| 少子化と高齢化が同時に進行すること | 少子高齢化 |
| 立法権、行政権、司法権の三つの権力を、それぞれ独立した機関に分担させ、互いに抑制し合うことで、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する政治制度 | 三権分立 |
| 国民の三大義務とは、納税の義務・勤労の義務ともう1つは何か。 | 教育の義務 |
| 憲法を守り、国民の権利と自由を保障する役割を担う機関、憲法の番人とは? | 最高裁判所 |
| 行政府の主体たる内閣を議会の信任によって存立させる政治制度 | 議院内閣制 |
| 憲法第41条によって、「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定められています。 | 国会 |
| 国民が政治的な意思決定や政策の形成に直接参加する形態の民主主義 | 直接民主制 |
| 裁判官が裁判を行うにあたって、国会からも内閣からも干渉を受けないという原則がある。この原則を何というか。 | 裁判所の独立 |
| 地域住民の手によってそれぞれの地域の政治が行われることを何というか。 | 地方自治 |
| 一般の人々の考えや意見、感じていることを示すもの | 世論 |
| 日本の中央銀行であり、国の通貨政策の中核を担っている銀行 | 日本銀行 |
| 個人や法人の所得や資産に直接かかる税金のこと | 直接税 |
| 株主が、自身の出資した会社が利益をあげたときに得られるお金を何と言うか。 | 配当 |
| 仕事と家庭生活を両立させることを何というか。 | ワークライフバランス |
| 需要量が供給量を上回ったとき、価格はどうなるか。 | 上昇する |
| 個人や家族、コミュニティの福祉や幸福を促進し、社会全体の公正や平等を追求するための活動や政策、制度 | 社会福祉 |
| 国民の福祉の向上を国家の重要な責務とし、社会保障制度などを通じて国民の生活を保障しようとする国家 | 福祉国家 |
| 国際平和や安全を維持するために、国連総会または安全保障理事会の決議にもとづいて行われる活動を何というか。 | 平和維持活動 |
| 発展途上国の支援や環境破壊などの問題に対して、市民が自主的に活動する非政府組織の略称を何というか。アルファベットで答えよ。 | NGO(Non-Governmental Organization) |
| 限りある資源を効率的に利用し、将来にわたって使い続けていく社会を何というか。 | 持続可能な社会 |
| 国際連合(UN)の日本語表記を答えよ。 | 国際連合(United Nations) |
| 個人または団体がその方針や意図を広く多数の者に向かって知らせるための文書や演説。 声明文(せいめいぶん)・宣言書(宣言)を意味する外来語。 | マニフェスト |
| 国会の中に設置されている予算の審議をする委員会 | 予算委員会 |
| 政府の行政機関が広報活動や情報提供を行うための手段として、国民に対して提供する情報を何というか。 | 公報 |
| 国際的な協力と平和を促進し、国際紛争の平和的解決を目指す国際機関を何というか。 | 国際連合(UN) |
| 日本国憲法第9条が規定する内容を簡潔に述べよ。 | 戦争の放棄と武力の行使の否定 |
| 政府が市民に提供する様々なサービスや支援を総称して何というか。 | 公共サービス |
| 国の予算案を審議し、承認するための議会を何というか。 | 国会 |
| 憲法改正を行うためには、どの議会で何割の賛成が必要か。 | 両議会で3分の2以上の賛成 |
| 憲法改正が成立した場合、どの選択肢が実施されるか。 | 国民投票 |
関連記事
東大生が教えるオンライン塾おすすめ8選!入会金・料金を徹底比較
【オンライン塾】月謝が安い!中学生に人気15選!費用を安くするオンライン塾
社会の勉強はタブレット学習教材が中学生におすすめな理由
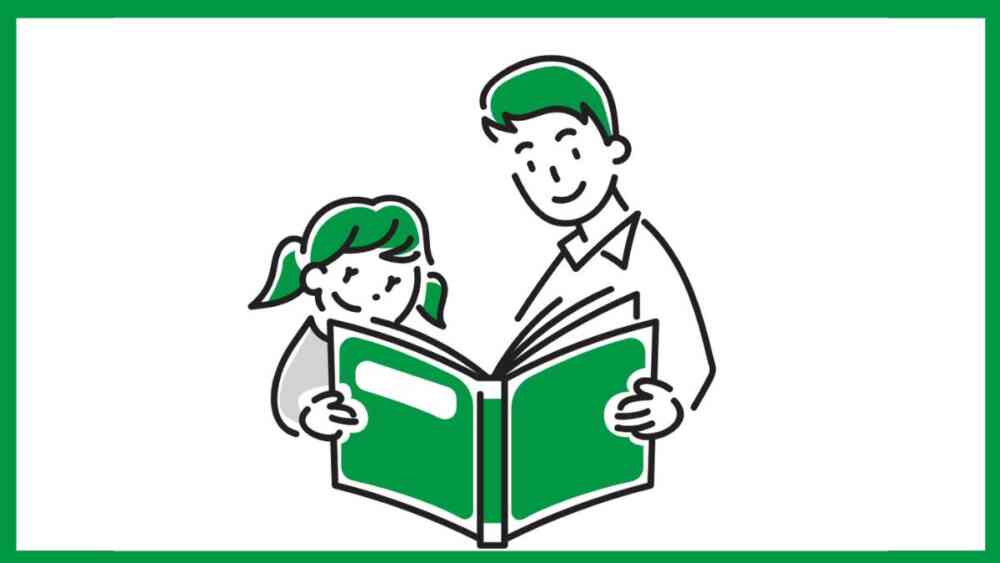
中学生の社会の勉強は、タブレット学習教材で勉強するのも良い方法。
なぜなら、タブレット学習教材を利用することで、ゲーム感覚で集中して学習できるからです。
タブレット学習教材には、学校の授業内容を予習・復習できるものや、苦手な分野を克服するためのものなど、さまざまな種類があります。
また、中学生の学年や学習レベルに合わせて選べるため、中学生一人ひとりに合った学習ができます。
タブレット学習教材は、中学生がゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な中学生でも楽しく学習できるでしょう。
また、タブレット学習教材には、中学生の学習状況を保護者が確認できる機能が付いているものもあるので、中学生の学習進捗を把握できます。
以下は、中学生向けのタブレット学習教材のおすすめポイント。
・学校の授業内容を予習・復習できる
・苦手な分野を克服できる
・中学生の学習レベルに合わせて選べる
・中学生がゲーム感覚で学習できる
・保護者が子どもの学習状況を確認できる
タブレット学習教材は、勉強が嫌いな中学生、学校の授業に遅れを取っている中学生や、勉強が苦手な中学生にもおすすめです。
中学生におすすめタブレット学習教材比較表
| タブレット学習教材名 | 月謝 | 特長 |
| 進研ゼミ:中学講座 | 中学1年生:6,400円〜 | ベネッセが提供している、タブレット学習教材。中学生の利用者数No.1。 |
| すらら | 小中コース 8,800円〜 | AI×アダプティブラーニング「すらら」、マナブをサポートする最先端学習システム。小学生から高校生まで、国・数・理・社・英の5教科を学習できるICT教材 |
| スマイルゼミ | 7,480円〜 | 「まなぶ」「みまもる」「たのしむ」の3つのバランスを大切にして、勉強したい気持ちを逃さない。 |
| デキタス | 中学生:5,280円〜 | 勉強嫌いでも、勉強が習慣化できる!おすすめのタブレット学習教材 |
※オンライン料金の詳細については公式サイトからお問い合わせください。※社名をタップすると公式ホームページに移動します。
※学年や講師ランク・授業時間により料金は変動します。
進研ゼミ:中学講座は中学生におすすめの教材
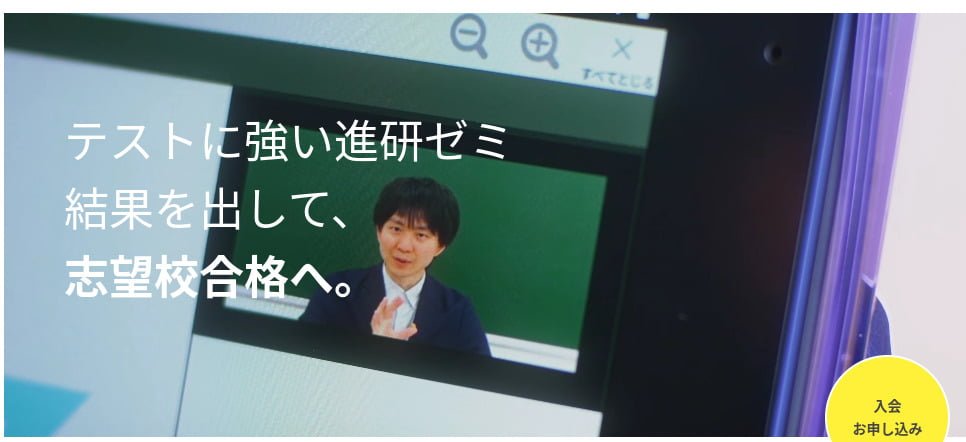
中学生利用者NO.1!進研ゼミ:中学講座の基本情報
| 月謝 | 【月謝例】 中学1年生:6,400円〜 中学2年生:6,570円〜 中学3年生:7,090円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、理科、社会、英語 |
| 学習機能 | 教科書対応のテキストで、予習も復習もバッチリ! お使いの教科書に合わせたテキストなので、予習はもちろん復習にも効率的に |
| 管理機能 | AIのレッスン提案で迷わない実力に合わせて学習スタート 学習達成後のごほうびでやる気が続く |
| サポート体制 | 月1回、赤ペン先生がお子さま一人ひとりを添削し、丁寧に指導。担任制なので、毎回同じ先生に提出する楽しみがうまれ、毎月の学習の仕上げとしてしっかり取り組めます。 |
進研ゼミ中学講座の特長
進研ゼミ中学講座は、ベネッセコーポレーションが提供している中学生向けの通信教育です。
1969年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。進研ゼミ中学講座の特長は、以下の通りです。
- 学校の授業内容に沿った教材で、予習・復習が効率的にできる。
- タブレット学習を利用することで、ゲーム感覚で学習できます。
- 赤ペン先生による添削指導で、記述力や思考力を鍛えられる。
- 応用問題や演習問題で、実力を身につけられる。
- 夏休み特訓や冬期講習など、季節ごとの特別講座が充実。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、中学生の学習状況を把握できます。
進研ゼミ中学講座は、中学校の授業内容をしっかり学びたい、記述力や思考力を鍛えたい、夏休みや冬休みの学習を充実させたい、といった中学生におすすめです。
\中学生の利用者NO.1の通信教育/
安心して利用できる
↓↓↓
すらら:無学年方式オンライン教材

「すらら」の基本情報
| 受講費用の安さ | ■入会金 ・小中・中高5教科コース:7,700円 ・小中・中高3教科、小学4教科コース:11,000円 ■3教科(国・数・英)コースの月謝例 ・小中コース・中高コース 月額:8,800円〜 小学1年生~中学3年生までの3教科(国・数・英)の範囲が学び放題 |
| 対応科目・コース | 4教科(国・数・理・社)コース 5教科(国・数・理・社・英)コース 無学年方式で中学英語も先取り学習できる |
| 学習機能 | キャラクターによるレクチャーからドリル機能が充実 「すらら」は読み解くだけではなく、見て、聞いて学べる |
| 管理機能 | 「すらら」はAI搭載型ドリルだから自分のつまずきポイントがわかる! |
| サポート体制 | 学習習慣の身に付け方を始めとした学習に関する悩みや、基礎学力、成績を上げるための学習設計をサポートします。 |
すららの特長
すららは、株式会社すららネットが提供している中学生向けのオンライン学習教材です。
2010年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
すららの特長は、以下の通りです。
- 学年にとらわれない無学年方式で、中学生のペースに合わせて学習できます。
- 中学生の弱点をAIが自動診断し、苦手な分野を効率的に克服できます。
- ゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な中学生でも楽しく学習できます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、中学生の学習状況を把握できます。
すららは、学習に苦手意識を持っている中学生や、効率的に学習を進めたい中学生におすすめです。
当サイトで人気No.1の通信教材!
是非!すららを選択肢の一つに
↓↓↓
スマイルゼミ:最適な学びが継続するタブレット教材
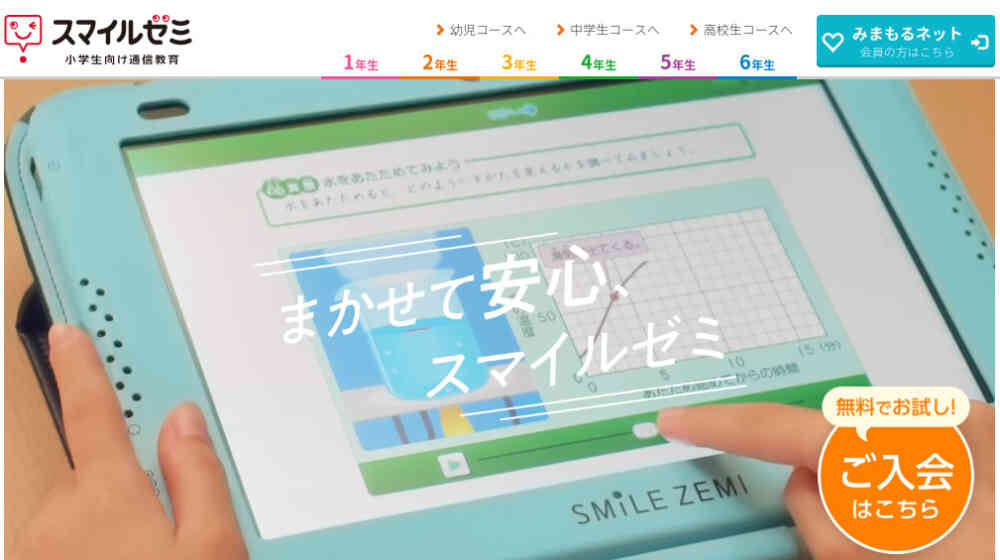
スマイルゼミの基本情報
| お手軽な受講費用 | 【中学1年生】月謝例 <標準クラス> ・7,480円〜:12か月一括払い/月あたり |
| 対応科目・コース | 国語・数学・理科・社会はもちろんのこと、英語やプログラミングも1年生から学習できる |
| 学習機能 | アニメーションによる解説で公式の持つ意味を正しく理解できる 手をついて書ける学習専用タブレットを使用 |
| 管理機能 | スマイルゼミのタブレットは、利用時間を「1日〇時間」という形で制限可能 |
| サポート体制 | 全額返金保証制度あり |
スマイルゼミの特長
スマイルゼミは、ジャストシステムが提供している中学生向けのタブレット学習教材。
2012年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
スマイルゼミの特長は、以下の通りです。
- タブレット端末を使って学習できるので、ゲーム感覚で楽しく学べます。
- 中学生の学習状況をAIが分析して、一人ひとりに合った学習内容を自動的に提案してくれます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、中学生の学習状況を把握できます。
スマイルゼミは、学習に苦手意識を持っている中学生や、効率的に学習を進めたい中学生におすすめです。
中学生の学びが継続するタブレット
\返金保証制度あり/
↓↓↓
中学生の社会の勉強に最適なタブレット教材:デキタス
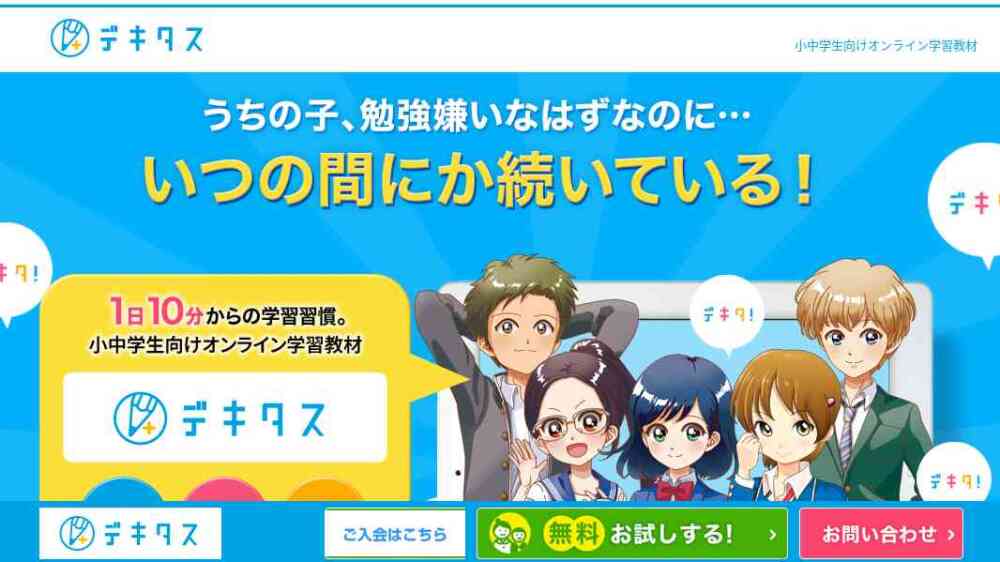
中学生におすすめ!デキタスの基本情報
| 項目 | デキタスの公式サイト |
| 受講費用 | 中学生:5,280円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、地理、歴史、公民、国文法、英語検定 |
| 学習機能 | ポップなキャラクター&わくわくする授業! |
| 管理機能 | テストモード搭載 |
| サポート体制 | 学習結果は表・グラフ・カレンダー等でひと目で確認することができます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
教科書の内容を確実に理解
学校の成績が上がる!
↓↓↓
デキタスの公式サイトチェック!
デキタスのおすすめポイント
学校の勉強を確実に理解していくことを目指し開発された、小中学生用オンライン学習教材です。
教科書内容に合った映像授業や、演習問題。さかのぼり学習で前の学年前の授業に戻ったり、定期テスト問題を作成して挑戦したりと、学校の勉強を自宅で、自分のペースで自由に行えます。
以下にデキタスの特徴を3つ紹介します。
段階的な学習体系: デキタスは「授業」→「○×チェック」→「基本問題」→「チャレンジ問題」というスモールステップで構成され、基礎から応用まで段階的に学習が進められます。この体系により、生徒は小さな成功体験を積み重ねながら学習し、「デキタ!」の達成感を実感できます。
デキタ'sノートと複合学習: デキタスでは授業に沿った穴埋め式ノートが印刷可能であり、デジタル教材と紙と鉛筆を組み合わせて効果的な学習ができます。この複合学習により、視覚的なデジタル学習と手書きによるノート作成が組み合わさり、理解の定着が促進されます。
学習習慣の形成: デキタスは学習結果を表・グラフ・カレンダーで確認し、保護者と共有する機能があります。親子で学習状況を共有し、成績アップを目指すことで学習習慣が自然に形成されます。
教科書の内容を確実に理解
学校の成績が上がる!
↓↓↓
おすすめ塾
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
オンライン個別指導そら塾
※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師マナリンク
※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!
オンラインプロ教師のメガスタ!
※圧倒的な合格実績を誇る!学生講師からプロ講師まで多数在籍!きっと生徒にピッタリの講師が見つかるはずです。
トライのオンライン個別指導塾
※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!
オンライン家庭教師WAM
※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!
オンライン家庭教師ナイト
※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!
家庭教師の銀河
※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
まとめ:【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)

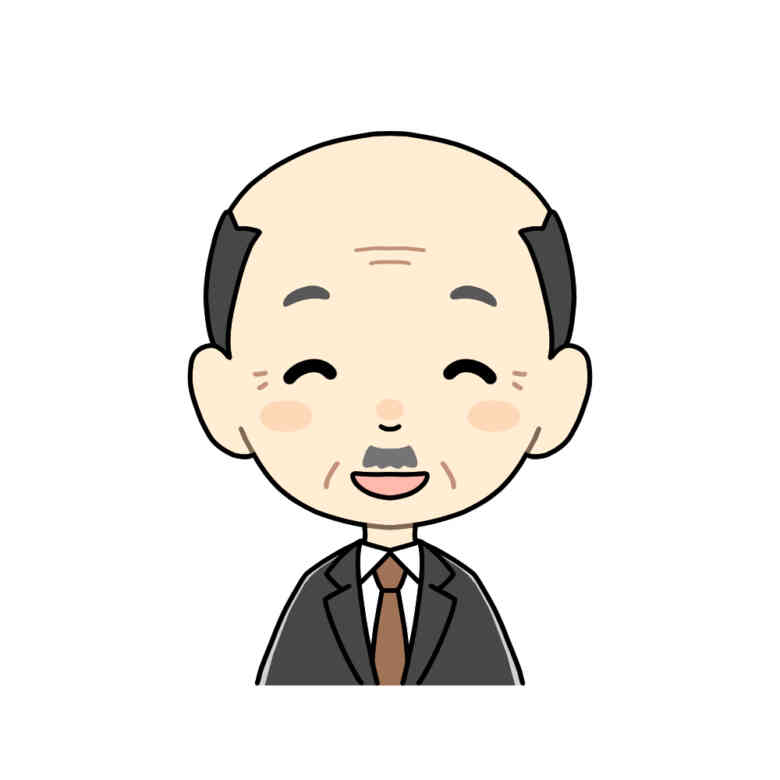
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今回の記事、「【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)」は参考になりましたか?
高校入試の社会でよく出る問題についてよくわかりました。

以上、「【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)」でした。
まとめ:【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)
まとめ
高校入試社会】よく出る問題のまとめです。
地理、歴史、公民の各分野から選ばれた120問の一問一答形式です。
この社会の一問一答は、高校入試で頻繁に出題される重要なトピックに焦点を当てています。
地理では、日本や世界の地形や気候に関する問題が、歴史では日本史や世界史の主要な出来事と人物に関する問題が、公民では政治や経済、社会問題に関する問題が含まれています。
これを通じて、幅広い知識と理解が求められ、高校入試に備えるための有用な資料となるでしょう。
高校入試対策の記事
高校入試対策の記事
高校入試におすすめ塾の紹介
オンライン塾


