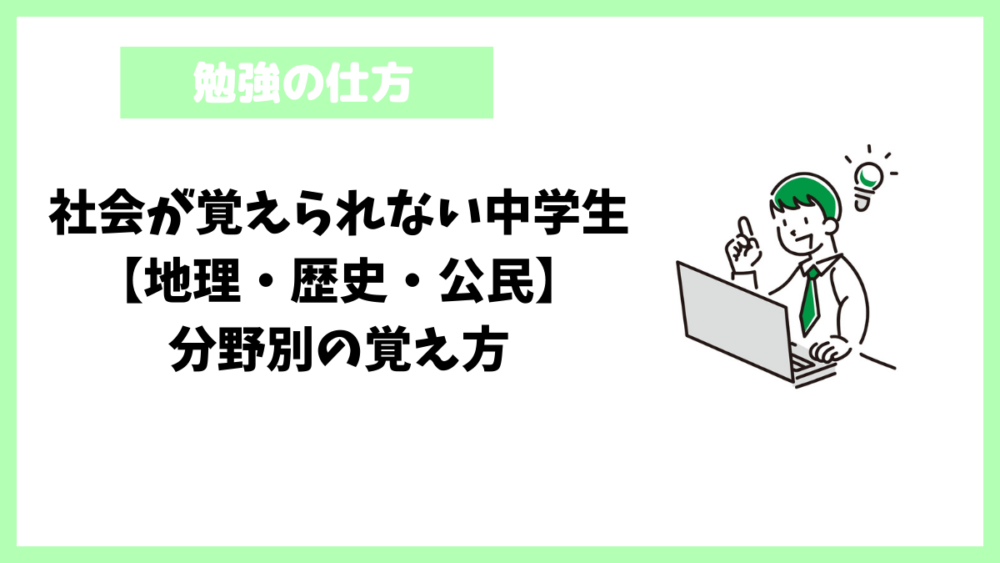
「※この記事には一部PRが含まれます」
塾オンラインドットコム「合格ブログ」です。
小学生と中学生向けに、勉強に役立つ情報を発信している教育メディアです。
今回のお悩みはこちら。

社会が覚えられない中学生です。
社会の覚え方を教えてください
中学生の社会はコツさえ覚えれば簡単!
今回は、中学生の社会の覚え方について紹介します。

中学生の社会の勉強法って気になりますよね?
実は、今回紹介する「社会が覚えられない中学生【地理・歴史・公民】分野別の覚え方」を読めば、社会の分野別の覚え方がわかります。
なぜなら、社会の勉強法として、生徒に実践していた内容だからです。
この記事では、中学生の社会の覚え方(地理・歴史・公民)を具体的に紹介しています。
記事を読み終わると、社会の勉強に役立つ内容になっています。
読み終えるとわかること
中学生の社会の勉強の仕方
中学生の地理の覚え方
中学生の歴史の覚え方
中学生の公民の覚え方
社会勉強におすすめ!タブレット学習教材の紹介
効率よく成績を上げたいのであれば!東大生と東大院生の指導が受けられる!「トウコベ:東大生のオンライン個別指導」がおすすめです。
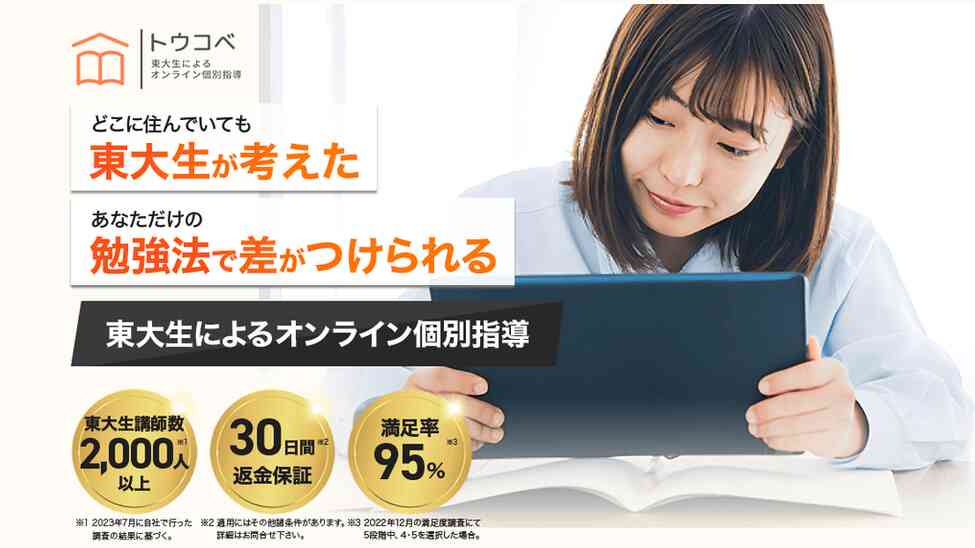
東大生と東大院生から教えてもらえると高額のイメージがありますが、なんと!月額9,900円〜から!低料金で高品質の授業が受けられます。
参考記事:【トウコベ】口コミ・評判を徹底解説!知っておきたい口コミの真実
Contents
社会が覚えられない中学生【地理・歴史・公民】分野別の覚え方
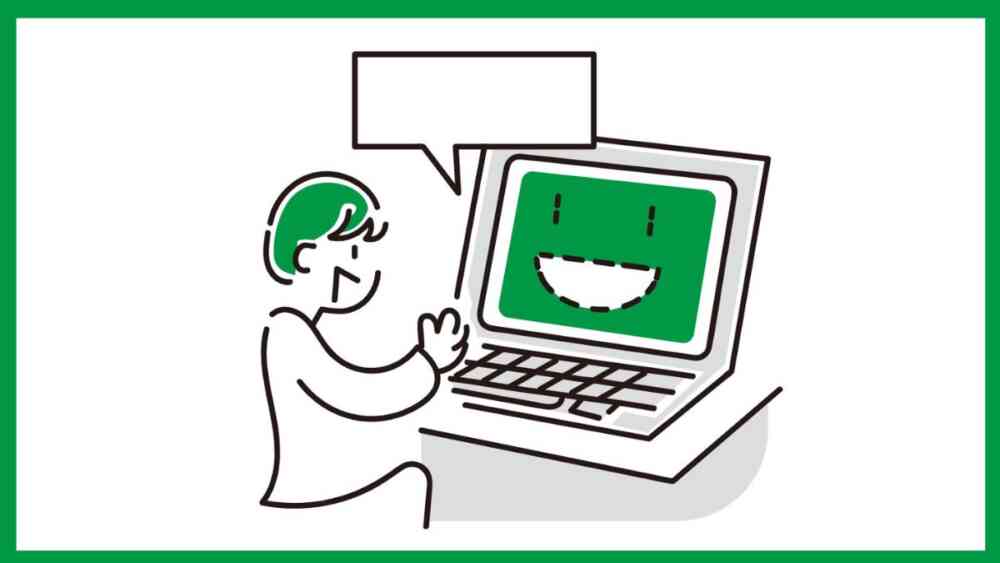

社会の勉強の基本についてまとめてみました。
以下のポイントについて説明しています。
- 社会は暗記科目ですか?
- 中学生が効率よく暗記する方法は?
- 社会の教科書をよく読み覚える
- 確認テストを実施する
社会は暗記科目ですか?
中学生の社会は暗記科目になります。
なぜなら、定期テストでは、社会の知識を問われる問題が多く出題されるからです。
そのため、暗記が得意な中学生は社会のテストで点数が稼げます。
一方、社会が苦手な中学生は、社会の勉強法や暗記の仕方がわからない事が多いのも事実です。
社会は暗記することで一定の点数を取れるため、暗記の仕方を覚えることが大切になります。
暗記の仕方を覚えることで、社会の勉強が楽しくなり、社会の成績が上がることを願っています。

中学生が効率よく暗記する方法は?
中学生の社会は、暗記が重要な勉強法の一つです。
しかし、単に用語を詰め込むだけでは、なかなか頭に入ってきません。
そこで、ここでは中学生が社会を効率よく暗記する方法をいくつかご紹介します。
1.五感を刺激する
暗記は、複数の感覚を刺激することで効果がアップします。
社会の場合、以下の方法が有効です。
- 声に出して読む:教科書や資料集の内容を声に出して読むことで、視覚と聴覚の両方の刺激を与えられます。
- 書き写す:手書きでノートに書き写すことで、運動感覚と視覚の刺激を与えられます。
- 図やイラストを活用する:図やイラストを活用することで、視覚的に情報を理解しやすくなります。
- 動画を見る:社会に関する動画を見ることで、視覚と聴覚の刺激を与えられます。
2.関連付けして覚える
バラバラの情報を覚えるよりも、関連付けして覚える方が効率的です。例えば、歴史上の人物であれば、その人物が活躍した時代や事件と関連付けて覚えると良いでしょう。
自分に合った方法を見つけて、楽しみながら社会を勉強しましょう。

社会の教科書をよく読み覚える
社会の勉強法の基本は、教科書を繰り返て読んで暗記すること。
理由は、中学生の定期テストは教科書を中心に出題されるからです。
教科書を繰り返し読んで重要語句を暗記することで、定期テストには十分対応できます。
社会の成績を上げるためには、教科書の内容をしっかりと把握して、重要語句を暗記することがとても重要となります。
教科書は一度読んだだけでは暗記できないので、教科書を覚えるコツとしては、最低7回は読むようにしてください。
なぜなら、「教科書7回読み勉強法」というのがあるからです。
覚えられない場合は、声に出して音読したほうが効率的に内容を記憶できることもあります。
これは声に出して読むことで、五感が刺激され、脳が活発になると言われています。
また、重要語句を書いて覚える方法もあります。
社会の勉強法で最も大切なのは、教科書を何度も反復して勉強するということです。
自分にあった覚え方をマスターして、繰り返し読んで教科書を暗記してください。

参考記事:社会の点数を上げる方法中学生編│目指せ90点以上!テスト勉強の仕方
確認テストを実施する
教科書を繰り返して読んで暗記したならば、次は確認テストの実施です。
確認テストを実施する理由は、覚えたことが確実に暗記できているかを確認して、覚えたことを社会の学力として定着させるためです。
その場では覚えていたけれど、時間が経つと忘れてしまう、そんな経験はありませんか?
確認テストで覚えたことを毎回確認し暗記の徹底を図ります。
確認テストは学校のワークなどでやるのがおすすめです。
授業で使っているので定期テスト対策にもなるからです。
「教科書をよく読んで覚える」→「覚えた内容を確認する」この繰り返しで社会の知識が身につきます。
社会の勉強法で最も大切なのは、何度も反復して勉強するということです。
一度覚えた内容も、すぐに忘れてしまっては意味がありません。
それを防ぐのが反復学習です。
中学生におすすめ!
森塾のオンライン部門!オンライン個別指導生徒数No.1のそら塾
※保護者が選ぶオンライン学習塾NO.1を獲得!しかも低料金!
成績保証と返金保証制度!安心して入会できる!オンライン家庭教師WAM
※難関大の講師が生徒に寄り添い成績アップ!プラス20点の成績保証!
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師は全員東大生・東大院生!最高レベルの授業がこの価格で実現!
参考記事:【そら塾の口コミ・評判】ひどい?塾経験者が徹底調査した結果は?
中学生の社会(地理)の点数を上げる方法


中学生の社会科学習の出発点として、地理の基本を掘り下げていきましょう。
地理は世界を理解する鍵となります。
以下のポイントについて説明しています。
- 地理の勉強の基本:教科書の重要語句の暗記と理解
- 中学生の地理:地図の勉強法
- 地理の要点を覚えるテクニック
- 地理クイズとゲーム:学習の楽しさを取り入れる方法
- 地理の勉強のポイント
地理の勉強の基本:教科書の重要語句の暗記と理解
地理の学習において、教科書の重要語句を暗記することは基本中の基本です。
中学生にとって、地理は暗記科目というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、ただ闇雲に用語を詰め込むだけでは、すぐに忘れてしまいます。
そこで、ここでは教科書の重要語句を効率的に暗記し、理解を深めるためのポイントをご紹介します。
地理の用語を分類する
地理の用語は、大きく分けて以下の3種類に分類できます。
- 場所を表す用語:山脈、河川、都市、国名など
- 現象を表す用語:気候、植生、農業、工業など
- 人々の活動を表す用語:貿易、交通、観光など
まず、用語をこの3種類に分類することで、体系的に覚えることができます。
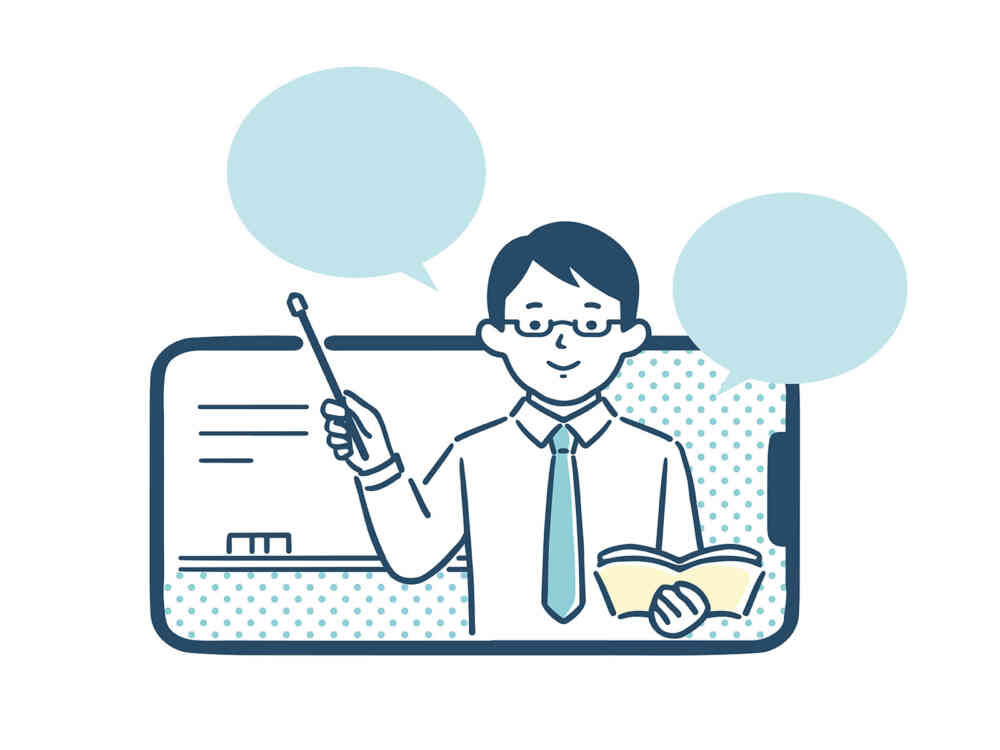
参考記事:【高校入試社会】よく出る問題!一問一答形式で120問(地理・歴史・公民)
中学生の地理:地図の勉強法
地図は、社会科や理科で学習するだけでなく、日常生活においても様々な場面で役立ちます。
ここでは中学生が地図の読み方を効率的に学習するためのポイントをご紹介します。
- 地図記号の理解:地図上のシンボルや記号を解釈し、地理的な要素や特徴を識別します。
- 縮尺の把握:地図の縮尺を理解し、実際の距離と地図上の距離を関連づけます。
- 方位の確認:北、南、東、西などの方位を把握し、地図上での方向を正確に特定します。
- 高低差の理解:標高線や等高線を読み取り、地形の高低差を理解します。
- 地図の種類の認識:さまざまな地図種類(物理地図、政治地図、気象地図など)を識別し、目的に合った地図を選択します。
地図は地理学習の不可欠なツールであり、場所の把握や地理的な関係の理解に役立ちます。
地図の読み方は、日々の練習によって上達します。
地図を身近な存在にして、色々な場面で活用してみましょう。

地理の要点を覚えるテクニック
地理学習を効果的に進めるための方法を紹介します。
関連付けながら覚える
バラバラの用語を覚えるのではなく、関連付けながら覚えることで、記憶が定着しやすくなります。
例えば、以下のような関連付けが考えられます。
- 場所と気候:熱帯雨林気候であれば、熱帯雨林が分布する。
- 場所と産業:沿岸部であれば、漁業が盛んである。
- 場所と文化:仏教徒が多い地域であれば、仏教寺院が多い。
用語を覚える際には、必ず関連する知識も一緒に覚えるようにしましょう。
地図を活用する
用語の意味を理解するには、地図を活用することが重要です。例えば、「山脈」という用語を覚える際には、実際に地図上で山脈を確認してみましょう。地図上で場所を確認することで、用語がよりリアルなものとして理解しやすくなります。
図表を活用する
地理の教科書には、図表が多く掲載されています。図表は、用語の意味を理解したり、地理的な関係性を把握したりするのに役立ちます。図表の説明をよく読み、理解を深めましょう。
これらのテクニックを組み合わせて、地理の要点を効果的に覚え、学習成果を向上させましょう。

地理の勉強のポイント
地理の学習のポイントは、周りの出来事と関連づけること。
理由は、周りの出来事と関連付けることで印象に残るからです。
例えば、会話の中で農産物の生産地を教えるだけで、中学生は覚えた知識を身近に感じ、自然に覚えるでしょう。
そして気候や地形は産業とも関係しており、気候・地形・産業の知識が線でつながった時は「面白い」と感じ、地理への興味が高まる可能性があります。
地理の重要語句は関連付けて覚えることをおすすめします。
【地図を見ながら勉強】
地理の勉強は、農産物や気候のことがよく出てきたり統計資料やグラフなどが出てきます。
こういった問題に対応するには、農作物がどこで作られているのか?地図上のどこなのか?などが分かっていないと、解答を導けません。
したがって、地名の暗記も地理の勉強には必要です。
その際に地図と地名をリンクさせて覚えるのがポイントです。
学校の教科書や地図帳を参考にして、地名や地形、気候などと一緒に場所も一緒に暗記していきます。
一度に全部の地名を覚えていくことは大変です。
しかし、地図と関連付けることで効率よく覚えられます。
地理は地図帳を片手に勉強するのがおすすめです。
【記述問題に慣れる】
地理は教科書を覚えていけば、問題集の正答率も上がってくると思います。
地理でさらに得点を伸ばしたい場合は記述問題に取り組むのがポイントです。
入試などでは資料に関する記述問題が出題される傾向にあるので、記述問題をしっかり学習する必要があります。
記述問題が苦手な場合は、それほど多くの時間を費やす必要はありません。
入試で地理の得点を伸ばしたければ記述問題にも積極的に取り組んでください。
参考記事:【必見】オンライン塾の選び方|失敗しない7つのポイントを徹底解説
中学生の歴史の覚え方
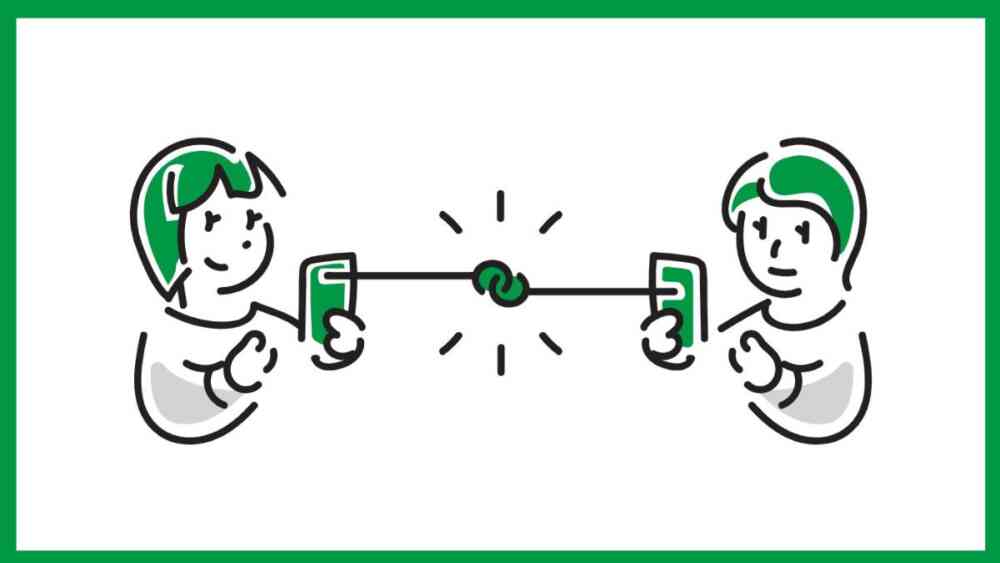

歴史学習に焦点を当て、過去の出来事と人々を探求します。
以下のポイントについて説明しています。
- 中学生が歴史を楽しく学ぶコツ
- 中学生が歴史の教科書を効率的に勉強する方法
- 中学生が歴史上の人物と出来事を効率的に覚える方法
- 定期的に復習する
- 歴史の勉強のポイント
中学生が歴史を楽しく学ぶコツ
歴史は暗記科目と思われがちですが、単に過去のことを覚えるだけでなく、人間社会のしくみや変化を理解する科目です。
ここでは中学生が歴史を楽しく学ぶためのコツをご紹介します。
時代区分をストーリーとして捉える
歴史は、まるで一つの大きな物語のように、時代ごとに様々な出来事が起こっています。例えば、江戸時代であれば、政治、経済、文化など、様々な側面から江戸時代の様子をストーリーとして捉えてみましょう。
重要人物を主人公として考える
歴史上には、様々な人物が登場します。教科書や資料集で示されている重要人物を主人公として、その人物がどのような行動をしたのか、なぜそのような行動をしたのかを考えてみましょう。まるで歴史小説を読むような感覚で、人物の生き様を追いかけてみるのも面白いです。
出来事を漫画やアニメで想像してみる
歴史上の出来事を、漫画やアニメのストーリーのように想像してみるのも効果的な学習方法です。例えば、桶狭間の戦いであれば、織田信長と今川義元がそれぞれどんな作戦を立てていたのか、戦場の様子はどのようなものだったのかを想像してみましょう。
歴史は、単に過去のことを学ぶだけでなく、現在や未来を考えるためのヒントを与えてくれます。
主体的に学習に取り組むことで、より深い理解と教養を身につけることができます。

中学生が歴史の教科書を効率的に勉強する方法
歴史の教科書は、単に暗記するだけでなく、理解して学習することが重要です。
しかし、多くの情報が詰め込まれており、どのように学習を進めれば良いのかわからない中学生も多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは中学生が歴史の教科書を効率的に勉強し、理解を深めるための方法をご紹介します。
授業をしっかり聞く
授業中は、先生の説明に集中し、ノートを丁寧に取るようにしましょう。わからないことがあれば、積極的に質問しましょう。
教科書を読み込む
授業で習った内容を復習するために、教科書をじっくりと読み込みましょう。重要なポイントやキーワードに線を引いたり、マーカーで囲ったりして、目立たせておくと効果的です。
年表を活用する
歴史の流れを理解するために、年表を活用しましょう。年表を見ながら、教科書の内容を整理してみましょう。
図表や写真を読み解く
教科書には、図表や写真がたくさん掲載されています。これらの図表や写真は、文章だけでは理解しにくい内容を解説するのに役立ちます。図表や写真を見ながら、説明文をよく読むようにしましょう。
まとめノートを作る
教科書の内容を自分なりにまとめたノートを作ることで、理解を深めることができます。ノートには、重要なポイントだけでなく、自分の感想や疑問なども書き込んでおくと良いでしょう。
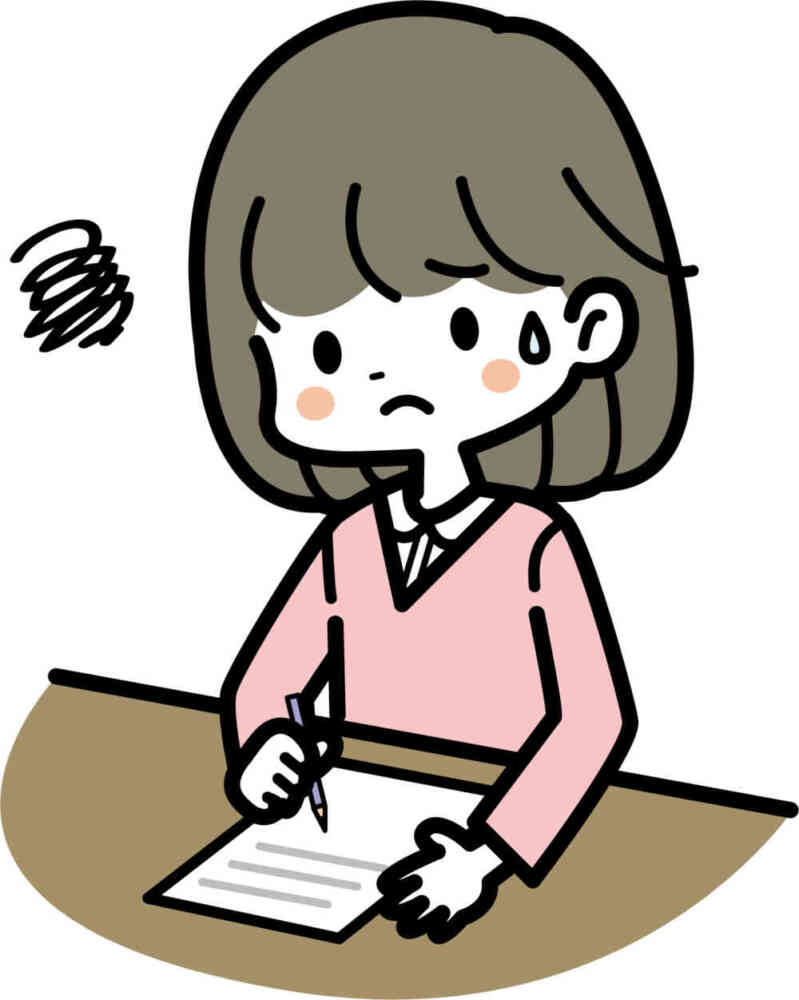
参考記事:【英語がわからない中学生】超簡単!ゼロから理解できる勉強法を解説
中学生が歴史上の人物と出来事を効率的に覚える方法
歴史上には、多くの人物と出来事があり、中学生にとって覚えるのは大変と感じるかもしれません。
しかし、効率的な方法を意識することで、無理なく記憶し、理解を深めることができます。
関連付けながら覚える
バラバラの人物や出来事を覚えるのではなく、関連付けながら覚えることで、記憶が定着しやすくなります。例えば、
- 政治家であれば、その人物が活躍した時代や政治体制、行った政策などを関連付けて覚える。
- 文化人であれば、その人物の代表的な作品や思想、時代の背景などを関連付けて覚える。
- 出来事であれば、その出来事の原因や結果、影響などを関連付けて覚える。
- このように、人物や出来事と関連する情報を一緒に覚えることで、より深い理解につながります。
語呂合わせやストーリーを活用する
語呂合わせやストーリーは、覚えにくい名前や年代を楽しく覚えるのに役立ちます。例えば、
- 年号であれば、「明治維新:1868年(イッパイロクハチ)」のように、数字を語呂合わせにする。
- 人物名であれば、「織田信長:オダノブナガ(おだのぶなが)」のように、名前の頭文字をとる。
- 出来事であれば、「黒船来航:ペリー提督が黒い船で来航した」のように、ストーリー形式で覚える。
- 自分に合った語呂合わせやストーリーを考えて、楽しみながら記憶しましょう。
イメージ図や年表を活用する
イメージ図や年表は、人物や出来事の関係性や流れを視覚的に理解するのに役立ちます。
- イメージ図であれば、人物や出来事をイラストや記号で表し、矢印などで関係性を示す。
- 年表であれば、時間軸に沿って人物や出来事を並べ、重要なポイントに印をつける。
- イメージ図や年表を活用することで、頭の中を整理しやすくなり、記憶が定着しやすくなります。
個々の学習スタイルに合わせて、最適なアプローチを選択してください。

参考記事:中学生の暗記の苦手を解決!たった3つのコツで暗記が得意になる方法
定期的に復習する
定期的な復習は、学んだ知識を長期記憶に定着させるために重要です。
復習のタイミングとしては、学習した翌日、一週間後、一か月後といった具合に、間隔をあけて行うと効果的です。
これを「スパイラル学習」と呼びます。
また、復習の際には、ただノートを読み返すだけでなく、クイズ形式で自分に問いかけたり、他の人に説明する方法が有効です。
定期的な復習を習慣化することで、知識が確実に定着し、試験前の一夜漬けに頼らずに済むようになります。
これにより、学習の負担が軽減され、学びの楽しさを実感できるでしょう。
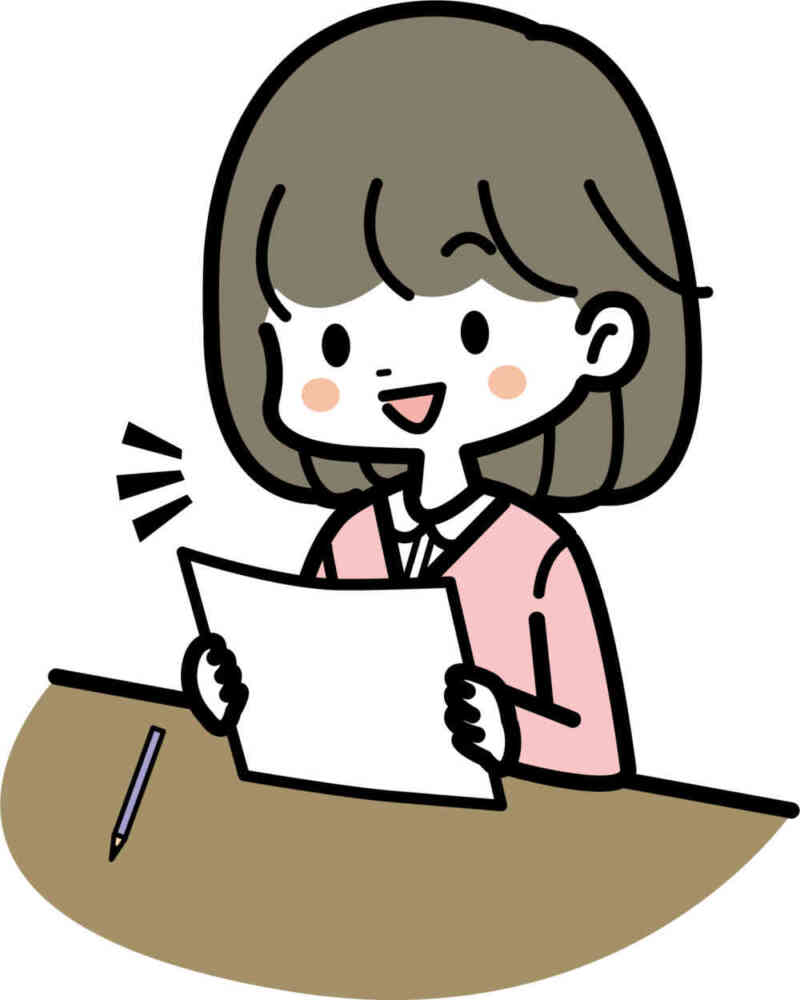
参考記事:社会の点数を上げる方法中学生編│目指せ90点以上!テスト勉強の仕方
歴史の勉強のポイント
中学生が歴史上の出来事を丸暗記しようとすると、途中で挫折をすることがあります。
そうならないためにも歴史の勉強のコツは、時代の流れや時代背景、因果関係を知ることで効率よく暗記できます。
出来事にはそれぞれつながりがあるため、時系列を整理して覚えるとすんなりと頭に入るものです。
しかし歴史上の出来事を個別に丸暗記しようとすると関連性がわからず、重要語句がバラバラになってしまうため、効率が悪くなります。
特に実力試験や高校入試の場合には全時代が出題の範囲になるので、時系列で時代のできごとをしっかりと押さえていかなければならないのです。
歴史の勉強のコツは、時代の流れや時代背景、因果関係を知ることが大切です。
【重要語句を暗記】
時代の流れを理解したなら、次は教科書の重要語句とその意味の暗記です。
暗記の方法は先ほど説明しましたが、人それぞれなので自分にあった暗記方法で覚えることがポイントです。
歴史で高得点を狙うためには、漢字を覚えるのも大切になります。
また、歴史上の出来事を語呂合わせで覚えるのも効果があります。
なぜなら、出来事を順番に並べ替えろという問題も出題されるからです。
教科書の重要語句を覚えることで高得点が狙えます。
【歴史の漫画を読んで勉強する】
中学生の歴史を勉強するために、歴史の漫画を読んで勉強するのもおすすめです。
理由は、漫画は絵がメインなので文字がメインの教科書と比べて、読みやすい点が挙げられます。
漫画は、時代背景や登場人物などが物語として説明されているので、頭に入りやすいのも特徴です。
したがって、漫画のほうが、すんなりと歴史の勉強ができる可能性があります。
しかし、漫画に夢中になって勉強時間が疎かになるケースもあるので注意が必要です。
そうならないためにも、時間を決めて漫画を読んで歴史を理解するのが良いでしょう。
オンライン家庭教師
塾より成績が上がる!オンライン家庭教師のWAM
※難関大学の講師が親切丁寧に指導!忙しい生徒にピッタリ!
短期間で成績向上!オンライン家庭教師:マナリンク
※動画でプロの講師が選べる画期的なシステム
リーズナブルな料金設定!オンライン家庭教師銀河
※中学生:1コマ30分:1,375円〜!お得に選ぶなら!銀河!
中学生の公民の覚え方


中学生の公民の勉強法について解説します。
- 中学生が公民の基本概念を効率的に覚える方法
- 公民の教科書を使った勉強法
- 中学生が政府の仕組みと機能を効率的に理解する方法
- 公民の勉強のポイント
中学生が公民の基本概念を効率的に覚える方法
公民の学習では、政治、法律、市民権など、抽象的な概念が多く登場します。
これらの概念を単に暗記しようとしても、すぐに忘れてしまう可能性があります。
ここでは中学生が公民の基本概念を効率的に覚え、理解を深めるための方法をご紹介します
関連付けながら覚える
バラバラの概念を覚えるのではなく、関連付けながら覚えることで、記憶が定着しやすくなります。例えば、
- 政治であれば、国家の仕組みや政治制度、選挙制度など、関連する概念を一緒に覚える。
- 法律であれば、民法、刑法、憲法など、代表的な法律の種類とその内容を一緒に覚える。
- 市民権であれば、基本的人権、政治参加権、経済活動権など、市民権の種類とその内容を一緒に覚える。
このように、関連する概念を一緒に覚えることで、より深い理解につながります。

公民の教科書を使った勉強法
中学生にとって、公民は暗記科目と捉えられがちですが、単に用語や知識を詰め込むのではなく、社会のしくみや仕組みを理解することが重要です。その基盤となるのが教科書です。
教科書を丁寧に読み込む
教科書は、公民学習の土台となる重要な情報が詰まっています。最初から最後まで丁寧に読み込み、各単元の構成や論理的な流れを把握しましょう。わからない言葉や用語があれば、辞書や事典で調べ、理解を深めます。
図表やイラストを活用する
教科書には、図表やイラストが多く掲載されています。これらの図表やイラストは、抽象的な概念を理解するのに役立ちます。各図表やイラストの意味をしっかりと理解し、説明文と合わせて読み解きましょう。
マーカーや付箋を活用して整理する
重要な箇所や覚えたい箇所には、マーカーや付箋を活用して目印をつけましょう。自分だけのオリジナル教材を作っていくことで、復習が効率的に行えます。
ノートに書き写してまとめる
教科書の内容をノートに書き写すことで、理解を深め、記憶を定着させることができます。自分の言葉でまとめることで、より深い理解につながります。
公民は、社会の一員として必要な知識や技能を身につけるための科目です。主体的に学習に取り組むことで、より深い理解と教養を身につけることができます。

参考記事:都立入試の社会│出題傾向と対策ポイント!よく出る問題はこれだ
中学生が政府の仕組みと機能を効率的に理解する方法
政府の仕組みと機能は、複雑で抽象的な概念として捉えられがちです。
しかし、中学生にとって重要な学習内容であり、社会の一員として必要な知識を身につけるための基盤となります。
中学生が政府の仕組みと機能を効率的に理解し、記憶を定着させるための方法をご紹介します。
政府の役割を理解する
政府は、国民の生活を守るために様々な役割を担っています。主な役割は以下の通りです。
- 立法:法律を作る
- 行政:法律に基づいて政策を実行する
- 司法:法律に基づいて裁判を行う
- 外交:他の国との関係を築く
- 防衛:国を守る
これらの役割を理解することで、政府がどのような仕事をしているのか、なぜその仕事をしているのかを理解しやすくなります。

参考記事:【中学生】成績が上がるノートの取り方!頭のいい人のノートを紹介
公民の勉強のポイント
公民の勉強のポイントは、日頃からニュースや新聞に興味を持つことです。
興味のある内容は中学生も率先して見るため、記憶の定着が早くなります。
中学生がわからない言葉は保護者の方が補足して説明してあげると記憶に定着しやすくなります。
またニュースや新聞が難しいと感じる中学生には、情報バラエティー番組などがわかりやすくておすすめです。
【ニュースに興味を持つ】
公民の勉強のポイントは、日頃からニュースや新聞に興味を持つこと。
興味のある内容は中学生も率先して見るため、記憶の定着が早くなります。
中学生がわからない言葉は保護者の方が補足して説明してあげると記憶に定着しやすくなります。
またニュースや新聞が難しいと感じる中学生には、情報バラエティー番組などがわかりやすくておすすめです。
公民の勉強も単語を覚えるだけでなく、歴史的な背景や因果関係を理解することで、全体の流れを把握することがポイントです。
なぜなら、公民は時代の流れを読み解くことを重視しているからです。
公民で学ぶ内容は難しい内容のものが多く、国会や選挙の話などは、学習してもモチベーションが上がりません。
用語やシステムの話で飽きてしまうこともあると思いますが、興味のある分野から徐々に覚えることで公民の理解が増すことになります。
【教科書と資料集を使う】
公民の勉強は教科書が基本になりますが、資料集を活用するのもおすすめです。
理由は、資料集には多くの写真やイラストが掲載されているため、視覚的に理解しやすいからです。
そのため、公民が苦手な中学生でも資料集を見ているだけで、興味が湧く効果も期待できます。
資料集に掲載されている内容は定期テストや入試でも問われることが多いため、有効活用するべき教材なのです。
社会の点数を上げる方法:中学生編


社会の成績をすぐに上げるための勉強法を紹介!
試してみてください。
- 社会の点数を上げる方法:中学生編
- 1日で社会を覚える方法
社会の点数を上げる方法:中学生編
「社会」は主に「暗記」が必要な科目。
歴史上の人物や地理の国名、公民(政治経済)の用語など、大半が覚えるべき事柄です。
要するに、「一種のクイズ」なので、「知っているか、知らないか」を尋ねているだけ。
この科目は考えて答えるよりも、思考力はほぼ不要。
才能や知能指数は関係ありません。
むしろ、試験前にどう過ごしていたかや、どのように暗記の工夫をしたかといった姿勢が採点に影響します。
中学生の社会の成績をすぐに上げるための勉強法にはいくつかのポイントがあります。
以下は効果的なアプローチです。
・要点をまとめる
授業や教科書を読みながら、重要な要点やキーワードをメモしましょう。これにより、大量の情報を整理しやすくなります。
・マインドマップを活用する
マインドマップは情報を視覚的に整理するのに役立ちます。テーマを中心に枝を広げ、関連するトピックや事実を追加していくと、複雑な情報も理解しやすくなります。
・効果的な暗記法を使う
歴史上の人物や地理の要素など、社会科目は暗記が必要な要素が多いです。効果的な暗記法を見つけ、例えば「フラッシュカード」や「口頭で繰り返す」などで定着させましょう。
・問題集を活用する
定期テストや模試の問題集を解くことで、実際の試験に近い形で学習できます。学校で配布された問題集や補習教材を使い、問題の傾向や出題パターンを把握しましょう。
・先取り学習を行う
授業で扱った内容を予習し、理解を深めることで、授業内での理解がより効果的になります。先取り学習は自己学習の重要な要素です。
・効率的な学習時間を確保
長時間勉強するよりも、短時間で集中的に学習する方が効果的です。集中力が高い時間帯を見極め、計画的に学習時間を確保しましょう。
・教材や参考書を複数使う
一つの教材だけでなく、複数の教材や参考書を使うことで、同じ内容を異なる視点から理解できます。これにより、より深い理解が可能になります。
これらのポイントを組み合わせて、中学生の社会の成績向上を目指しましょう。

1日で社会を覚える方法
1日で社会をすべて覚えるのは不可能ですが、効率的な学習方法で短期間で知識を習得することは可能です。
試験範囲を絞り込む
1日で社会をすべて覚えることは現実的ではありません。まずは、テスト範囲や試験に出題されやすいポイントを絞り込みましょう。教科書や資料集、過去問などを参考に、重点的に学習すべき項目をリストアップします。
キーワードを覚える
各単元の重要なキーワードをピックアップし、意味を理解して覚えましょう。キーワードを覚えることで、文章全体の流れを把握しやすくなり、記憶の定着にも効果があります。
年表を活用する
歴史の流れを理解するには、年表を活用することが重要です。主要な出来事や人物を年表に沿って確認することで、全体像を把握しやすくなります。
図表やイラストを活用する
図表やイラストは、抽象的な概念を理解するのに役立ちます。教科書や資料集に掲載されている図表やイラストを積極的に活用しましょう。
問題集や過去問を解く
問題集や過去問を解くことで、自分の理解度を確認することができます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを分析し、同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。
繰り返し復習する
せっかく覚えたことも、復習しないとすぐに忘れてしまいます。定期的に復習することで、長期記憶に移行しやすくなります。
1日で社会をすべて覚えることは不可能なので、焦らずに計画的に学習することが大切です。また、暗記だけに頼らず、理解を深めることを意識しましょう。
参考記事:マナリンクの口コミと評判を調査!料金の真実と選ばれる理由とは?
【Q&A】社会が覚えられない中学生に関するよくある質問


【Q&A】社会が覚えられない中学生に関するよくある質問を紹介します。
- 中学生の社会の覚え方は?
- 中学生が勉強できない理由は何ですか?
- 中学生が効率よく暗記する方法は?
- 中1の社会は何から始めますか?
中学生の社会の覚え方
以下に「中学生の社会の覚え方」を表形式でまとめました。
| 方法 | 内容と使い方 |
|---|---|
| 教科書をざっと読む | 全体の流れを把握するために、まず教科書を一通り読み、太字や図表をチェックする。 |
| 語呂合わせを活用 | 覚えにくい年号や出来事を語呂合わせにして、楽しく記憶する。例:「いい国(1192)作ろう鎌倉幕府」。 |
| 地図や年表を使う | 地図で地理を視覚的に覚えたり、年表で歴史の流れを整理して記憶を定着させる。 |
| ノートに書き出す | 重要な用語や出来事をノートに書き、自分の言葉で要点をまとめることで理解を深める。 |
| 暗記カードを使う | 問題と答えをカードの表裏に書き、クイズ形式で繰り返し確認する。 |
| 関連付けて覚える | 歴史なら出来事同士、地理なら地名と特産品など、関連性を持たせて記憶する。 |
| テスト形式で復習する | 市販の問題集や自作のテストを使い、覚えた内容をアウトプットして確認する。 |
| 短時間を繰り返す | 1回の学習を20〜30分に区切り、集中して学び、その後繰り返し復習する。 |
| 視覚的な道具を活用 | 白地図、フラッシュカード、赤シートなど視覚に訴える道具を活用して効率的に暗記する。 |
| 身近な話題と関連付ける | ニュースや生活に関連する公民のテーマを調べ、学んだ内容を現実と結びつける。 |
中学生が効率よく社会を覚える方法を簡単に実践できるようになります。

中学生が勉強できない理由は何ですか?
以下に「中学生が勉強できない理由」を表形式でまとめました。
| 理由 | 内容と説明 |
|---|---|
| 勉強方法が分からない | 効率的な学習法や自分に合った勉強スタイルが見つけられていないため、時間をかけても成果が出にくい。 |
| 目標が明確でない | テストや将来のための目標が曖昧で、勉強に対するモチベーションが湧かない。 |
| スケジュール管理が苦手 | 学校や部活で忙しく、勉強時間をうまく確保できていない。 |
| 集中力が続かない | 勉強中にスマホやテレビなどの誘惑が多く、長時間集中するのが難しい。 |
| 苦手科目への苦手意識 | 特定の科目に対して「難しい」「無理だ」と思い込み、取り組む意欲を失っている。 |
| 基礎が身についていない | 小学校の内容や基礎的な知識が不足しており、中学の内容に対応できなくなっている。 |
| 親や教師からの過度なプレッシャー | 親や教師からの期待が高く、ストレスで勉強に集中できない。 |
| 勉強する環境が整っていない | 騒がしい環境や快適でない部屋で勉強しているため、効率が下がる。 |
| 友達との競争意識の欠如 | 周囲の友達が勉強に対して積極的でないため、自分もやらなくて良いと思ってしまう。 |
| 体調やメンタルの問題 | 疲労や睡眠不足、ストレスなどで心身が不調になり、学習に集中できない。 |
中学生が勉強できない理由を具体的に理解し、問題を解決するためのサポートがしやすくなります。

中学生が効率よく暗記する方法は?
以下に「中学生が効率よく暗記する方法」を表形式でまとめました。
| 方法 | 内容と説明 |
|---|---|
| 繰り返し復習する | 学んだ内容を1時間後、翌日、1週間後と何度も復習することで記憶を定着させる。 |
| 短時間に区切る学習法 | 1回の暗記時間を20〜30分に区切り、集中して取り組む。短時間の学習を複数回繰り返すのが効果的。 |
| 語呂合わせを活用 | 年号や用語をリズムや言葉に乗せて覚える。例:「いい国(1192)作ろう鎌倉幕府」。 |
| フラッシュカードを使う | 問題と答えをカードに書き、クイズ形式で繰り返し確認する。 |
| 赤シートを活用 | ノートや単語帳を赤シートで隠し、記憶をアウトプットする練習をする。 |
| 書いて覚える | 手を動かしてノートに書き出すことで、記憶が強化されやすい。単語や重要ポイントを繰り返し書く。 |
| 関連付けて覚える | 関連性のある情報をグループ化して記憶。例:歴史の出来事と年号、地名と特産品をセットで覚える。 |
| 視覚的なツールを使う | 白地図や年表、図解などを活用し、視覚的に覚えられるよう工夫する。 |
| 声に出して覚える | 覚えたい内容を声に出して読み上げることで、聴覚を使った記憶が促進される。 |
| 睡眠を利用 | 学習後すぐに睡眠をとることで、記憶が脳に定着しやすくなる。 |
中学生が効率よく暗記するための具体的な方法を実践でき、学習効果を向上させることができます。

中1の社会は何から始めますか?
中1の社会は、地理分野からスタートします。
世界の国々や地域、地形など初めて学ぶ内容が多く、最初は戸惑うかもしれません。
地理の学習では、地図帳を活用し、地名や国の特徴を視覚的に覚えることがポイントです。
「用語の意味を理解する」「事項の関連性を押さえる」ことで記憶が定着しやすくなります。
テストでは地図と用語を結びつける問題がよく出題されるので、普段から関連付けを意識した学習を心がけましょう。
タブレット学習教材が中学生の社会の勉強におすすめな理由

中学生の社会の勉強は、タブレット学習教材で勉強するのも良い方法。
なぜなら、タブレット学習教材を利用することで、ゲーム感覚で集中して学習できるからです。
タブレット学習教材には、学校の授業内容を予習・復習できるものや、苦手な分野を克服するためのものなど、さまざまな種類があります。
また、子どもの年齢や学習レベルに合わせて選べるため、子ども一人ひとりに合った学習ができます。
タブレット学習教材は、子どもたちがゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な子どもでも楽しく学習できるでしょう。
また、タブレット学習教材には、子どもの学習状況を保護者が確認できる機能が付いているものもあるので、子どもの学習進捗を把握できます。
以下は、中学生向けのタブレット学習教材のおすすめポイント。
・学校の授業内容を予習・復習できる
・苦手な分野を克服できる
・子どもの年齢や学習レベルに合わせて選べる
・子どもたちがゲーム感覚で学習できる
・保護者が子どもの学習状況を確認できる
タブレット学習教材は、勉強が嫌いな中学生、学校の授業に遅れを取っている中学生や、勉強が苦手な中学生にもおすすめです。
中学生におすすめタブレット学習教材比較表
| タブレット学習教材名 | 月謝 | 特徴 |
| 進研ゼミ:中学講座 | 中学1年生:6,400円〜 | ベネッセが提供している、タブレット学習教材。中学生の利用者数No.1。 |
| すらら | 小中コース 8,800円〜 | AI×アダプティブラーニング「すらら」、マナブをサポートする最先端学習システム。小学生から高校生まで、国・数・理・社・英の5教科を学習できるICT教材 |
| スマイルゼミ | 7,480円〜 | 「まなぶ」「みまもる」「たのしむ」の3つのバランスを大切にして、勉強したい気持ちを逃さない。 |
| デキタス | 中学生:5,280円〜 | 勉強嫌いでも、勉強が習慣化できる!おすすめのタブレット学習教材 |
※オンライン料金の詳細については公式サイトからお問い合わせください。※社名をタップすると公式ホームページに移動します。
※学年や講師ランク・授業時間により料金は変動します。
進研ゼミ:中学講座は中学生の社会の勉強におすすめの教材
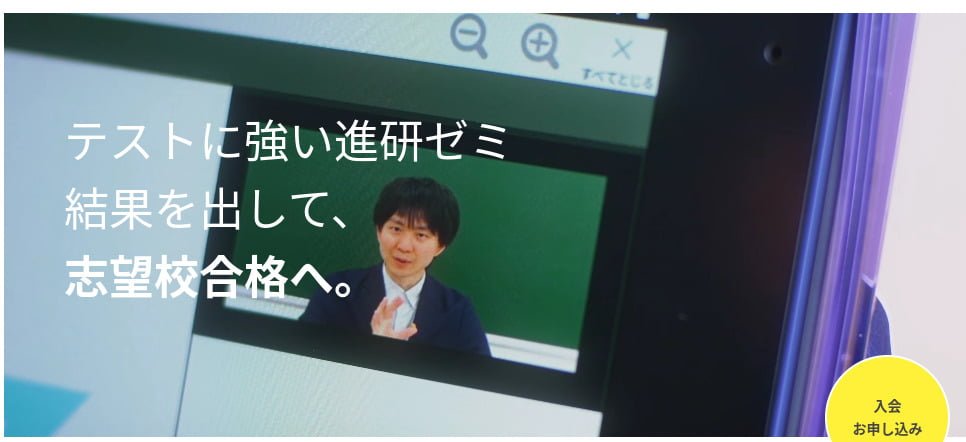
中学生利用者NO.1!進研ゼミ:中学講座の基本情報
| 月謝 | 【月謝例】 中学1年生:6,400円〜 中学2年生:6,570円〜 中学3年生:7,090円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、理科、社会、英語 |
| 学習機能 | 教科書対応のテキストで、予習も復習もバッチリ! お使いの教科書に合わせたテキストなので、予習はもちろん復習にも効率的に |
| 管理機能 | AIのレッスン提案で迷わない実力に合わせて学習スタート 学習達成後のごほうびでやる気が続く |
| サポート体制 | 月1回、赤ペン先生がお子さま一人ひとりを添削し、丁寧に指導。担任制なので、毎回同じ先生に提出する楽しみがうまれ、毎月の学習の仕上げとしてしっかり取り組めます。 |
進研ゼミ中学講座の特徴
進研ゼミ中学講座は、ベネッセコーポレーションが提供している中学生向けの通信教育です。
1969年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。進研ゼミ中学講座の特徴は、以下の通りです。
- 学校の授業内容に沿った教材で、予習・復習が効率的にできる。
- タブレット学習を利用することで、ゲーム感覚で学習できます。
- 赤ペン先生による添削指導で、記述力や思考力を鍛えられる。
- 応用問題や演習問題で、実力を身につけられる。
- 夏休み特訓や冬期講習など、季節ごとの特別講座が充実。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
進研ゼミ中学講座は、中学校の授業内容をしっかり学びたい、記述力や思考力を鍛えたい、夏休みや冬休みの学習を充実させたい、といった中学生におすすめです。
\中学生の利用者NO.1の通信教育/
安心して利用できる
↓↓↓
すらら:無学年方式で社会の勉強ができるオンライン教材

「すらら」の基本情報
| 受講費用の安さ | ■入会金 ・小中・中高5教科コース:7,700円 ・小中・中高3教科、小学4教科コース:11,000円 ■3教科(国・数・英)コースの月謝例 ・小中コース・中高コース 月額:8,800円〜 小学1年生~中学3年生までの3教科(国・数・英)の範囲が学び放題 |
| 対応科目・コース | 4教科(国・数・理・社)コース 5教科(国・数・理・社・英)コース 無学年方式で中学英語も先取り学習できる |
| 学習機能 | キャラクターによるレクチャーからドリル機能が充実 「すらら」は読み解くだけではなく、見て、聞いて学べる |
| 管理機能 | 「すらら」はAI搭載型ドリルだから自分のつまずきポイントがわかる! |
| サポート体制 | 学習習慣の身に付け方を始めとした学習に関する悩みや、基礎学力、成績を上げるための学習設計をサポートします。 |
すららの特徴
すららは、株式会社すららネットが提供している中学生向けのオンライン学習教材です。
2010年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
すららの特徴は、以下の通りです。
- 学年にとらわれない無学年方式で、子どものペースに合わせて学習できます。
- 子どもの弱点をAIが自動診断し、苦手な分野を効率的に克服できます。
- ゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な子どもでも楽しく学習できます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
すららは、学習に苦手意識を持っている子どもや、効率的に学習を進めたい子どもにおすすめです。
当サイトで人気No.1の通信教材!
是非!すららを選択肢の一つに
↓↓↓
スマイルゼミ:釈迦の勉強が継続するタブレット教材
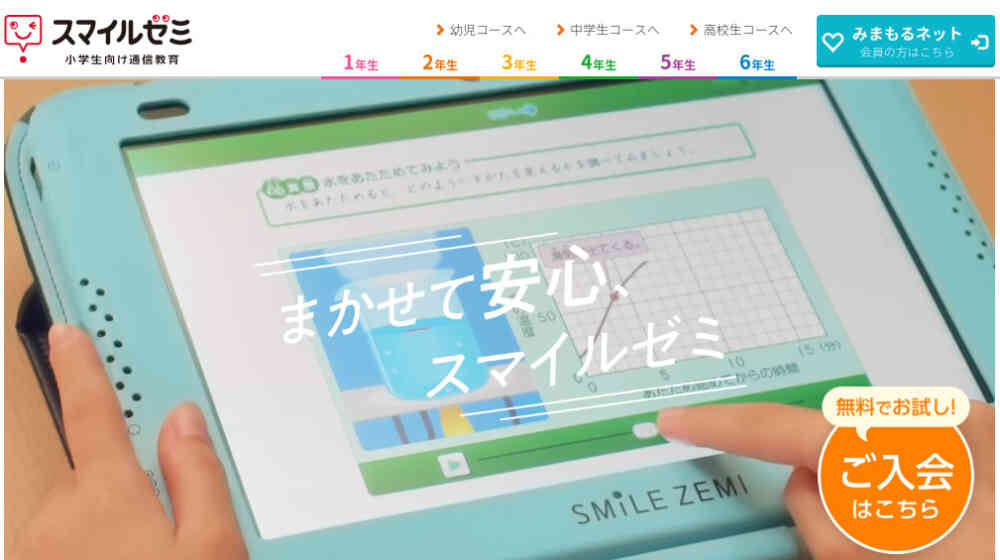
スマイルゼミの基本情報
| お手軽な受講費用 | 【中学1年生】月謝例 <標準クラス> ・7,480円〜:12か月一括払い/月あたり |
| 対応科目・コース | 国語・数学・理科・社会はもちろんのこと、英語やプログラミングも1年生から学習できる |
| 学習機能 | アニメーションによる解説で公式の持つ意味を正しく理解できる 手をついて書ける学習専用タブレットを使用 |
| 管理機能 | スマイルゼミのタブレットは、利用時間を「1日〇時間」という形で制限可能 |
| サポート体制 | 全額返金保証制度あり |
スマイルゼミの特徴
スマイルゼミは、ジャストシステムが提供している中学生向けのタブレット学習教材。
2012年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
スマイルゼミの特徴は、以下の通りです。
- タブレット端末を使って学習できるので、ゲーム感覚で楽しく学べます。
- 子どもの学習状況をAIが分析して、一人ひとりに合った学習内容を自動的に提案してくれます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
スマイルゼミは、タブレットで最適な学習を継続させたい人におすすめです。
中学生の学びが継続するタブレット
\返金保証制度あり/
↓↓↓
中学生に最適なタブレット教材:デキタス
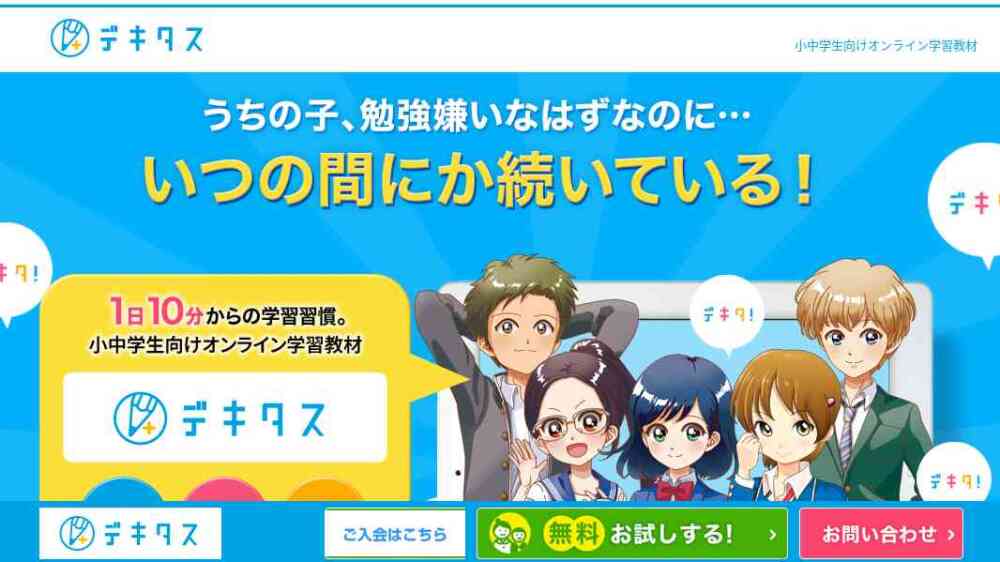
中学生におすすめ!デキタスの基本情報
| 項目 | デキタスの公式サイト |
| 受講費用 | 中学生:5,280円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、地理、歴史、公民、国文法、英語検定 |
| 学習機能 | ポップなキャラクター&わくわくする授業! |
| 管理機能 | テストモード搭載 |
| サポート体制 | 学習結果は表・グラフ・カレンダー等でひと目で確認することができます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
教科書の内容を確実に理解
学校の成績が上がる!
↓↓↓
デキタスの公式サイトチェック!
デキタスのおすすめポイント
学校の勉強を確実に理解していくことを目指し開発された、小中学生用オンライン学習教材です。
教科書内容に合った映像授業や、演習問題。さかのぼり学習で前の学年前の授業に戻ったり、定期テスト問題を作成して挑戦したりと、学校の勉強を自宅で、自分のペースで自由に行えます。
以下にデキタスの特徴を3つ紹介します。
段階的な学習体系: デキタスは「授業」→「○×チェック」→「基本問題」→「チャレンジ問題」というスモールステップで構成され、基礎から応用まで段階的に学習が進められます。この体系により、生徒は小さな成功体験を積み重ねながら学習し、「デキタ!」の達成感を実感できます。
デキタ'sノートと複合学習: デキタスでは授業に沿った穴埋め式ノートが印刷可能であり、デジタル教材と紙と鉛筆を組み合わせて効果的な学習ができます。この複合学習により、視覚的なデジタル学習と手書きによるノート作成が組み合わさり、理解の定着が促進されます。
学習習慣の形成: デキタスは学習結果を表・グラフ・カレンダーで確認し、保護者と共有する機能があります。親子で学習状況を共有し、成績アップを目指すことで学習習慣が自然に形成されます。
教科書の内容を確実に理解
学校の成績が上がる!
↓↓↓
高校入試対策の記事
まとめ:社会が覚えられない中学生【地理・歴史・公民】分野別の覚え方

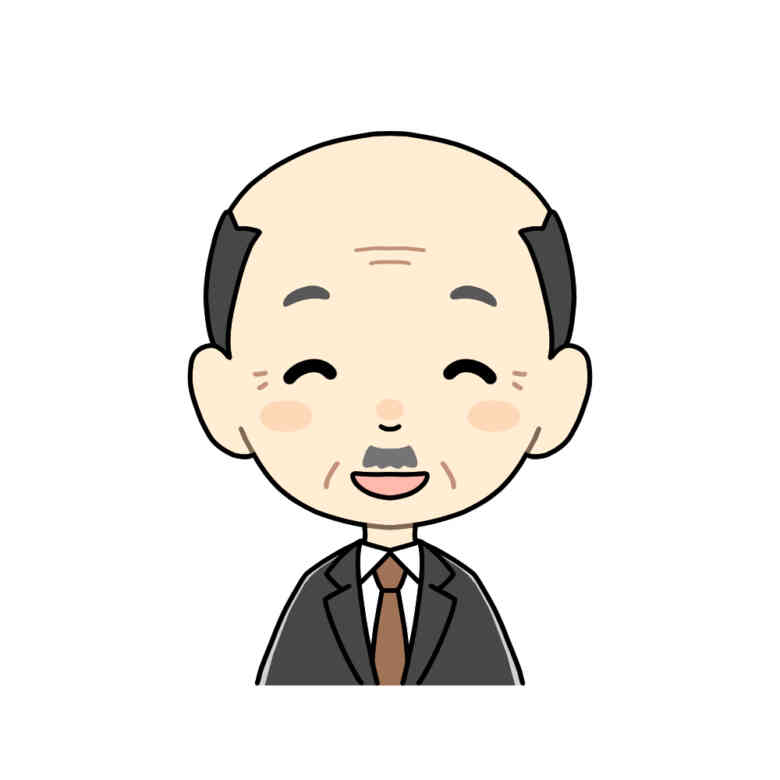
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、社会が覚えられない中学生【地理・歴史・公民】分野別の覚え方は参考になりましたでしょうか?
中学生の社会の覚え方について理解しました。

以上、「社会が覚えられない中学生【地理・歴史・公民】分野別の覚え方」でした。
まとめ:社会が覚えられない中学生【地理・歴史・公民】分野別の覚え方
まとめ
中学生の社会の勉強で地理、歴史、公民を効果的に覚えるための要点をまとめます。
1.アクティブラーニング
単なる読書だけでなく、地図を自分で作成し、歴史的な事件を模擬体験するなど、体験的な学習を取り入れましょう。
2.視覚的支援
イラスト、図表、地図、タイムラインを使用して情報を視覚化し、記憶に残りやすくします。
3.キーワードと要点の抽出
各トピックのキーワードや要点をノートにまとめ、重要な情報を整理しましょう。
4.ストーリーテリング
地理や歴史の出来事を物語として語り、関連性を強調します。
5.グループ勉強
友達と共同学習を行い、情報の共有とディスカッションを通じて理解を深めます。
6.オンラインリソース
インターネットを活用し、オンライン教材や動画を活用して学習をサポートします。
7.模擬テストとクイズ
定期的な模擬テストやクイズを受けて知識を確認し、自己評価を行います。
8.実践と関連付け
学習内容を実生活や現代の出来事と結びつけ、抽象的な概念を具体的な事例に関連付けて理解します。
これらのアプローチを組み合わせて、地理、歴史、公民の学習を効果的かつ楽しみながら進めましょう。自分の学習スタイルに合った方法を見つけ、好奇心を育むことが大切です。
中学生におすすめ塾
おすすめ塾
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
オンライン個別指導そら塾
※オンライン個別指導塾生徒数No.1!生徒満足度94.3%!優秀な講師陣の授業が全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師マナリンク
※プロの講師のみが在籍!紹介動画で講師が選べる画期的なシステム!ホームページから誰でも閲覧できます!
オンラインプロ教師のメガスタ!
※圧倒的な合格実績を誇る!学生講師からプロ講師まで多数在籍!きっと生徒にピッタリの講師が見つかるはずです。
トライのオンライン個別指導塾
※TVCMでおなじみの家庭教師のトライのオンライン版、これまでの指導実績から独自の学習ノウハウで生徒を指導!
オンライン家庭教師WAM
※個別指導で実績のある!個別指導WAMのオンライン版、難関大学の講師が塾よりも成績を上げます!
オンライン家庭教師ナイト
※定期テスト対策に強く!授業日以外のサポートで勉強を習慣づけながら成績向上!PC無料貸し出し!
家庭教師の銀河
※「自立」にこだわる学習法で定期テスト・受験対策も可能。手厚いチャットサポートで生徒も安心!オンライン対応。
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。

