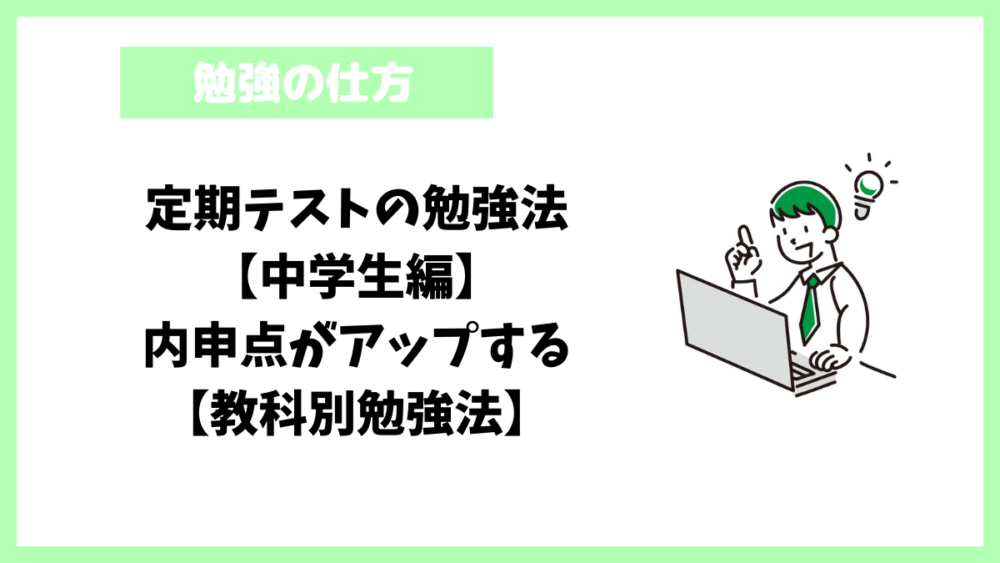
「※この記事には一部PRが含まれます」
高校受験の国語長文読解で、なかなか点数が伸びないと悩んでいませんか?
「時間が足りない」「内容が頭に入ってこない」といった中学生の皆さんの共通の悩みを解決するため、この記事では、長文読解の具体的な「コツ」と効率的な対策、そして今日から実践できる勉強法を徹底的に解説します。
この記事を読めば、国語の長文読解に対する苦手意識が克服され、自信を持って本番に臨めるようになりますよ。
おすすめ塾
国語に特化した!貴重な塾
東大生オンライン個別指導!
東大生との1対1での対話を通して、
文章題にも強くなる「一生モノ」の読解力
国語の苦手が解消できる!
東大生の指導で国語の点数アップ
↓↓↓
「ヨミサマ。」公式ホームページ
Contents
- 1 はじめに:高校受験「国語の長文読解」なぜ苦手と感じるの?
- 2 高校入試 国語における長文読解の出題傾向と必要な力
- 3 点数アップにつながる長文読解の基本ステップと「コツ」
- 4 【ジャンル別】高校受験 国語 長文読解の「読むコツ」と「解くコツ」
- 5 高得点に直結!記述問題・抜き出し問題の「書き方」のコツ
- 6 合格へ導く!効果的な長文読解問題の「復習方法」
- 7 長文読解力を高める効果的な勉強法と練習方法
- 8 読解力アップのために取り組むべき日常習慣(国語の読解力を高める方法はありますか?)
- 9 高校受験当日に差がつく長文読解の直前対策
- 10 成績が上がった先輩たちの勉強法・成功事例
- 11 【Q&A】高校受験対策の国語!長文読解のコツに関するよくある質問
- 12 まとめ:【高校受験国語】長文読解の「コツ」点数を劇的に上げる対策と勉強法
はじめに:高校受験「国語の長文読解」なぜ苦手と感じるの?

高校受験を控える皆さんにとって、国語の長文読解は大きな壁に感じられるかもしれませんね。
多くの生徒さんが「長文読解は難しい」「どう対策すればいいか分からない」という共通の悩みを抱えています。
しかし、その原因を理解し、正しい「コツ」を知ることで、必ず得意科目に変えることができます。
- 長文読解でつまずく、中学生が抱えるよくある原因
- この記事で得られる具体的なメリットと得点アップへの道
長文読解でつまずく、中学生が抱えるよくある原因
国語の長文読解で点数が伸び悩む原因はいくつかあります。
たとえば、文章を漠然と読んでしまい、筆者の主張や登場人物の心情を正確に読み取れていないケースです。
問題文を先に読むか本文を先に読むか迷ってしまい、時間配分がうまくいかないという時間不足の悩みもよく聞かれます。
記述問題の書き方が分からない、選択肢でいつも迷ってしまうといった具体的な解答テクニックの不足も、つまずきの原因となることが多いです。
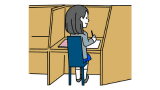
この記事で得られる具体的なメリットと得点アップへの道
この記事を読むことで、皆さんは国語の長文読解に関する具体的な「コツ」と対策法を体系的に学ぶことができます。
「時間が足りない」という悩みに対しては、速読のコツや効率的な問題の解き方を。
「内容が頭に入ってこない」という悩みには、本文の読み方や要点把握のコツを解説します。
最終的には、高校受験の国語長文読解で自信を持って高得点を目指せるようになるための、具体的な学習ロードマップを手に入れることができますよ。
高校入試 国語における長文読解の出題傾向と必要な力

高校入試の国語では、長文読解が合否を分ける重要な要素となります。
出題される文章の種類や問われる内容をあらかじめ把握しておくことで、効率的な対策が可能になります。
- 説明的文章(論説文・説明文など)で問われること
- 文学的文章(小説・物語文など)で問われること
- よく出る設問形式(選択・記述・抜き出し問題)
説明的文章(論説文・説明文など)で問われること
説明的文章、いわゆる論説文や説明文では、筆者の主張や主題を正確に読み取る力が問われます。
説明的文章(論説文・説明文など)で問われる力
- 筆者の主張や主題を正確に読み取る力
- 何を一番伝えたいのかを読み取る
- なぜその主張をしているのか、理由を考える
- 文章全体の構成を理解する力
- 各段落がどうつながっているかを把握する
- グラフや図表などの資料を読み解く力
- 文章だけでなく、図や表の情報も組み合わせて考える
- 情報を多角的に整理・理解する力
- 複数の情報を比較し、筆者の意図をつかむことが求められる

文学的文章(小説・物語文など)で問われること
文学的文章、特に小説や物語文では、登場人物の心情の変化を読み解く力が中心となります。
文学的文章(小説・物語文など)で問われる力
- 登場人物の心情の変化を読み解く力
- 感情の動きだけでなく、その「変化」に注目する
- 行動・言動・情景描写から心情を推測する力
- セリフや動作、まわりの様子などをヒントにして、気持ちを客観的に読み取る
- 場面の変化と心情の関係を読み取る力
- 時間や場所の移り変わりが、登場人物にどんな影響を与えているかを考える
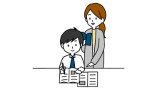
よく出る設問形式(選択・記述・抜き出し問題)
高校入試の長文読解では、主に選択問題、記述問題、抜き出し問題の3つの形式が出題されます。
よく出る設問形式(選択・記述・抜き出し問題)で問われる力
- 選択問題
- 紛らわしい選択肢の中から、最も適切なものを選ぶ判断力が必要
- 選択肢の根拠を本文から見つける力が問われる
- 記述問題
- 設問の意図を正確に読み取る力が求められる
- 自分の言葉で論理的かつ的確に答える表現力が必要
- 抜き出し問題
- 本文中から、指定された条件に合う語句や文を一字一句正しく探す力が必要
- 文章全体の構造を理解して、該当箇所をすばやく見つける力が求められる
点数アップにつながる長文読解の基本ステップと「コツ」

ここからは、国語の長文読解で確実に点数を上げるための基本的なステップと具体的な「コツ」について、詳しく解説していきます。
このステップを実践することで、「時間が足りない」「問題文が頭に入ってこない」といった悩みを解消し、効率的に学習を進めることができるようになりますよ。
- ステップ①:問題文と設問、どちらを先に読むべきか?
- ステップ②:本文の読み方と要点把握のコツ
- ステップ③:選択肢問題で間違えないための考え方
- ステップ④:記述問題が書けない理由と書き方の基本
- ステップ⑤:時間が足りない人のための読解スピード強化術(国語 長文読解 全部読むべき?)
ステップ①:問題文と設問、どちらを先に読むべきか?
長文読解に取り組む際、まず迷うのが「問題文(本文)を先に読むか、それとも設問を先に読むか」という点です。
結論から言うと、多くの場合、設問を先にざっと読むのがおすすめです。
ステップ①:問題文と設問、どちらを先に読むべきか?
- おすすめは「設問を先に読む」こと
- どんな問いがあるかを把握してから本文を読むことで、目的意識が持てる
- 本文を先に読むと起こりやすい問題
- 重要な部分が分からず、何度も読み返すことになり時間のロスにつながる
- 設問を先に読むメリット
- 本文を読むときに「どこに注目すればよいか」が分かる
- 探すべき情報が明確になり、読み進めやすくなる
- 全体を効率よく理解できるようになる

ステップ②:本文の読み方と要点把握のコツ
本文を読む際には、ただ漫然と読むのではなく、効率的に要点を把握する「コツ」があります。
ステップ②:本文の読み方と要点把握のコツ
- ただ読むのではなく「目的を持って読む」ことが大切
- 効率的に読むためのポイント
- 段落ごとにキーワードやキーセンテンスに線を引く
- 必要に応じて簡単なメモを取る
- 注目すべき要素
- 接続詞(例:「しかし」「つまり」「したがって」など)に注目すると、文の展開や筆者の考えがつかみやすい
- 指示語(例:「これ」「それ」「そのような」など)は、何を指しているかを確認することで理解が深まる
- 「長文は全部読むべきか?」という疑問について
- 全体の流れや内容をつかむためにまずは全て読むのが基本
- そのうえで、設問に関係する部分を重点的に読む意識を持つと、時間の節約にもつながる

ステップ③:選択肢問題で間違えないための考え方
選択肢問題は、一見簡単そうに見えても、紛らわしい選択肢に惑わされやすいという落とし穴があります。
ここで重要なのは、「本文に書かれていること」と「自分の推測」を明確に区別することです。
正解の選択肢は必ず本文中に根拠があります。
ステップ③:選択肢問題で間違えないための考え方
- 選択肢問題の落とし穴
- 一見簡単そうに見えるが、紛らわしい選択肢に惑わされやすい
- 正解を選ぶための基本姿勢
- 「本文に書かれていること」と「自分の推測」を分けて考える
- 正解は必ず本文に根拠がある
- 具体的な解き方のポイント
- 各選択肢が本文のどこに対応しているかを確認する
- 本文と少しでも違う表現がないかを慎重にチェックする
- 間違えやすい選択肢の特徴
- 「〜だと思われる」「〜だろう」などの曖昧な表現を含むもの
- 本文に書かれていない内容や、自分の想像が入った選択肢は消去する
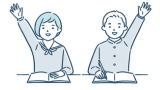
ステップ④:記述問題が書けない理由と書き方の基本
記述問題は、「何を書けばいいか分からない」「うまくまとめられない」という悩みを抱える中学生が多いです。
記述問題で点数が取れない最大の理由は、設問の意図を正確に捉えられていないこと、そして解答の「型」を知らないことにあります。
書き方の基本は、まず設問が「何を」問いているのかを明確にすることです。
次に、本文の中から解答に必要な要素(キーワード、理由、具体例など)を抜き出し、それらを組み合わせて論理的に文章を構成します。
ステップ④:記述問題が書けない理由と書き方の基本
- 記述問題でよくある悩み
- 「何を書けばいいか分からない」
- 「うまくまとめられない」
- 記述で点が取れない主な原因
- 設問の意図を正確に読み取れていない
- 解答の「型(パターン)」を知らない
- 書き方の基本ステップ
- 設問が何を聞いているかを明確にする
- たとえば「理由を述べよ」なのか、「気持ちを説明せよ」なのかを把握する
- 本文から答えに必要な要素を探す
- キーワード、理由、具体例などをピックアップする
- 抜き出した要素を組み合わせて、論理的にまとめる
- 主語・述語を意識し、意味が通る文に仕上げる
- 設問が何を聞いているかを明確にする
- 短い記述の練習法(例)
- 「〜だからだ。」の形で理由を簡潔に述べる練習をする
- 制限字数(30字以内など)に合わせて伝えたいことをしぼる力を身につける

ステップ⑤:時間が足りない人のための読解スピード強化術(国語 長文読解 全部読むべき?)
高校受験の国語長文読解で「時間が足りない」という悩みは非常に切実です。
読解スピードを上げるには、単に速く読む練習をするだけでなく、効率的な読解術を身につけることが重要です。
ステップ⑤:時間が足りない人のための読解スピード強化術
- 「時間が足りない」という悩みは多くの受験生が抱えている
- 読解スピードを上げるために必要なこと
- ただ速く読むのではなく、効率よく読む力を身につけることが大切
- 設問を先に読んで、注目すべき箇所に目星をつける練習を繰り返す
- 「本文を全部読むべきか?」の答え
- 基本的にはすべてに目を通すべき(全体の流れをつかむため)
- ただし、設問に関係する部分はより集中して丁寧に読む意識が必要
- 語彙力の強化も読解スピードアップに直結
- 知らない言葉が多いと読むたびに止まってしまい、時間ロスにつながる
- 日ごろから新聞・読書・語彙プリントなどで言葉に触れる習慣をつける
スピードだけを求めるのではなく、「読むべき場所を見抜く力」と「語彙力の底上げ」が重要です。
おすすめ塾
国語に特化した!貴重な塾
東大生オンライン個別指導!
東大生との1対1での対話を通して、
文章題にも強くなる「一生モノ」の読解力
国語の苦手が解消できる!
東大生の指導で国語の点数アップ
↓↓↓
「ヨミサマ。」公式ホームページ
参考記事:ヨミサマ【国語塾】の口コミ・評判は?良い・悪い声を本音で専門家が徹底分析
【ジャンル別】高校受験 国語 長文読解の「読むコツ」と「解くコツ」

高校受験の国語長文読解では、文章のジャンルによって読解の「コツ」が異なります。
説明的文章と文学的文章、それぞれの特性を理解し、適切なアプローチで読む・解く練習をすることで、確実に点数アップを目指せます。
- 説明的文章の読解コツ3選
- 文学的文章の読解コツ4選(物語文 コツ 高校受験対策も含む)
説明的文章の読解コツ3選
説明的文章(論説文・説明文など)は、筆者の主張や論理展開を正確に理解することが重要です。
「漠然と読み流してしまう」という悩みを抱える方は、以下のコツを意識して読んでみましょう。
筆者の主張と主題を正確に掴む方法
説明的文章では、まず筆者が最も伝えたいことは何か、つまり文章全体の「主題」を把握することが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 筆者の主張・主題を正確に読み取ること |
| 最初に意識すべきこと | 文章全体の「主題」を把握する |
| 主題が示されやすい場所 | - 文章の冒頭- 文章の結び- 各段落の冒頭や末尾 |
| 注目すべき接続詞 | 「つまり」「要するに」「したがって」など(結論を示す) |
| 主張の見つけ方のコツ | 結論を示す接続詞の後の文に注目することで、筆者の主張を見つけやすくなる |
「つまり」「要するに」「したがって」といった結論を示す接続詞の後に注目すると、筆者の主張を見つけやすくなります。
接続詞や指示語をヒントに読み進めるテクニック
文章の論理展開を理解するためには、接続詞と指示語が非常に重要なヒントになります。
接続詞や指示語をヒントに読み進めるテクニック
- 接続詞と指示語は、文章の流れを理解する重要な手がかり
- 接続詞に注目するコツ
- 「しかし」「だが」などの逆接の接続詞が出てきたら要注意
- その後に筆者の反対意見や新しい視点が述べられることが多い
- 指示語に注目するコツ
- 「これ」「それ」「あれ」などの指示語は、直前や少し前の内容を指している
- 指している内容を正確に特定すると、文章の意味がより明確に理解できる
接続詞と指示語を見逃さずに読むことで、文章のつながりや筆者の意図がぐっと分かりやすくなります。
対比関係や具体例に注目する読解法
説明的文章では、二つの事柄を比較する「対比関係」や、抽象的な内容を分かりやすくするための「具体例」がよく用いられます。
対比関係や具体例に注目する読解法
- 説明的文章では、次の2つに注目することで内容が理解しやすくなる:
- 対比関係
- 具体例
- 対比関係に注目するコツ
- 「Aは〇〇だが、Bは△△である」などの表現に注目
- 対比によって筆者の主張や重要な違いが強調されることが多い
- 「〜に対して」「一方で」などの言葉が出てきたら要チェック
- 具体例に注目するコツ
- 「例えば」「具体的には」などの語句の後に注目
- その前に出てきた抽象的な内容をわかりやすく説明している
- 具体例を理解することで、筆者の言いたいことが深く理解できる
このように、「対比」と「具体例」は読解のカギです。
文章の構造をつかむ助けになります。

参考記事:【中学生国語の勉強法】基礎力アップ!読解・記述・文法の苦手を攻略
文学的文章の読解コツ4選(物語文 コツ 高校受験対策も含む)
文学的文章(小説・物語文など)は、登場人物の心情を読み解くことが中心となります。
「小説文・物語文が苦手」という悩みを持つ方は、以下のコツを実践してみましょう。
登場人物の心情変化を読み解くポイント
物語文で最も重要なのは、登場人物の「気持ち」や「感情」がどのように変化していくかを追うことです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 登場人物の心情の「変化」を読み取ること |
| 心情の表現方法 | - 直接「悲しい」「うれしい」などと書かれる場合もある - 多くは間接的に表現される |
| 心情を読み取る手がかり | - セリフ(話し方や言葉づかい)- 行動(どんな行動をとったか) - 表情(顔の様子など)- 情景描写(まわりの風景や雰囲気) |
| 読み進めるときの考え方 | - 「なぜこの時、この行動をとったのか?」 - 「なぜこの言葉を言ったのか?」と自問しながら読む |
このように整理すると、物語文を読むときに何を意識すればよいかが明確になります。
場面(時間・場所・状況)の変化を整理する
物語文では、時間や場所、季節などの「場面」が変化することがよくあります。
この場面の変化は、登場人物の心情や物語の展開に深く関わっていることが多いです。
場面(時間・場所・状況)の変化を整理するポイント
- 物語文では、場面の変化がよく出てくる
- 時間(例:朝→夜)
- 場所(例:教室→帰り道)
- 季節や天気(例:晴れ→雨)
- 場面の変化は、登場人物の心情や物語の展開と深く関係している
- 例:明るい日差しから急に雨が降る → 気持ちの変化を象徴していることがある
- 変化のポイントに注目して読むと良い
- 「いつ」「どこで」「どんな状況か」を整理しながら読む
- 場面の変化と気持ちや出来事の変化を結びつけて考えると、物語の流れがつかみやすくなる
場面の移り変わりに気づくことで、登場人物の心の動きや物語の意味がより深く理解できるようになります。
客観的な視点で本文から正確に読み取る
文学的文章の読解で最も重要な「コツ」の一つは、「自分の感情や解釈を交えずに、本文に書かれていることだけを根拠にする」という客観的な視点を持つことです。
客観的な視点で本文から正確に読み取るポイント
- 自分の感情や主観を交えずに読むことが大切
- 「登場人物の気持ちを勝手に想像しない」ように意識する
- 答えはあくまで本文の中にあるという前提で読む
- 本文に書かれている情報を根拠として使う
- たとえ直接書かれていなくても、本文中のヒントから読み取る
- セリフ
- 行動
- 情景描写 などの要素から考える
- 常に自問する意識を持つ
- 「この答えの根拠は本文のどこにあるか?」と自問自答しながら読む
主観ではなく、本文に忠実に読み取る姿勢が、正確な読解につながります。
情景描写が示す意味を考える
物語文では、自然の風景や天候、周囲の物の様子などを描いた「情景描写」が頻繁に出てきます。
これらの描写は、単なる背景ではなく、登場人物の心情を暗示したり、今後の展開の伏線となったりすることがあります。
情景描写が示す意味を考えるポイント
- 物語文では、情景描写(風景・天候・まわりの様子)がよく登場する
- 情景描写は単なる背景ではない
- 登場人物の心情を暗示することがある
- 物語の展開の伏線になっている場合もある
- 具体的な例
- 「嵐の夜」→ 登場人物の不安な気持ちや、これから起こる不穏な出来事の前ぶれかもしれない
- 読み取りのコツ
- 情景描写が登場人物の気持ちや物語全体の雰囲気にどう影響しているかを考える
- 描写と心情・展開のつながりを意識して読む
情景描写は、登場人物の感情や物語の意味を深く理解する手がかりになります。
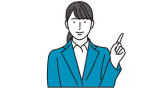
参考記事:国語の文章問題を解くコツを中学生にアドバイス!国語の苦手を克服
高得点に直結!記述問題・抜き出し問題の「書き方」のコツ
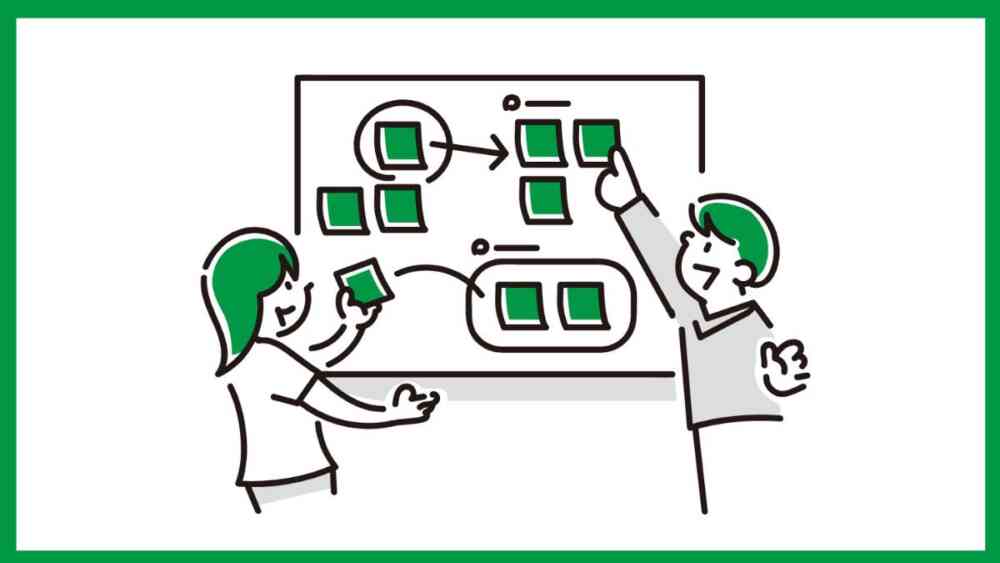
高校受験の国語では、記述問題と抜き出し問題の対策が、合否に大きく影響します。
特に記述問題が苦手な方は、ここで解説する「書き方」の「コツ」を習得することで、確実に得点アップを目指せます。
- 記述問題の「型」を身につけるステップ
- 抜き出し問題で一字一句正確に解答する練習
- 要約問題を攻略する効果的なアプローチ
記述問題の「型」を身につけるステップ
記述問題は、「何を書けばいいか分からない」という悩みを抱える生徒が多いですが、実は解答には決まった「型」があります。
この型を身につけることで、どんな問題でも論理的かつ効率的に解答を作成できるようになります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ステップ① | 設問が何を問うているかを正確に把握する(理由・気持ち・内容説明などの設問の意図を読み取る) |
| ステップ② | 本文から必要なキーワードや根拠となる部分を探す(セリフ・行動・要点などをピックアップ) |
| ステップ③ | 設問の意図に合わせて、根拠を組み合わせて文章を作る(主語・述語を明確にし、論理的に構成する) |
| ステップ④ | 指定された字数内に収める練習をする(無駄を省き、簡潔に伝える力をつける) |
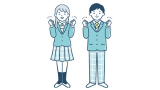
抜き出し問題で一字一句正確に解答する練習
抜き出し問題は、比較的簡単そうに見えますが、「一字一句、句読点まで正確に抜き出す」というルールを厳守しないと不正解になってしまいます。
本文中に似た表現があっても、設問の指示に合致しないものは間違いとなります。
抜き出し問題で一字一句正確に解答する練習のポイント
- 一見簡単そうでも要注意
- 少しのミス(文字の抜け・句読点の違い)でも不正解になることがある
- 正解するために守るべき基本ルール
- 一字一句、句読点まで正確に抜き出す
- 設問の指示にぴったり合った表現でなければ正解にならない
- 正確に抜き出すための手順
- 設問の指示を正しく理解する
- 何についての言葉を抜き出すのかを明確にする
- 本文中から完全に一致する部分を探す
- キーワードや内容が一致している箇所を注意深く読む
- 正確に抜き出す練習を繰り返す
- 繰り返すことで「読み落とし」や「うっかりミス」を防げる
- 設問の指示を正しく理解する
- 注意点
- 句読点や記号も抜き出しの一部と考える
- 少しでも違えば不正解になる可能性があるので、細部まで丁寧に確認
このような意識と練習を積み重ねることで、抜き出し問題を確実に得点源にできます。
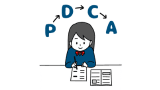
要約問題を攻略する効果的なアプローチ
要約問題は、文章全体の理解度と表現力が問われる、やや難易度の高い問題です。
この問題を攻略する効果的な「コツ」は、まず段落ごとに筆者が伝えたい中心的な内容(中心文)を見つけることです。
要約問題を攻略する効果的なアプローチ
- 要約問題の特徴
- 文章全体の理解力と表現力が問われる
- 難易度はやや高め
- 攻略のためのステップ
- 段落ごとに中心となる内容(中心文)を見つける
- 筆者がその段落で何を伝えたいかを読み取る
- 段落の中心文をつなげて全体の要旨を把握する
- 全体として筆者が主張していることを整理する
- 不要な情報を削り、指定字数にまとめる
- 具体例や繰り返し表現を省く
- 文章を簡潔かつ論理的に組み立てる
- 段落ごとに中心となる内容(中心文)を見つける
- 高得点を取るためのポイント
- 重要なキーワードを落とさないように意識する
- 書きすぎず、要点をしっかり絞って表現する
要約問題では「要点を正確につかむ力」と「必要な情報だけを整理する力」の両方が必要です。
練習を重ねてバランスよく身につけましょう。
おすすめ塾
講師のほとんどが東大・東大院生
東大生が指導する塾としてはコスパが良い
オンライン個別指導
部活が忙しい生徒にも対応!
自宅で勉強できるから、集中力UP!
成績アップの近道!
30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/
↓↓↓
トウコベの公式HPをチェック!
参考記事:トウコベの口コミ・評判・レビュー【小中学生の保護者向け】講師の質・サポート・効果を徹底検証
合格へ導く!効果的な長文読解問題の「復習方法」

問題を解き終えたら、まず解答解説を徹底的に読み込みましょう。
単に正解・不正解を確認するだけでなく、「なぜその答えになるのか」「自分の解答とどこが違うのか」「どのような思考プロセスで正解にたどり着くのか」を深く理解することが重要です。
特に間違えた問題については、解説を熟読し、自分の間違いの原因(読み違い、解釈違い、知識不足など)を特定しましょう。
解説に書かれている読解プロセスを追体験することで、次回の問題演習に活かせる「コツ」が見えてきます。
- 解答解説を徹底的に読み込む重要性
- 間違えた問題を必ず解き直す習慣
- 音読と要約で文章内容を深める練習
- 類題を解いて解法を定着させる
間違えた問題を必ず解き直す習慣
間違えた問題は、必ず時間を置いてから解き直す習慣をつけましょう。
すぐに解き直しても、答えを覚えてしまっている可能性があるからです。
たとえば、数日後や一週間後など、少し期間を空けてから改めて問題を解いてみてください。
この「解き直し」によって、本当にその問題の「コツ」や解法が身についたかを確認することができます。
もし再び間違えた場合は、まだ理解が不十分な部分があるため、再度解説を読み込み、必要であれば参考書などで関連知識を補強しましょう。

音読と要約で文章内容を深める練習
復習の際には、音読と要約を組み合わせることで、文章内容の理解をさらに深めることができます。
間違えた文章や理解が曖昧だった文章を声に出して読む「音読」は、黙読では気づきにくい文章のリズムや句読点の意味を意識し、より正確な読解につながります。
文章全体や段落ごとの「要約」に挑戦することで、文章の構造を把握する力や筆者の主張を的確に捉える力を養うことができます。
要約は、記述問題の対策にも直結するため、ぜひ積極的に取り組んでみてください。
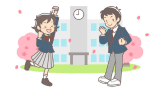
類題を解いて解法を定着させる
同じタイプの問題で間違えやすい場合は、「類題」を解くことが解法を定着させる有効な「コツ」です。
たとえば、「心情変化の読み取り」が苦手であれば、同じようなテーマの小説文を。
「筆者の主張の読み取り」が苦手であれば、別の論説文を解いてみましょう。これにより、特定の解法や読解の「コツ」が様々な文章で通用するかを確認し、応用力を高めることができます。
問題集の「類題」や「発展問題」を活用したり、過去問で似た出題形式を探して解いてみるのも良い方法です。
おすすめ塾
参考記事:そら塾の口コミ・評判を徹底調査|良い・悪い口コミから特徴と向いている子
長文読解力を高める効果的な勉強法と練習方法
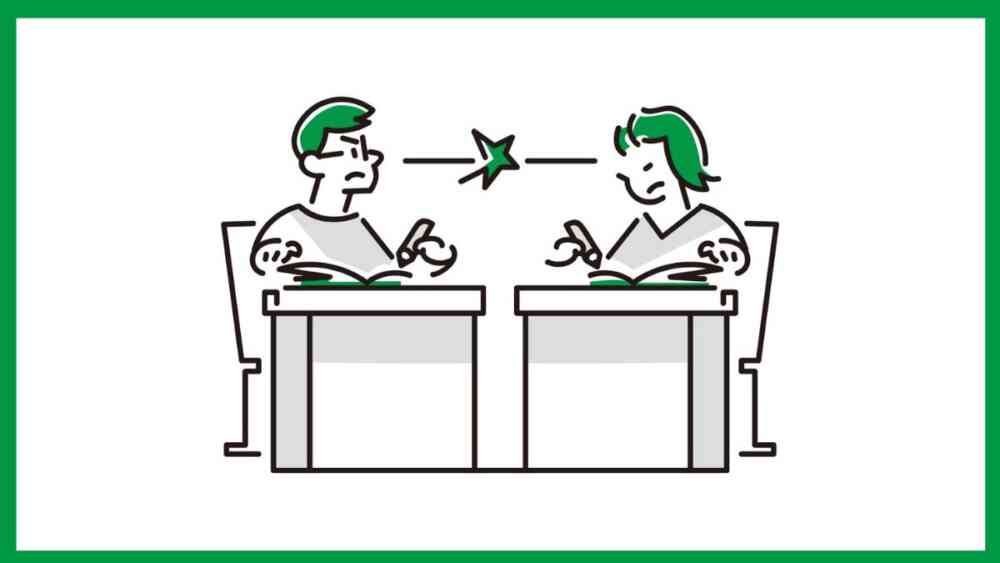
国語の長文読解力を根本的に高めるためには、日々の効果的な勉強法と練習が欠かせません。
ただ問題を解くだけでなく、基礎力を着実に積み上げることで、「国語 文章問題 コツ 中学生」の皆さんが苦手意識を克服し、得意科目に変えることができます。
- 語彙力・漢字力の強化で読解力を底上げ
- 段落ごとに要約する練習法
- 高校受験 国語 読解 問題集のおすすめと活用法
- 高校受験 国語 長文読解 問題 無料で使える教材と活用法
語彙力・漢字力の強化で読解力を底上げ
読解力は、語彙力と漢字力に大きく左右されます。
知らない単語や読めない漢字が多いと、文章を読むたびに思考が中断され、内容が頭に入ってこないという悩みにつながります。
そのため、日頃から語彙力・漢字力の強化に取り組みましょう。
語彙力・漢字力の強化で読解力を底上げするポイント
- 読解力は語彙力と漢字力に大きく左右される
- 知らない言葉が多いと、文章を読むたびに理解が止まってしまう
- 内容がスムーズに頭に入らず、集中力が途切れやすくなる
- 語彙力・漢字力を強化するためにできること
- 問題集や参考書で知らない単語・漢字に出会ったらノートにまとめる
- 意味や使い方を調べて、自分の言葉で覚える習慣をつける
- 新聞やニュース記事を読む
- 語彙や漢字が実際にどう使われているかを文章の中で確認できる
- 問題集や参考書で知らない単語・漢字に出会ったらノートにまとめる
- 日々の積み重ねが読解力アップにつながる
- 毎日の小さな努力が、文章を読む力の大きな土台になる
語彙や漢字が増えるほど、文章を読むスピードも理解度も自然と上がっていきます。コツコツ取り組むことがポイントです。

中学生の漢字帳について知りたい方、漢字の勉強ができる中学生がやっている勉強法と漢字ドリル10選
段落ごとに要約する練習法
文章全体の構造を理解し、筆者の主張を把握するためには、「段落ごとの要約」が非常に有効な練習法です。
段落ごとに要約する練習法のポイント
- 「段落ごとの要約」は文章の構造を理解するのに効果的
- 筆者の主張や要旨をつかみやすくなる
- 基本的なやり方
- 各段落を読み終えたあとに
→ その段落で筆者が最も伝えたいことを20〜30字程度でまとめる
- 各段落を読み終えたあとに
- この練習で身につく力
- 重要な部分と補足・具体例を区別する力
- 段落ごとの役割(主張・説明・例など)を意識して読めるようになる
- 最終的な目標
- 段落ごとの要約をつなげて、文章全体の要旨を正しく把握する力を育てる
この練習を繰り返すことで、文章を「ただ読む」から「構造的に読む」読み方へとステップアップできます。

高校受験 国語 読解 問題集のおすすめと活用法
高校受験の国語長文読解対策には、適切な問題集を選ぶことが非常に重要です。
「高校受験 国語 長文読解 問題集 おすすめ」を探している方は、自分のレベルに合ったものを選びましょう。
具体的には、基礎固め用の問題集で読解の基本ルールを学び、次に実践演習用の問題集で応用力を高めるのがおすすめです。
解説が丁寧で、なぜその答えになるのか論理的に説明されている問題集を選ぶと、自己学習の効果が格段に上がります。
問題集は一度解いたら終わりではなく、間違えた問題を何度も解き直すことで、「コツ」を定着させることができます。

参考記事:【必見】都立入試の国語|傾向・配点・過去問対策|完全ガイド
高校受験 国語 長文読解 問題 無料で使える教材と活用法
「高校受験 国語 長文読解 問題 無料」で探している方もいるかと思います。インターネット上には、無料の長文読解問題やプリントを提供しているサイトが多数あります。
これらを上手に活用することも、読解力向上の「コツ」です。
ただし、無料教材を利用する際は、解説がしっかりしているか、問題の質が高いかを確認することが重要です。
「無料で手軽に多くの問題に触れる」という目的で利用し、有料の問題集と組み合わせて活用するのが最も効果的です。
読解力アップのために取り組むべき日常習慣(国語の読解力を高める方法はありますか?)

国語の長文読解力を飛躍的に向上させるためには、日々の学習だけでなく、日常生活の中で読解力を養う習慣を取り入れることが非常に効果的です。
「国語の読解力を高める方法はありますか?」という悩みを抱える方は、ぜひこれらの習慣を試してみてください。
- 読書・新聞・コラムで文章に慣れる
- 学校の教科書を使った読み返し勉強法
- 日常生活でできる読解トレーニング
読書・新聞・コラムで文章に慣れる
読解力を高める最も基本的な方法は、様々な文章に触れることです。
小説や物語文が苦手な方は、まず興味のある分野の小説を読んでみましょう。
新聞の社説やコラム、ニュース記事などは、論理的な文章に慣れる絶好の教材です。
最初は難しく感じるかもしれませんが、毎日少しずつでも読み続けることで、文章の構造や言葉の選び方に自然と慣れていきます。
これにより、複雑な文章でも抵抗なく読み進められるようになるでしょう。

学校の教科書を使った読み返し勉強法
意外と見落とされがちなのが、学校の国語の教科書を徹底的に読み返すことです。
教科書には、説明的文章も文学的文章も、良質な文章が厳選して掲載されています。
授業で習った内容を思い出しながら、再度音読したり、段落ごとの要点をまとめたりする練習をしてみましょう。
特に、教科書に載っている問題や解説を深く理解することは、基本的な読解力と解答力を養う上で非常に重要です。
「読解力アップの基礎固め」として、教科書を有効活用してください。
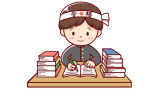
日常生活でできる読解トレーニング
読解トレーニングは、机に向かって勉強する時だけではありません。
日常生活のちょっとした時間でも実践できます。
たとえば、テレビのニュースのテロップやインターネット記事の見出しを「要約」してみる。商品の説明書やお店の案内の文章を読み、「この文章で最も伝えたいことは何か?」を考えてみる。
このような意識的な取り組みは、文章の要点を素早く掴む力を養い、「国語 文章問題 コツ 中学生」で検索する皆さんの読解力アップに繋がります。
高校受験当日に差がつく長文読解の直前対策

高校受験当日は、これまでの努力の成果を発揮する大切な日です。
特に国語の長文読解では、試験本番で実力を最大限に出し切るための「直前対策」が非常に重要になります。
「緊張して集中できない」「時間配分がうまくいかない」といった悩みを抱える方は、ここで解説する「コツ」を実践してみてください。
- 試験本番の時間配分と読み方の順序
- 緊張しても落ち着いて読める心の準備法
- 前日・当日にやっておくべきことリスト
試験本番の時間配分と読み方の順序
試験本番では、限られた時間内で効率的に長文読解を解き進めることが求められます。
事前に時間配分をシミュレーションしておくことが重要な「コツ」です。
試験本番の時間配分と読み方の順序のポイント
- 限られた時間内で効率的に解くことが求められる
- 時間の使い方を事前にシミュレーションしておくことが大切
- 時間配分の工夫
- 大問ごとの目安時間をあらかじめ決めておく
- 例:「この長文は〇分以内で解く」と決めておくと安心
- 大問ごとの目安時間をあらかじめ決めておく
- 解く順番の工夫
- 問題文全体をざっと見てから解き始める
- 以下のような基準で、自分に合った順序を決めておく
- 得意なジャンルから解く
- 配点の高い問題から解く
- メリット
- 計画的に進めることで、焦らず落ち着いて取り組める
- 時間切れや後半の雑なミスを防げる
事前のシミュレーションと順序の工夫が、本番でのパフォーマンスを大きく左右します。

緊張しても落ち着いて読める心の準備法
試験本番は、誰でも緊張するものです。
しかし、緊張によって集中力が散漫になり、普段なら読める文章が頭に入ってこないという悩みを抱える受験生は少なくありません。
そこで、「落ち着いて読める心の準備法」を身につけておきましょう。
たとえば、試験開始前に数分間目を閉じて深呼吸をする、「自分はこれだけ勉強してきたから大丈夫」と心の中で唱えるといったルーティンを決めておくと良いでしょう。
問題文全体を一度ざっと見渡すことで、心のゆとりを持つこともできます。

前日・当日にやっておくべきことリスト
高校受験の前日や当日には、特別な勉強をするよりも、これまでの努力を最大限に発揮するための準備に徹しましょう。
| タイミング | やるべきこと | 補足ポイント |
|---|---|---|
| 前日 | 早めに就寝し、十分な睡眠を取る | 体調管理を最優先にする |
| 前日 | 新しい問題には手を出さない | 不安を増やさず、落ち着いた気持ちで過ごす |
| 前日 | 苦手な問題の解説部分だけを軽く見直す | 過去に解いた問題集から選ぶとよい |
| 当日 | 試験会場に余裕をもって到着する | 落ち着いて準備を整えるため |
| 当日 | 試験直前に慌てて詰め込まない | これまでの勉強を信じて臨む |
新しい問題に手を出さないことが重要な「コツ」です。
成績が上がった先輩たちの勉強法・成功事例

国語の長文読解で「本当に点数が上がるのか不安」「何から始めたらいいか分からない」という悩みを抱えている方もいるかもしれません。
ここでは、実際に成績を伸ばし、高校受験に合格した先輩たちの具体的な勉強法や、塾経験者からのアドバイスをご紹介します。
成功事例から「コツ」を学び、ぜひ皆さんの学習に取り入れてみてください。
- 偏差値が10上がった生徒の読解勉強法とは?
- 塾経験者からのアドバイス:家庭学習で意識すべき3つのこと
- 読解が苦手だった中学生が変わった理由
偏差値が10上がった生徒の読解勉強法とは?
ある先輩は、国語の長文読解で偏差値が10も上がったそうです。
その「コツ」は、「間違えた問題を徹底的に分析し、納得できるまで何度も解き直すこと」でした。
特に、解説を熟読し、「なぜこの選択肢は間違いで、なぜこの選択肢が正解なのか」を論理的に説明できるまで深く理解することに時間をかけたそうです。
小説文が苦手だったため、「物語文 コツ 高校受験」として、週に数冊の小説を読み、登場人物の心情を追う練習を継続的に行ったことで、苦手意識を克服できたと語っています。
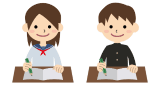
塾経験者からのアドバイス:家庭学習で意識すべき3つのこと
多くの生徒を指導してきた塾経験者からのアドバイスとして、家庭学習で特に意識すべき3つの「コツ」があります。
- 「時間を意識して問題を解くこと」:本番を想定し、常に時間を計りながら問題に取り組むことで、時間配分の感覚を養うことができます。
- 「音読を習慣にすること」:黙読では見落としがちな文章のリズムや接続詞のつながりを意識し、正確な読解力を鍛えることができます。
- 「なぜ間違えたのかを言語化すること」:自分の弱点を明確にすることで、効率的な復習につながります。
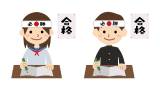
読解が苦手だった中学生が変わった理由
以前は国語の読解が「最も苦手な科目」だった中学生が、高校受験を前に見事に克服し、得点源に変えた事例があります。
その生徒は、「国語 文章問題 コツ 中学生」というキーワードで情報収集を始めたそうです。
「まず自分のレベルに合った簡単な問題集から始め、解説を徹底的に読み込む」ことを実践しました。
週に一度、図書館で好きなジャンルの本を借りて読み、活字に慣れるようにしたそうです。
小さな成功体験を積み重ね、苦手意識を払拭したことが、大きな変化に繋がった「コツ」と言えるでしょう。
おすすめ塾
国語に特化した!貴重な塾
東大生オンライン個別指導!
東大生との1対1での対話を通して、
文章題にも強くなる「一生モノ」の読解力
国語の苦手が解消できる!
東大生の指導で国語の点数アップ
↓↓↓
「ヨミサマ。」公式ホームページ
参考記事:【中学生向け】オンライン塾ランキング20選!料金・高校受験対策も徹底比較
【Q&A】高校受験対策の国語!長文読解のコツに関するよくある質問

【Q&A】高校受験対策の国語!長文読解に関するよくある質問を紹介します。
- Q1:国語の長文読解で、文章は全部読むべきですか?それとも部分読みでも大丈夫?
- Q2:国語の読解力を高めるためには、どんな勉強方法が効果的ですか?
- Q3:高校受験の国語長文読解には、具体的にどんな種類の文章が出題されますか?
- Q4:国語の長文読解対策として、おすすめの問題集や無料の問題はありますか?
Q1:国語の長文読解で、文章は全部読むべきですか?それとも部分読みでも大丈夫?
A1:基本的には、文章全体を一度は読むことをおすすめします。
全体の流れや筆者の主張、物語の背景を理解するためには、全文を読み通すことが不可欠だからです。
時間を意識して効率的に読む「部分読み」のテクニックを組み合わせることが重要です。
具体的には、設問を先に読んでから本文の重要な箇所に集中する、接続詞や指示語に注目して要点を押さえるといった方法です。
全文をざっと読み、必要な箇所を深く読み込むというメリハリが得点アップのコツになりますよ。
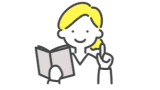
Q2:国語の読解力を高めるためには、どんな勉強方法が効果的ですか?
A2:国語の読解力を高めるには、複数のアプローチを組み合わせることが効果的です。
まず、語彙力と漢字力を強化することが大切です。
知らない言葉が多いと、文章の内容が頭に入ってきません。
次に、段落ごとに要約する練習をしてみましょう。
これは、文章の要点を素早く掴む力を養うのに役立ちます。
学校の教科書や良質な読解問題集の解説を徹底的に読み込み、なぜその答えになるのかを理解する復習も欠かせません。
日頃から様々な文章に触れる(読書や新聞、コラムなど)習慣も、読解力向上に繋がりますよ。
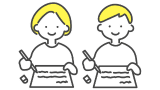
Q3:高校受験の国語長文読解には、具体的にどんな種類の文章が出題されますか?
A3:高校受験の国語長文読解で出題される文章は、主に以下の2種類に分けられます。
- 説明的文章(論説文・説明文・随筆など): 筆者の考えや事柄について説明する文章です。筆者の主張や論理展開、構成を正確に読み取る力が問われます。社会問題、科学、文化など幅広いテーマから出題されます。
- 文学的文章(小説・物語文など): 登場人物の心情や出来事を描いた文章です。登場人物の気持ちの変化や、場面の移り変わり、情景描写が示す意味などを読み取る力が求められます。
これらの文章の種類ごとに、「読むコツ」や「解くコツ」が異なりますので、それぞれの特徴を理解して対策を進めることが重要です。

Q4:国語の長文読解対策として、おすすめの問題集や無料の問題はありますか?
A4:はい、国語の長文読解対策には、自分のレベルに合った問題集を選ぶことが大切です。
まずは基礎固め用の問題集で読解の基本を学び、その後、実践演習用の問題集で応用力を高めていくのがおすすめです。
解説が丁寧で、なぜその答えになるのか論理的に説明されている問題集を選ぶと、自己学習がしやすくなりますよ。
インターネット上には無料で利用できる長文読解の問題やプリントも多数あります。「高校受験 国語 長文読解 問題 無料」などで検索すると見つけられますので、これらを演習量を増やすために活用するのも良いでしょう。
ただし、無料教材は解説が不十分な場合もあるため、有料の問題集と組み合わせて使うのが効果的です。
人気ランキング
人気のオンライン塾・家庭教師ランキング
毎月、多くのお問い合わせを頂いております!
第1位:東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
第2位:オンライン家庭教師「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
第3位:オンライン個別指導「そら塾」
※オンライン個別指導塾で生徒数No.1の実績!リーズナブルな料金で学校の成績がグングン伸びる!「お得に始めるならここ一択」
まとめ:【高校受験国語】長文読解の「コツ」点数を劇的に上げる対策と勉強法

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
以上、「【高校受験国語】長文読解の「コツ」点数を劇的に上げる対策と勉強法」でした。
まとめ:長文読解の「コツ」を掴み、高校受験国語で合格を掴み取ろう!
まとめ
ここまで、高校受験の国語長文読解で点数を劇的に上げるための「コツ」と対策、そして具体的な勉強法について詳しく解説してきました。
長文読解は、正しいアプローチと継続的な努力によって、必ず得意科目に変えることができます。
- 問題文と設問を効果的に読み進める「基本ステップ」
- 説明的文章と文学的文章、それぞれの「読むコツ」と「解くコツ」
- 高得点に直結する記述・抜き出し問題の「書き方」
- 合格に導く効果的な「復習方法」
- 読解力を根本から高める日々の「勉強法」と「日常習慣」
- 試験本番で実力を発揮するための「直前対策」
- 先輩たちの「成功事例」
これらの「コツ」を実践し、「時間が足りない」「内容が頭に入ってこない」といった悩みを一つずつ解消していきましょう。
皆さんの高校受験成功を心から応援しています!
国語の勉強法
国語の勉強法です。
参考にしてください。


