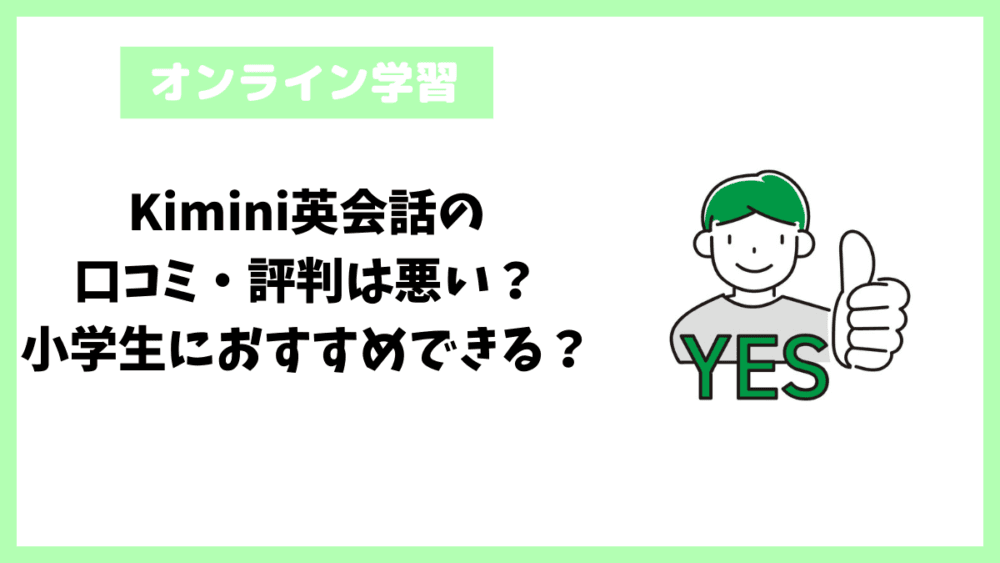
「※この記事には一部PRが含まれます」
高校受験は、お子さまにとって大きな人生の転機ですが、「行きたい高校」と「親が行かせたい高校」の意見が食い違い、お悩みの保護者さまや生徒さんは多いのではないでしょうか。
実は、この悩みは多くのご家庭で共通して起こるものです。
27年以上学習塾に携わり、800以上の教室を調査してきた専門家集団である塾オンラインドットコム編集部が、なぜこのような意見の対立が生まれるのか、その心理的背景を深く掘り下げます。
この記事では、お子さまと保護者さまが互いに納得できる進路を見つけるための具体的な解決策を、専門的な知見と豊富な経験に基づいてお伝えします。
記事のポイント
親子で「意見が違う理由」を理解する
「対話」と「尊重」が解決の鍵
後悔しないための「多角的な視点」
体験談とQ&Aで「共感」と「安心」を提供する
人気ランキング
人気のオンライン塾・家庭教師ランキング
毎月、多くのお問い合わせを頂いております!
第1位:東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
第2位:オンライン家庭教師「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
第3位:オンライン個別指導「そら塾」
※オンライン個別指導塾で生徒数No.1の実績!リーズナブルな料金で学校の成績がグングン伸びる!「お得に始めるならここ一択」
Contents
高校選びで親と子供の意見が違うのはなぜ?

高校選びで親子間の意見が食い違うのは、決して珍しいことではありません。
それぞれが重視するポイントが異なるため、どうしてもズレが生じてしまいます。
ここでは、お互いの視点を理解し、すれ違いの背景にある心理を探っていきましょう。
- 子供が重視するポイント(学校生活・部活動・友人関係)
- 親が重視するポイント(偏差値・学費・進学実績)
- 「進路 親と意見が合わない」ときの心理的背景
子供が重視するポイント(学校生活・部活動・友人関係)
子供にとって高校生活は、単なる勉強の場ではありません。
新しい友人との出会いや、好きな部活動に打ち込むこと、充実した学校行事など、勉強以外の「楽しさ」が大きなモチベーションとなります。
たとえば、「あの先輩がいるからこの高校に行きたい」「高校でもサッカーを続けたい」といった理由で志望校を選ぶケースは少なくありません。
中学生は、これから始まる高校生活全体をイメージして、自分の「居場所」や「青春」を重視する傾向があります。
「毎日楽しく通学できるか」という点が、子供の高校選びにおいて非常に重要なのです。
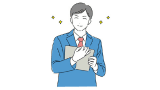
親が重視するポイント(偏差値・学費・進学実績)
一方、親は子供の将来を第一に考えています。
そのため、感情よりも「現実的な条件」を重視する傾向があります。
具体的には、「大学進学実績」や「偏差値」といった学力面だけでなく、家計に直結する「学費」、そして毎日通うことを考えると無視できない「通学距離」などが挙げられます。
「将来、後悔しないように」「安定した道を選んでほしい」という親心から、つい客観的な数字やデータに頼りがちになるのです。

「進路 親と意見が合わない」ときの心理的背景
親子の意見が合わないとき、その背景には深い心理が隠されています。
子供は「自分の選択を信じてくれない」という不満や「親の期待に応えられない」というプレッシャーを感じることがあります。
一方、親は「子供の将来が心配」という不安や、「なぜ自分の考えを理解してくれないのだろう」というもどかしさを抱えています。
このすれ違いは、お互いの価値観や見えている世界が違うからこそ起こる、非常に自然なことなのです。

参考記事:都立高校の志望校の選び方・決め方をわかりやすく5分で解説!
高校選びを親が決めるべき?

高校選びの最終決定権は、誰が持つべきなのでしょうか。
親が主導権を握るメリットがある一方で、子供の将来に大きなリスクを与える可能性もあります。ここでは、それぞれの立場からメリットとデメリットを見ていきましょう。
- 親が志望校を決めるメリットと安心感
- 高校を親が決めることによるリスクとデメリット
- 子供の意思を尊重する重要性
親が志望校を決めるメリットと安心感
親が志望校を決めることには、いくつかのメリットがあります。
まず、親は社会経験が豊富であり、高校卒業後の進路や社会情勢をより現実的に見ています。
そのため、将来性や安定性を重視した選択ができ、子供の「もしも」に対する不安を軽減できます。
受験までの計画を立てやすく、親子で目標を共有することで、効率的に学習を進められるという安心感もあります。
特に、「高校受験の負担が心配」な親にとっては、一つの安心材料となるでしょう。
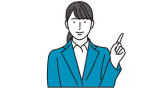
高校を親が決めることによるリスクとデメリット
しかし、親が志望校を一方的に決めてしまうことには、大きなリスクが伴います。
最大のデメリットは、子供が高校に入学してから「モチベーションを失う可能性」があることです。
自分で選んでいないため、「勉強する意味がわからない」「何のためにこの学校にいるんだろう」と感じ、学習意欲が低下してしまうかもしれません。
将来、困難に直面した際に「親のせいだ」と責任を転嫁してしまうことも考えられます。
このことは、親子関係に亀裂が入る原因ともなりかねません。
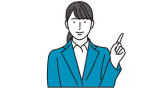
子供の意思を尊重する重要性
高校生活は、子供自身が過ごすものです。
だからこそ、子供の意思を尊重することが何よりも大切です。
たとえ子供の希望する高校が、親の考える理想と異なっていたとしても、その選択をサポートする姿勢を見せることで、子供は「自分の人生を自分で決める力」を養うことができます。
たとえ後で困難に直面したとしても、自分の選択なので前向きに取り組むことができるでしょう。

参考記事:行きたい高校が決まらない!志望校の決め方と高校選び方ガイド
高校受験で親と子供の意見が違うときの解決法

親子で意見が食い違ってしまったとき、どのように話し合えば良いのでしょうか。
感情的にならず、お互いの意見を尊重しながら解決へと導くための具体的な方法をご紹介します。
- 冷静に話し合うためのポイント
- お互いの希望を整理する方法
- 第三者(先生・塾講師・カウンセラー)に相談する効果
冷静に話し合うためのポイント
話し合いを始める前に、まずはお互いが冷静になることが重要です。
感情的になると、建設的な議論はできません。
「この高校に行きたい、なぜなら…」と理由を明確に伝えられるように準備をしましょう。
親は、子供の話を最後まで聞く姿勢を見せてください。
例えば、「なぜその高校に行きたいのか」「どんな高校生活を送りたいのか」を質問し、子供の気持ちを理解しようと努めることが大切です。
「親も子供も、意見は違ってもお互いを思いやっている」という前提で話し合うことが、解決への第一歩です。

お互いの希望を整理する方法
話し合いの場では、お互いが大切にしているポイントを客観的に整理することが大切です。
以下のような表を作ると、思考が整理され、冷静に建設的な議論ができます。
特に「共通点/妥協点」を意識することで、親子の納得感につながります。
| 項目 | 親の希望 | 子供の希望 | 共通点/妥協点 |
|---|---|---|---|
| 偏差値 | ○○高校(偏差値XX)/できるだけ上のレベル | △△高校(偏差値YY)/自分の実力に合う学校 | 「無理のない範囲でチャレンジ校を併願する」など妥協案を検討 |
| 学費 | 公立高校を希望(経済的負担を減らしたい) | 私立高校を希望(校風や施設に魅力) | 奨学金制度や特待生制度を調べ、選択肢を広げる |
| 通学時間 | 30分以内(安全・体力面の考慮) | 1時間以内でも可(通いたい学校がある) | 実際に通学ルートを体験してみて負担を確認 |
| 部活動 | 特にこだわらない/学業優先 | 強い部活がある学校に行きたい | 勉強との両立が可能かを事前に確認し、時間管理の約束をする |
| 校風・雰囲気 | 落ち着いた環境/大学進学率重視 | 明るく活発な校風/友人関係を楽しみたい | オープンスクールに参加して、実際の雰囲気を確かめる |
| 将来の進路 | 大学進学を重視 | 将来はまだ未定、まずは高校生活を充実させたい | 高校の進学実績を一緒に調べて参考にする |
このように整理することで、「何が共通していて、何がすれ違っているのか」が明確になります。
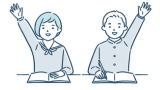
第三者(先生・塾講師・カウンセラー)に相談する効果
親子だけで話し合っても平行線になってしまう場合、第三者に相談するのも有効です。
学校の担任の先生や塾の講師は、受験や高校の情報に精通しており、客観的なアドバイスをくれます。
私の経験上、専門家に相談することで、さまざまな視点から解決策を見つけられることがあります。
「第三者を交えることで、親も子も冷静になれる」「専門家だからこその、納得できる意見がもらえる」という大きなメリットがあるのです。
学校選びで後悔しないためのチェックポイント

後悔しない高校選びをするためには、どのような点に注目すべきでしょうか。
表面的な情報だけでなく、将来を見据えた多角的な視点を持つことが大切です。
- 偏差値と合格可能性をどう考えるか
- 学費・通学時間・通学環境の重要性
- 部活動や校風の違いが与える影響
- 高校受験「昔と今」の違いを理解する
偏差値と合格可能性をどう考えるか
偏差値は、志望校選びの一つの基準となりますが、それがすべてではありません。
大切なのは、「その偏差値が自分の学力と合っているか」「無理なく合格できるか」という点です。
例えば、偏差値が60の高校を目指す場合、現在の学力が55であれば、今後の努力次第で十分合格圏内に入れます。
しかし、45の場合、相当な努力が必要となり、入学後も授業についていくのが大変になるかもしれません。
「背伸びしすぎて、入学後に苦労しないか」という視点を持つことが重要です。

学費・通学時間・通学環境の重要性
学費や通学時間は、高校生活の満足度を左右する重要な要素です。
現在、国が推進する「高等学校等就学支援金制度」により、私立高校の授業料に対する支援が拡大しています。
しかし、完全な無償化ではなく、家庭の収入に応じて支援額が異なり、授業料以外の費用もかかります。
例えば、文部科学省の調査によると、私立高校の年間平均授業料は約45万円ですが、施設設備費や修学旅行費などを含めた合計額は、公立高校よりも年間で約70万円多くかかる場合があります。
この費用の差が家計に大きな負担とならないか、親子で話し合うことが大切です。
通学時間が片道1時間30分以上になると、体力的にも精神的にも負担が大きくなり、勉強や部活動に支障をきたす可能性もあります。

部活動や校風の違いが与える影響
部活動や校風は、子供の高校生活を豊かにする上で欠かせない要素です。
例えば、「運動系の部活動が盛んで、規律が厳しい高校」もあれば、「文化系の部活動が充実しており、個性を尊重する校風の高校」もあります。
子供がどんな環境で学び、成長したいかを具体的にイメージすることが大切です。
「受験メンタルトレーナー」の視点からは、お子さまが部活動に打ち込むことでストレスを解消し、学習意欲を高めるケースが多く見られます。
「進路アドバイザー」の視点からは、校風がお子さまの個性や人間関係に与える影響を考慮することが、充実した3年間を送る上で不可欠だとお伝えしています。
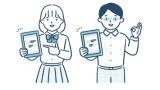
高校受験「昔と今」の違いを理解する
親世代の高校受験と、今の高校受験には大きな違いがあります。
「昔は学区が厳格に分かれていた」「大学進学よりも就職が一般的だった」など、親の経験だけでは測れない部分があるのです。
例えば、「親世代には馴染みの薄いオンラインでの説明会や、探求型学習を重視する高校が増えている」といった新しい情報も増えています。
親と子が同じ目線で情報を集めることが、すれ違いを防ぐ第一歩です。
| チェック項目 | 注目すべき点 | 考えるべき視点・具体例 |
|---|---|---|
| 偏差値と合格可能性 | 偏差値はあくまで目安。合格可能性と入学後の学力維持を重視 | 偏差値60の学校を志望→現状55なら努力で可能圏内、45なら入学後の授業負担が大きい可能性。「背伸びしすぎて後悔しないか」を確認 |
| 学費 | 授業料+その他費用(施設費・修学旅行費等)を考慮 | 私立は公立より年間約70万円多い場合も。就学支援金制度を活用できるか、家計負担が続けられるかを親子で検討 |
| 通学時間・環境 | 通学距離や時間、交通手段の安全性 | 片道90分以上は体力・学習・部活に支障。実際の通学ルートを体験して負担を確認 |
| 部活動 | 運動系・文化系・学校ごとの力の入れ方 | 部活動はストレス解消やモチベ維持に効果的。自分が続けられるかを具体的にイメージ |
| 校風 | 規律重視型 or 自由・個性尊重型などの違い | 学校説明会やオープンスクールで雰囲気を確認。お子さまの性格・将来像に合うかが重要 |
| 高校受験「昔と今」の違い | 親世代との環境差を理解すること | 昔:学区制・就職型多め/今:進学重視・オンライン説明会・探求型学習。親の経験だけに頼らず最新情報を共有 |
親の視点と子供の視点の違いをどうすり合わせるか

お互いの意見の違いを理解した上で、どのようにして納得のいく選択をすれば良いのでしょうか。
ここでは、親と子が歩み寄るための具体的な方法をご紹介します。
- 子供の夢を尊重しながら現実的な選択をする方法
- 親が高校受験で後悔しないために意識すべきこと
子供の夢を尊重しながら現実的な選択をする方法
子供が「行きたい高校」や「将来なりたい姿」に夢を描くのは、とても自然で大切なことです。
親としては学費や進学実績を考えて現実的な選択を勧めたくなりますが、一方的に意見を押しつけると、親子関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。
大切なのは、夢を否定するのではなく「どうすれば夢に近づけるか」を一緒に考える姿勢です。
例えば、子供が「将来プロのサッカー選手になりたい」と言った場合、親が現実を指摘するだけではなく、次のように話し合うことができます。
- 「サッカー部が強い高校を選びながら、勉強もきちんと続けよう」
- 「もしプロになれなくても進学できる道を残しておこう」
このように、子供の夢を“否定する”のではなく“叶えるための方法を一緒に模索する”ことで、親子の信頼関係を守りつつ、現実的な進路を検討できます。

親が高校受験で後悔しないために意識すべきこと
高校受験は、親にとっても大きな決断の時期です。
後悔を防ぐためには、まず「子供の選択を信じる勇気を持つ」ことが最も大切です。
たとえ親が希望していた高校と違っても、子供が自分の意思で選び、努力して進んだ道は、将来大きな糧となります。
親の期待通りでなかったとしても、「自分で選んだ道だから頑張れる」「納得して次のステージに進める」という体験そのものが子供を強くします。
偏差値や学費といった現実的な条件に目を向けることも大切ですが、同時に「進路の幅は一つではない」「高校受験での選択が将来をすべて決めるわけではない」という視点を持つと、過度な不安や後悔を防ぐことができます。
実際の体験談から学ぶ高校選び

実際に親と子の意見が異なり、悩みを乗り越えた家族の体験談は、あなたのヒントになるかもしれません。
ここでは、いくつかの事例を見ていきましょう。
- 子供の希望を優先して良かったケース
- 親の希望を優先したときに起きた後悔
- 親子で納得感を得た成功事例
子供の希望を優先して良かったケース
- 娘は演劇に強い関心を持ち、演劇科のある高校を希望していた。
- 父親は「偏差値が低いから反対」と言い、進学に難色を示していた。
- しかし、母親は娘の強い熱意を信じ、最終的に子供の希望を優先して進学を決断。
- 高校生活では演劇活動を通じて自信をつけ、大きく成長。
- 現在は、海外の大学で演劇を学ぶ夢を実現している。
- 親として「娘の気持ちを尊重して本当に良かった」と心から思える結果となった。
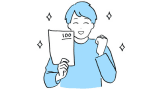
親の希望を優先して後悔したケース
- 息子は美術が好きで、美術科のある高校を志望していた。
- しかし親は「将来の就職を考えると普通科が安心」と考え、普通科高校を強く勧めた。
- 最終的に、息子は親の意見を優先して普通科高校へ進学。
- ところが、学習内容や雰囲気に馴染めず、高校生活を楽しめなかった。
- 結果として、勉強へのモチベーションが下がり、自信を失ってしまった。
- 親自身も「子供のやりたいことをもっと尊重すべきだった」と後悔することになった。
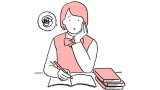
親子で納得感を得た成功事例
- 息子は「強いサッカー部のある私立高校」を志望していた。
- 親は「学費が高い私立よりも、家計に優しい公立が良い」と考えていた。
- 意見が対立したため、家族で学校説明会やオープンスクールに一緒に参加。
- 実際に雰囲気を見て、親も子も「通学距離や学習環境の違い」を実感した。
- 最終的に、学費面と部活動のバランスを考え、奨学金制度のある私立高校に進学することで合意。
- 息子は部活動に熱中しながらも勉強を両立し、親も「経済的に無理なく応援できる」と安心できた。
- 親子で一緒に検討したからこそ、「選んで良かった」と納得感を持てる進路選択になった。
高校受験で親がしんどいときの対処法
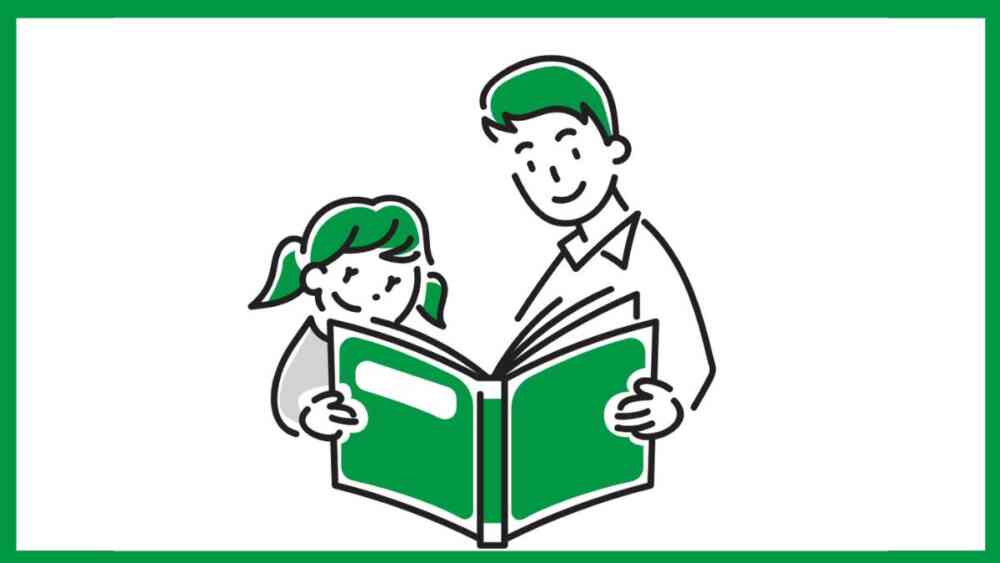
子供の受験は、親にとっても大きなストレスとなります。
ここでは受験メンタルトレーナーの経験を元に、親自身が心身ともに健康な状態で子供をサポートするための方法をお伝えします。
- 親自身の不安やストレスとの向き合い方
- サポート役に徹するための心構え
- 周囲の支援や情報源を活用する方法
親自身の不安やストレスとの向き合い方
子供の進路が思うように進まないと、親はつい 「私の育て方が悪かったのでは」「もっとできることがあったのでは」 と自分を責めてしまいがちです。
私の経験では、この自己否定が強くなると、親子ともに精神的に疲れてしまいます。
まずは 「自分も親として精一杯やっている」 と認めることが大切です。
そのうえで、ストレスを溜め込みすぎない工夫をしましょう。
- 軽い運動や散歩をする
- 信頼できる人に話を聞いてもらう
- 趣味やリラックスできる時間を持つ
受験期は子供だけでなく親も試される時期です。自分自身をケアできる親ほど、子供を支える力も強くなります。

サポート役に徹するための心構え
受験メンタルトレーナーとして多くの親子を見てきて感じるのは、「親は子供の伴走者であるべき」 ということです。
親が道を決めるのではなく、子供が選んだ道を一緒に歩むサポーターになる姿勢が理想です。
例えば、
- 「毎日『頑張れ』と繰り返す」 → プレッシャーになる場合がある
- 「今日はどんな勉強をしたの?」と穏やかに聞く → 子供は自分を理解してもらえたと感じる
こうした小さな言葉の違いが、子供の安心感につながります。親が 「信じて見守る」 姿勢を示すことが、子供の自立心やモチベーションを育てます。

周囲の支援や情報源を活用する方法
受験期に一番危険なのは、親が一人で抱え込みすぎることです。
私が関わったご家庭でも、「もっと早く相談してくれれば…」と感じるケースが少なくありません。
- 学校の先生や塾の講師に相談する
- 同じ悩みを持つ保護者と情報交換をする
- 必要なら専門家やプロの力を借りる
「一人で解決しなければならない」という思い込みを手放すことで、親自身の心が軽くなり、結果的に子供へのサポートの質も高まります。

参考記事:高校受験「親がしんどい」と感じてしまう|それはおかしいことではありません
【高校選び】親と意見が違うときの解決策に関するよくある質問【Q&A】
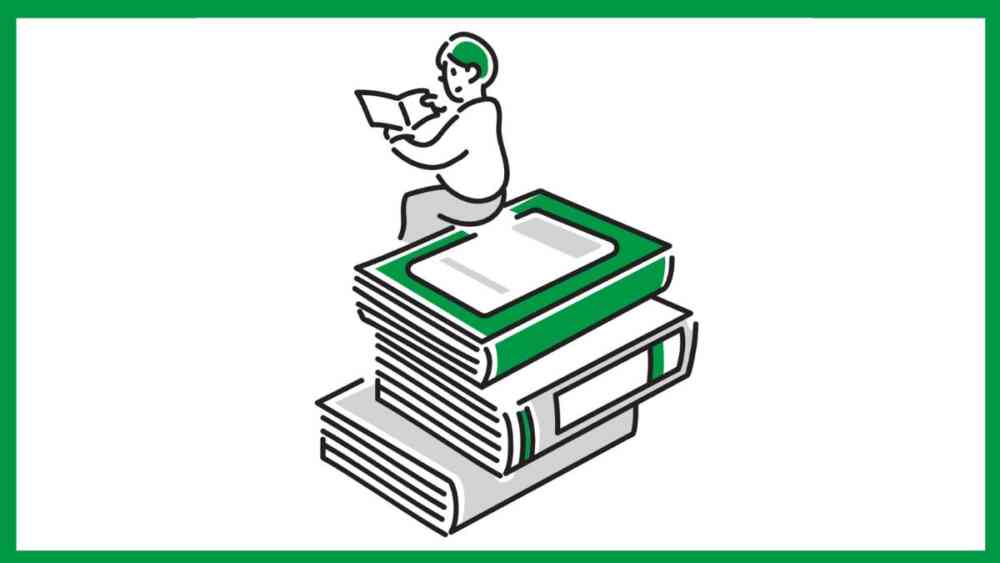
【高校選び】親と意見が違うときの解決策に関するよくある質問を紹介します。
- Q1. 親が希望する高校と、子供が希望する高校の偏差値に大きな差がある場合、どうすれば良いですか?
- Q2. 親が「将来つぶしが効かない」と反対するのですが、どう説得すれば良いですか?
- Q3. 高校見学や説明会に親が行ってくれません。どう誘えば良いですか?
- Q4. 高校受験で親の意見を聞いて後悔しないか心配です。どう考えればいいですか?
Q1. 親が希望する高校と、子供が希望する高校の偏差値に大きな差がある場合、どうすれば良いですか?
この場合、まず「なぜその偏差値の差が生まれたのか」を冷静に分析することが重要です。
親は「子供が苦労しないか」、子供は「自分の行きたい学校に行きたい」という気持ちが背景にあります。
解決策としては、「間に立つ第三者(塾講師や学校の先生)に相談する」のが有効です。
進路アドバイザーは、中学生の今の学力や性格から、現実的な選択肢を複数提示し、親子での話し合いをサポートしています。」
複数の選択肢を提示されることで、親子で納得できる中間地点が見つかることがあります。
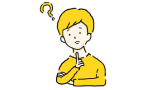
Q2. 親が「将来つぶしが効かない」と反対するのですが、どう説得すれば良いですか?
親が「将来つぶしが効かない」と反対するのは、「子供の将来に対する漠然とした不安」が原因です。
この不安を取り除くには、子供が志望する高校の具体的なメリットを、将来のキャリアプランと結びつけて説明することが効果的です。
例えば、「この高校で興味のある分野を専門的に学ぶことで、将来は○○の仕事に就きたい」といった具体的な目標を伝えることで、親も「この子は将来を考えているんだ」と安心してくれやすくなります。
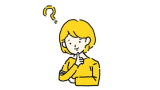
Q3. 高校見学や説明会に親が行ってくれません。どう誘えば良いですか?
親が「忙しい」「行っても意味がない」と考えている場合、まずは「この高校に行きたい具体的な理由」を伝えることが大切です。
例えば、「この学校の○○部がとても強くて、どうしても見たいんだ」や「この学科でしか学べないことがあって、どうしても親にも見てほしい」など、「親の時間を割いてもらう価値がある」と感じてもらえるように誘いましょう。
親が一人で行くのが大変な場合、「学校の先生や、教育業界の専門家が主催する合同説明会に参加してみる」という選択肢もあります。
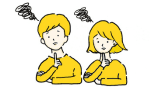
学校説明会に関する記事:高校の学校説明会に参加して志望校を決める7つのポイントを紹介!
Q4. 高校受験で親の意見を聞いて後悔しないか心配です。どう考えればいいですか?
親の意見に従うことが不安なのは当然の気持ちです。
しかし、「親の意見を聞いた=自分の意見を捨てた」と考えるのではなく、「親の意見も尊重した上で、最終的な決断をした」と捉えることが大切です。
親の意見には、社会経験からくる客観的な視点や、子供への愛情が含まれています。
「親も自分のために真剣に考えてくれた」という事実を認めることで、後悔の気持ちは和らぐはずです。
それでも心配な場合は、学校の先生や塾の先生に相談するなど、第三者の専門家を頼ることを検討してみてください。
おすすめ塾
まとめ:【高校選び】親と意見が違うときの解決策〜後悔しない進路選びのヒント

親と子供で意見が違うことは、決して悪いことではありません。
それは、お互いが真剣に将来を考えている証拠です。
大切なのは、感情的にならず、「なぜ意見が違うのか」を理解し、「どうすれば納得できる選択ができるか」を共に考えることです。
このプロセスを通じて、子供は自分の人生を自分で選択する力を身につけ、親は子供の成長を心から応援できるようになるでしょう。
【高校選び】親と意見が違うときの解決策!後悔しない進路選びのヒント
ポイント
志望校選びは、親と子どもにとって大切なステップであり、時には意見がぶつかることもあります。
しかし、お互いの意見を尊重しながら話し合いを重ねることで、最適な選択が見えてくるものです。
親はサポート役として情報を提供し、子どもが自分の意思で未来を切り開けるよう支えていくことが大切です。
最終的に、親と子どもが一緒に進んだこのプロセスが、受験の成功だけでなく、その後の充実した学校生活と成長につながることを願っています。
高校受験の進路指導に関する記事
進路指導に関する記事
執筆者のプロフィール
【執筆者プロフィール】

塾オンラインドットコム【編集部情報】
塾オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営経験者、ファイナンシャルプランナー、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。小学生・中学生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
塾オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram


