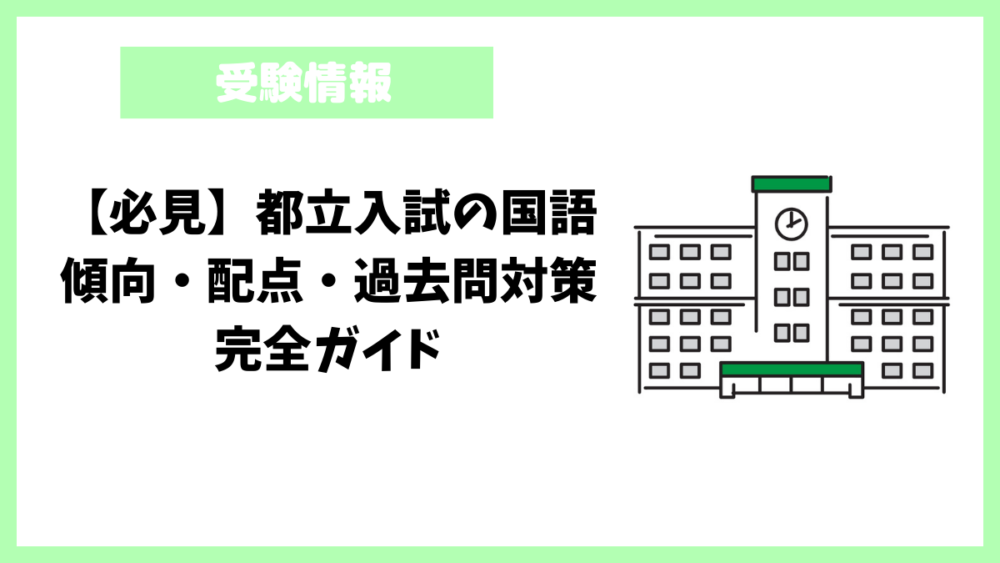
※この記事には一部PRが含まれます。
都立高校入試の国語、どう対策すればいいの?
「文章を読むのが苦手」「記述問題が全然書けない」──そんな悩みを抱えていませんか?
この記事では、2026年の都立高校入試に向けて、国語の最新傾向と対策法をわかりやすく解説します。
論説・小説・古文・記述問題など各分野の攻略ポイントに加え、得点アップに直結する勉強法や時間配分のコツまで、元個別指導塾教室長の視点から丁寧にまとめました。
都立国語が苦手な受験生でも、合格点を取るために必要な対策が1ページでわかるガイドです。
記事のポイント
都立高校入試【国語】の出題傾向と対策ポイント
都立国語の大問別対策【過去問で徹底分析】
都立高校 国語対策の効率的な勉強法&裏ワザ
令和7年度:都立国語の出題予想と直前チェック
参考記事:ヨミサマ【国語塾】の口コミ・評判は?良い・悪い声を本音で専門家が徹底分析
Contents
都立高校入試【国語】の出題傾向と対策ポイント
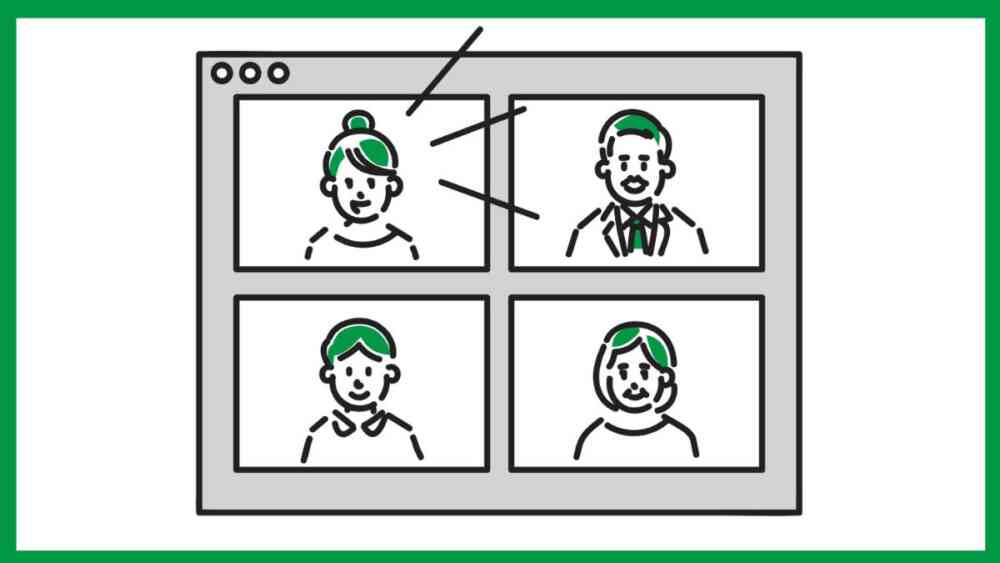
都立高校入試の国語で高得点を狙うためには、出題傾向を正確に把握し、戦略的に学習を進めることが不可欠です。
闇雲に問題を解くのではなく、どの分野から、どのような形式で、どれくらいの配点で出題されるのかを知ることで、効率的な対策が可能になります。
この章では、都立国語の出題範囲と分野別の傾向、大問ごとの配点と難易度、そして過去の平均点推移から見た難易度の変化、さらに過去問をいつから始めるべきかについて詳しく解説します。
- 国語の出題範囲と分野別の傾向(論説・小説・古典)
- 大問ごとの配点と難易度
- 国語の平均点と難易度の推移
- 過去問はいつから始めるべき?おすすめの開始時期と理由
国語の出題範囲と分野別の傾向(論説・小説・古典)
都立高校入試の国語は、大きく「論説文(説明的文章)」「小説(文学的文章)」「古典(古文・漢文)」の3つの分野から出題されます。
それぞれの分野で問われる内容は以下の通りです。
| 分野 | 主な出題内容 | 出題の特徴・傾向 |
|---|---|---|
| 論説文 | 論理的な文章の読解、筆者の主張の把握 | 現代社会の課題や、抽象的なテーマを扱うことが多い。記述問題も頻出。 |
| 小説 | 登場人物の心情や情景の把握、表現技法の理解 | 物語の展開や、主人公の心情変化を読み解く問題が中心。 |
| 古典 | 古文・漢文の読解、歴史的仮名遣い、語彙知識 | 古典常識や基本的な文法知識が必要。現代語訳や内容理解を問う。 |
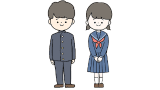
大問ごとの配点と難易度
都立高校入試の国語は、通常大問が5つで構成されており、それぞれ配点と難易度に特徴があります。
| 大問 | 内容 | 配点(目安) | 難易度(目安) | 対策のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 論説文(小問、記述) | 20点 | 標準〜やや難 | 筆者の主張と根拠を正確に読み取る練習。 |
| 2 | 小説(小問、心情把握) | 20点 | 標準 | 登場人物の心情変化に着目し、場面ごとの変化を追う。 |
| 3 | 古典(古文) | 15点 | 標準 | 歴史的仮名遣い、古典単語、基本的な文法の学習が重要。 |
| 4 | 古典(漢文) | 15点 | 標準 | 句法や漢字の意味を覚える。書き下し文の練習も有効。 |
| 5 | 作文(記述) | 30点 | 標準〜やや難 | 与えられた条件を守り、論理的な構成で文章を作成する練習。 |
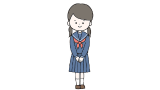
参考記事:東京の高校受験!内申点はいつから?計算方法・内申点対策を徹底解説
国語の平均点と難易度の推移
過去数年間の都立高校入試 国語の平均点を見ると、年度によって変動はあるものの、概ね70点台前半で推移しています。
これは、基礎的な読解力があれば一定の点数は取れる一方で、記述問題や応用問題で得点に差がつきやすいことを示しています。
特に、作文や要約などの記述力が求められる問題で差が出やすく、ここを攻略できるかが高得点へのカギとなります。
平均点が低下した年は、文章自体の難易度が上がったり、記述問題の条件や評価基準が厳しくなったりする傾向が見られます。
| 年度 | 数値(点) |
|---|---|
| 2025年 | 75.0点 |
| 2024年 | 75.9点 |
| 2023年 | 80.8点 |
| 2022年 | 68.8点 |
| 2021年 | 72.5点 |
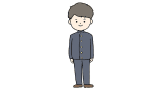
参考:令和7年東京都立高等学校入学者選抜学力検査結果に関する調査について
過去問はいつから始めるべき?おすすめの開始時期と理由
都立高校入試の国語の過去問は、遅くとも中学3年生の夏休み明け(9月頃)から始めることをおすすめします。
この時期までに基本的な読解力や語彙力が備わっていると、過去問演習から得られる効果が格段に上がります。
かつて私が指導した生徒の中には、基礎が固まらないまま過去問を解き始め、文章の内容が理解できず、かえって苦手意識を強めてしまったケースもありました。
まずは、教科書の音読や基礎的な読解問題集で土台を築くことが大切です。
都立に強い塾
個別指導なら森塾|定期テスト対策・内申点対策に強い塾
※成績保証制度は授業に自信があるからできること!しかも低料金!
個別指導WAM|難関大学の講師が親切・丁寧に合格まで導く!
※成績保証制度・月謝無料などの各種キャンペーン実施中!
都立高校入試|国語の大問別対策【過去問で徹底分析】

都立高校入試の国語で高得点を取るためには、大問ごとの特徴を理解し、それぞれに特化した対策を行うことが重要です。
闇雲に問題を解くのではなく、各分野でどのような読解力や表現力が求められるのかを把握することで、効率的な学習が可能になります。
ここでは、論説文、小説、古典、そして多くの受験生が苦手とする記述・要約問題の具体的な出題パターンと対策について詳しく解説していきます。
- 都立高校入試対策:国語の出題傾向
- 論説文(説明的文章)の傾向と対策
- 小説(文学的文章)の傾向と対策
- 古典(古文・漢文を含む)の傾向と対策
- 記述問題・要約問題の出題パターンと対策
都立高校入試対策:国語の出題傾向
都立高校入試対策:国語の出題傾向を表にしてみました。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 論説文・説明文 | ● | ● | ● | ● |
| 随筆・日記 | ||||
| 小説 | ● | ● | ● | ● |
| 詩 | ||||
| 俳句 | ● | |||
| 古典 | ● | ● | ● | |
| 漢字 | ● | ● | ● | ● |
| 四字熟語 | ||||
| ことわざ・慣用句 | ||||
| 文法 | ● | ● | ● | ● |
| 作文等 | ● | ● | ● | ● |
都立高校入試において、国語は主要科目であり、その得点は合否に直結します。
出題傾向としては、論説文、小説、古典からバランスよく出題され、基礎的な読解力から、記述・要約といった高度な表現力まで幅広く問われるのが特徴です。
特に、文章全体を把握し、筆者の意図を正確に読み取る読解力が求められます。
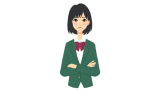
論説文(説明的文章)の傾向と対策
論説文は、筆者の主張とその根拠を正確に読み取ることが求められます。
抽象的な内容や専門用語が含まれることもありますが、文章の構成(序論・本論・結論)を意識して読むと理解しやすくなります。
対策としては、接続詞や指示語に注目すること、そして段落ごとの要点をまとめる練習が効果的です。
かつて私が指導した生徒で、論説文が苦手だった子が、段落ごとにマーカーでキーワードに印をつける習慣をつけたところ、論理の流れを捉えられるようになり、得点が向上しました。

参考記事:V模擬で高得点を取る勉強法と活用ポイントを教えます!【都立高校入試対策】
小説(文学的文章)の傾向と対策
小説では、登場人物の心情や情景の変化を読み解くことが重要です。
特に、心情を表す言葉や、比喩表現、セリフに注目しましょう。
場面転換を意識して読むことで、物語の流れを把握しやすくなります。
対策としては、登場人物の関係性や置かれた状況を図に書き出す練習も有効です。
感情移入しすぎず、客観的に文章を分析する視点を養うことが大切です。

参考記事:国語の文章問題を解くコツを中学生にアドバイス!国語の苦手を克服
古典(古文中心)の傾向と対策
都立高校入試の古典は、近年では古文のみが出題されており、漢文は過去5年間出題されていません。
そのため、対策も古文に重点を置くのが現実的です。
古文では、歴史的仮名遣いや基本的な古典単語、助動詞・助詞などの文法知識が問われます。
まずは基本的な語彙や文法をしっかり覚えることが最優先です。
声に出して読むことでリズムや言い回しに慣れることができ、理解が深まります。
私が指導した生徒には、有名な物語の冒頭を毎日音読させ、古文特有の言葉づかいに自然に慣れさせるようにしていました。

記述問題・要約問題の出題パターンと対策
記述問題や要約問題は、都立国語の配点の高い重要ポイントです。単に答えを見つけるだけでなく、文章全体の要点を把握し、自分の言葉で論理的に説明する力が求められます。
出題パターンとしては、筆者の主張や登場人物の心情を〇〇字以内で説明させるもの、文章全体を要約させるものなどがあります。
対策としては、「何が問われているのか」を正確に理解し、文章中から必要な情報を過不足なく抜き出し、簡潔にまとめる練習を繰り返しましょう。
模範解答と比較し、自分の解答のどこが不足しているかを分析することが重要です。
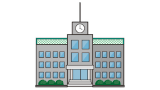
都立高校入試対策:国語の問題数と時間配分
都立高校入試における国語の時間配分について以下の表にまとめてみました。
ちなみに国語の制限時間は50分です。
| 解答数 | 時間配分 | |
| 大問1 | 5 | 1分 |
| 大問2 | 5 | 1分 |
| 大問3 | 5 | 13分 |
| 大問4 | 5 | 13分 |
| 大問5 | 5 | 17分 |
| 合計 | 25 | 45分 |
都立に強いオンライン塾
無料体験で入会金が免除になる!オンライン個別指導そら塾
※保護者が選ぶオンライン学習塾NO.1を獲得!しかも低料金!
圧倒的な合格実績!オンラインプロ教師のメガスタ!
※全国に40,000人の講師が在籍!きっとあなたにピッタリの講師が見つかる!
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師は全員東大生・東大院生!最高レベルの授業がこの価格で実現!
都立国語の漢字対策|5点を確実に取るために

都立高校入試の国語では、毎年必ず漢字の読み書き問題が出題され、得点源となる重要な5点を占めています。
漢字は、覚えた分だけ確実に点数に結びつきやすい分野です。
この章では、都立国語の漢字問題の出題形式や配点、頻出パターン、そして効果的な学習法まで、「落とせない5点」を確実に取るための対策を詳しく解説していきます。
- 出題形式と配点|毎年どんな漢字が出る?
- 漢字の頻出パターンと出題傾向【読み・書き】
- 本番直前にチェックすべき漢字リストと覚え方のコツ
出題形式と配点|毎年どんな漢字が出る?
都立高校入試の漢字問題は、通常、大問1の小問として出題されます。
配点は1問1点の場合が多く、読みと書きがそれぞれ数問ずつ出題されるのが一般的です。
例えば、読み問題では「供給」の読み方を問われたり、書き問題ではひらがなで書かれた「しんぽ」を漢字で書かせる、といった形式です。
出題される漢字は、中学校で学習する常用漢字が中心です。
中には日常生活であまり使わないような熟語や、間違いやすい漢字が含まれることもあります。
長年指導してきましたが、ここでミスをする生徒は、基本的な漢字の定着が不十分な場合が多いです。
油断せず、基礎からしっかり対策することが重要です。

参考記事:漢字の勉強ができる中学生がやっている勉強法と漢字ドリル10選
漢字の頻出パターンと出題傾向【読み・書き】
都立国語の漢字問題には、いくつかの頻出パターンと出題傾向があります。
- 読み問題
- 音読みと訓読みの区別:「今日(きょう)」と「今日(こんにち)」のように、文脈によって読み方が変わる漢字。
- 送り仮名に注意する読み方:「行われる」「行う」など、送り仮名で読みが変わるもの。
- 常用漢字の範囲外からの出題:基本的には常用漢字が中心ですが、ごく稀に発展的な語彙が出ることがあります。
- 書き問題
- 同音異義語:「効果」と「高価」、「こうかい(後悔・航海)」のように、同じ読みで異なる漢字。
- 部首や画数を間違えやすい漢字:「憂鬱」「薔薇」といった複雑な漢字。
- 熟語の構成:「上下」「左右」のように、漢字の並び順や意味の構成を問うもの。
私が担当した生徒で、「環境」という漢字の書き取りが苦手な生徒がいました。
その生徒は「かんきょう」と音で覚えるだけでなく、「環(めぐる)境(さかい)」のように、それぞれの漢字が持つ意味を理解することで、確実に書けるようになりました。
意味で覚えることは、単なる丸暗記よりも定着率が高まります。
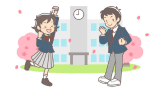
本番直前にチェックすべき漢字リストと覚え方のコツ
入試本番直前は、新しい漢字を覚えるよりも、これまでに学習した漢字の総復習と、特に間違いやすい漢字の最終確認に徹しましょう。
- 直前チェックリストの作成:これまでの模擬試験や問題演習で間違えた漢字をリストアップし、その漢字だけを集中的に復習します。
- 「書ける」だけでなく「見た瞬間に読める」か確認:読み問題は、反射的に読めるレベルになっているかを確認しましょう。
- 同音異義語、類義語の最終確認:意味の違いを問う問題に対応できるよう、似た読みの漢字や似た意味の熟語を再確認します。
私が教えていた生徒の中には、直前に間違えやすい漢字だけをカードに書き出して持ち歩き、隙間時間に確認するという工夫をしていました。
視覚と聴覚、そして書くという動作を組み合わせることで、記憶の定着を促すことができます。
本番で「あれ、この漢字、どっちだっけ?」とならないよう、自信を持って解答できるように準備しましょう。
都立高校入試:国語対策の効率的な勉強法&裏ワザ

都立高校入試の国語で目標点に到達するためには、ただやみくもに問題を解くだけでは不十分です。
効率的な勉強法と、知っていると差がつく「裏ワザ」的なテクニックを組み合わせることが大切です。
ここでは、国語の効率的な学習の進め方、試験時間50分を最大限に活用するための時間配分のコツ、そして多くの受験生が苦手とする記述問題・要約問題攻略の「型」について、具体的なアドバイスをお伝えします。
- 国語の基礎固めと読解力・語彙力アップのステップ
- 解答時間50分を最大限に活かす時間配分とコツ
- 記述問題・要約問題攻略の「型」
- 知っておくと得する都立国語の裏ワザ・テクニック
国語の基礎固めと読解力・語彙力アップのステップ
国語の勉強は、まず「語彙力」と「文法力」の基礎固めから始めましょう。
知らない言葉が多いと、どんな文章も理解できません。
毎日継続して文章を読む習慣をつけることが読解力向上には不可欠です。
かつて私が指導した生徒で、読書習慣がなかった子が、新聞のコラムを毎日読むことを習慣化したところ、文章を読み解くスピードと精度が格段に上がりました。
少しずつでも良いので、良質な文章に触れる機会を増やしましょう。

参考記事:都立高校入試対策!教科別勉強法・出題傾向・内申対策【高校受験完全ガイド】
解答時間50分を最大限に活かす時間配分とコツ
都立高校入試の国語は、試験時間が50分と限られています。
この時間を最大限に活用するためには、大問ごとに目安の時間を設定することが重要です。
例えば、小問集合や選択問題は短時間で、論説文や小説の記述問題には時間をかけるなど、配点や難易度に応じたメリハリをつけましょう。
【都立国語|現実的な時間配分表(見直し含む)】
| 大問 | 内容 | 目安時間(分) | 対策のコツ |
|---|---|---|---|
| 1 | 論説文 | 10 | 選択肢は速く、記述は丁寧に進める。 |
| 2 | 小説 | 10 | 登場人物の心情を追いつつ、時間配分を意識。 |
| 3 | 古典(古文) | 7 | 知らない単語は前後の文脈で推測、わからなければ次へ。 |
| 4 | 古典(漢文) | 6 | 句法を意識し、意味が取れなければ深追いしない。 |
| 5 | 作文 | 12 | 最初に構成を考え、書く時間を確保。論理の一貫性を意識。 |
| ― | 見直し時間 | 5 | 記述・作文のミスや空欄を重点的にチェック。 |
もし途中で解答に詰まってしまったら、潔く次の問題に移る勇気も必要です。
最後に時間を見つけて戻るという戦略が、焦りを防ぎ、冷静な判断を促します。
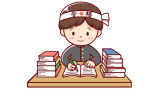
参考記事:【中学生国語の勉強法】基礎力アップ!読解・記述・文法の苦手を攻略
記述問題・要約問題攻略の「型」
国語の記述問題や要約問題は、一見難しそうに見えますが、実は解答の「型」を覚えることで格段に書きやすくなります。
- 要約問題:「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」という5W1Hの要素を意識し、不要な具体例は削る。
私が担当した生徒には、過去問の模範解答を何度も書き写し、解答のパターンを体に染み込ませるよう指導しました。
この反復練習が、本番でのスムーズな記述に繋がります。
- 記述問題:「〜という点」「〜によって」「〜と考えられる」といった、論理的な接続や表現の型を身につける。
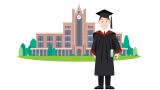
知っておくと得する都立国語の裏ワザ・テクニック
都立国語の入試には、知っていると解答時間を短縮したり、ミスを減らしたりできる「裏ワザ」的なテクニックが存在します。
【都立国語 入試対策の裏ワザテクニック一覧】
| 出題分野 | 裏ワザテクニック | 解説 |
|---|---|---|
| 論説文(説明文) | 設問を先読みしてから本文を読む | 先に設問の内容を把握しておくことで、「何を意識して読めばいいか」が明確になります。特に記述問題や主張把握は、この順序で読んだ方が迷いが減ります。 |
| 小説 | 心情の変化は「セリフ・行動・地の文のズレ」に注目 | 主人公の気持ちはセリフではなく「地の文」や「動作の変化」に現れやすい。セリフと地の文が食い違うときは、内面の葛藤を読み取るチャンス。 |
| 古文 | 主語を補いながら現代語訳する習慣を | 古文では主語が省略されがち。誰の行動か迷ったら、「登場人物の行動順」「敬語の相手」から推測し、メモ書きすると正答率が上がります。 |
| 漢字・語彙 | 四字熟語・慣用句・類義語は選択肢の消去法を使う | 意味がわからない語があっても、明らかに文脈と合わないものを消去すれば、2択までは絞れます。選択肢の「語感」も大事。 |
| 作文(記述) | 「結論→理由→具体例」の3段構成をテンプレに | 与えられたテーマには、最初に自分の考え(結論)を書き、理由と具体例を順番に続けることで、読みやすく論理的な構成になります。練習しておくと安定した点が取れます。 |
【元教室長からの裏ワザアドバイス】
- 本文中に「正解の根拠がある」と思って探す
- 都立国語の多くの問題は、本文に根拠が明確にあるように作られています。「なんとなく」ではなく、「本文のどこに書いてあるか」を探すクセをつけましょう。
- 「問の直前の段落」に答えのヒントがある
- 特に説明文の内容理解問題は、「設問に該当する段落の直前」が狙われることが多いです。
- 記述問題は「設問文のキーワードを写す」ことから始める
- 書き出しに困ったら、「○○とは〜である」や「○○から△△がわかる」など、設問文の言い回しを使うと書きやすくなります。
都立に強い塾
個別指導なら森塾|定期テスト対策・内申点対策に強い塾
※成績保証制度は授業に自信があるからできること!しかも低料金!
個別指導WAM|難関大学の講師が親切・丁寧に合格まで導く!
※成績保証制度・月謝無料などの各種キャンペーン実施中!
2026年:都立国語の出題予想と直前チェック

2026年の都立高校入試国語に向けて、最新の出題傾向を予測し、直前対策を行うことは非常に重要です。
過去の出題傾向から、特に狙われやすい分野や、直前1週間で集中して取り組むべきこと、そして自身の苦手単元を最終確認するための具体的な方法について解説します。
これらの情報を活用して、本番で最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、万全の準備をしましょう。
- 2026年は〇〇が狙われる?過去の出題との比較
- 国語の直前1週間でやるべきこと
- 苦手単元克服のための“最終確認表”
2026年は〇〇が狙われる?過去の出題との比較
過去数年の都立高校入試国語の出題傾向を見ると、特定の分野が連続して多く出題されたり、逆にしばらく出題されていない分野が翌年に大きく扱われたりすることがあります。
例えば、近年は論説文における社会問題や科学技術に関するテーマが多く見られますが、過去には心情描写の複雑な小説が出題された年もありました。
2026年度は、特に古典分野で、文法的な知識だけでなく、時代背景を問うような応用問題が増える可能性も考えられます。
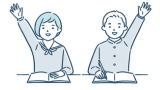
国語の直前1週間でやるべきこと
入試直前の1週間は、新しい知識を詰め込むよりも、これまで学習した内容の総復習と苦手分野の最終確認に徹しましょう。
特に、以下の3点に注力することをおすすめします。
- 過去問の解き直し:特に間違えた問題をもう一度解き、なぜ間違えたのかを徹底的に分析してください。
- 記述・要約問題の最終確認:これまでに解いた記述・要約問題の模範解答を読み返し、自分の解答と比較する。
- 古典の重要語句・句形の復習:古典単語帳や文法書を見直し、基礎知識を定着させます。
私が教えていた生徒の中には、直前期に焦って新しい問題集に手を出し、かえって混乱してしまったケースがありました。
焦らず、着実にこれまで積み上げてきたものを確認することが、合格への近道です。
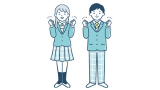
苦手単元克服のための“最終確認表”
入試直前に自分の苦手単元を客観的に把握し、効率よく復習するためには、「最終確認表」を作成するのが効果的です。
例えば、以下のような表を作り、理解度を視覚化します。
| 分野 | 単元 | 理解度 | 対策内容 |
|---|---|---|---|
| 論説文 | 筆者の主張の把握 | △ | 接続詞・指示語に着目した読解演習 |
| 小説 | 心情の変化 | ○ | 場面ごとの心情変化をメモ |
| 古典 | 古典単語・歴史的仮名遣い | × | 単語帳・文法書を使った暗記、問題演習 |
| 作文 | 構成の仕方 | △ | 模範解答の構成を分析、アウトライン作成練習 |
△や×の単元を優先的に復習し、自信を持って本番に臨めるようにしましょう。
【Q&A】都立入試の国語・出題傾向・配点等に関するよくある質問

都立高校入試の国語について、受験生や保護者の皆さんが抱えるよくある疑問や不安にお答えします
。国語が苦手でも合格できるのか、効率的な学習方法、そして過去問で点が取れない場合の対処法など、長年の指導経験から得た知見をもとに、具体的なアドバイスを提供します。
これらの疑問を解消することで、安心して学習に集中し、目標達成に向けて自信を持って進むことができるでしょう。
- 都立高校の国語の難易度は?
- 都立高校入試の国語の平均点は?
- 都立入試の国語の漢字の配点は?
- 都立高校入試の国語の満点は?
- 都立高校入試は700点満点ですか?
都立高校の国語の難易度は?
都立高校入試の国語は、他の科目と比べて比較的得点しやすいと言われています。
その理由は、平均点が毎年安定して高いからです。
例えば、2024年度の平均点は75.9点と、高得点をキープしています。
問題の内容は教科書の基礎的な知識をもとに構成されており、漢字や読解問題など、中学生が日ごろの授業や定期テストで目にする形式が多いです。
ただし、記述問題では採点基準が厳しいこともあるので、答え方の練習が必要です。
「基礎は簡単だけど記述で差がつく」と意識して対策するのが成功のカギです。
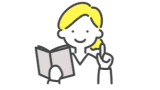
都立高校入試の国語の平均点は?
都立高校入試の国語は、毎年平均点が高めで、2024年度には75.9点を記録しました。
この点数は他の科目と比べても高い傾向にあり、得点しやすい科目と言えます。
一方で、全体的に点数が取りやすいからこそ、平均点に届かないと不利になる可能性があります。
特に漢字や基本的な読解問題で確実に得点を取ることが重要です。
過去問を使って、時間内に解く練習をしておくと、効率よく得点を伸ばせます。
得点が安定しやすい科目として計画的に対策しましょう。

都立入試の国語の漢字の配点は?
都立高校入試の国語では、漢字だけで20点分が配点されています。
大問1で漢字の読み5問(各2点)、大問2で漢字の書き5問(各2点)が出題されるのが基本の形式です。
これは全体の20%に相当し、都立入試では漢字が非常に重要な位置を占めています。
例えば、「環境(かんきょう)」「挑戦(ちょうせん)」など、中学生が日ごろ習う漢字が中心です。
漢字の読み書きで失点を減らすことが、高得点への第一歩です。
日常的に漢字練習帳や過去問を活用しましょう。

都立高校入試の国語の満点は?
都立高校入試の国語は100点満点です。
その中で、漢字の配点が20点と大きな割合を占めており、残りの80点は読解や記述問題、文法の問題で構成されています。
100点満点というシンプルな配点ながら、漢字や記述問題の比重が高い点が特徴です。
例えば、読解問題では、物語文や説明文の要点を押さえる力が求められます。
記述式の解答では採点基準に合った正確な文章を書くことが得点アップにつながります。
全体を通してバランスよく対策を進めましょう。

都立高校入試は700点満点ですか?
都立高校入試は、学力検査と内申点を合計した1020点満点で評価されます。
学力検査は5教科で700点満点、内申点(調査書点)は300点満点です。
2024年度以降は英語スピーキングテスト(ESAT-J)が加わり、これが20点満点で計算されます。
最終的な合否はこれらの合計点で決まります。
学力検査で高得点を取るためには、各科目で得点できるポイントを押さえつつ、内申点の対策も進めておくことが重要です。
全体のバランスを意識して受験に臨みましょう。
国語の勉強にタブレット学習教材が中学生におすすめ!
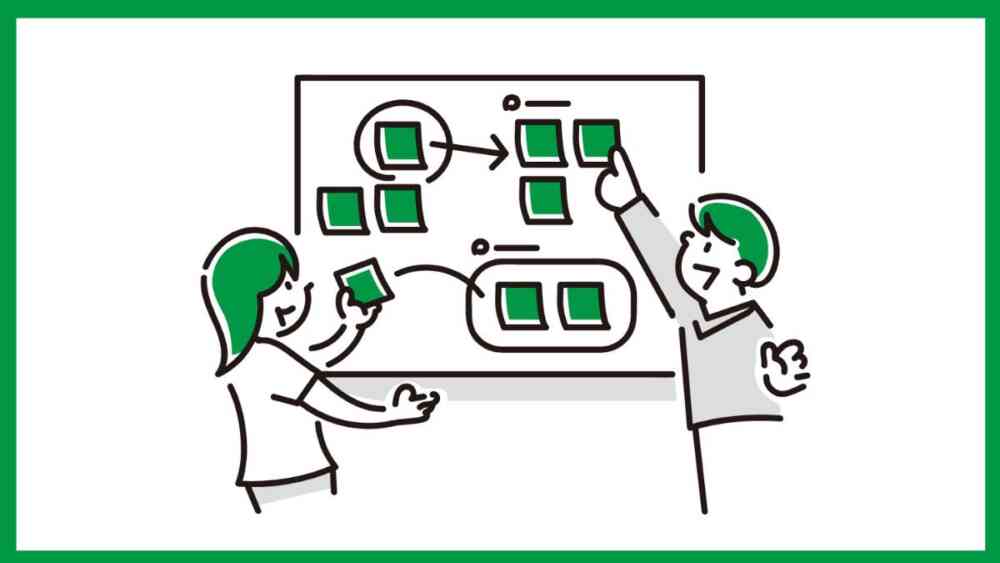
国語の勉強におすすめタブレット学習教材比較表
| タブレット学習教材名 | 月謝 | 特徴 |
| 進研ゼミ:中学講座 | 中学1年生:6,400円〜 | ベネッセが提供している、タブレット学習教材。中学生の利用者数No.1。 |
| すらら | 小中コース 8,000円〜 | AI×アダプティブラーニング「すらら」、マナブをサポートする最先端学習システム。小学生から高校生まで、国・数・理・社・英の5教科を学習できるICT教材 |
| スマイルゼミ | 7,480円〜 | 「まなぶ」「みまもる」「たのしむ」の3つのバランスを大切にして、勉強したい気持ちを逃さない。 |
| デキタス | 中学生:5,280円〜 | 勉強嫌いでも、勉強が習慣化できる!おすすめのタブレット学習教材 |
※オンライン料金の詳細については公式サイトからお問い合わせください。※社名をタップすると公式ホームページに移動します。
※学年や講師ランク・授業時間により料金は変動します。
進研ゼミ:中学講座は国語の勉強におすすめの教材
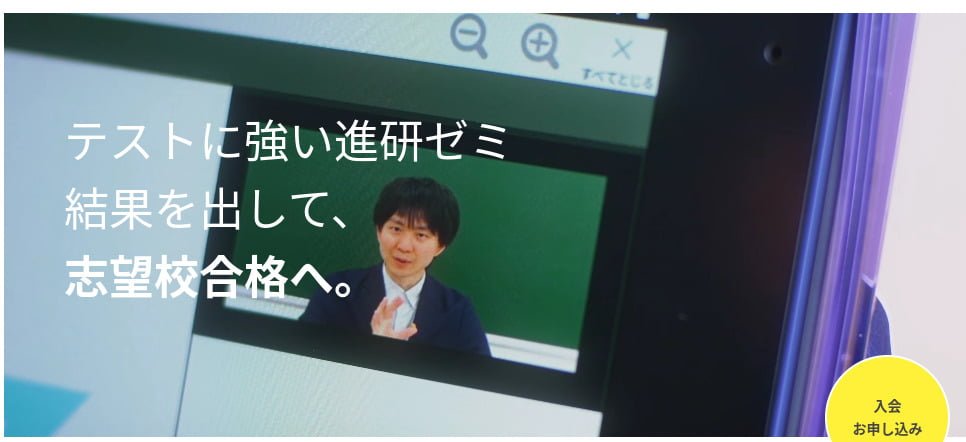
中学生利用者NO.1!進研ゼミ:中学講座の基本情報
| 月謝 | 【月謝例】 中学1年生:6,400円〜 中学2年生:6,570円〜 中学3年生:7,090円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、理科、社会、英語 |
| 学習機能 | 教科書対応のテキストで、予習も復習もバッチリ! お使いの教科書に合わせたテキストなので、予習はもちろん復習にも効率的に |
| 管理機能 | AIのレッスン提案で迷わない実力に合わせて学習スタート 学習達成後のごほうびでやる気が続く |
| サポート体制 | 月1回、赤ペン先生がお子さま一人ひとりを添削し、丁寧に指導。担任制なので、毎回同じ先生に提出する楽しみがうまれ、毎月の学習の仕上げとしてしっかり取り組めます。 |
進研ゼミ中学講座の特徴
進研ゼミ中学講座は、ベネッセコーポレーションが提供している中学生向けの通信教育です。
1969年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。進研ゼミ中学講座の特徴は、以下の通りです。
- 学校の授業内容に沿った教材で、予習・復習が効率的にできる。
- タブレット学習を利用することで、ゲーム感覚で学習できます。
- 赤ペン先生による添削指導で、記述力や思考力を鍛えられる。
- 応用問題や演習問題で、実力を身につけられる。
- 夏休み特訓や冬期講習など、季節ごとの特別講座が充実しています。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
進研ゼミ中学講座は、中学校の授業内容をしっかり学びたい、記述力や思考力を鍛えたい、夏休みや冬休みの学習を充実させたい、といった中学生におすすめです。
\中学生の利用者NO.1の通信教育/
安心して利用できる
↓↓↓
進研ゼミ中学講座の公式HP
すらら:無学年方式オンライン教材で国語の勉強

「すらら」の基本情報
| 受講費用の安さ | ■入会金 ・小中・中高5教科コース:7,700円 ・小中・中高3教科、小学4教科コース:11,000円 ■3教科(国・数・英)コースの月謝例 ・小中コース 月額:8,800円〜 小学1年生~中学3年生までの3教科(国・数・英)の範囲が学び放題 ・中高コース 月額:8,800円〜 |
| 対応科目・コース | 4教科(国・数・理・社)コース 5教科(国・数・理・社・英)コース 無学年方式で中学英語も先取り学習できる |
| 学習機能 | キャラクターによるレクチャーからドリル機能が充実 「すらら」は読み解くだけではなく、見て、聞いて学べる |
| 管理機能 | 「すらら」はAI搭載型ドリルだから自分のつまずきポイントがわかる! |
| サポート体制 | 学習習慣の身に付け方を始めとした学習に関する悩みや、基礎学力、成績を上げるための学習設計をサポートします。 |
すららの特徴
すららは、株式会社すららネットが提供している中学生向けのオンライン学習教材です。
2010年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
すららの特徴は、以下の通りです。
- 学年にとらわれない無学年方式で、子どものペースに合わせて学習できます。
- 子どもの弱点をAIが自動診断し、苦手な分野を効率的に克服できます。
- ゲーム感覚で学習できるので、勉強が苦手な子どもでも楽しく学習できます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
すららは、学習に苦手意識を持っている子どもや、効率的に学習を進めたい子どもにおすすめです。
当サイトで人気No.1の通信教材!
是非!すららを選択肢の一つに
↓↓↓
すららの公式サイトはこちらから
スマイルゼミ:国語の学びが継続するタブレット教材
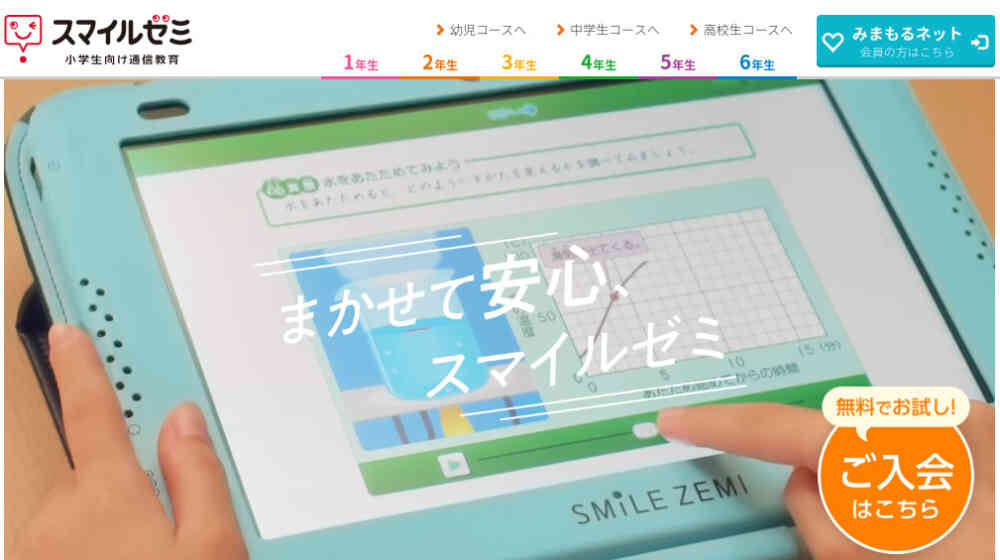
スマイルゼミの基本情報
| お手軽な受講費用 | 【中学1年生】月謝例 <標準クラス> ・7,480円〜:12か月一括払い/月あたり |
| 対応科目・コース | 国語・数学・理科・社会はもちろんのこと、英語やプログラミングも1年生から学習できる |
| 学習機能 | アニメーションによる解説で公式の持つ意味を正しく理解できる 手をついて書ける学習専用タブレットを使用 |
| 管理機能 | スマイルゼミのタブレットは、利用時間を「1日〇時間」という形で制限可能 |
| サポート体制 | 全額返金保証制度あり |
スマイルゼミの特徴
スマイルゼミは、ジャストシステムが提供している中学生向けのタブレット学習教材。
2012年にスタートして以来、多くの中学生に利用されてきました。
スマイルゼミの特徴は、以下の通りです。
- タブレット端末を使って学習できるので、ゲーム感覚で楽しく学べます。
- 子どもの学習状況をAIが分析して、一人ひとりに合った学習内容を自動的に提案してくれます。
- 保護者向けのサポートサイトがあり、子どもの学習状況を把握できます。
スマイルゼミは、タブレットで最適な学習を継続させたい人におすすめです。
中学生の学びが継続するタブレット
\返金保証制度あり/
↓↓↓
スマイルゼミの公式サイトをチェック
中学生の国語の勉強に最適なタブレット教材:デキタス
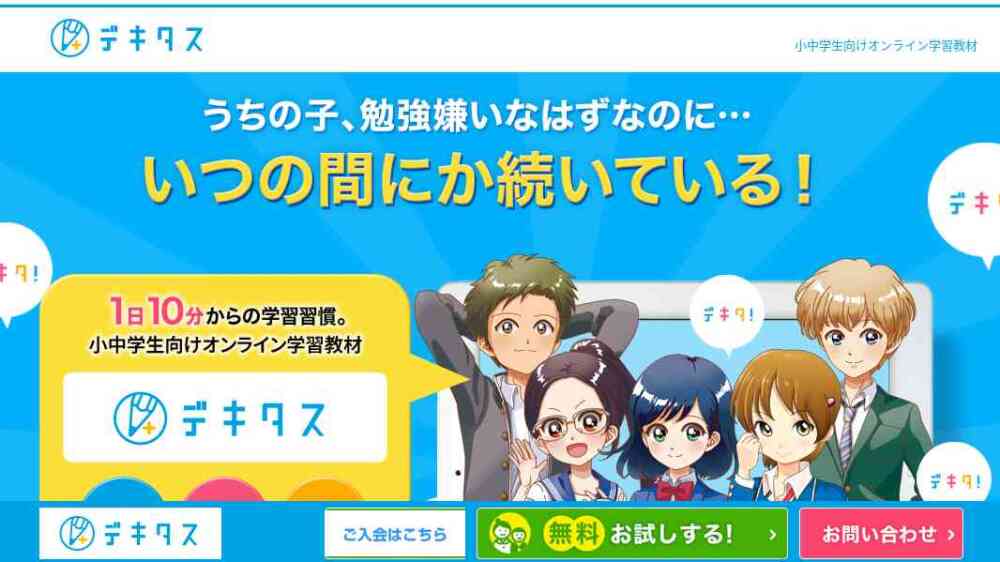
中学生におすすめ!デキタスの基本情報
| 項目 | デキタスの公式サイト |
| 受講費用 | 中学生:5,280円〜 |
| 対応科目・コース | 国語、数学、英語、理科、地理、歴史、公民、国文法、英語検定 |
| 学習機能 | ポップなキャラクター&わくわくする授業! |
| 管理機能 | テストモード搭載 |
| サポート体制 | 学習結果は表・グラフ・カレンダー等でひと目で確認することができます。 |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
デキタスのおすすめポイント
学校の勉強を確実に理解していくことを目指し開発された、小中学生用オンライン学習教材です。
教科書内容に合った映像授業や、演習問題。さかのぼり学習で前の学年前の授業に戻ったり、定期テスト問題を作成して挑戦したりと、学校の勉強を自宅で、自分のペースで自由に行えます。
以下にデキタスの特徴を3つ紹介します。
段階的な学習体系: デキタスは「授業」→「○×チェック」→「基本問題」→「チャレンジ問題」というスモールステップで構成され、基礎から応用まで段階的に学習が進められます。この体系により、生徒は小さな成功体験を積み重ねながら学習し、「デキタ!」の達成感を実感できます。
デキタ'sノートと複合学習: デキタスでは授業に沿った穴埋め式ノートが印刷可能であり、デジタル教材と紙と鉛筆を組み合わせて効果的な学習ができます。この複合学習により、視覚的なデジタル学習と手書きによるノート作成が組み合わさり、理解の定着が促進されます。
学習習慣の形成: デキタスは学習結果を表・グラフ・カレンダーで確認し、保護者と共有する機能があります。親子で学習状況を共有し、成績アップを目指すことで学習習慣が自然に形成されます。
教科書の内容を確実に理解
学校の成績が上がる!
↓↓↓
デキタスの公式サイトチェック!
まとめ:【必見】都立入試の国語|傾向・配点・過去問対策|完全ガイド

都立高校入試の国語を攻略し、目標の高校に合格するためには、今から計画的に、そして効率的に学習を進めることが何よりも大切です。
これまで解説してきた出題傾向の把握、頻出問題への対策、そして効率的な勉強法を実践することで、皆さんの国語の得点は大きく伸びるはずです。
ここでは、具体的な学習スケジュールと過去問の活用法、そして志望校別の戦略的アプローチについて、最後にまとめとしてお伝えします。
おすすめの3か月学習スケジュール【都立国語 勉強スケジュール】
都立国語の3か月学習スケジュールは、以下のように進めるのが理想的です。
| 月数 | 学習内容 | 具体的な取り組み |
|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 基礎固めと苦手分野の洗い出し | 語彙・文法強化。論説・小説の基本的な読解練習。簡単な問題集で苦手単元を特定。 |
| 2ヶ月目 | 頻出問題の演習と記述・要約対策の基礎 | 過去問や頻出問題集で出題傾向に沿った演習。記述・要約問題の「型」を意識した練習。 |
| 3ヶ月目 | 実践演習と最終調整 | 時間を測って過去問を解く実戦演習。間違えた問題や記述を中心に徹底復習。 |
かつて私が指導した生徒で、このスケジュールを忠実に守った生徒は、着実に国語の点数を上げていました。
過去問の徹底活用と効果的な振り返り方法
過去問は、都立高校入試の国語対策における最強の教材です。
ただ解くだけでなく、以下の点を意識して活用し、徹底的に振り返りましょう。
- 時間配分を意識して解く:本番と同じ時間制限で解き、時間配分の感覚を養います。
- 解答だけでなく、解説を熟読する:なぜその答えになるのか、他の選択肢がなぜ違うのかを理解することが重要です。
- 記述・要約問題は模範解答と照らし合わせる:自分の解答のどこが不足しているのか、どのように表現すればより良くなるのかを分析します。
間違えた問題や苦手な形式の問題は、必ずノートにまとめ、繰り返し見直すことが、同じ間違いを繰り返さないための鍵となります。
志望校別の戦略的アプローチ
都立高校は、共通問題だけでなく、一部の学校で独自問題が課される場合もあります。
ご自身の志望校の過去問を研究し、その学校独自の出題傾向や難易度を把握することが重要です。
例えば、国語の作文の配点が高い学校であれば、より作文対策に力を入れる必要がありますし、古典の難易度が高い学校であれば、古典の基礎を徹底的に鍛えるべきです。
「あなただけの合格戦略」を立て、残りの期間を最大限に有効活用していきましょう。
国語の勉強法
国語の勉強法です。
参考にしてください。
国語の勉強法
都立関連の記事
都立高関連の記事
都立高校受験に強いオンライン塾・個別指導塾20選│偏差値アップ!
東京の高校受験!内申点はいつから?計算方法・内申点対策を徹底解説
都立入試の内申点(調査書点)を300点に換算する計算方法をわかりやすく解説
【2026年】都立高校入試の受験料と日程を全解説!いつ、どうやって払う?
都立高校推薦「小論文・作文」対策!過去問分析と模範解答を活用した書き方
【都立高校入試】過去問はいつからやるのか?何年分やるの?徹底解説
都立推薦で受かる子・落ちる子の違いとは?受かるためのポイント!
V模擬で高得点を取る勉強法と活用ポイントを教えます!【都立高校入試対策】
都立高校入試対策!教科別勉強法・出題傾向・内申対策【高校受験完全ガイド】
都立の高校説明会で気をつけること!高校見学はいつから始まるの?
【2026年】都立高校入試「理科の傾向と対策」記述・頻出分野を徹底解説
都立入試社会でよく出る問題まとめ!出題傾向&裏ワザを徹底解説
塾オンラインドットコムおすすめ塾の紹介
オンライン塾


