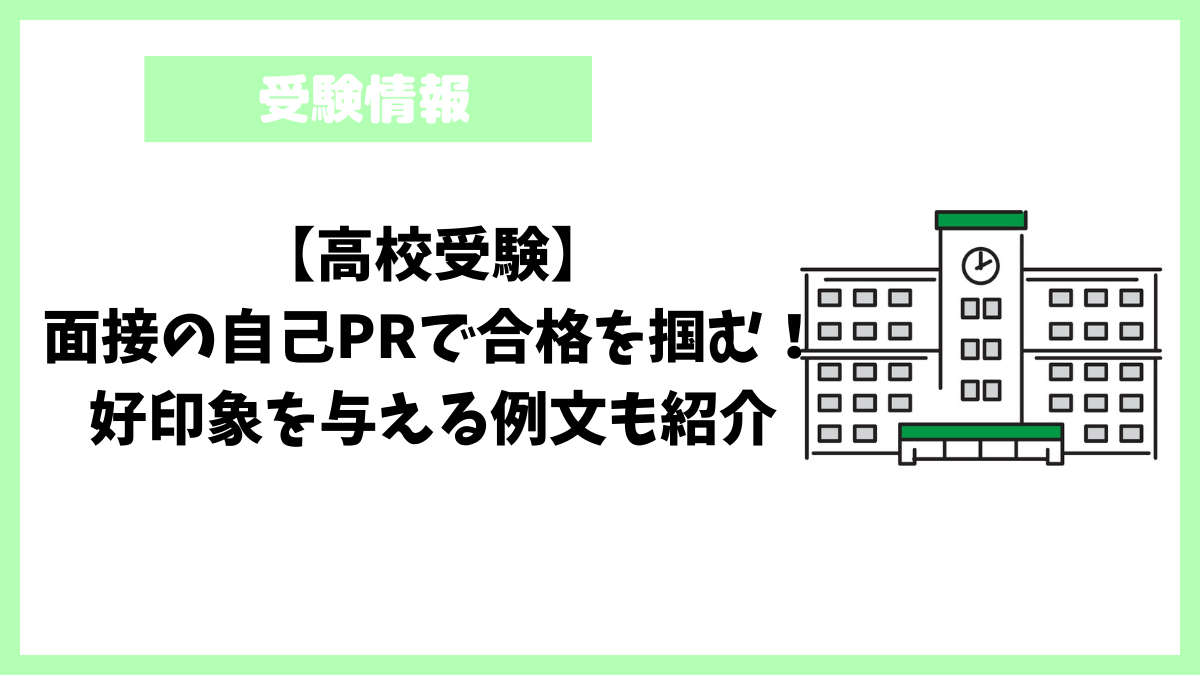
※この記事には一部PRが含まれます。
「理科は暗記が多そうで苦手…」「どうやって効率よく覚えればいいの?」とお悩みの皆さん、ご安心ください。
この記事では、私が長年大手個別指導塾の教室長として培った経験と、数々の合格実績から導き出した「高校受験理科で9割を目指す暗記法」を徹底解説します。
頻出分野の語呂合わせから、暗記が苦手な方でも実践できる効率UP勉強法、さらには合格者の成功事例まで、理科を得点源にするための秘訣を余すことなくお伝えします。
記事のポイント
高校受験理科の暗記が楽になる!よく出る問題と語呂合わせ一覧で効率アップ
高校入試対策|理科の分野別暗記法と効率的な学習戦略
高校受験理科の暗記が楽になる方法:語呂合わせとその他ツール
受験本番までにやっておきたい理科の勉強
東大生家庭教師
東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
当サイトで人気の「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
オンライン東大家庭教師友の会
※東大生をはじめとする難関大生がマンツーマンでオンライン指導!講師の2人に一人が厳しい採用基準を突破した現役東大生!
オンライン家庭教師e-live
※東大生や英学部生の講師が選べるオンライン家庭教師!オンライン家庭教師の実績は15年以上!信頼と実績のあるオンライン家庭教師
MeTULAB(ミートゥーラボ)
※講師は全員現役の東大生!大学受験、高校受験合格を目指す生徒に向けて、現役の東大生から親切・丁寧な個別指導が特徴
スタディコーチ
※講師は東大生・旧帝大・早慶生!勉強の計画作成や進捗管理を行うコーチンが特徴!スタッフの丁寧な対応が印象的なオンライン家庭教師
STRUX
※東大出身の塾長が生徒を合格に導いてくれる!勉強の仕方を生徒に合わせて指導してくれるオンライン家庭教師!
国語に特化した「ヨミサマ。」
※国語に特化したオンライン個別指導塾。講師は現役東大生のみ!国語の成績が上がれば、他の教科の成績にも好影響。
Contents
- 1 高校受験理科の暗記が楽になる!よく出る問題と語呂合わせ一覧で効率アップ
- 2 高校入試対策|理科の分野別暗記法と効率的な学習戦略
- 3 高校受験理科の暗記が楽になる方法:語呂合わせとその他ツール
- 4 生物の語呂合わせ暗記法を紹介
- 5 地学の語呂合わせ暗記法を紹介【高校受験用】
- 6 化学の語呂合わせ暗記法を紹介【中学生向け】
- 7 物理の語呂合わせ暗記法を紹介
- 8 高校受験対策理科:暗記しておきたい公式一覧とその使い方
- 9 分野別(生物・地学・物理・化学)理科勉強法と対策
- 10 【高校受験】理科の基本的な勉強法(暗記法)とよくある質問
- 11 受験本番までにやっておきたい理科の勉強
- 12 合格者の暗記成功事例と実践ポイント
- 13 まとめ:【高校受験理科】暗記が苦手でも9割取れる!頻出語呂合わせ&効率UP勉強法
高校受験理科の暗記が楽になる!よく出る問題と語呂合わせ一覧で効率アップ

高校受験の理科で高得点を取るためには、単なる知識の丸暗記ではなく、出題傾向を理解し、効率的な暗記法を取り入れることが不可欠です。
このセクションでは、なぜ理科の暗記が重要なのか、そしてどのような問題が頻出するのか、さらには暗記と理解・応用のバランスについて詳しく解説していきます。
- 高校受験理科で暗記が必要な理由とは?
- 理科は暗記で高得点が稼げる
- 高校受験対策:理科でよく出る問題
- 【分野別】高校受験理科で特に暗記が必要な単元
- 暗記だけでなく「理解」と「応用」のバランスが重要
高校受験理科で暗記が必要な理由とは?
高校受験の理科は、一見計算問題が多いように思えますが、実は知識問題の配点が高く、暗記が合否を分ける重要な鍵となります。
特に、生物や地学分野では、用語や現象を正確に覚えているかが問われ、暗記力があれば着実に得点源にできます。
たとえば、細胞の構造や天体の動きなど、基本知識がなければ応用問題も解けません。
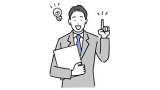
理科は暗記で高得点が稼げる
理科は、主要科目と比較して、暗記した知識が直接点数に結びつきやすい特性があります。
数学や英語のように複雑な思考力を要求される場面が少なく、覚えた分だけ確実に点数を稼げるため、効率的に学習を進めれば短期間での成績アップも可能です。
私が指導した生徒の中には、理科を苦手としていたにもかかわらず、暗記に特化した学習で短期間に得意科目に変え、見事合格を勝ち取ったケースも少なくありません。
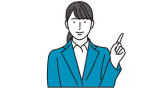
高校受験対策:理科でよく出る問題
高校受験の理科では、各分野で頻出するテーマや問題形式があります。
理科の頻出テーマを把握し、優先的に暗記することが効率的な学習への第一歩です。
具体的には、
- 生物では「植物のつくりと働き」「動物の分類」
- 地学では「天気と気象」「地震と火山」
- 化学では「化学変化と原子・分子」
- 物理では「力と運動」「電流と回路」
などが毎年よく出題されます。

参考記事:【高校入試理科】よく出る問題!一問一答形式で120問(生物・地学・物理・化学)
【分野別】高校受験理科で特に暗記が必要な単元
理科の各分野において、特に暗記が求められる単元を把握することは、効率的な学習計画を立てる上で非常に重要です。
生物では植物の分類や動物の系統樹、体のつくりなど、覚えるべき用語が多いです。
地学では気象現象の名称や地層の種類、岩石の分類が挙げられます。
化学では元素記号や化学式、化学反応の種類、物理では単位や法則の名称、記号などが、基礎となる暗記のポイントになります。

暗記だけでなく「理解」と「応用」のバランスが重要
理科の学習において、暗記は非常に重要ですが、単なる丸暗記では応用問題に対応できません。
現象や法則の「なぜそうなるのか」を理解した上で暗記することで、知識が定着し、初見の問題にも対応できる力が身につきます。
たとえば、オームの法則を覚えるだけでなく、なぜ電圧と電流が比例するのかを理解すると、計算問題への応用力が格段に上がります。
この「理解→暗記→応用」のサイクルを意識することが、真の学力向上に繋がります。
おすすめ塾
講師のほとんどが東大・東大院生
東大生が指導する塾としてはコスパが良い
オンライン個別指導
部活が忙しい生徒にも対応!
自宅で勉強できるから、集中力UP!
成績アップの近道!
30日間の返金保証制度も安心!

\トウコベの資料をダウンロード/
↓↓↓
トウコベの公式HPをチェック!
関連記事
トウコベの口コミ・評判・レビュー【小中学生の保護者向け】講師の質・サポート・効果を徹底検証
高校入試対策|理科の分野別暗記法と効率的な学習戦略
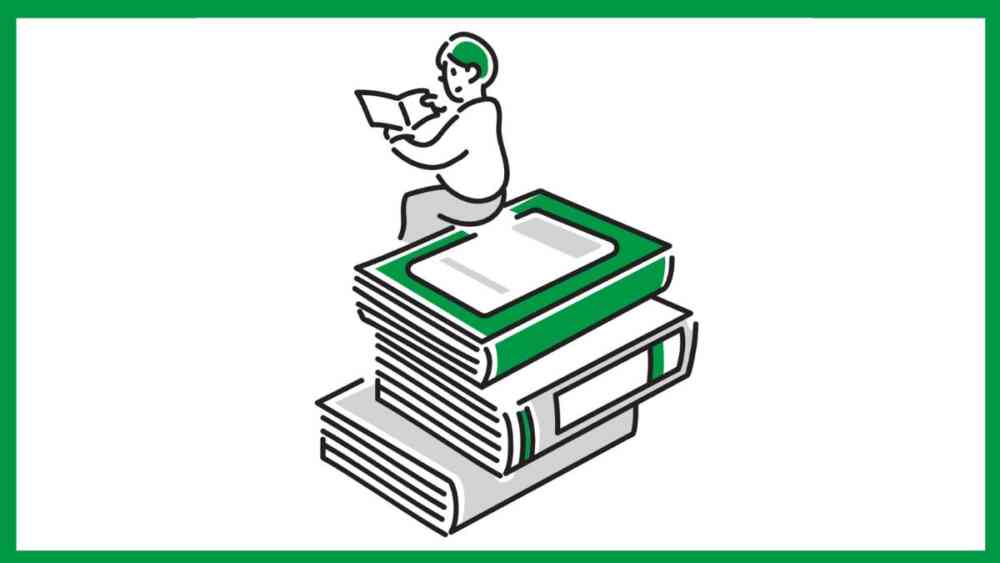
理科の各分野には、それぞれ特性に合わせた効果的な暗記法が存在します。
このセクションでは、生物、地学、物理、化学それぞれの暗記のコツと、理科全体の学習を効率的に進めるための具体的な戦略、そしてモチベーションを維持する方法について詳しく解説していきます。
- 生物の暗記法
- 地学の暗記法
- 物理の暗記法
- 化学の暗記法
- 理科の暗記効率を最大化する勉強計画の立て方
- 忘れにくい!理科の暗記に役立つ具体的な記憶術
- 暗記を継続するためのモチベーション維持術
生物の暗記法
生物分野は、用語や分類が多く、視覚的な要素を多く含むため、図やイラストを活用した暗記法が特に効果的です。
たとえば、植物のつくりを覚える際には、実際に絵を描いて部位の名称を書き込む、動物の分類では系統樹を自作して特徴を書き出す、といった方法がおすすめです。
単語カードの裏表に用語と図を書き、視覚と文字情報を結びつけるのも非常に有効です。
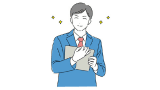
地学の暗記法
地学分野は、地球の構造や気象、天体など、壮大なスケールの現象を扱います。
暗記の際は、現象の「流れ」や「因果関係」を理解することが重要です。
たとえば、低気圧の発生と天候の変化を関連付けて覚える、地層の形成過程を時系列で把握するといった方法が有効です。
イラストや図解が多い参考書を活用し、視覚的に全体像を捉えることで、複雑な用語も整理して覚えることができます。

物理の暗記法
物理分野は、公式や単位の暗記が中心ですが、公式が導かれる「原理」を理解することが何よりも大切です。
単に公式を暗記するだけでなく、「なぜこの公式を使うのか」「どのような状況で適用できるのか」を理解することで、応用問題にも対応できるようになります。
具体的な例題を解きながら、公式の使い方を体で覚える反復練習も不可欠です。
物理では、目で見て、手で書いて、頭で考える、多角的なアプローチが効果的です。
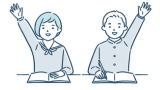
化学の暗記法
化学分野は、元素記号や化学式、反応式など、厳密なルールに基づいた暗記が求められます。
周期表は必ず覚えるべき基本中の基本です。
語呂合わせやカードを使った反復学習が非常に有効です。
化学反応式を覚える際には、実際に自分で手を動かして書く練習を繰り返すことで、自然と身につきます。
実験の様子を解説する動画を見ることで、抽象的な化学反応を視覚的に理解し、記憶に定着させることもできます。
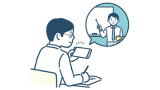
理科の暗記効率を最大化する勉強計画の立て方
理科の暗記効率を上げるためには、計画的な学習が不可欠です。
まず、苦手な分野と得意な分野を明確にし、苦手な分野に重点的に時間を割り当てましょう。
そして、毎日短時間でも良いので、継続的に暗記に取り組む習慣をつけます。
たとえば、朝の通学中に語呂合わせを確認したり、寝る前にその日学習した内容を振り返ったりするなど、スキマ時間を有効活用することが暗記定着の鍵です。
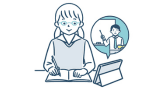
忘れにくい!理科の暗記に役立つ具体的な記憶術
理科の暗記では、一度覚えた知識を忘れにくくするための工夫が必要です。
たとえば、エビングハウスの忘却曲線を意識した復習サイクルを取り入れましょう。
具体的には、学習した内容を「1日後」「1週間後」「1ヶ月後」といった間隔で繰り返し復習することで、長期記憶として定着しやすくなります。
声に出して覚える、人に説明するなど、五感をフル活用した学習法も非常に効果的です。
※エビングハウスの忘却曲線の理論を応用した効果的な学習法として、定期的な復習が推奨されています
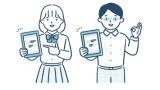
暗記を継続するためのモチベーション維持術
暗記学習は地道で単調になりがちですが、モチベーションの維持が成功の鍵を握ります。
目標を細分化し、達成するたびに小さなご褒美を設定したり、学習の進捗を記録して可視化したりすると良いでしょう。
私の指導経験でも、親御さんが学習ノートにコメントを残したり、一緒に目標達成を喜んだりすることで、生徒のモチベーションが劇的に向上した例を数多く見てきました。
親子で協力して、楽しく学習できる環境を整えましょう。
高校受験理科の暗記が楽になる方法:語呂合わせとその他ツール

「暗記って、やっぱり大変…」そう感じている皆さん、ご安心ください。
暗記をグッと楽にする強力な味方、それが「語呂合わせ」です。
このセクションでは、語呂合わせの賢い活用法から、オリジナルの語呂合わせの作り方、さらには暗記を助けるアプリや動画、そして暗記を習慣化するための具体的なコツまで、幅広くご紹介します。
- 記憶を助ける語呂合わせの活用法
- 【ユーザー参加型】効果的な語呂合わせの作り方
- 理科の暗記を楽しむためのコツ
- 理科の暗記を助けるおすすめアプリ・参考書
- 動画・音声(聞き流し)を活用した記憶定着術
- 暗記が苦手な人必見!理科の暗記を習慣化するコツ
記憶を助ける語呂合わせの活用法
語呂合わせは、無味乾燥な情報を、覚えやすく、忘れにくい形に変える魔法のツールです。
特に理科では、元素記号、岩石名、生物の分類など、羅列された用語を覚える際に絶大な効果を発揮します。
既存の有名な語呂合わせを活用するのはもちろんのこと、自分にとって覚えやすいオリジナルの語呂合わせを作成することも非常に有効です。
たとえば、「水兵リーベ僕の船…」のように、メロディーに乗せて覚えるのも良い方法です。

【ユーザー参加型】効果的な語呂合わせの作り方
語呂合わせは、自分で作ると記憶に残りやすいという特徴があります。
ここでは、効果的な語呂合わせを作るためのヒントをいくつかご紹介しましょう。
- キーワードを音で表現:覚えたい言葉を、親しみやすい言葉や数字の音に変換します。
- ストーリー性を持たせる:無関係な単語でも、短い物語にして連結すると覚えやすくなります。
- 面白さやインパクト:笑える、少し奇抜な語呂合わせの方が、印象に残りやすいものです。
- 身近なものを利用:自分の好きなものや、日常でよく使う言葉を使うと、より記憶に残りやすくなります。
たとえば、「マグマが冷えてできる岩石」にはいくつか種類があり、それを覚える語呂合わせに「カコセン ハンレイ アンリュウ ゲンデイ」があります。
これは、「花崗岩(かこうがん)、閃緑岩(せんりょくがん)、斑れい岩(はんれいがん)、安山岩(あんざんがん)、流紋岩(りゅうもんがん)」などの岩石を覚えるための言葉です。
でも、「なんだか覚えにくいな」と思ったら、自分なりにストーリーを作ってみると効果的です。
「かっこいい子どもがせんべいを半分こ、あんまりリュウがんと」みたいに、ちょっと変で面白い話にしてみると、意外と忘れにくくなります。

理科の暗記を楽しむためのコツ
暗記を「楽しい」と感じることは、継続に直結します。
たとえば、クイズ形式で家族や友人と問題を出し合ったり、学習アプリのゲーム感覚で取り組んだりすると良いでしょう。
私が教室長時代に実践していたのは、生徒が自分で問題集の解答欄を隠し、正解したら好きなシールを貼るというものでした。
視覚的な達成感は、意外と大きなモチベーションになります。
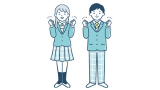
理科の暗記を助けるおすすめアプリ・参考書
現代の学習には、便利なツールがたくさんあります。
暗記を助けるおすすめのアプリや参考書をいくつかご紹介します。
- アプリ
- Anki:フラッシュカード形式で効率的な復習が可能なアプリ。自分でカードを作成できるため、苦手な分野を重点的に対策できます。
- Quizlet:用語と定義をセットで覚えるのに最適なアプリ。クイズ形式で楽しく学習できます。
- 参考書例
- 『くわしい 中学理科』シリーズ(文英堂):各単元の要点がイラスト・図解で分かりやすくまとめられており、理解しながら暗記したい中学生にぴったり。
- 『中学&高校入試 パーフェクト一問一答 理科』(受験研究社)中学3年間の理科(生物・地学・化学・物理)の学習内容を全てカバーしているから、中1~高校入試直前まで使えます。
動画・音声(聞き流し)を活用した記憶定着術
YouTubeなどの動画コンテンツは、視覚と聴覚の両方から情報を取り入れられるため、記憶の定着に非常に効果的です。
特に、実験の様子や物理現象のアニメーションなどは、文字だけではイメージしにくい内容を具体的に理解するのに役立ちます。
解説動画を音声だけにして聞き流すことで、通学中や家事をしながらでも学習を進めることができ、スキマ時間を有効活用できます。

暗記が苦手な人必見!理科の暗記を習慣化するコツ
「暗記が苦手」と感じる最大の理由は、継続することの難しさにあります。
習慣化のコツは、小さく始めることです。
たとえば、「今日は寝る前に理科の用語を5つだけ覚える」といった具体的な目標を設定し、それを毎日クリアすることから始めましょう。
慣れてきたら徐々に量を増やしていきます。
学習記録をつけたり、家族に「今日はここまで覚えたよ!」と報告したりすることも、良い習慣を続けるためのサポートになります。
生物の語呂合わせ暗記法を紹介

生物は、高校受験の理科の中でも特に覚えることが多い分野です。
「動物の名前」「植物の分類」「体のしくみ」など、たくさんの用語が出てきます。
でも、心配はいりません!
語呂合わせを使えば、楽しく・効率よく覚えられます。
ここでは、よく出るテーマごとに、語呂合わせを使った覚え方を紹介します。
- 成虫で冬を越す昆虫
- 爬虫類
- 両生類
- 合弁花類
- 単子葉類
- 裸子植物
- 茎に養分を与える植物
- 茎に養分を蓄える植物
- その他の重要生物用語の語呂合わせ
成虫で冬を越す昆虫
昆虫の中には、成虫の姿で寒い冬を乗り越えるものがいます。
これを覚える語呂合わせとしては、
「おお!カブとテントがモンシロとタテハで冬越し」 が有名です。
- オオカマキリ
- カブトムシ(幼虫の場合もあるが、成虫越冬の例も多い)
- テントウムシ
- モンシロチョウ
- タテハチョウ これは、実際の冬越しの様子をイメージしやすく、記憶に残りやすいでしょう。
爬虫類
爬虫類の特徴は「変温動物」「肺呼吸」「硬いウロコ」などです。
代表的な動物を覚えるには、
「カメとヘビがワニと一緒にヤモリで登る」 という語呂合わせがあります。
- カメ
- ヘビ
- ワニ
- ヤモリ このように、関連する動物を一つのストーリーにすることで、単なる羅列よりも記憶に残りやすくなります。
両生類
両生類は、幼生期は水中でエラ呼吸、成体は陸上で肺呼吸と皮膚呼吸をする変温動物です。
代表的な動物は、「カエルとイモリとサンショウウオ」 です。
語呂合わせにするなら、「カエルのイモリ、サンショウする」 などと覚えることができます。
実際に、私が指導した生徒で、この語呂合わせで両生類を完璧に覚えた生徒がいました。
合弁花類
合弁花類は、花弁がくっついている植物の仲間です。
代表例として、「アサガオ、タンポポ、ヒマワリ、ツツジ、サクラソウ」 などが挙げられます。
語呂合わせは、「朝からタンポポ、ひまにツツジ、桜そう」 といったように、身近な植物をリズムに乗せて覚えると良いでしょう。
単子葉類
単子葉類は、子葉が1枚、根がひげ根、葉脈が平行脈といった特徴があります。
代表例は、「イネ、ムギ、トウモロコシ、ユリ、ススキ、タケ」 です。
これらを覚える語呂合わせは、「稲と麦とトウモロコシ、ユリとススキの竹やぶで」 などとすると、視覚的なイメージも伴い記憶に定着しやすくなります。
裸子植物
裸子植物は、胚珠がむき出しになっている植物で、花弁や萼がないのが特徴です。
代表例は、「マツ、スギ、イチョウ、ソテツ」 です。
語呂合わせは、「待つすぎ、いちようそてつ」 が有名で、多くの受験生が活用しています。
シンプルで覚えやすいのが利点ですね。
茎に養分を与える植物
茎に養分を与える植物は、ジャガイモ、サトイモ、レンコンなどがあります。
これらを覚える語呂合わせは、「芋けんぴ、里芋、レンコン、茎に栄養」 とすると、少しユニークで記憶に残りやすいかもしれません。
このように、少し語呂合わせにひねりを加えることで、より強いインパクトを与え、忘れにくくできます。
その他の重要生物用語の語呂合わせ
生物分野には、他にも覚えにくい重要用語がたくさんあります。
たとえば、血液の凝固に関わる血球は「赤(血球)白(血球)血小板(けっしょうばん)」 や、植物の光合成に必要なものとして「水と二酸化炭素で光合成」などがあります。
このように、短く、リズム感のある言葉で覚えたい情報をまとめることで、効率的に多くの知識を暗記することができます。
地学の語呂合わせ暗記法を紹介【高校受験用】

地学は、「地球ってどうなってるの?」「宇宙ってどこまで広がってるの?」といった大きなテーマを学ぶ分野です。
でもその分、出てくる言葉や現象もスケールが大きく、覚えるのがちょっと大変です。
そんなときに役立つのが、語呂合わせや図でイメージしながら覚える学習法!
このセクションでは、特につまずきやすい「火成岩」と「鉱物」にしぼって、覚えやすくて面白い語呂合わせを紹介します。
- 火成岩の暗記法
- 鉱物の種類
- 鉱物の色
- その他の重要地学用語の語呂合わせ
火成岩(かせいがん)を語呂でスッキリ暗記!
火成岩は「マグマが冷えて固まった岩石」のこと。
冷える場所によって2種類に分けられます。
【深成岩(地下でゆっくり冷える)】
→ 粒が大きめで、見た目もゴツゴツしている
語呂合わせ:「カコセン ハンレイ」
- カ:花崗岩(かこうがん)
- コ:閃緑岩(せんりょくがん)
- セン:斑糲岩(はんれいがん)
【火山岩(地表近くで急に冷える)】
→ 粒が細かく、軽石のように軽いことも
語呂合わせ:「アンリュウ ゲンデイ」
- アン:安山岩(あんざんがん)
- リュウ:流紋岩(りゅうもんがん)
- ゲン:玄武岩(げんぶがん)
\覚え方のコツ/「カコセン・ハンレイ! アンリュウ・ゲンデイ!」と、リズムに乗って唱えるだけで自然に覚えられます。
鉱物(こうぶつ)も物語風に暗記!
岩石の中に入っているキラキラしたかけら、それが「鉱物」です。
主な鉱物は、次のようなものがあります。
- 石英(せきえい)
- 長石(ちょうせき)
- 雲母(うんも)
- 輝石(きせき)
- 角閃石(かくせんせき)
- カンラン石(かんらんせき)
これらを覚えるための語呂合わせがこちら!
「長石の石、雲と角と輝き、感動で石をカンラン!」
ちょっと長めですが、ストーリーみたいに読めるので記憶に残りやすいです。
実際に生徒にも人気があります!
鉱物の色を覚えるコツは「セットで覚えること」
鉱物には、それぞれ見た目の色に特徴があります。
| 鉱物名 | 色の特徴 |
|---|---|
| 石英 | 無色透明 |
| 長石 | 白色 |
| 雲母 | 黒色・褐色 |
| 輝石 | 黒色 |
| 角閃石 | 黒色 |
| カンラン石 | 黄緑色 |
ポイント!→「鉱物の名前と色は、必ずセットで覚えよう!」
たとえば、「カンラン石=黄緑色」は、入試でもよく出ます。
覚えたことを表にまとめて、見える化するのもおすすめです!
その他の重要地学用語の語呂合わせ
地学分野には他にも、気象に関する用語(前線、高気圧・低気圧など)や、天体に関する用語(惑星の名前、星座など)で、覚えにくいものがあります。
たとえば、太陽系の惑星の並び順は、「水(すい)金(きん)地(ち)火(か)木(もく)土(ど)天(てん)海(かい)冥(めい)王(おう)」 という語呂合わせが昔から使われています。(※現在は冥王星は準惑星ですが、語呂合わせとしては有効です。)
このように、それぞれの単元で、覚えにくい部分には積極的に語呂合わせを活用していくと良いでしょう。
化学の語呂合わせ暗記法を紹介【中学生向け】

化学は「とにかく暗記が多い…」と感じる人が多い分野です。
元素記号や化学式、反応式など、正確な知識が求められるので、最初は大変かもしれません。
でも安心してください!
語呂合わせを使えば、覚えるのがグッと楽になります。
このセクションでは、中学理科の化学でよく出る項目を、語呂合わせを使ってわかりやすく覚えるコツを紹介していきます。
- 元素の周期表
- 気体:2個の原子が結びついて分子になる
- 金属:原子1個で分子になる
- その他の重要化学用語の語呂合わせ
- 化学反応式・イオン式の覚え方
元素の周期表は「化学のスタートライン」
まずは周期表の中でも、特によく出るグループ(族)から覚えましょう。
| グループ名 | 元素の名前 | 語呂合わせ |
|---|---|---|
| 1族(アルカリ金属) | Li, Na, K, Rb, Cs, Fr | リッチな母ちゃん、なでるなカリウム、ルビーのセシウム、フランス |
| 2族(アルカリ土類金属) | Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra | 可愛いストロボ、ばあちゃんランラン |
| 18族(希ガス) | He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn | ヘンリーねぇちゃん、あるからね、クリプトンのクセノン |
これらの語呂は、リズムに乗って繰り返すだけで自然と覚えられます!
2個の原子でできる気体は語呂でまとめて暗記!
化学の気体には、2つの同じ原子が結びついてできる分子があります。
これは「分子の形」としてよくテストに出ます!
| 気体名 | 分子式 |
|---|---|
| 水素 | H₂ |
| 酸素 | O₂ |
| 窒素 | N₂ |
| 塩素 | Cl₂ |
| フッ素 | F₂ |
| 臭素 | Br₂ |
| ヨウ素 | I₂ |
これらの気体は、語呂合わせでまとめて覚えると便利!
語呂合わせ:「すいへい にお ふっくら しゅっと よう」(すい=水素、へい=平和の窒素、に=二酸素、…)
金属は原子1つで分子になるってほんと?
気体とは逆に、金属の多くは原子1個だけでそのまま存在します。
たとえば…
- 銅(Cu)
- 鉄(Fe)
- アルミニウム(Al)
- 亜鉛(Zn)
- 金(Au)
- 銀(Ag)
これは「暗記」というよりも、金属の性質として知っておくと便利です。
「金属は1個でOK」とざっくり覚えておきましょう!
その他の重要化学用語の語呂合わせ
化学には、上記以外にも「沈殿」「酸化・還元」「酸・アルカリ」など、多くの重要用語があります。
- 沈殿の覚え方:例えば、「水に溶けない塩化物」は「えん(塩)があるから沈(ちん)と銀(銀)」 で、塩化銀(AgCl)が沈殿するというように覚えます。
- 酸とアルカリ:リトマス試験紙の色の変化は、「赤青酸(さん)性、青赤アルカリ」 と覚えると、視覚的に分かりやすいです。
このように、複雑な化学反応や物質の性質も、短い語呂合わせで覚え、問題を解く際にスムーズに知識を引き出せるようにすることが得点アップの鍵です。
化学反応式・イオン式の覚え方
化学反応式やイオン式は、ただ暗記するだけでなく、反応の前後で何がどう変化したのかを理解することが不可欠です。
しかし、何度も書く練習を繰り返すことで、自然と式を覚えることができます。
- 反復練習:ノートに何度も繰り返し書いたり、ホワイトボードに書き出したりすることで、手で覚えることができます。
- 視覚化:反応物をブロックのようにイメージして組み合わせるなど、自分なりに視覚化すると、式の意味が理解しやすくなります。
- 語呂合わせの活用:例えば、有名な化学反応である「中和反応」の基本的な形は「酸+塩基→塩+水」ですが、これも「酸と塩基が仲良くすると塩と水ができる」といったようにストーリーにすると覚えやすいでしょう。
これらの工夫で、化学反応式やイオン式への苦手意識を払拭し、得意分野に変えていきましょう。
参考記事:【中学生の理科勉強法】定期テスト「暗記」攻略法!苦手でも90点超えを狙う
物理の語呂合わせ暗記法を紹介
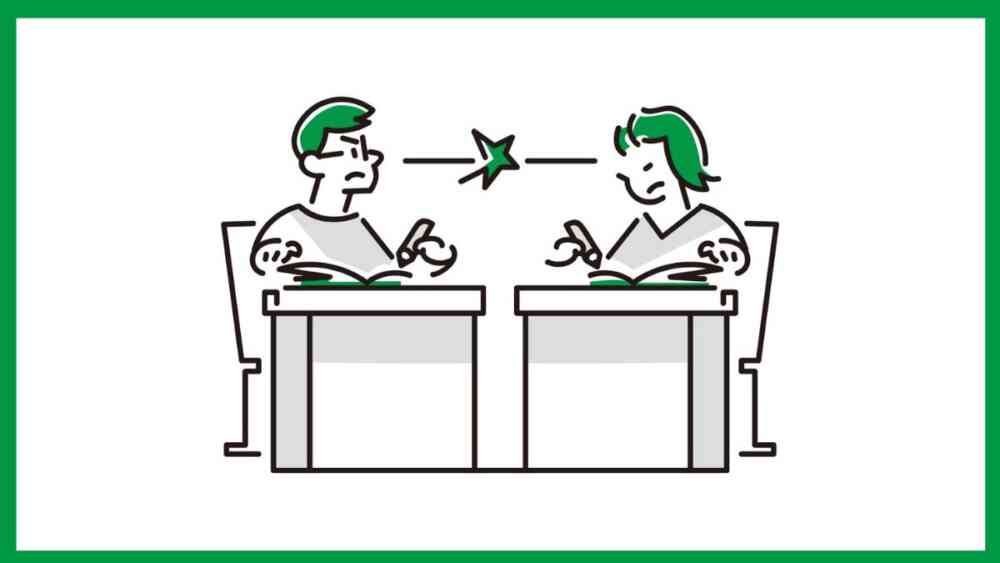
物理は、「理科の中でも計算が多い分野」。
基本の公式や単位をしっかり覚えるだけで、グッと解きやすくなります!
ここでは、力・仕事・エネルギー・電気・熱や光といった物理のよく出る単位や公式を、「語呂合わせ」などを使って楽しく覚える方法を紹介します。
- 【力学単位】
- 【仕事・エネルギー単位】
- 【電気単位】
- 【熱・光単位】
- その他の重要物理用語の語呂合わせ
- 物理法則・公式の理解と暗記のポイント
【力学の単位】~まずは物理の土台から!
力学は「動き」や「力」を扱う単元です。
よく出る単位をしっかり覚えておきましょう。
| 用語 | 単位 | 覚え方(語呂合わせ) |
|---|---|---|
| 力(ちから) | ニュートン(N) | 「力でニュートン!」 |
| 質量(しつりょう) | キログラム(kg) | 「質量キロでずっしり!」 |
| 速さ(はやさ) | メートル毎秒(m/s) | 「速さはメートルパー秒!」 |
| 圧力(あつりょく) | パスカル(Pa) | 「圧力かかってパスカル!」 |
【仕事とエネルギーの単位】~力が働くとどうなる?
仕事やエネルギーの計算は、高得点のカギになります。
| 用語 | 単位 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 仕事 | ジュール(J) | 「仕事はジュール!」 |
| 仕事率 | ワット(W) | 「仕事率はワットでスピード感!」 |
| エネルギー | ジュール(J) | 「エネルギーもジュールでOK!」 |
ポイント:ジュールは「どれだけの量」、ワットは「どれだけ速く」をイメージして使い分けましょう!
【電気の単位】~よく出るけど混乱しやすい単元
電気の単位は種類が多くて覚えにくい人も。でも、語呂でスッと覚えましょう。
| 用語 | 単位 | 語呂合わせ |
|---|---|---|
| 電流 | アンペア(A) | 「電流アンペア!流れるぞ!」 |
| 電圧 | ボルト(V) | 「電圧ボルトでビリビリ!」 |
| 抵抗 | オーム(Ω) | 「抵抗オームで通しにくい!」 |
| 電気量 | クーロン(C) | 「電気量はクーロン!たまるよ!」 |
【熱と光の単位】~日常にもつながる身近な単元
熱や光は感覚的にとらえやすい分野です。
| 用語 | 単位 | ポイント |
|---|---|---|
| 熱量 | ジュール(J)、カロリー(cal) | 食べ物のカロリー=熱のエネルギー |
| 温度 | 摂氏(℃) | 水が0℃で氷に、100℃で沸騰する |
ポイント:熱量もエネルギーなので、ジュールと共通して覚えておくと効率的!
その他の重要物理用語の語呂合わせ
物理分野には、他にも光の屈折や反射、音の伝わり方など、言葉で覚えるべき現象や法則があります。
- 光の屈折:「水面に近づくほど光は曲がる」 といった現象を、実際に図を描きながらイメージすると記憶に残りやすいです。
- 音の速さ:気温が上がると音の速さも速くなる、という関係性を「暑いと音が速い」とシンプルに覚えるのも良いでしょう。
これらの現象は、単なる暗記ではなく、現象が起こるメカニズムを理解することが、深い記憶に繋がります。
物理法則・公式の理解と暗記のポイント
物理の公式は、丸暗記するだけではすぐに忘れてしまいます。
重要なのは、その公式が何を意味しているのか、なぜそのような形になるのかを理解することです。
- 公式の導出過程を理解する:公式がどのように導き出されたのかを知ることで、記憶の定着度が格段に上がります。
- 単位を確認する:公式に登場する物理量の単位を意識することで、計算ミスを防ぎ、公式の理解を深めることができます。
- 具体例で覚える:実際に数字を入れて計算してみることで、公式がどのように使われるかを体感し、記憶に定着させることができます。
- 自分で「説明」してみる:誰かに公式の意味を説明するように声に出してみると、理解が深まります。
かつて私が指導していた生徒で、物理公式が苦手だった生徒がいました。
その生徒は、公式を「自分だけの言葉」で解釈し直し、それをノートにまとめるという方法で克服しました。
たとえば、オームの法則(V=IR)を「電圧は電流と抵抗の力比べ」と表現するなど、彼なりの解釈を加えることで、単なる記号の羅列ではなく、意味のある情報として記憶していました。
高校受験対策理科:暗記しておきたい公式一覧とその使い方

理科、特に物理や化学の分野では、様々な公式が登場します。
これらの公式を正確に暗記し、適切に使いこなせるかどうかが、得点を大きく左右します。
このセクションでは、中学1年生から3年生までに習う主要な理科の公式を一覧で紹介し、ただ覚えるだけでなく、効果的に活用するためのヒントも提供します。
- 中学1年生:理科の公式
- 中学2年生:理科の公式
- 中学3年生:理科の公式
- 公式を忘れないための反復学習法
中学1年生:理科の公式
自分で語呂合わせを作るのも良い方法です。
公式を一覧にしましたので、自分で覚えやすいように工夫をしてみましょう。
| 公式 | 式 |
|---|---|
| 顕微鏡の倍率 | 顕微鏡の倍率 = 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率 |
| 反射の法則 | 入射角 = 反射角 |
| 屈折の公式 | ① 空気中から水中(ガラス中)に光が進む場合:入射角 > 屈折角 \n ② 水中(ガラス中)から空気中に光が進む場合:屈折角 > 入射角 |
| フックの法則 | ばねののびは力の大きさに比例すること |
| 圧力の公式 | 圧力 = 力 / 面積 |
| 浮力の公式 | 浮力 = 空気中の物体の重さ - 液体中の物体の重さ |
| アルキメデスの原理 | 物体には押しのけた液体の重さと等しい浮力がはたらく |
| 密度の公式 | 密度 = 質量 / 体積 |
| 質量パーセント濃度の公式 | 質量パーセント濃度 = (溶質の質量 / 溶液の質量) × 100 |
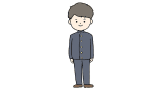
中学2年生:理科の公式
| 公式 | 式 |
|---|---|
| 直列回路の電流 | I1 = I2 = I3 |
| 並列回路の電流 | I1 + I2 = I3 |
| 直列回路の電圧 | V1 = V2 + V3 + V4 |
| 並列回路の電圧 | V1 = V2 = V3 = V4 |
| オームの法則 | R = V / I |
| 電力 | P = I × V |
| ジュール熱 | Q = P × t |
| 電力量 | W = P × t |
| 右ねじの法則 | (電流による磁界の向き) |
| フレミング左手の法則 | (電流と磁界による力の向き) |
| レンツの法則 | (誘導電流の向き) |
| 質量保存の法則 | (化学変化前後で質量は保存) |
| 定比例の法則 | (化学変化での質量比は一定) |
| 湿度 | 湿度(%) = (水蒸気量 / 飽和水蒸気量) × 100 |
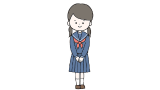
中学3年生:理科の公式
| 公式 | 式 |
|---|---|
| 速さ | 速さ = 距離 / 時間 |
| 仕事 | 仕事 = 力 × 力の向きに動いた距離 |
| 仕事率 | 仕事率 = 仕事 / かかった時間 |
| 力学的エネルギー | 力学的エネルギー = 位置エネルギー + 運動エネルギー |
| 春分・秋分の南中高度 | 春分・秋分の南中高度 = 90° - 緯度 |
| 夏至の南中高度 | 夏至の南中高度 = 90° - 緯度 + 23.4° |
| 冬至の南中高度 | 冬至の南中高度 = 90° - 緯度 - 23.4° |
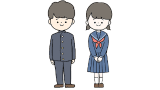
公式を忘れないための反復学習法
公式は、一度覚えただけではすぐに忘れてしまいます。長期的に記憶に定着させるためには、計画的な反復学習が不可欠です。
- 毎日短時間でも見直す:毎日の学習ルーティンに、公式の見直し時間を組み込みましょう。
- 問題を解きながら覚える:公式は、問題を解く中で自然と身についていくものです。多くの問題に触れ、公式を適用する練習を繰り返しましょう。
- 公式集を作成する:自分で公式をノートにまとめたり、カードに書き出したりすることで、アウトプットの機会を増やし、記憶を強化できます。
- 人に説明する:友達や家族に公式の意味や使い方を説明することで、自分の理解度を確認し、記憶を確かなものにできます。
重要なのは、「使って覚える」 という意識です。
公式は知識として持つだけでなく、武器として使いこなせるように練習を重ねましょう。
分野別(生物・地学・物理・化学)理科勉強法と対策

高校受験の理科では、生物、地学、物理、化学の4分野すべてから出題されます。
それぞれの分野には異なる特性があるため、効果的な学習法も異なります。
このセクションでは、各分野に特化した勉強法と、つまずきやすいポイントへの対策を具体的に解説し、理科全体の得点力アップに繋げます。
- 高校受験対策理科:生物の勉強法
- 高校受験対策理科:地学の勉強法
- 高校受験対策理科:物理の勉強法
- 高校受験対策理科:化学の勉強法
- 各分野でつまずきやすいポイントと解決策
高校受験対策理科:生物の勉強法
生物を効果的に学ぶためには、基本概念の習得、視覚的な資料の活用、実験と観察の実施、定期的な復習、グループ学習などが重要。
基礎知識をしっかり理解し、図表や模型を用いて概念を視覚化し、実験や観察を通じて理論を実践に結びつけ、定期的に復習し、友達やクラスメイトと共に学習することで、生物学の勉強を効率的かつ楽しみながら学習できるでしょう。
高校受験対策の生物の勉強法は、教科書の暗記が中心。
繰り返し学習して知識を定着させるのがポイント。
以下の単元を理解しているかチェックしてみてください。
| 1年生 | 植物の分類・植物のはたらき・植物のからだのつくり |
| 2年生 | 動物の分類・生物と細胞・人体 |
| 3年生 | 生物の成長と細胞分裂・遺伝の規則性・無性生殖と有性生殖 |
中学生の生物は、「植物」「動物」「細胞分裂」「遺伝の法則」が学習のポイントです。
生物の勉強は、教科書の重要語句をしっかりと暗記して、重要語句の役割を覚えることが重要です。
ノートに、分類などをまとめることで、記憶に残りやすくなり、復習の時も役立ちます。

参考記事:【2026年】都立高校入試「理科の傾向と対策」記述・頻出分野を徹底解説
高校受験対策理科:地学の勉強法
地球の概念の理解、観察の実施、地図読解力の向上、地球科学の応用に関心を持つこと。
地学の基本的な要素や地球のプロセスを徹底的に理解し、実際に野外で観察や調査を行い、地球の現象を直接体験することが大切。
地図を読み解くスキルを磨き、地球科学の知識を現実の問題に応用することに興味を持つことで、地学の学習が効率的にできるでしょう。
地学の場合も、生物のように「分類図」や「分類表」のまとめをすると理解しやすくなります。
教科書の地学用語を暗記して、問題演習に取り組んでください。
以下の単元を理解しているかチェックしてみてください。
| 1年生 | 火山と火成岩・堆積岩・地層・地震 |
| 2年生 | 日本の天気・空気中の水蒸気・大気のはたらき |
| 3年生 | 惑星の動き・太陽の一日・一年の動き・星の一日・一年の動き・月の満ち欠けと動き |
中学生の地学は、法則を理解してから問題演習に取り組むことで、地学の知識が定着します。
地学は用語を暗記しただけだと、問題が解けないことがあるので、法則や公式もしっかりと理解してください。
「地質」「気象」「天体」は、中学生の苦手な分野でもあるため、しっかりと復習してください。
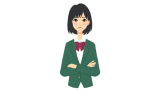
ケアレスミスについて知りたい方、【ケアレスミス対策】中学生がテスト前に読めば効果的
高校受験対策理科:物理の勉強法
物理を効果的に学ぶためには基本的な法則と概念の理解、実験と観察の実施、数学的スキルの向上、物理学の応用に関心を持つことが重要。
基礎的な物理学の法則や概念を徹底的に理解し、実験や観察を通じて物理学の原理を実際に確認し、数学的スキルを向上させて物理学の問題に取り組む力を高め、物理学の応用に興味を持つことで、物理学の学習を効果的かつ魅力的に学習できます。
物理の場合は、まず原理を理解することが重要。
法則や公式を暗記して、問題演習を繰り返して解いて、解法のパターンを身につけてください。
以下の単元を理解しているかチェックしてみてください。
| 1年生 | 光・音・力 |
| 2年生 | 電気とそのエネルギー・回路とオームの法則・電流と磁界・電磁誘導 |
| 3年生 | 仕事とエネルギー・力のつり合い・物体の運動 |
中学生の物理の勉強は、「原理を理解する」ことがポイント。
原理を理解して、物理の法則や公式を暗記した上で、問題演習に取り組んでください。
「光・音・力」「電気」「運動とエネルギー」は、法則や公式を覚えて、基本問題を繰り返しとくことで、応用力が身につきます。

高校受験対策理科:化学の勉強法
化学を効果的に学ぶためには基本的な概念の理解、実験と観察の実施、視覚化、問題解決能力の養成、定期的な復習、興味を持つことが重要。
基礎知識の理解を重視し、実験や観察を通じて概念を実践に結びつけ、図表やモデルを活用して視覚的に理解し、問題解決能力を鍛え、定期的な復習を行い、自分の興味を追求することが大切。
具体的に化学の場合は、物質名とその性質について覚えることが勉強のポイント。
化学式や化学反応式は繰り返し学習して覚えてください。
以下の単元を理解しているかチェックしてみてください。
| 1年生 | 水溶液・物質の状態変化・物質とその性質・気体の性質 |
| 2年生 | 化学変化と物質の質量・原子と分子・化学式・化学変化と化学反応式 |
| 3年生 | 酸とアルカリ・中和とイオン・電解質と非電解質とイオン・電気分解・電池とイオン |
中学生の化学は、理解しにくい分野ですが、「物質・気体・水溶液の濃度」「化学反応」「化学式・化学反応式」「イオン・酸」「アルカリ・中和」については、しっかりと復習してください。
化学の勉強のポイントは、暗記して、計算問題をたくさん解くことです。
物質名やその性質、実験器具などの使い方を理解して、問題演習に取り組んでください。

各分野でつまずきやすいポイントと解決策
私が長年、個別指導塾で多くの生徒を見てきた経験から、各分野で特につまずきやすいポイントとその解決策をまとめました。
| 分野 | つまずきやすいポイント | 解決策 |
|---|---|---|
| 生物 | 用語の多さと類似性 | 図解ノートの作成やカード学習で視覚的に整理する。類似用語は比較表を作り、違いを明確にする。 |
| 地学 | 現象の抽象性、全体像の把握 | 動画やシミュレーションでイメージを掴む。タイムライン(時間軸)で現象の前後関係を整理する。 |
| 物理 | 公式の適用、計算ミス | 公式の導出過程を理解し、意味を把握する。単位の確認を徹底し、計算過程を丁寧に記述する習慣をつける。 |
| 化学 | 元素記号・化学式・反応式の暗記 | 周期表の語呂合わせを徹底。反復練習で化学反応式を体に染み込ませる。物質の性質を身近な例と結びつける。 |
どの分野でも共通して言えるのは、苦手意識を持ったらすぐに個別指導の先生や学校の先生に相談することです。
疑問を放置せず、早めに解決することが合格への近道です。
おすすめタブレット学習教材
中学生に大人気のタブレット学習教材|進研ゼミ中学講座
※部活と勉強を両立しながら志望高校合格に必要な学力を育む講座
ゲーム感覚で勉強できる!無学年式オンライン教材【すらら】
※国・数・理・社・英の5教科対応、一人ひとりの理解度に合わせて学習可能
全9教科・全教材が個別指導式で最適に学べる!SMILE ZEMI中学コース
※“ジブン専用”の定期テスト対策で9教科まるごと点数アップ!
参考記事:テストの点数が悪い中学生!原因と解決方法|親が知っておくべき対処法
【高校受験】理科の基本的な勉強法(暗記法)とよくある質問

高校受験理科の学習を進める上で、具体的な暗記法だけでなく、日々の勉強の質を高める基本的なアプローチも非常に重要です。
このセクションでは、効率的な学習サイクルの確立、受験生からよく寄せられる暗記に関する悩みへの回答、そして学習をサポートするおすすめの教材やツールについて詳しく解説していきます。
- 効率アップの鉄則:一問一答 → 対話式復習
- 理科の暗記でよくある悩みとQ&A
- 暗記した内容を忘れないための復習サイクル
- すぐに使える!おすすめ教材・参考書
- 市販一問一答教材(例をピックアップ)
- オンライン・YouTube動画・アプリ系ツール
効率アップの鉄則:一問一答 → 対話式復習
理科の暗記学習で最も効率的なのは、「一問一答」を繰り返すことです。
ただ機械的に答えるだけでは不十分。
さらに効果を高めるのが「対話式復習」です。
- 一問一答で知識の確認:まずは、一問一答問題集や自作のカードを使って、基本的な用語や現象が覚えているかを確認します。
- 対話式復習で深い理解:正解した問題も不正解だった問題も、「これはどういう意味だったかな?」「なぜこうなるんだろう?」と自分自身に問いかけ、声に出して説明してみるのです。
たとえば、「『光合成』とは?」と聞かれたら、「植物が光のエネルギーを使って、水と二酸化炭素からデンプンと酸素を作る働きのこと」と説明してみましょう。
このアウトプットのプロセスが、知識をより強固なものにし、忘れにくくします。

理科の暗記でよくある悩みとQ&A
私が教室長時代に生徒や保護者からよく相談された、理科の暗記に関する代表的な悩みとその回答をまとめました。
- Q1. 「どうしても暗記が続かない…」
- A1. 毎日「最小限の目標」を設定し、達成したら自分にご褒美をあげましょう。 たとえば、「今日は元素記号を5つ覚えるだけ」など、無理のない範囲でスタートしてください。小さな成功体験が継続に繋がります。
- Q2. 「覚えたはずなのに、すぐに忘れてしまう…」
- A2. 復習のタイミングが重要です。 エビングハウスの忘却曲線を参考に、覚えたら「1日後」「1週間後」「1ヶ月後」と複数回見直すサイクルを作りましょう。また、「アウトプット」の機会を増やすこと(人に説明する、問題を解くなど)で定着が促進されます。
- Q3. 「理科の用語が多すぎて、どこから手をつければいいか分からない」
- A3. まずは過去問を解き、頻出分野や単元を把握することから始めましょう。 全てを完璧に覚えるのではなく、「出やすいところから優先的に」 取り組むのが効率的です。
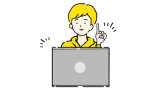
暗記した内容を忘れないための復習サイクル
暗記した内容を長期記憶に定着させるためには、適切なタイミングでの復習が不可欠です。
以下に、効果的な復習サイクルを提案します。
- 当日: 学習した直後(5分~10分程度)に、内容を簡単に振り返る。
- 翌日: 前日に学習した内容を再度確認する。
- 1週間後: 1週間分の内容をまとめて復習する。
- 1ヶ月後: 1ヶ月分の内容をまとめて復習する。
このサイクルを習慣化することで、忘れにくくなり、最終的な定着に繋がります。
計画的に復習日をスケジュールに組み込むことを強く推奨します。
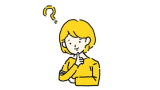
すぐに使える!おすすめ教材・参考書
暗記学習を効率的に進めるために、市販されている良質な教材や、手軽に利用できるツールを活用しましょう。

市販一問一答教材(例をピックアップ)
市販の一問一答形式の教材は、知識の確認と反復に非常に適しています。
- 『塾で教わる高校入試理科 一問一答』: 厳選された頻出問題で効率的に知識を定着させられます。
- 『高校入試 ひとつずつわかりやすく。理科』: 各単元の重要事項がコンパクトにまとまっており、復習にも最適です。
これらの教材は、間違えた問題にチェックをつけ、何度も繰り返すことが重要です。
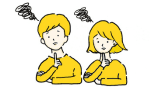
オンライン・YouTube動画・アプリ系ツール
現代の学習に欠かせないのが、オンラインツールや動画、アプリです。
- YouTubeの理科解説動画: 複雑な実験や現象を、視覚的に分かりやすく解説してくれる動画が豊富にあります。特に、化学反応や物理現象のイメージが掴みにくい場合に活用すると良いでしょう。
- 学習アプリ: 語呂合わせアプリや、フラッシュカード機能を持つアプリなど、ゲーム感覚で楽しく暗記ができるものが多数あります。移動時間などのスキマ時間にも活用できます。
| ツール種類 | 特徴 | おすすめ活用法 |
|---|---|---|
| YouTube動画 | 視覚的に分かりやすく、複雑な現象の理解を助ける。 | 理解しにくい単元の補足学習や、実験の事前学習・復習に。 |
| 学習アプリ | ゲーム感覚で楽しく暗記できる。スキマ時間で学習可能。 | 毎日の通勤・通学時間や、休憩時間の数分間を使って、単語や公式の反復学習に。 |
| 市販一問一答教材 | 厳選された頻出問題で効率的に知識を定着。 | 学習の初期段階での基礎固めや、定期的な知識確認に。間違えた問題はチェックを入れ、何度も繰り返し解く。 |
受験本番までにやっておきたい理科の勉強

高校受験に向けて、理科の暗記はいつまでに終わらせればいいのか、過去問はいつから取り組むべきかなど、疑問は尽きないでしょう。
このセクションでは、受験本番を想定した実践的な学習法として、過去問の活用、内申点対策、そして直前期に効果的な学習戦略について解説していきます。
- 理科の過去問をやって高校受験対策
- 理科の内申点を上げて高校受験対策
- 効率的な過去問の活用法と見直し術
- 直前期にやるべき理科の暗記対策
- 過去問の活用:10〜15回繰り返し習得術
- 秋以降にやるべき「アウトプット重視学習」とミス対策
理科の過去問をやって高校受験対策
過去問は、高校受験対策の最重要ツールです。
単に問題を解くだけでなく、以下の点を意識して取り組んでください。
- 出題傾向の把握:志望校の理科で、どの分野がよく出題され、どのような問題形式が多いのかを分析します。
- 時間配分の練習:実際の試験時間に合わせて問題を解く練習をすることで、本番での時間管理能力を高めます。
- 苦手分野の特定:解けなかった問題、間違えた問題は、自分の弱点です。徹底的に復習し、類題を解いて克服しましょう。
私が指導していた生徒で、過去問を徹底的に分析することで、理科の点数を15点以上伸ばして合格を勝ち取った生徒がいました。
その生徒は、各高校の出題傾向を詳細にノートにまとめ、それに合わせて自分の学習計画を調整していました。
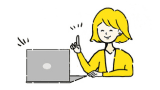
過去問対策について知りたい方、高校受験の過去問の使い方【完全ガイド】いつから?何年分?合格への近道
理科の内申点を上げて高校受験対策
高校受験では、当日の学力検査だけでなく、中学3年間の内申点も非常に重要です。
理科の内申点を上げるためには、以下の点を意識しましょう。
- 定期テスト対策:定期テストは内申点に直結します。教科書やワーク、学校のプリントを徹底的に復習し、満点を目指すつもりで臨みましょう。
- 提出物の期限厳守と丁寧さ:実験レポートや宿題など、提出物は期限を守り、丁寧な字で、分かりやすくまとめることが大切です。
- 授業態度:積極的に授業に参加し、質問があれば遠慮なく先生に尋ねましょう。
内申点は、日々の積み重ねが評価されるものです。
今から意識して取り組むことが、将来の大きなアドバンテージとなります。
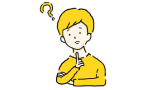
効率的な過去問の活用法と見直し術
過去問は、ただ解きっぱなしにするのではなく、その後の見直しが最も重要です。
- 採点後、すぐに解き直し:間違えた問題は、なぜ間違えたのか原因を分析し、解説を読んで理解した上で、必ず自分で解き直しましょう。
- 「なぜ正解したのか」も確認:たとえ正解した問題でも、勘で当たっただけかもしれません。「なぜこの選択肢が正解で、他の選択肢が不正解なのか」 を説明できるようにするまで確認しましょう。
- 苦手な問題はスクラップ:間違えやすい問題や、何度も間違える問題は、ノートに切り貼りしたり、デジタルで保存したりして、自分だけの苦手問題集を作り、定期的に見直しましょう。

直前期にやるべき理科の暗記対策
受験直前期は、新しい知識を詰め込むよりも、これまで学習した内容の総復習と弱点補強に徹するべき時期です。
- 頻出分野の最終確認:過去問の分析から得られた頻出分野の知識を最終確認します。特に、暗記が不十分な用語や公式がないかチェックしましょう。
- 苦手分野の総ざらい:これまでに蓄積した「苦手問題集」や「間違えた問題」に再度取り組み、完璧にします。
- 体調管理も重要:睡眠時間を削って無理に詰め込むのは逆効果です。質の良い睡眠をとり、体調を万全に保つことが、学習効率を最大限に引き出す鍵です。
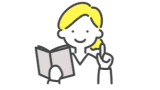
過去問の活用:10〜15回繰り返し習得術
過去問は、一度解いただけではその効果を十分に引き出せません。
最低でも志望校の過去問を10年分、できれば15年分、繰り返し解き、習得することを強く推奨します。
- 1回目:時間を計って解き、現在の実力と傾向を把握。
- 2回目以降:間違えた問題を中心に、時間をかけずに反復練習。正解するまで繰り返す。
- 繰り返しによる習得:同じ問題を何度も解くことで、問題形式や出題者の意図、解答のパターンが自然と身につきます。
私が担当した生徒の中には、志望校の過去問を5年分、合計3回以上繰り返して解き、理科で満点に近い点数を取って合格した生徒がいました。
その生徒は「同じ問題でも、繰り返し解くたびに新しい発見があった」と語っていました。

秋以降にやるべき「アウトプット重視学習」とミス対策
夏休みまではインプット(知識を覚える)が中心ですが、秋以降はアウトプット(覚えた知識を使う)を重視した学習に切り替えましょう。
- 演習問題の量を増やす:塾のテキストや市販の問題集で、応用問題や実践問題を積極的に解いてください。
- 「なぜ間違えたか」を徹底分析:間違えた問題は、「知識不足か、解釈ミスか、計算ミスか」 を明確にし、それぞれに合わせた対策を立てます。
- ミス対策チェックリストの活用:よくある計算ミスや、問題を読み違えるなどのミスパターンを自分だけのチェックリストにまとめ、問題を解き終わった後に必ず確認する習慣をつけましょう。これにより、「知っているのに点が取れない」という受験生の共通の悩みを解消できます。
合格者の暗記成功事例と実践ポイント

高校受験理科の暗記で苦戦している皆さん、諦める必要はありません。
これまで多くの生徒を指導してきた中で、暗記を克服し、理科を得点源に変えて見事合格を掴み取った生徒たちの事例をいくつかご紹介します。
理科の成績が上がったリアルな体験談から、明日から実践できるポイントを見つけてみてください。
- リアルな体験談・親子でできる暗記法
- 学習記録を家族と共有する習慣づくり
リアルな体験談・親子でできる暗記法
かつて私が担当したある生徒は、理科の計算は得意でしたが、生物や地学の暗記が壊滅的に苦手でした。
特に、用語の羅列を見ると「もう無理…」と諦めてしまうタイプでした。
しかし、生徒の母親が非常に協力的で、二人で以下の暗記法を実践した結果、見事理科の点数を20点以上伸ばし、志望校に合格できました。
| 取り組み方法 | 内容の概要 |
|---|---|
| 語呂合わせの共同制作 | 覚えにくい用語は、親子で一緒に「面白い語呂合わせ」を考えました。例えば、元素記号なら、お父さんが好きなアニメのキャラクター名に無理やり関連付けて覚えたりしていました。自分で考えた語呂合わせは、やはり忘れにくいのです。 |
| 「親が先生役」のテスト | 母親が教科書や問題集からランダムに問題を出題し、生徒が答えるという形式を毎日10分程度継続しました。間違えたらすぐに正解を教え、なぜ間違えたのかを一緒に考えます。この「対話式復習」が、彼の理解を深め、記憶を定着させました。 |
| 「合格への道のり」を可視化 | 理科の学習範囲を大きな紙に書き出し、覚えた単元、テストで点が取れた単元に色を塗っていくという「見える化」をしました。「あとこれだけ頑張ればいいんだ!」 という達成感が、彼のモチベーションを大きく支えました。 |
また、別の例では、部活動が忙しい生徒がいました。
その生徒は、市販の一問一答教材とYouTubeの解説動画を徹底的に活用しました。
通学時間や部活の休憩時間にスマホで動画を見たり、アプリで問題を解いたりと、スキマ時間を徹底的に活用することで、効率的に暗記を進めていました。
生徒の成功は、「時間を有効に使うこと」 の重要性を教えてくれました。

学習記録を家族と共有する習慣づくり
お子さんの学習をサポートする上で、保護者の皆さんが家庭で「明日からできること」として、学習記録を家族と共有する習慣を取り入れることを強くお勧めします。
- 親子で学習ノートをチェック:お子さんが理科の暗記で使っているノートや、問題集の進捗状況を一緒に確認しましょう。
- 「頑張ったこと」を具体的に褒める:「今日はここを覚えたんだね、すごいね!」「この問題、前は間違えてたけど解けるようになったね!」など、具体的に褒めることで、お子さんの自己肯定感が高まり、次への意欲に繋がります。
- 学習の目標を共有する:「今週はここまで覚える」「この単元の問題は完璧にする」など、小さな目標を親子で共有し、達成したら一緒に喜ぶことで、お子さんは「一人じゃない」という安心感を得られます。
私が見てきた成功事例の多くは、単に「勉強しろ」と声をかけるだけでなく、家族が具体的な行動で学習をサポートし、共に喜び、共に乗り越える姿勢がありました。
親子の協力体制が、高校受験という大きな壁を乗り越えるための最強の味方となるのです。
人気ランキング
人気のオンライン塾・家庭教師ランキング
毎月、多くのお問い合わせを頂いております!
第1位:東大生によるオンライン個別指導トウコベ
※講師のほとんどが現役東大生!しかも、圧倒的な低価格を実現!安心の返金保証制度で生徒の成績アップをサポートします。
第2位:オンライン家庭教師「東大先生」
※当サイトで人気の東大生によるオンライン家庭教師!講師全員が現役東大生・東大院生!資料請求で勉強が変わること間違いなし!
第3位:オンライン個別指導「そら塾」
※オンライン個別指導塾で生徒数No.1の実績!リーズナブルな料金で学校の成績がグングン伸びる!「お得に始めるならここ一択」
参考記事:そら塾の口コミ・評判を徹底調査|良い・悪い口コミから特徴と向いている子
まとめ:【高校受験理科】暗記が苦手でも9割取れる!頻出語呂合わせ&効率UP勉強法

高校受験理科の暗記は、多くの受験生が苦手意識を持つポイントですが、決して乗り越えられない壁ではありません。
重要なのは、「効率的な方法を知り、それを実践し、継続すること」 です。
今回ご紹介したように、語呂合わせを効果的に活用したり、分野別の勉強法を取り入れたり、便利なツールを上手に使いこなしたりすることで、暗記はぐっと楽になり、点数アップに繋がります。
私が27年間、多くの生徒を指導してきた中で痛感するのは、「暗記は才能ではなく、工夫と努力で誰でも伸ばせる能力」 だということです。
【高校受験理科】暗記が苦手でも9割取れる!頻出語呂合わせ&効率UP勉強法
まとめ
このブログでは、高校受験における理科の暗記術を効果的に身につけるための方法を紹介しました。
覚えやすく楽しく学ぶための語呂合わせを活用することで、理科の知識を効率よく習得できます。
暗記が苦手な受験生にとって、この方法は特に有効です。
さまざまな科目にまたがる多くの用語や公式を覚えるのは大変な作業ですが、適切な語呂合わせを使えば、その負担を軽減することができます。
ただし、単に覚えるだけでなく、理解を深めるためにも、暗記対策には工夫が必要です。
定期的な復習や問題演習を通じて、知識を定着させることが重要です。
さらに、自分に合った学習スタイルや効果的な学習計画を立てることも大切です。このブログを参考にして、理科の暗記を効果的に行い、高校受験に成功するための一歩を踏み出しましょう。
勉強に関するおすすめ記事
ポイント
都立高校に関連する記事
都立高関連の記事
都立高校受験に強いオンライン塾・個別指導塾20選│偏差値アップ!
東京の高校受験!内申点はいつから?計算方法・内申点対策を徹底解説
都立入試の内申点(調査書点)を300点に換算する計算方法をわかりやすく解説
【2026年】都立高校入試の受験料と日程を全解説!いつ、どうやって払う?
都立高校推薦「小論文・作文」対策!過去問分析と模範解答を活用した書き方
【都立高校入試】過去問はいつから始める?1月でいい子・早めた方がいい子の違い
都立推薦で受かる子・落ちる子の共通点?受けていい人・厳しい人の判断基準
V模擬で高得点を取る勉強法と活用ポイントを教えます!【都立高校入試対策】
都立高校入試対策!教科別勉強法・出題傾向・内申対策【高校受験完全ガイド】
都立の高校説明会で気をつけること!高校見学はいつから始まるの?
【2026年】都立高校入試「理科の傾向と対策」記述・頻出分野を徹底解説
都立入試社会でよく出る問題まとめ!出題傾向&裏ワザを徹底解説

